自宅で不動産業(宅建業)を始めたいとお考えでしょうか?宅建業を自宅で開業できるか不安に感じる方は少なくありません。自宅を事務所にする場合、賃貸契約の用途制限やマンション管理規約、看板の設置や郵便受けの名称、さらに専任宅建士の配置など懸念事項が多岐にわたります。
こうしたポイントを整理し、自宅で宅建業免許を取得するための可否判断や審査で見られる要件をわかりやすく解説します。実は、自宅兼事務所でも条件を満たせば宅建業の免許取得は可能です。
行政庁の審査観点に即した対策をとることで、自宅開業のハードルを下げられます。本記事では、宅建士資格を保有する行政書士が電子申請から保証協会加入、営業開始まで一気通貫でサポートする内容も交えて、全国どこでも対応可能な安全・確実な進め方をご紹介します。全国対応のオンライン申請により、ご自宅からでも迅速に免許取得手続きが進められますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください(LINE・お電話・お問い合わせフォームで受付中です)。
自宅での宅建業免許の可否と事務所要件

このトピックでは、自宅(自宅兼事務所)で宅建業免許を取得する際に満たすべき事務所要件を具体的に解説します(法律上の本店要件とも呼ばれます)。自宅を事務所とする場合でも、住居スペースと業務スペースの独立性、玄関から事務所への動線の確保、看板や郵便受けへの名称表示、来客対応スペースの有無などが審査でチェックされます。
さらに、所在地の用途地域による制限やマンションの管理規約・賃貸契約で事務所利用が許可されているかも重要です。自宅でもこれらの条件をクリアすれば宅建業免許は十分取得可能ですので、現実的な対策を踏まえてポイントを見ていきましょう。
自宅事務所の独立性・表示物・保管体制
自宅を宅建業の事務所とする際、まず重要なのは生活空間と業務空間の明確な分離です。事務所スペースは壁や扉で区切られた独立した部屋である必要があります。ふすまやカーテンで仕切っただけの空間では「独立した形態」と認められにくく、少なくとも固定壁(パーテンションも可能。ただし都道府県にもよる)と扉で専用スペースを確保しましょう。
玄関から事務所への動線も直接確保しなければならず、事務所に入るためにリビング等の生活スペースを通過するレイアウトは不可とされています。ワンルームなど居住空間と事務所部分が一体化してしまう間取りでは許可は厳しいのが実情です。
事務所としての体裁も整える必要があります。具体的には固定の机と椅子、パソコン、固定電話、プリンター/複合機などを備え、業務にふさわしい環境を用意します。特に電話回線は自宅のプライベート番号とは別に事務所専用番号を用意することが望ましいです(現在の制度上、携帯電話番号のみでは事務所の連絡先として不十分となる場合があります)。
また、事務所入り口には事務所名の表札や看板を掲示し、郵便受けにも会社名(屋号)を表示しておきます。これは対外的に宅建業者の事務所であると明示するために不可欠です。免許申請時にも、こうした名称表示の有無が写真で確認されます。
さらに、契約書や重要事項説明書、取引台帳など含む宅建業法上の帳簿類を適切に保管できる体制も求められます。個人情報や機密事項を扱うため、鍵付きのキャビネットや金庫を用意して書類を厳重に管理しましょう。日常的に家族が立ち入らない専用スペースであること、そして施錠保管により情報漏洩リスクに配慮していることが重要です。
以上を事前に整えておけば、申請時の事務所写真や書類審査でもスムーズに認められます。事前チェックで不足が判明した場合でも、行政書士に相談すれば迅速に補正指示を受けることができ、写真の撮り直し等の手間を防げます。プロの行政書士に相談して準備を進めると安心です。
賃貸・区分所有物件での留意点(管理規約/使用目的)
自宅を事務所にする場合、その建物が持ち家か賃貸か、また戸建てかマンションかによってクリアすべき条件が変わります。まず賃貸物件の場合、賃貸借契約書の使用目的欄を確認しましょう。
一般の賃貸契約では「居住専用」と定められていることが多く、事務所利用が明記されているケースは稀です。もし契約書上で事務所使用可と明記されていれば、その契約書を添付するだけで足りますが、多くの場合はそうでないため大家からの事務所使用承諾書を別途用意する必要があります。
承諾書には、物件を宅建業の事務所として使用して良い旨を明記してもらいます。賃貸が公営住宅(都道府県営住宅、市営住宅)やUR賃貸の場合、契約で用途外使用が禁止されており使用承諾が得られないため、自宅事務所としての開業は残念ながら諦めるしかありません。
次にマンションなど区分所有物件の場合は、管理規約の確認が重要です。規約に「当該住戸の事務所利用可」といった記載があれば問題ありませんが、事務所利用不可と定められていたり何も言及がない場合は、管理組合に掛け合って事務所使用許可を得る必要があります。
理事会の了承など正式な許可を文書で取得し、それを申請時に提出しなければなりません。賃貸マンションの場合はさらにハードルが上がります。物件所有者である大家からの使用承諾書に加え、管理規約上も事務所利用が可能であることが求められます。
もし規約で禁止されていれば管理組合に事情を説明して許可を得る二段構えとなり、現実的には難航するケースもあります。実務的には、一棟まるごと一人のオーナーが貸している物件であれば大家の承諾書だけで済むため比較的スムーズですが、分譲マンションの1室を借りているような場合はオーナーと管理組合双方の許可が必要となり、高いハードルとなります。
持ち家のケースでは比較的問題は少ないですが、共有名義になっている場合は他の共有者全員から使用承諾書を取っておく必要があります。また、所在地の用途地域にも留意しましょう。第一種低層住居専用地域など厳しめの住宅地でも、宅建業の事務所開設自体は法律上可能ですが、近隣の生活環境に配慮が求められます。
来客用の駐車スペース確保や騒音への注意など、地域住民への影響を最小限にする工夫も大切です。なおマンションによっては来客の出入り制限や看板掲出禁止のルールがある場合もあります。このような場合でも、小さなプレートを部屋の前に掲示する程度であれば黙認されるケースもありますが、事前に管理組合やオーナーと相談しておく方が安全です。
以上のように物件ごとの制約をクリアするには、関係者(大家や管理組合)との調整が不可欠です。必要な承諾書類や説明文書の作成については行政書士がサポート可能ですので、事前に専門家へ相談しておくとスムーズです。物件オーナーや管理組合とのやりとりも、行政書士が間に入ることで円滑に進められます。
専任宅建士の常勤性・雇用証明の実務
宅建業免許を申請するには、各事務所ごとに専任の宅地建物取引士(専任宅建士)を1名以上設置することが法律で義務付けられています(従業員5人に1人以上)。専任宅建士とは、その事務所にフルタイムで勤務し宅建業務に専従する宅建士のことで、単に資格を持っているだけでは足りず他の仕事を兼ねない常勤社員である必要があります。
したがって、例えば代表者が宅建士資格を持っていても他の会社の役員を兼任していたり、公務員など別職業についている場合は「専任」と認められません。また、自宅兼事務所の場合であってもテレワーク主体の在宅勤務だからといって他の仕事との掛け持ちが許されるわけではない点に注意が必要です。専任宅建士は基本的にその免許業者一社にフルタイムで勤務し、いつでも事務所で業務に従事できる状態でなければなりません。
専任宅建士の常勤性を証明するために、免許申請時には様々な書類を提出・提示します。まず必要なのが「専任の宅建取引士設置に係る誓約書」で、専任宅建士となる者が他に兼職がないこと等を宣誓する書類です。加えて、その宅建士の宅建士証のコピー(有効な宅建士証を保有している証明)も添付します。さらに場合によっては、社会保険の加入状況や雇用証明に関する書類も求められます。(大阪府や奈良県は不要、兵庫県は必要)
専任性の客観的な証明として、その宅建士が当該業者の社会保険に加入していることは有力な裏付け資料になります。小規模な新設法人などでは必須提出ではないこともありますが、雇用保険の被保険者証や健康保険被保険者証(会社名の記載あり)などを用意しておくとよいでしょう。提出書類の具体例としては、雇用契約書または勤務証明書を添付する自治体もあります。
なお、専任宅建士としてカウントできるのはその会社の役員か従業員のみです。外部の人を業務委託で「名義貸し」的に専任にすることは認められません。よくある落とし穴は、親族や知人に宅建士がいて手伝ってもらう場合でも、正式に雇用して常勤従業員になってもらわなければ専任宅建士とはみなされないことです。また、申請者本人が宅建士であるケースでも、もし別業種の会社を経営していたり副業を持っていると審査で指摘される可能性があります。
以上のような専任宅建士の要件については、提出書類の不備があると補正を求められて免許取得が遅れてしまいます。例えば雇用契約書の日付や社会保険の加入時期と申請時期の整合性など、細かな点までチェックされますので注意しましょう。立証資料の作り込みによって審査期間の短縮も期待できますので、不安な場合は行政書士など専門家の事前レビューを受けるのが確実です。専門家に依頼すれば、これら証明書類の適切な整備もサポートしてもらえます。
自宅での宅建業免許・電子申請の手順

このトピックでは、自宅で宅建業免許を取得する際の具体的な手続きの流れを、昨今主流になりつつある電子申請を中心にご紹介します。宅建業免許の申請手順は大きく、事前相談・準備→申請書類の作成→提出(オンライン送信)→補正への対応→許可→営業保証金の供託または保証協会加入→営業開始という流れになります。
紙申請と電子申請で基本的な必要書類は同じですが、オンラインの場合はパソコン環境や電子署名の準備、PDF化の作業など独特のステップがあります。本章では電子申請に必要な環境準備や注意点、紙申請との違い、そして提出後の標準的な審査期間や補正対応、免許取得後に行う保証協会手続きまで、時系列に沿って解説します。初めての方でも流れが掴めるよう具体的なガイドとポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
電子申請と紙申請の違い・環境準備
現在、宅建業免許の申請手続きは多くの都道府県でオンライン申請(電子申請)に対応し始めています。電子申請では、自宅や会社のパソコンからインターネット経由で申請書類を提出でき、行政庁の窓口へ出向く必要がありません。
一方、電子申請を利用するには事前にいくつかの環境準備が必要です。まずGビズIDプライムという法人用の認証アカウントを取得します。GビズIDは申請者(法人代表者または個人事業主)の本人確認を経て発行されるため、取得に1〜2週間程度かかることがあります。早めに登録手続きを済ませましょう。
また、電子申請システム(国土交通省のe-MLIT)に対応したPC環境も整えます。推奨ブラウザ(ChromeやEdge等)やPDF閲覧ソフト、必要に応じてICカードリーダライタ(マイナンバーカード等で電子署名する場合)が利用できる状態にしておきます。
申請書類はすべてPDFデータ等で提出するため、紙の書類や写真はスキャナで取り込み電子化する作業が発生します。スキャナがない場合はスマートフォンのスキャンアプリ等で代用できますが、解像度や容量に注意が必要です。
紙申請との違いとして、電子申請ではやり取りのスピードが上がるメリットがあります。例えば書類不備の補正依頼がある場合、電話やメールの通知で迅速に連絡が来るため、郵送より早く対応できます。また紙申請では控えの書類に受付印を押してもらう手続きがありましたが、電子では受付完了メールや申請履歴のスクリーンショットが控えの代わりとなります。
必要に応じてPDFで申請内容を保存しておくとよいでしょう。なお、オンライン化に対応していない地域もまだあります。その場合は書面申請となりますが、当事務所では電子申請・書面申請いずれにも対応し、最適な方法で進めます。電子申請の初期設定や環境構築はつまずきやすいポイントですので、不安な場合は行政書士に代行を依頼することで時間と労力を大幅に節約できます。
免許申請書作成・添付書類・審査期間の実務
次に、宅建業免許申請書および添付書類の準備についてです。法人で申請する場合、基本的に登記事項証明書(商業登記簿謄本)や役員の略歴書、専任宅建士や政令使用人(支店長等)に関する書類などが必要です。個人事業で申請する場合は身分証明的な書類(住民票、身分証明書など)や略歴書等が求められます。
共通して必要なのが、先述の事務所を証明する資料です。具体的には事務所の平面図(間取り図)や付近の案内図、建物の権利関係を示す書面(登記簿や賃貸契約書、使用承諾書)に加え、事務所内部と外観の写真を提出します。
写真は5~10枚程度を求められるケースが多く、事務所入口、事務机、応接スペース、宅建業者票(標識)設置予定場所、郵便受け名称表示、契約書保管庫(鍵付きキャビネット)など、要件を満たしていることが一目で分かるように撮影します。「生活感が映り込んでいないか」「家族の私物が置かれていないか」等にも注意し、必要であれば一時的に片付けてから撮影しましょう。例えば写真にゲーム機や漫画本棚など業務と無関係なものが写っていると審査が厳しくなると言われています。役所に提出する写真は、できるだけ事務所らしい雰囲気になるよう工夫することがポイントです。
申請書類一式をオンラインで送信すると、役所での審査が始まります。各都道府県知事免許の場合、標準的な審査期間はおよそ30日~40日程度と言われています(時期や案件によっては前後します)。審査期間中に担当官から補正依頼(追加資料や修正の指示)が出ることもあります。典型的な補正事項としては、会社の商号や代表者氏名の不一致、先述した事務所写真の不足や不鮮明、添付書類の漏れがあります。
特に初めての申請ではどうしても見落としがちですが、こうした補正は通知を受けてから対応するとまた数日~1週間程度ロスしてしまいます。したがって、申請前に想定される補正事項を先回りして潰しておくことが大切です。例えば住所表記は登記事項証明書や住民票の記載通りに統一する、法人名や代表者名のフリガナまで完全に一致させる、必要書類はリストアップしてチェックを入れる等の対策が有効です。
行政書士に依頼した場合、提出前に専門家の目で不備がないか確認しますので、補正リスクを大幅に減らすことができます。「どの書類を添付すべきか分からない」「写真はこの写り方で大丈夫か?」といった疑問も、その場で解消してから申請できるため結果的に免許取得までの期間短縮につながります。
スケジュールに余裕がない場合ほど、プロのサポートを受けてゼロ補正を目指すことをおすすめします。補正対応も行政書士に任せれば迅速ですので、安心して結果を待つことができます。万一補正の連絡が来ても、当事務所が速やかに対応し申請を完璧な状態へ仕上げます。
許可後~保証協会加入・営業開始まで
審査を無事通過すると、都道府県から免許通知(郵送ハガキ等)がお手元(事務所)に届きます。これが宅建業者として免許が下りたことの証です。ただし、免許が下りただけではまだ営業開始できません。宅地建物取引業法では、免許取得後に営業を開始するための前提として営業保証金の供託または保証協会への加入を義務付けています。
営業保証金とは万一取引事故があった際に取引先へ弁済するための預け金で、本店1000万円(支店がある場合は支店ごとに500万円追加)を法務局に供託する必要があります。資金的負担が非常に大きいため、実務上はほとんどの業者が保証協会への加入を選択します。
保証協会(業界団体の宅建協会と一体運用)に加盟すれば、営業保証金の供託は免除され、その代わり本店60万円(支店1か所につき30万円)の弁済業務保証金分担金を納めます。例えば本店のみで営業する場合、60万円を協会に預託すれば足り、残り940万円は用意しなくて済む計算です。加えて入会金や年会費が別途かかりますが(地域にもよりますが初年度合計で20~50万円程度)、それでも供託1000万円に比べれば格段にハードルが低いため、大多数の新規業者が協会加入を選ぶのが現状です。
保証協会へ加入するには、免許通知が届いてから協会(宅地建物取引業協会・不動産保証協会の各都道府県本部)に入会申込を行います。申込から実際の入会承認までは2~3週間程度かかることがありますので、免許がおりたら速やかに動きましょう。入会手続きでは免許通知書の写しや会社概要書類の提出、説明会への参加、分担金の納付などが必要です。
全て完了すると「弁済業務保証金分担金納付済証明書」が発行されます。この証明書を持って改めて免許権者(知事または大臣)に供託(協会加入)完了の届出を行えば、晴れて営業を開始できる状態となります。免許取得から3か月以内にこの手続きを完了しないと免許が失効してしまいますので注意してください。
営業開始前に準備すべきことも整理しておきます。まず事務所に標識(業者票)の掲示をしましょう。業者票とは免許証番号・商号・代表者名・宅建業者である旨等を記載した看板で、事務所の見やすい場所に掲示が義務付けられています。
保証協会に加入した場合はその旨(〇〇保証協会所属)も標識に記載します。当事務所では標識のひな形もご提供可能です。また、専任宅建士の資格者証(宅建士証)も事務所に備え付け、従業者名簿や各種帳簿類(取引台帳、重要事項説明書の控えファイルなど)の様式を整えましょう。
お客様に交付する重要事項説明書や契約書のフォーマットも事前に用意し、専任宅建士が記名押印できる状態にしておく必要があります。さらに、名刺や広告物、ホームページ等にも免許番号や所属協会などの法定表示事項を入れることをお忘れなく。
不動産の広告を行う際には、免許番号や取引態様を明示することが宅建業法で定められています。例えばホームページの会社概要や物件情報ページ、折込チラシやポータルサイトの店舗情報欄などに「○○知事⑴第○○号」「所属団体○○保証協会」等と記載することで遵法性と信頼性を高めます。
以上、免許取得後から営業開始までの一連の流れをご説明しました。許可後の各種手続きや初動の整備は意外と煩雑ですが、当事務所では免許取得後のフォローまで一括してサポートしております。保証協会入会手続きの代行はもちろん、営業開始前チェックリストに沿って必要事項を漏れなくご案内しますので、初めてでも安心です。行政書士に相談いただければ、許可取得から開業までスムーズに伴走いたします。
宅建業免許申請を行政書士に依頼するメリットと当事務所の強み
このトピックでは、宅建業免許の取得手続きを専門家(行政書士)に依頼することのメリットと、大倉行政書士事務所ならではの強みについて解説します。初めて免許申請を行う方にとって、法令要件の解釈や書類作成は大きな負担です。
プロに任せることで安心感と手続きの迅速化が得られ、結果的に早く安全に免許を取得できます。また当事務所は宅建士資格を保有する行政書士が直接対応し、不動産業・建設業での実務経験も豊富なため、実践的なアドバイスと徹底した書類チェックが可能です。
料金についても明確な基準を設け、全国対応で電子申請にも精通しております。ここでは、そうした専門家に依頼する具体的なメリットを3つの観点でご紹介し、他にはない当事務所の提供価値をお伝えします。免許取得への不安を取り除き、スタートダッシュを成功させるために、ぜひ専門サービスの活用をご検討ください。
安心とスピード(補正回避)
行政書士に依頼する一番のメリットは、手続きの正確性が飛躍的に向上することです。経験豊富な行政書士であれば、各都道府県の審査ポイントを踏まえて事前に書類を作り込むため、不備による補正をほぼゼロに抑えることができます。例えば事務所写真の撮り方一つとっても、申請担当者がチェックする観点を知っていますので、「ここは生活感が見えるから撮り直しましょう」「この角度から看板が写るようにしましょう」といった具体的な指示が可能です。
結果として一度の申請でスムーズに受理・許可され、無駄なやり取りが省けます。補正連絡が来てから素人が対応するのは大変ですが、行政書士に任せれば速やかに適切な修正を行い、審査の停滞を最小限にできます。
また、行政書士は日頃から役所との窓口対応に慣れており、申請書が受理されてから許可が下りるまでのプロセス管理もお任せできます。提出後、「今審査はどの段階か」「追加書類は必要か」といった気になる点は逐一行政書士が確認し、適宜お客様に報告します。提出日・補正・許可予定日など進捗をタイムラインで共有しますので、不安なくお待ちいただけます。
万一予定より長引く場合も、行政書士が担当部署に照会し原因を把握してご説明します。こうしたきめ細かな連絡とフォローにより、初めての方でも終始安心して手続きを進められます。行政書士への依頼は費用がかかると思われがちですが、結果的に時間短縮による機会損失の防止や、書類作成・役所訪問に費やす労力の削減効果を考えると、非常に大きな価値があります。
もちろん、初回相談は無料で承っております。当事務所ではLINEやメール、電話でお気軽に質問や見積依頼をしていただけます。実際に「ここが不安」「何から始めれば?」という段階からでも、専門家が寄り添ってお答えしますので、まずは一度お問い合わせください。早めにプロを巻き込むことで、結果的に最短での免許取得とビジネス開始が実現します。
宅建士資格保有の行政書士が直接対応
当事務所の大きな強みの一つが、担当行政書士自身が宅地建物取引士(宅建士)資格を保有していることです。宅建業界の国家資格者としての視点と、行政書士として許認可手続を扱う視点の両方を持ち合わせているため、実務に即したサポートが可能です。
他の行政書士事務所では法手続き面のサポートはできても、宅建業務そのものの現場感覚に乏しい場合があります。例えば、専任宅建士の常勤性について単に法律上必要だから書類を揃えるだけでなく、実際に開業後にどのように専任宅建士として業務をこなすべきかまで踏み込んでアドバイスします。
在宅勤務が中心の場合の注意点や、兼任が疑われない勤務実態の作り方など、行政庁の目線と業界の実情を踏まえた具体策をご提案できます。また、契約書や重要事項説明のひな型整備、営業開始後のレインズ(指定流通機構)への登録手続きなど、免許取得後に待ち受ける実務も見据えてサポートします。宅建士資格保有者だからこそ、法定手続きと実務運用の双方に強く、お客様に“一歩進んだ安心”を提供できるのです。
結果として誠実で的確な申請書が出来上がり、審査官にも良い印象を与えることにつながります。「行政書士〇〇」ではなく「宅建士でもある行政書士」が対応する当事務所ならではの強みを、ぜひご活用ください。
不動産・建設業界の実務経験+明瞭な料金体系
宅建業の許可申請は書面上のチェックも多いですが、実際には不動産業界の商習慣や建築業界の知識があるとよりスムーズに進められる場面があります。当事務所の行政書士は、かつて建設会社や不動産会社に勤務していた実務経験があります。そのため、建物用途の専門用語、近隣対策の勘所など現場目線での助言が可能です。
下記のとおり料金面でもご安心いただけます。当事務所では料金レンジの明示と追加費用発生条件の事前説明を徹底しております。
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。
そして、日本全国どの地域からのご依頼にも対応可能なのも当事務所の特徴です。電子申請の仕組みをフル活用し、遠隔地のお客様でもオンラインで打ち合わせから書類授受まで完結します。
当事務所は全国対応であり、地域ごとの細かな運用の違いも事前にリサーチして申請書に反映します(例えば大阪府は自宅兼事務所に厳しめ等、各自治体の特色を踏まえます)。電子申請未対応の地域でも、書類一式をこちらで準備・郵送し、お客様にご署名いただくだけで進めることも可能です。地理的ハンデを感じさせないサポート体制で、お客様の宅建業開業を全力でバックアップいたします。
自宅での宅建業免許で詰まりやすいポイント

このトピックでは、自宅を事務所とする宅建業免許申請において特に注意すべきポイントを、NG例・OK例を交えながら具体的に解説します。事務所要件のチェックでは、どんな写真がNGとなりやすいか、専任宅建士の常勤性では見落としがちな落とし穴、電子申請におけるミスの多い箇所など、読者ご自身でセルフチェックできる内容を盛り込みました。
一度自分で確認してみて、詰まりそうだと感じたら早めに対策することが肝心です。NG例とOK例を知ることで、申請準備の段階で問題点を発見しやすくなります。専門家に相談する前にセルフチェックする材料としてぜひお役立てください。それでは順に見ていきましょう。
自宅事務所要件チェック(写真NG例/OK例)
<NG例>
- 生活感が映り込んでいる
リビングの一角に机を置いただけで、後ろにソファやテレビ、子供のおもちゃが写っている写真はアウトです。プライベート空間と業務空間が混在しており独立性が確認できません。 - 看板・表札がない
玄関ドアや門柱に事務所名の表札や看板が出ていない状態はNGです。写真で入口が写っているのに何の表示も無いと、「本当にここで営業するのか?」と思われます。小さくても構いませんので、会社名や屋号を表示してください。ポスト(郵便受け)にも同様に名前を出しておきます。 - 郵便受けの未整備
ポストが写った写真で、他の家族名はあるのに会社名が書かれていないとNGです。他社から郵便が届かないおそれがあるためです。必ず会社名シール等を貼付しましょう。 - 家族の動線と共用
事務所への入り口が家族共用の玄関のみで、そこからリビングを経由しないと事務スペースに行けない間取りはNGです。写真でも、その動線上に生活空間が広がっている様子が見えると不合格につながります。可能なら勝手口など別の出入り口を事務所専用にするか、玄関入ってすぐの部屋を事務所に充てるなど工夫しましょう。
<OK例>
- 完全独立した個室
玄関入ってすぐ右手の部屋を事務所にした例では、ドアを閉めれば他の居室とは隔絶された空間になっています。写真でも、ドアに社名プレートが貼られ、中は事務所備品のみ置かれている様子が確認できます。生活用品は一切見当たらず、ビジネス専用ルームとわかる状態です。 - 事務机+応接セット
部屋の中に事務用デスク(PC設置)と、来客用の小さな応接セット(テーブルと椅子2脚)が両方写っている写真は好印象です。面談スペースを兼ね備えており、業務を継続的に行う体制が整っていると評価されます。狭い場合は折りたたみ椅子でもよいので、お客様用椅子を机の向かい側に置いて撮影するなど工夫しましょう。 - 事務所のみ利用の動線
勝手口から直接事務所部屋に入れる間取りの場合、その勝手口を事務所の入口として利用している写真は高評価です。家族は別の玄関を使う、または事務所部屋には家族は立ち入らない運用であることが明確になります。同様に、玄関入ってすぐ独立した部屋で他の空間と行き来がない場合もOKです。要はお客様を案内する際に生活感のある場所を通らずに済むかどうかがポイントです。
以上を踏まえて、自宅事務所の写真を撮る前に今一度チェックしてみましょう。不安な場合は行政書士に現状写真を見せてアドバイスを仰ぐことも可能です。「ここに生活用品が写っています」「この掲示を追加しましょう」といった具体的指示を受ければ、撮り直しによる申請遅延を防ぐことができます。事前に専門家へ相談することで、OK例に近い状態に整えてから本番の撮影・申請に臨むことができます。
自宅事務所チェックリスト:開業前の確認ポイント
自宅を宅建業の事務所にする際に、事前に確認・準備しておきたいポイントをチェックリスト形式でまとめました。以下の項目について、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 独立した事務所空間の確保–居住スペースとは壁・扉・パーテンション等で区切られた専用の部屋がありますか?(カーテンのみでは不可)
- 事務所専用の出入口–戸建ての場合は勝手口等を事務所専用にできますか?集合住宅の場合は玄関から事務所まで生活空間を経由せず案内できますか?
- 玄関・室内への名称表示–玄関ドアや門柱に会社名(屋号)の表札・看板を出していますか?
- 郵便受けへの表示–ポスト(郵便受け)に会社名を表示していますか?郵便物が確実に届くよう、略称ではなく正式名称で表記しましょう。
- 固定の事務用デスク・椅子–一時的な机ではなく、PC作業や書類作成に耐える事務机と椅子を設置済みですか?(折り畳みではなく常設のもの)
- 事務機器の設置–パソコン、プリンター/複合機、電話機、ファックス(必要なら)などオフィス機器は揃っていますか?
- 固定電話回線の用意–事務所連絡先として固定電話またはFAX番号を取得済みですか?携帯番号のみの場合、今後導入を検討しましょう。
- インターネット環境–安定したインターネット回線はありますか?(電子申請やオンライン業務に必須)Wi-Fiの届き具合もチェック。
- 応接スペースの有無–お客様を迎える簡易な応接スペース(テーブル・椅子)は用意できますか?狭い場合でも椅子2脚程度追加できる余地は確保しましょう。
- 重要書類の保管設備–契約書や帳簿類をしまう鍵付きキャビネットや金庫はありますか?書類紛失・情報漏洩対策として必要です。
- 事務所内の防犯–窓やドアの施錠は確実ですか?貴重書類があるため、防犯面でも安全な部屋か確認しましょう(戸建て1階の場合は特に)。
- 物件の用途制限確認–自宅所在地の用途地域は宅建業の事務所設置に問題ないか把握していますか?(用途地域による開業不可は基本ありませんが、看板規制等に注意)
- マンション管理規約の確認–区分所有マンションの場合、管理規約で事務所利用が禁止されていないか確認済みですか?必要に応じ管理組合の許可を得ましたか?
- 賃貸借契約の用途許可–賃貸物件の場合、契約書で事務所使用が許可されていますか?許可されていない場合、大家から使用承諾書を取得しましたか?
- 共有名義物件の承諾–持ち家が共有名義なら、他の共有者全員から事務所使用の承諾を得ましたか?書面で残しておくと安心です。
- 写真の内容チェック–写真に生活用品や私物が写り込んでいませんか?また暗すぎたりピンボケしていないか確認しましたか?必要なら再撮影しましょう。
- 専任宅建士の確保–専任の宅建士は確保済みですか?また、その方は他社に勤務していないことを確認しましたか?(申請までに雇用契約締結・社会保険加入等を予定)
以上のチェック項目を満たせば、自宅兼事務所であっても宅建業免許取得の準備はほぼ万端です。もし満たしていない項目があれば、早めに対策を講じましょう。行政書士に事前相談いただければ、上記チェックを踏まえた具体的なアドバイスを差し上げます。
よくある質問(FAQ)
Q1.自宅(賃貸物件)でも宅建業免許の取得・開業は可能でしょうか?
A1.はい、可能です。ただし物件オーナーや管理規約の許可を得るなど所定の条件クリアが必要です。賃貸住宅の場合、契約書に居住専用と書かれていることが多いため、そのままでは事務所に使えません。
大家さんに事情を説明し、事務所使用承諾書を作成してもらえれば申請は受理されます。またマンションなら管理規約が事務所利用を禁じていないか確認し、必要なら管理組合の許可を取ります。こうしたハードルはありますが、条件を満たせば自宅兼事務所で免許取得は十分可能です。
実際、コスト節約のため自宅開業するケースも増えており、行政庁も要件クリアさえすれば許可を出しています。不安な場合は事前に行政書士など専門家に相談し、オーナー説得の文案作成や必要書類準備をサポートしてもらうと良いでしょう。
Q2.自宅で開業する場合、やはり看板や表札、ポストの名前表示は必須ですか?
A2.はい。規模の大小に関係なく、事務所の名称表示は実質的に必須とお考えください。法律上、宅建業者は事務所ごとに免許票(標識)を掲げる義務があります。自宅兼事務所でも屋内の見やすい場所に免許票を掲示する必要がありますし、そもそも表札・看板がないとその場所が宅建業の事務所だと認識されません。郵便物も届かなくなる恐れがあります。保証協会に加入する場合も事務所名の表示は求められます。
小さくても構いませんので、玄関先に会社名の表示をしましょう。ポストにも会社宛名が書かれていないと郵便事故の原因になりますので注意です。以上より、看板・表札・ポスト表示は実質必須とお考えください。なお、戸建てなら門柱にプレートを付ける、マンションならインターホン横のネームプレートを会社名に差し替えるなどの方法があります。申請時の写真にも写る部分ですので、忘れず対応しましょう。
Q3.マンションの規約で「住居専用」となっていました。事務所利用不可の場合、打つ手はありますか?
A3.規約で明確に禁止されている場合はハードルが高いですが、管理組合の許可を得られれば道が開けます。まず管理会社や理事長に相談し、小規模な事務所利用(来客は少人数で騒音等出さない)であることを説明して許可を求めます。
理事会決議が必要な場合もありますが、認めてもらえれば管理組合の承諾書や議事録を添付することで申請可能です。規約に事務所禁止と書かれていなくても黙示のルールとして敬遠される場合もあるので、その場合も同様に相談しておくと安心です。
一方、UR賃貸や公営住宅は用途外使用厳禁で許可が下りません。この場合は残念ながら自宅開業は諦めるか、事務所だけ別に借りる必要があります。マンション規約の問題は個別性が高いので、行政書士に規約を見せて判断を仰ぐと確実です。許可を得るための説明資料作成なども代行可能ですのでご相談ください。
Q4.専任宅建士の「常勤性」とは具体的に何を求められますか?
A4.常勤性とは、その宅建士がフルタイムでその事務所の業務に従事することを意味します。具体的には週5日・1日7~8時間程度勤務し、他の仕事を一切兼ねていない状態です。審査では、専任宅建士として届出た人が他社の役員や社員になっていないかチェックされます。また通常通勤できないほど遠方に住んでいる場合も常勤とみなされません。証明としては、専任宅建士本人の誓約書と宅建士証のコピーを提出します。自治体によっては健康保険証の写しや雇用証明書などを求める場合もあります。
要は「御社の宅建士はうちでしっかり働いています」と客観的に示すことが重要です。なお、従業員5人(宅建業に従事する者)につき1人以上の割合で設置義務があります。開業当初は代表者1名のみでも、その人が専任宅建士であれば要件クリアです。専任宅建士が他の仕事を始めたり退職した場合は2週間以内に後任を設置し、30日以内に届出しなければなりませんので、開業後も注意しましょう。
Q5.電子申請するにはどんな機材や環境が必要ですか?
A5.パソコンとインターネット環境が必須です。スマートフォンだけでの申請は現実的ではありません。具体的にはWindowsPC(推奨)に加え、PDF閲覧・編集ソフト、スキャナーまたはスマホのスキャンアプリがあると良いでしょう。
さらに申請者本人確認のためのGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。その際に電子証明としてマイナンバーカードか商業登記所発行の電子証明書を使います。マイナンバーカードを利用する場合はICカードリーダライタが必要です。あとはメールアドレスや電話番号(連絡先として)も準備してください。
インターネット回線はできるだけ高速・安定したものが望ましいです。大容量ファイルをアップロードすることもあるため、Wi-Fi環境推奨です。まとめると、PC+ネット+電子証明環境+PDFスキャン環境がそろえば電子申請は可能です。もし機材を新たに揃えるのが難しい場合は、無理せず紙申請にするか、行政書士に電子申請代行を依頼する方法もあります。当事務所では電子申請フルサポートしておりますので、ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
Q6.営業保証金の供託と保証協会への加入は何が違うのでしょうか?費用はどれくらいですか?
A6.営業保証金の供託は、宅建業者が自社の費用負担で法務局に保証金を預ける方法です。主たる事務所ごとに1000万円という高額な供託が必要ですが、預けたお金は無利息で保管されます(廃業時に戻ってきます)。
一方、保証協会への加入は業界団体の保証制度を利用する方法で、本店60万円・支店30万円の分担金を協会に納めれば供託が免除されます。分担金は将来的に退会時に返還されますが、協会の運営費として入会金や年会費(地域により初年度20~50万円程度)が別途かかります。費用面で言えば、供託は1000万単位のお金を長期間拘束されるのに対し、協会加入は初期コスト数十万+毎年数万の会費という違いです。ほとんどの新規業者は資金負担の軽い保証協会ルートを選択しています。
協会に加入すると、不動産保証協会(または全宅保証)の会員となり、研修や各種サービスも受けられるメリットがあります。一方、自前で供託するメリットは毎年の会費負担が無いくらいですが、1000万円を即用意できる会社は少ないでしょう。結論として費用負担を考えれば保証協会加入が現実的です。
Q7.免許が下りた後はすぐ広告したり営業を開始しても良いのでしょうか?
A7.営業開始はもう一歩です。宅建業免許の知事通知(許可がおりたというハガキ等)が届いた段階では、まだ営業を開始できません。まず営業保証金の供託または保証協会加入の届出を済ませる必要があります。これを免許権者(知事または大臣)が受理して初めて「営業可能」となります。
実務的には、保証協会への加入手続きが完了し、保証協会から発行される加入完了証明を知事に提出した後に営業開始となります。したがって、免許通知が届いた日~協会手続き完了までの数週間は、物件の広告や媒介契約の締結など宅建業としての行為は控えてください。免許番号が付与され正式に名乗れるのは協会加入後です。協会入会手続き中に「免許申請中」と明記して広告するのも原則NG(トラブル防止の観点から)とされています。
ですので、免許取得→保証協会入会完了→営業開始の順番を守りましょう。なお、標識(業者票)の掲示も営業開始までに済ませておく必要があります。全て整った段階で、晴れて広告・営業解禁となります。それまでにWebサイトやチラシの準備を進め、スタートダッシュに備えておくと良いでしょう。
Q8.「全国対応」とありますが、遠方(他府県)からの依頼でも本当に手続き可能ですか?
A8.はい、可能です。当事務所は電子申請による全国対応を実現しています。宅建業免許の申請先は営業所の所在地の都道府県になりますが、電子化の進展により、当事務所(奈良)から他府県の申請をオンラインで行うことができます。
ヒアリングは電話やZoom等で行い、書類の授受は郵送やメール添付で完結します。お客様ご本人が役所へ出向く必要も基本ありません。地域によって申請書類の様式や運用に若干の違いがありますが、そこは事前に各都道府県の手引きを取り寄せ精査しますのでご安心ください。「全国対応」とは言え各地域のルールを軽視することなく、地元の行政書士と同等以上の知識で対応いたします。もちろん、奈良・大阪など近畿圏のお客様については対面でのお打ち合わせも可能です。遠方の場合でも、必要があれば提携先の行政書士事務所と連携し現地調査等を行う体制も整えています。距離に関係なく高品質なサービスを提供いたしますので、日本全国どちらからでもお気軽にご依頼ください。
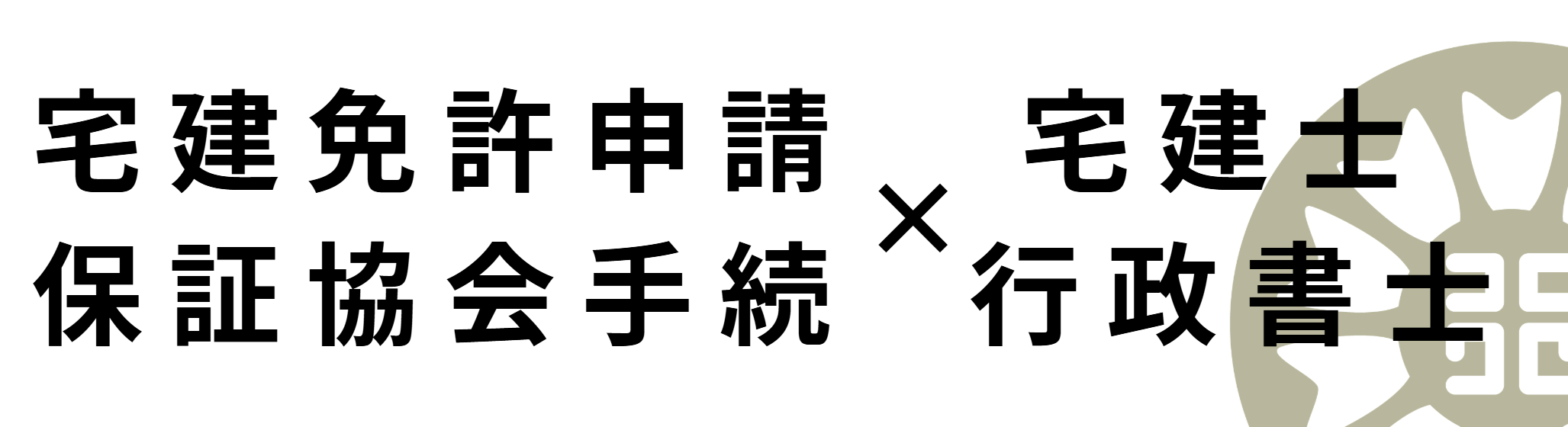
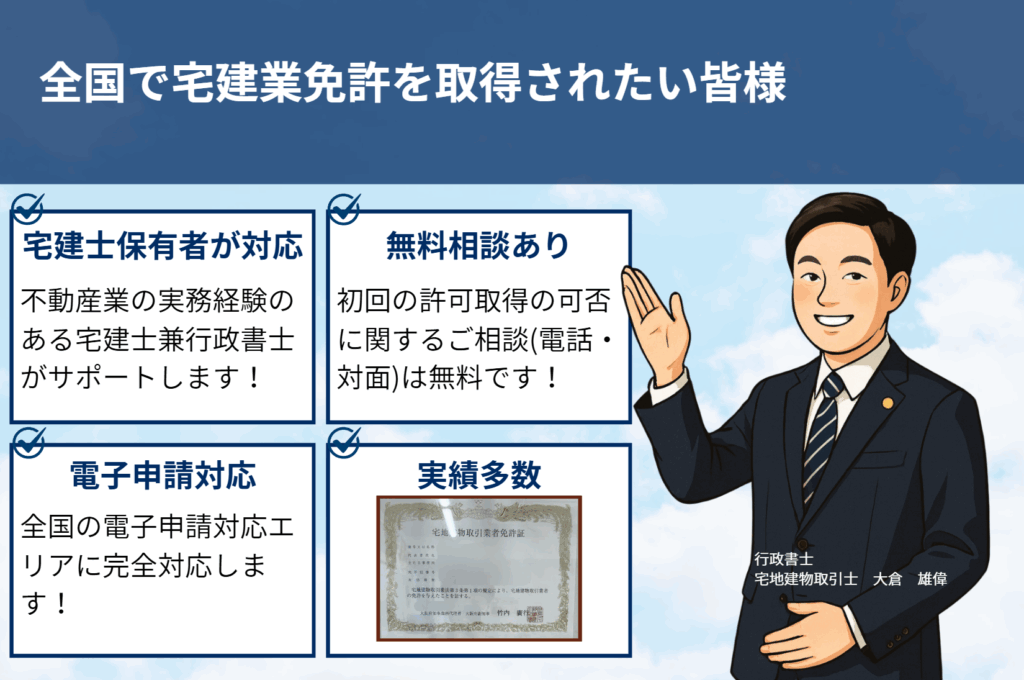
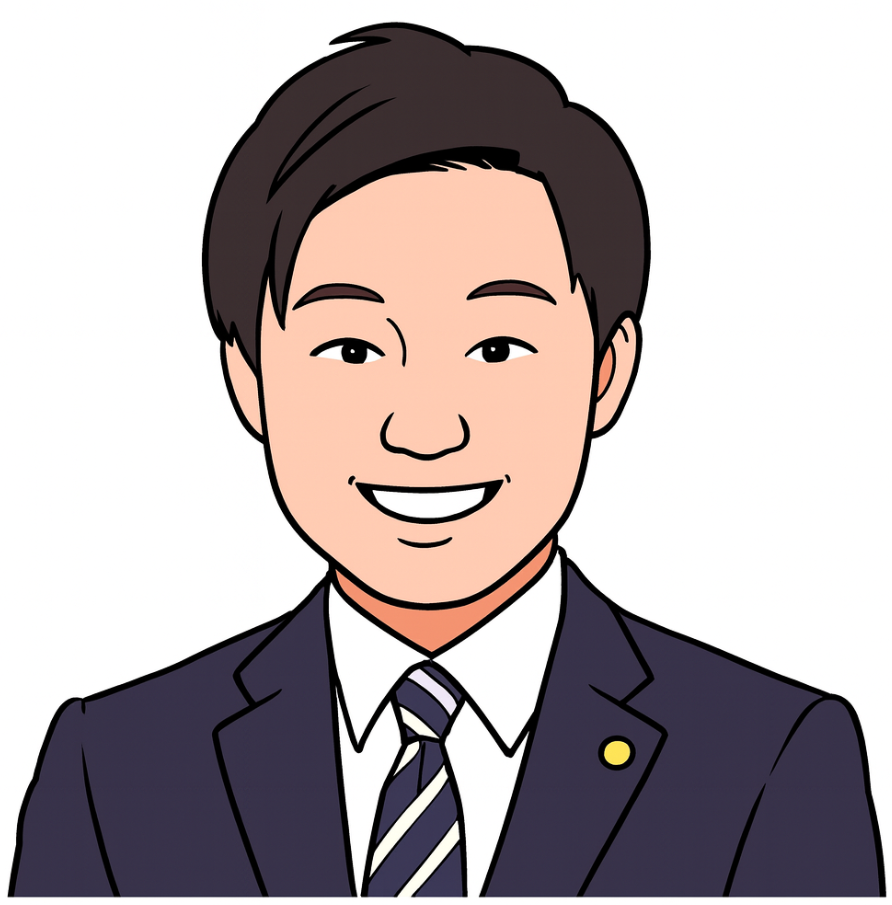
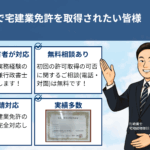
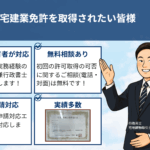
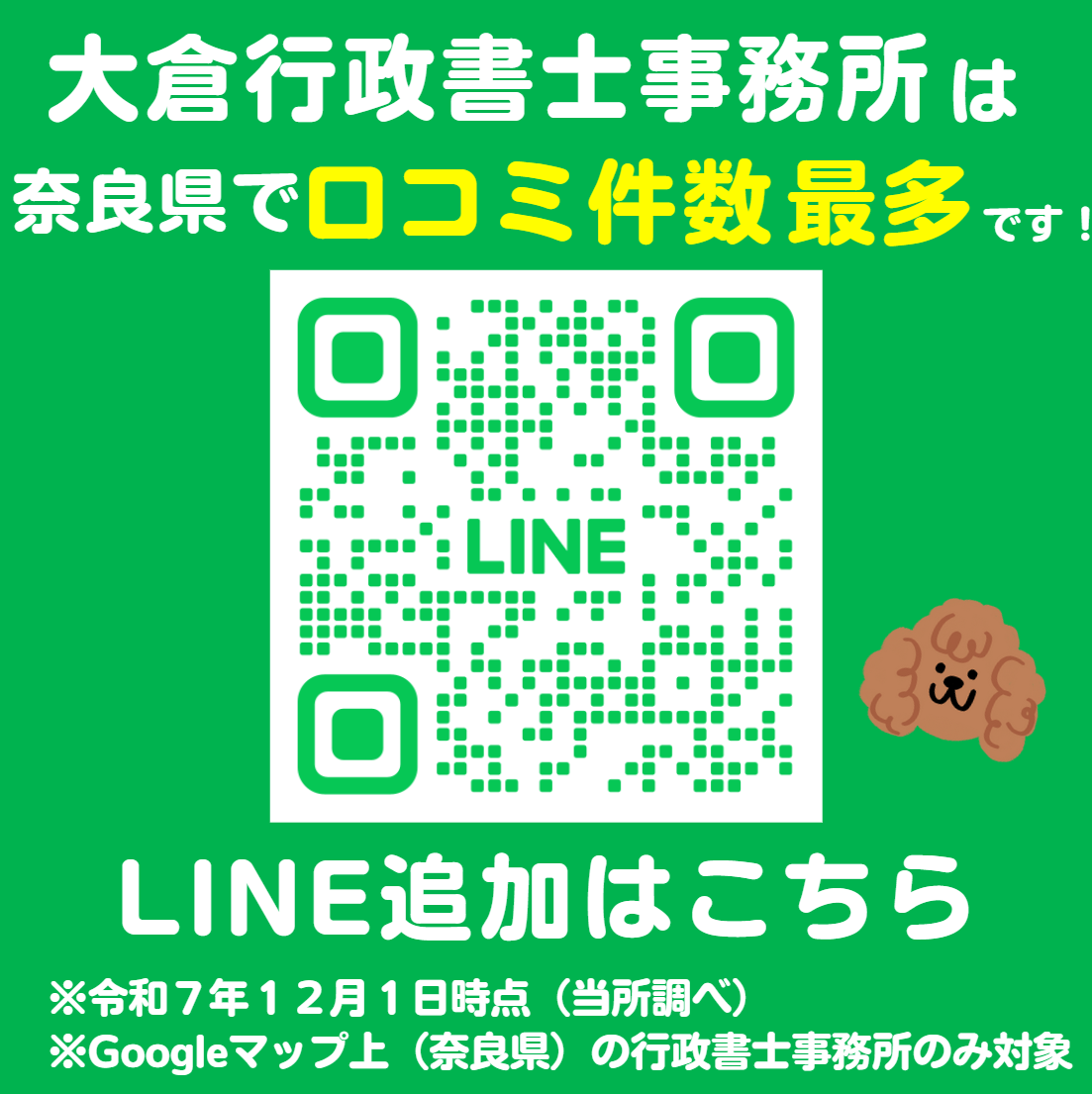
コメント