はじめに、不動産業を始めるにあたり、「宅建業免許(正式には宅地建物取引業の免許)が自分に必要かどうか」悩んでいませんか?免許が要る取引なのに無資格で営業すると宅建業法違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い罰則につながります。
一方で、すべての不動産取引に免許が必要なわけではなく、自分の物件を売るだけなど免許不要の例外もあります。本記事では「宅建業免許が必要となるケース」と「不要なケース」の線引きをわかりやすく解説し、免許が必要と判定された場合に確認すべき要件や、取得までのステップ・費用も説明します。
行政書士(宅建士資格保有)が監修しているので信頼性も万全です。免許の要否を判断できるチェックリストや、違反リスクの回避策、そしてプロに任せるメリットも紹介します。読み終えれば、ご自身のケースで免許がいるかいらないかスッキリ判定でき、その後に何を準備すれば良いかまで見通せます。それでは本題に入りましょう。
宅建業免許が“必要”になる行為の定義

宅建業免許が必要となる宅建業(宅地建物取引業)とは何かを定義します。ポイントは「対象となる物件(「宅地」または「建物」)」「取引の態様(自ら売買・交換、または代理・媒介)」そしてそれを「業(事業)として行うかどうか」の3つです。これらの要素をすべて満たす場合に免許が必要になります。
また「業として」の意味(不特定多数に対する反復継続)について誤解しやすい点を整理し、典型的に免許が必要なケースと、免許不要と勘違いしやすいグレーゾーンの例も紹介します。
宅建業の定義と3つの要素(宅地・建物/媒介・代理・自ら取引/業として)
まず「宅建業とは何か」を押さえましょう。法律上は「宅地又は建物について、次の行為を業として行うこと」を指します。
- 他人のために宅地または建物の売買・交換を行うこと
- 他人のために宅地または建物の賃貸の代理または媒介を行うこと
- 自己の物件を売買または交換することを業として行うこと
これらを簡単に言えば、不特定多数の人を相手に、土地や建物の売買・交換や賃貸の仲介を反復継続して行い、社会通念上事業とみなせる程度であれば宅建業に該当するということです。この3つの要素(対象物件・取引態様・業としての継続性)をすべて満たすとき、宅建業免許が必要となります。以下、それぞれの要素をもう少し具体的に説明します。
対象物件が「宅地」または「建物」かどうか
宅建業法で規定する「宅地」とは、簡単に言えば建物用の土地または現に建物のある土地のことです。一方「建物」は居住用・商業用問わず屋根と柱のある工作物(戸建て、マンション区分、倉庫など)を指します。
したがって、土地や建物以外(例:駐車場契約のあっせんのみ、太陽光パネル設備の売買等)は宅建業には該当しません。ただし更地であっても建物を建てる目的で取引される土地は「宅地」ですので注意しましょう。
取引態様が「自己の取引」か「代理・媒介」か
自分が当事者(売主・買主)となる売買や交換も取引に含まれます。一方、賃貸借については自ら貸主になる場合は取引に該当しません。他人同士の売買・交換・賃貸を仲介(媒介)したり代理する行為は、すべて宅建業法上の「取引」です。
まとめると、賃貸の貸主・借主本人として契約する場合(自社所有物件を貸し出す等)は宅建業ではないですが、売買や交換は自ら行っても宅建業に該当します。また第三者間の売買・賃貸をお手伝いする代理・仲介行為はすべて宅建業です。
「業として」(事業として反復継続して)行うか
1回きりの個人的な売買であれば宅建業と見なされませんが、それを反復または継続して行う意思・実態があれば「業」となります。ポイントは不特定の相手と繰り返すことです。例えば、自社の社員だけを対象に社宅のあっせんをする場合など対象が限定されていれば「不特定多数」とは言えず業に該当しません。
しかし友人や知人レベルであっても、特定の範囲に限定されていなければ対象が不特定と判断されるため、反復すれば業に該当します。また、営利目的かどうかは関係なく、仮に無償であっても不特定多数に反復継続すれば宅建業と見なされます。以上より、「不特定の相手に」「繰り返し」「利益を得る目的で」行う場合は免許が必要だと覚えておきましょう。
免許不要の例と誤解しやすい点

「一度だけなら免許は不要」と言われますが、1回でも反復の意思があれば業に該当します。また法人の場合、決算書に不動産売買収益が計上されていると審査で「宅建業に該当する取引では?」と疑われます。そのため実際は2回目以降でなくとも、継続的な事業と判断されれば免許が必要です。
免許不要の範囲に留めたいなら、不動産売買を臨時収入扱いにしないよう注意しましょう。
宅建業免許が必要な典型ケース(仲介業・買取再販・サブリース関連等)
ここでは、宅建業免許が必要となる代表的なケースをいくつか紹介します。当てはまる場合は迷わず免許取得を検討してください。
不動産仲介業全般
土地や建物の売買・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行うビジネスは、個人・法人問わず必ず免許が必要です。例えば不動産会社として第三者の物件を紹介し、契約を成立させて手数料を得る行為は宅建業そのものです。
賃貸専門の仲介業者や売買仲介業者はもちろん、知人の物件でも反復継続して仲介し対価を得るなら免許が必要です。
不動産の買取再販業
自ら不動産を買い取ってリフォーム・転売する、いわゆる「買取再販」も免許が必要です。自社が売主であっても、不特定の買主に反復して販売すれば宅建業に該当します。
たとえ自社保有物件でも、継続的に売買して利益を上げるビジネスモデルであれば免許を取得しなければなりません。「自分の物件だから大丈夫」は通用しない点に注意しましょう(1回限りの売却なら免許不要ですが、継続的なら必要となります)。
転貸+付随業務
物件オーナーから一括借り上げして又貸しするサブリース自体は、自社が貸主となるため宅建業ではありません(※詳細は後述)。しかし、サブリース業者がオーナーの代わりに他人に物件を紹介するような行為(例えば契約に至らなかった空室物件について第三者の賃借人募集だけ請け負う等)は、オーナーから見て仲介業務を委託している形になるため宅建業免許が必要です。
複数地域で事業展開する場合
1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合は各都道府県知事の免許で足りますが、2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合は「国土交通大臣免許」が必要です。たとえば本社が東京で支店を大阪に出す場合など、免許を知事免許から大臣免許へ切り替える手続きが求められます。
同一都道府県内でいくら支店を増やしても知事免許のままで構いませんが、エリアをまたぐ拡大時には免許区分の変更手続きを忘れないようにしましょう。
フランチャイズ加盟
有名不動産FC(フランチャイズ)に加盟する場合でも、自社が独立した法人・事業者である以上は自社で宅建業免許を取得する必要があります。フランチャイズ本部の免許で加盟店までカバーされることはなく、各社ごとに免許が求められます(本部が代理店として契約当事者になる特殊な形態を除きませんが、通常独立採算の加盟店は各社免許が必要です)。「フランチャイズに入るから免許なしで始められる」というのは誤解なので注意しましょう。
宅建業法に違反するとどうなる?無免許営業のリスク

宅建業免許が必要なのに無免許で営業を行うと、宅建業法第12条違反(無免許事業の禁止違反)となり、最も重い部類の罰則が科される可能性があります。その内容は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはその両方」という非常に厳しいものです。
例えば免許を持たずに賃貸物件の仲介業を行い手数料を得ていた業者が摘発されたケースもあります。また、免許を持たない人が「あたかも宅建業者であるように広告・表示すること」も禁じられており、これに違反した場合は100万円以下の罰金が科される規定があります。無免許のまま事業を行うリスクは事業停止や罰金だけでなく、信用失墜による廃業リスクにも直結します。必ず適法に免許を取得してから営業を始めましょう。
免許不要と誤解しやすいグレー例(自己物件の頻繁売却、副業仲介、親族間取引など)
次に、「免許はいらないだろう」と思われがちなグレーなケースを見てみましょう。以下のような場合は注意が必要です。
自社所有物件の頻繁な売買
自社で所有する不動産を売却する行為自体は「自ら売主」なので宅建業に該当しません。しかし、短期間に何度も売買を繰り返す場合は営利目的の転売とみなされ、たとえ自社物件でも業としての売買と判断される恐れがあります。
特に法人で不動産売買益が継続的に計上されていると行政庁から免許の有無を確認されます。年に数回以上の頻度で不動産売買を行うビジネスモデルであれば、「自社物件だから不要」とは考えず免許取得を検討すべきです。
副業で友人・知人の取引を仲介
知り合い同士の不動産売買を手伝って紹介料をもらうようなケースも、形式上は第三者間の媒介に当たります。一度限りで無報酬であれば直ちに宅建業とは言えないかもしれませんが、報酬を受け取った時点で業としての仲介行為と見なされる可能性が高いです。
特に繰り返し複数の友人知人の取引に関与すれば、不特定多数への媒介と判断され免許が必要になります。「友人相手だから大丈夫」は誤りで、たとえ好意でもお金を受け取るなら違法リスクがあります。
親族間だけの売買
親子や兄弟間など限定された範囲内の売買は、不特定多数相手ではないため基本的に宅建業には該当しません。しかし問題はその範囲を超えていないかです。例えば親族名義を利用して実質的に多数の第三者と売買しているような場合、免許逃れとみなされる可能性があります。身内同士の単発取引なら免許不要ですが、親族名義で反復売買するなどグレーな手法は避けましょう。
物件情報のマッチングサイト運営
最近は個人がSNSやウェブサイトで「買いたい人・売りたい人」を引き合わせ、成功報酬を得るビジネスも見られます。しかし、これも実質的に不動産の媒介行為に該当します。
単に情報掲示板を提供するだけならまだしも、成約時に報酬をもらえば免許無しでは違法です。過去には「ネットで不動産紹介します!」とSNS発信した無免許業者が摘発された例もあります。オンラインで完結しても宅建業は宅建業なので、報酬を得る以上は免許が必要と心得ましょう。
「名義貸し」での営業
免許を持たない者が、名義だけ宅建業者(免許保有者)に貸してもらって実態は自分で営業するケースがあります。これは厳禁ですし、法律上契約も無効となります。名義を貸した側の宅建業者も罰せられます。フランチャイズ本部や他の宅建業者の傘下で無免許営業することはできませんので、正規に免許を取得しましょう。
ITを活用した非対面取引
昨今はオンライン内見やIT重説(ITを利用した重要事項説明)など非対面で契約まで進める手法も普及しています。しかし、これらはあくまで手段がオンラインなだけで宅建業法の適用除外ではありません。
IT重説を行うにも宅建業者であり宅建士が説明することが前提です。したがって「ネットだけで仲介するからオフィスも免許も不要」といった解釈は成り立たず、オンライン完結でも免許と事務所は必要です。便利なIT活用と法令遵守は両立させましょう。
不動産会社社員としての副業
あなた自身が既に免許を持つ不動産会社に勤務している宅建士であった場合でも、会社の免許は会社の事業にしか使えません。勤務先とは別に個人で仲介を請け負うなら個人として免許が必要です。
また勤務先の物件を私的に仲介して紹介料を貰うのも同様にアウトです。宅建業者の従業員であること=自分が免許を持っているわけではない点に注意してください。
宅建業免許が必要だと判定された後の要件チェック

「自分は宅建業免許が必要だ」と分かったら、次は免許申請の要件を満たしているか確認しましょう。宅建業免許の取得には主に人的要件(専任の宅地建物取引士の設置、欠格事由に該当しないこと等)と物的要件(事務所の設置基準等)、そしてその他の要件(営業保証金の準備、標識の設置等)があります。
本章では特に重要な専任宅建士と事務所要件、および欠格要件(免許を受けられない事由)について詳しく解説します。それぞれチェックリスト形式で触れますので、免許申請前の自己診断にお役立てください。
専任宅建士の要件(常勤性・人数基準・登録の有効性等)
「専任の宅地建物取引士」とは、事務所ごとに設置が義務付けられた宅建士資格者のことです。免許を受けるには各事務所に最低1名以上の専任宅建士を置かなければなりません。ここでいう「専任」とは、その事務所に常勤し宅建業に専従することを意味します。
専任宅建士の具体的要件をチェックしましょう。
必要人数の基準
事務所の従業者(宅建業に従事する社員やスタッフ)の数に応じて5人に1人以上の割合で宅建士を置く必要があります。従業員が5人以下でも1名は必要、6~10人なら2名必要という具合です。※この人数算定はパートタイムでも原則含めますので注意してください。
宅建士資格の有効性
専任者となる人は有効な宅建士証を持っていなければなりません。宅建試験に合格しただけでは不十分で、都道府県に登録して交付される「宅地建物取引士証」(有効期限5年)を取得している必要があります。新規免許申請ではこの宅建士証のコピー提出を求められます。証明写真付きの宅建士証が手元にある状態にしておきましょう。
常勤性の確保
専任宅建士は他の仕事との掛け持ちが禁止されています。例えば、別会社の役員を兼任していたり、週数日の非常勤勤務しかできない人は専任とは認められません。基本は免許申請者の事務所にフルタイム勤務できる人を充てます。行政庁によっては念のため兼業状況の申告や就労証明書の提出を求める場合もあります。
名義貸しの禁止
宅建業同様に、宅建士資格者が名前だけ貸して実際は勤務していない、いわゆる「宅建士の名義貸し」は重い処分対象です。常勤でその事務所に勤務していないと判明した場合、免許申請は不許可・免許取消につながります。よって、社長自身が宅建士の場合は社長が専任になって構いませんが、別の事業で日中不在になるようでは認められません。毎日事務所に勤務できる人を選任しましょう。
複数事務所の場合
支店ごとに専任宅建士を配置する必要があります(本店にも必要)。人材が足りない場合は、免許取得前に採用や資格取得を進め、人員計画を整えてから申請しましょう。宅建士が退職して要件を満たせなくなった場合、2週間以内に補充しないと業務停止処分の可能性があります。継続的に基準を維持するよう気を付けてください。
事務所要件の実務(独立性・継続性・設備、マンション一室の可否等)
宅建業を営むには事務所(営業所)を設置する必要があります。「事務所」と認められるには宅建業法ならではの要件がありますので確認しましょう。
独立した専用スペース
住宅や他の店舗と区切られていない空間は事務所と認められません。例えば自宅の一室を事務所にする場合、居住スペースと明確に分離された空間である必要があります。居間の一角に机を置いただけでは不可です。
具体的には、壁や扉で仕切られた専用室であることが望ましく、少なくとも家族の生活空間とは区切られていなければなりません。
恒常的に業務ができる設備
事務所には宅建業を遂行するための設備が整っていなければなりません。具体的には、応接用の机や椅子、契約書類を保管する棚やPC、電話・FAX回線などです。特に固定の電話番号は重要視されます(携帯電話のみでは不可とする都道府県もあります)。
さらに宅建業者票(免許証番号等を記載した標識)を掲示できることも必要です。開業後は従業者名簿の備え付けなども義務付けられます。
看板・標識の表示
事務所には宅地建物取引業者であることを示す標識を掲げる義務があります(いわゆる業者票)。免許証番号や免許権者(知事or大臣)などを記載した標識を見えやすい場所に設置しなければなりません。自宅兼事務所の場合も表札や入口に業者票を掲げる必要があります。近隣に遠慮して表示しないのは違法となるので気を付けましょう。
マンションの一室でも可能
賃貸オフィスやマンションの一室を事務所にすること自体は問題ありません。ただし建物の管理規約を確認してください。住居専用物件で事務所利用が禁止されている場合、宅建業法上の事務所要件を満たせず免許が下りません。
契約前に用途制限のない物件か確認しましょう。また、賃貸借契約書に事務所利用の許可を明記してもらうことも大切です。
バーチャルオフィス・レンタルスペースは不可
郵便転送のみのバーチャルオフィスや、時間貸しの会議室などは事務所とは認められません。常設の拠点であることが要件です。コワーキングスペースの場合も、自社専用ブースを借り切って恒常的に使える形でなければ難しいでしょう。他業者と共同で使用する事務所も基本的に不可です。
欠格要件とチェック方法(役員・政令使用人・破産・罰金刑等)
欠格要件とは、「この条件に該当する人は免許を与えられない」というNG要件です。免許申請者(法人の場合は役員全員と政令で定める使用人※)及び宅建業に一定の影響力を持つ関係者について、この欠格事由に該当しないことが求められます。主な欠格要件をリストアップしますので、事前に自己チェックしましょう。
成年被後見人・被保佐人
精神上の障害等で判断能力が不十分として後見や保佐の審判を受けている人は免許を取得できません。また、未成年者も原則として免許不可ですが、法定代理人の同意を得て事業を営む場合など例外もあります(未成年で会社代表になるケースは稀でしょう)。
破産者で復権を得ていない
自己破産して免責許可(復権)を受けていない人は免許不可です。法人であれば破産手続開始決定を受けた時点で免許失効します。代表者が破産している場合も当然アウトです。
一定の法令違反経歴
不動産・金融に関する法令等で重い刑事処分を受けた人は、処分終了から5年間は免許が下りません。具体例として、禁錮以上の刑を受け服役・執行猶予中の期間や、宅建業法違反や暴力行為等で罰金刑を受けてから5年以内の期間などです(執行猶予付き判決の場合は猶予満了から5年)。また、過去に免許取消処分を受けてから5年経っていない者も欠格です。
暴力団員等反社会的勢力
申請者や役員等が暴力団員である場合、または過去に暴力団員であって5年経過しない場合も免許は不可です。さらに、暴力団と密接な関係を有する者も拒否される可能性があります。いわゆる暴排条例等に抵触する人を経営陣に含めてはいけません。
不正・不誠実な行為のおそれが明らかな場合
これは少し抽象的ですが、行政庁が「この人は不正な取引をしそうだ」と判断する事由です。過去に他の業法で行政処分を受けた履歴や、詐欺的商法に関与していた経歴などがあると問題視されます。特に「宅建業に関し不正または不誠実な行為をした者」は欠格と規定されています。心当たりがある場合は専門家に相談してください。
※「政令で定める使用人」とは
法人の場合支店長などの営業現場責任者を指します。これらの人も役員と同様に欠格要件チェックが行われます。さらに法人申請では主要株主(筆頭株主など)の身分も調査されることがあります。
宅建業免許が必要な場合・不要な場合/よくある質問(FAQ)
最後に、宅建業免許の要否や取得手続きに関して寄せられることの多い質問と回答をまとめます。
Q1.副業で友人の不動産売買を手伝う程度なら、宅建業免許は必要ありませんか?
A1.報酬を受け取るか、反復して行うなら必要です。単発で知人の売買を手伝い、しかも報酬ゼロであれば直ちに宅建業とは言えないかもしれません。しかし、1度でも成功報酬を受け取れば媒介行為に当たります。宅建業法は無報酬でも反復継続すれば業とみなす規定ですので、「副業程度」の認識でも実態が仲介ビジネスになれば免許が必要になります。違反すれば罰則もありますので、友人相手でも謝礼をもらうなら注意が必要です。迷う場合は専門家に相談して判断しましょう。
Q2.サブリース(不動産の又貸し)事業を始める際、宅建業免許は要りますか?
A2.原則として不要です。サブリースは自分が借りた物件を自分が貸主となって転貸するビジネスモデルです。宅建業法上は「自ら貸主」の行為なので、代理・媒介には該当せず免許は原則不要となります。ただし、「免許不要=ノールール」ではありませんのでご注意ください。なお、サブリースでもオーナー代理の入居者募集など宅建業に該当する業務を併せて行う場合は免許が必要になることもあります。
Q3.ウェブサイトで物件情報をマッチングさせ、成約したら成功報酬を得るだけなら無免許でも大丈夫?
A3.いいえ、それは宅建業に該当し免許が必要です。単なる広告掲載プラットフォーム提供で、契約関与も報酬も一切ないなら免許不要ですが、成約時に報酬を受領する時点で媒介行為とみなされます。最近はIT企業が不動産マッチングサービスを展開する例もありますが、実質仲介業と同じなら免許を取得して運営しています。仮に無免許で成功報酬を受け取れば不法な無免許営業となり、罰則の対象です。また無免許の者が「物件紹介できます」「不動産仲介やります」と広告表示するだけでも法律違反です。以上より、そのビジネスモデルで続けるならまず免許を取得すべきです。
Q4.宅建業の事務所は自宅の一室でも構築できますか?
A4.条件を満たせば可能です。自宅兼事務所とする開業者も多数います。ただし事務所要件を満たすよう工夫が必要です。まず、居住スペースと明確に区切られた専用空間を用意してください。扉付きの独立部屋であることが望ましいです。次に、マンションの場合は管理規約上「事務所利用可」であることを確認します。
Q5.個人で免許を取って営業していましたが、法人化する場合はどうなりますか?
A5.法人として新たに免許を取り直す必要があります。宅建業免許は営業主体(名義人)ごとに与えられるため、個人事業主としての免許を法人へ「引き継ぐ」ことはできません。具体的には、新しく設立した法人名義で新規免許申請を行い、免許交付を受ける必要があります。
その際、個人で営んできた実績は特に考慮されませんので、改めて要件を満たすこと(法人の役員の欠格要件チェック、事務所や専任宅建士の体制整備等)が必要です。一般的には法人設立後、個人から法人へ事業を引き継ぎながら並行して法人免許の許可を待つ形になります。個人名義の免許は法人免許取得後に廃業届を出すことになるでしょう。いずれにせよ法人化=免許も新規取得という点をお忘れなく。
Q6.免許取得後に新しく支店を出したら、どんな追加手続きが必要ですか?
A6.同一都道府県内の支店なら変更届、他都道府県に出すなら大臣免許への切替が必要です。まず、支店(従たる事務所)を設置する際は免許行政庁へ変更の届出を行います。届出には新事務所の所在地・専任宅建士情報などを記載します。同じ都道府県内であれば免許番号はそのままで届出のみでOKです。ただし他の都道府県に支店を出す場合、現在の知事免許から国土交通大臣免許に切り替える申請が必要となります。
また、新支店分の営業保証金の追加供託または保証協会への追加分担金納付も必要です。支店1箇所につき供託なら500万円追加、協会なら30万円追加納付となります。さらに支店ごとに宅建士の設置や標識の掲示も忘れず行ってください。
ここまで、宅建業免許が必要な場合・不要な場合の判断基準から、免許取得の具体的な要件や手続きまで詳しく説明しました。初めて免許申請に挑戦する方にとって、法令用語や準備事項の多さに戸惑われたかもしれません。しかし、本記事のポイントを押さえれば「自分で免許が必要かどうか」の判断はつくはずですし、必要となった場合にも何を準備すべきか全体像が見えたのではないでしょうか。
宅建業免許申請は当事務所にお任せください

当事務所(大倉行政書士事務所)では、この記事の監修者である行政書士(宅地建物取引士有資格者)が、免許が必要か否かの初期相談から申請書類作成、申請後のフォローまで一貫対応しております。不動産業界での実務経験を活かし、現場目線でスピーディーかつ的確にサポートすることで、最短スケジュールでの免許取得を目指します。
料金も明朗会計で追加費用は一切いただきません。全国オンライン対応しておりますので、遠方からのご依頼もお気軽にどうぞ。宅建業免許の取得・活用は不動産ビジネス成功の第一歩です。ぜひプロの力も活用しながら、円滑な開業を実現してください。最後までお読みいただきありがとうございました!
お問い合わせ
料金
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。
【関連記事】
>宅地建物取引業免許申請「大阪」
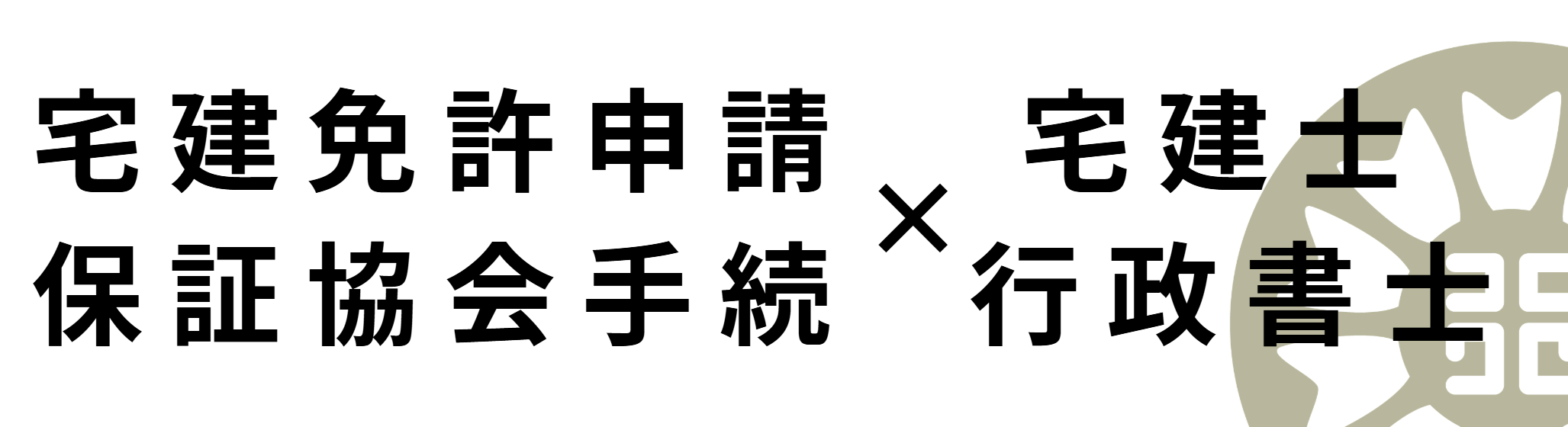
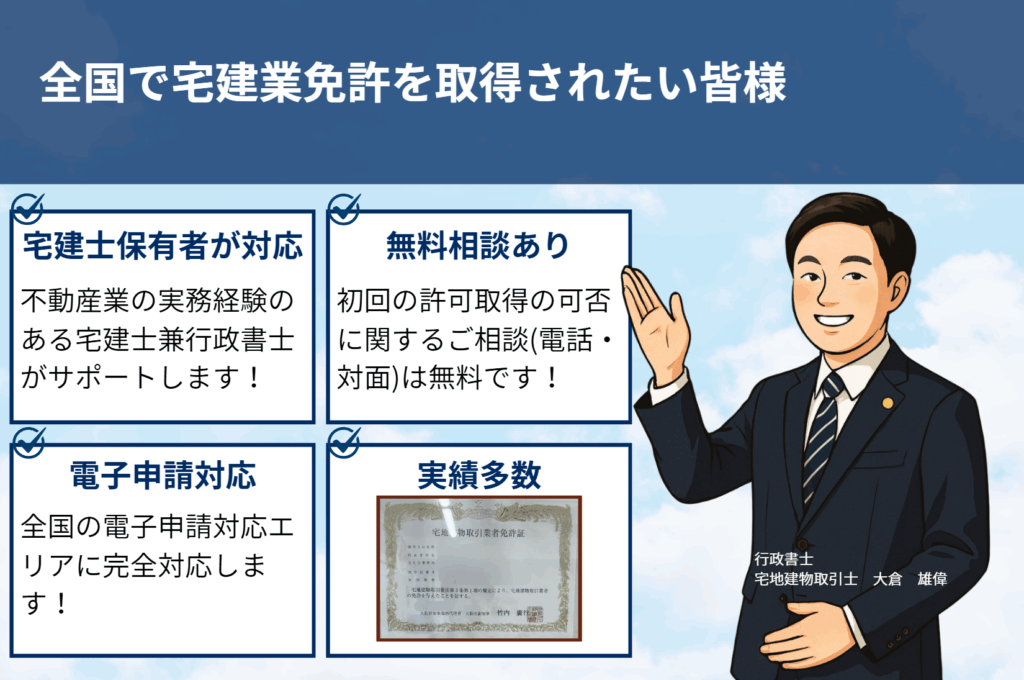
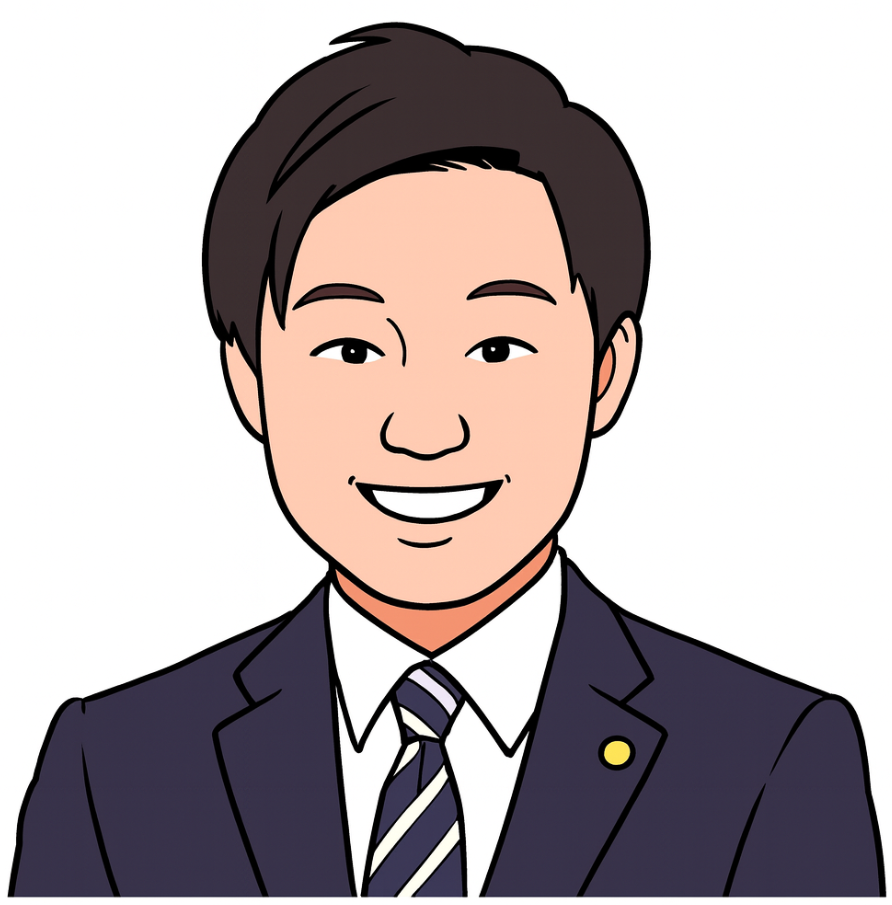
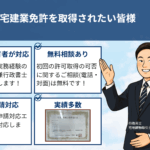
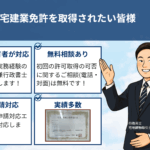
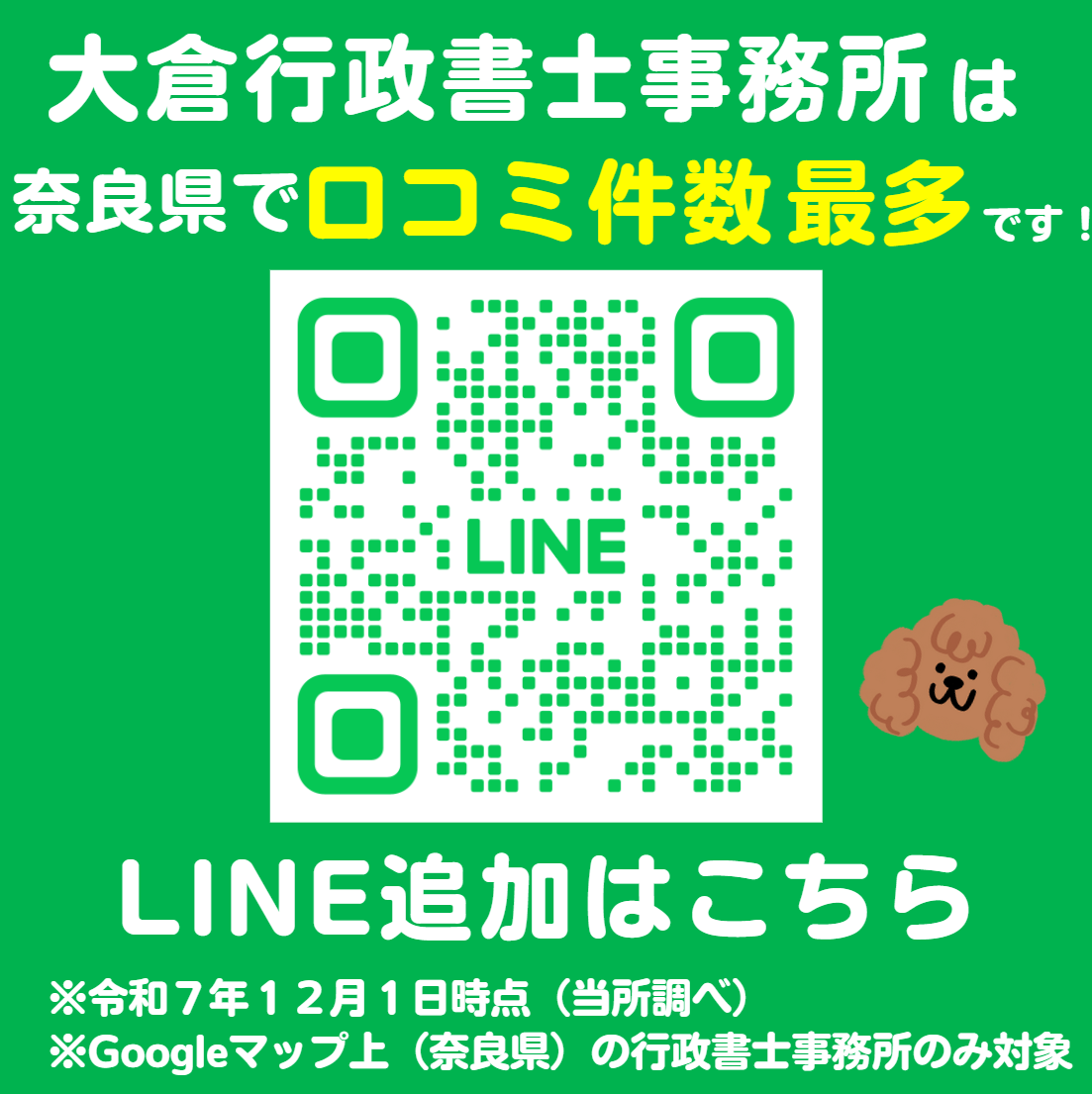
コメント