不動産業を開業するとき、「個人事業主として始めるべきか、それとも法人(会社)を設立すべきか」で悩む方は多いでしょう。宅地建物取引業(いわゆる不動産業)を営むには、必ず「宅地建物取引業の免許」(宅建業免許)を取得しなければなりません。
この宅建業免許は個人でも法人でも取得でき、それぞれ手続き上の特徴や開業後の運営面でメリット・デメリットがあります。個人で開業するか法人で開業するかは、資金計画や事業規模、社会的信用力などの観点から慎重に検討する必要があります。
本記事では、宅建業免許の観点から、個人で不動産業を開業する場合と、法人で開業する場合の違いをわかりやすく解説します。奈良県・大阪府をはじめ近畿圏で宅建業免許の取得を目指す方に向けて、スムーズに免許を取得するためのポイントや、行政書士に依頼するメリットもご紹介します。ぜひ開業形態の判断材料として最後までお読みください。
宅建業免許の基本:知事免許・大臣免許と個人・法人

このトピックでは、不動産業を始める際に必要な「宅建業免許」の基本について確認します。
宅建業免許には、営業所の所在地によって「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があります。
免許の種類によって申請先は異なりますが、どちらの免許でも効力に差はなく、日本全国で宅建業を営むことが可能です。また、免許を取得する主体は個人でも法人でも可能です。まずは、免許の種類と個人・法人での申請上の違いを押さえておきましょう。
宅建業免許とは?
「宅地建物取引業」(略して宅建業)を営むために必要な許可が宅地建物取引業免許です。宅建業とは、不特定多数を相手に土地や建物の売買・交換、賃貸のあっせん(仲介)などを事業として行うことを指します。
宅建業法により、これらの宅建業を行うには国や都道府県から免許を受けなければなりません。無免許で不動産の取引仲介等の営業を行うと罰則が科されるため、不動産業を始める際は必ず事前に免許を取得する必要があります。この免許を取得して初めて正式に宅建業者(不動産業者)として活動できるようになります。
なお、宅建業免許の有効期間は5年間で、引き続き営業を行う場合は有効期限満了前に更新手続きを行う必要があります。免許申請が受理されてから実際に免許が下りるまでには、都道府県知事免許でおおむね30日~45日程度、国土交通大臣免許では約60日程度を要します。
知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許には、事務所の設置形態に応じて都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。簡単に言えば、営業所(事務所)が1つの都道府県内にしかない場合は知事免許、営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣免許となります。
例えば、奈良県内または大阪府内のみに事務所を設けて営業するなら奈良県知事免許や大阪府知事免許を取得します。一方、大阪府と奈良県の両方に営業所を置く場合や、関西と関東など複数の地域に事務所を展開する場合は、国土交通大臣免許を取得することになります。
知事免許と大臣免許で免許の効力(全国で営業可能かどうか等)に差はありませんが、申請先や手数料が異なります。免許申請の提出先は、知事免許の場合は各都道府県庁の担当窓口、国土交通大臣免許の場合は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県経由で国への申請となります。
申請の細かな手続や必要書類は各都道府県の「宅建業免許申請の手引き(奈良の場合はこちら)」などで案内されていますので、事前によく確認しましょう。なお、新規申請時の法定手数料は、都道府県知事免許で33,000円、国土交通大臣免許で90,000円です。(※知事免許の場合は各都道府県の収入証紙で納付、大臣免許の場合は収入印紙で納付するのが一般的です。)
免許証の番号表記は、知事免許の場合「○○県知事(1)第○○○○号」、大臣免許の場合「国土交通大臣(1)第○○○○号」といった形式になります(括弧内の数字は免許の更新回数で、新規時は(1)となります)。
個人でも法人でも取得可能
宅建業免許は、個人(個人事業主)であっても法人(会社)であっても取得することができます。免許取得のための基本的な条件(要件)は個人・法人で大きな違いはありません。
例えば、各事務所ごとに専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置すること、事務所として利用できる施設を用意すること、申請者や役員が破産や一定の犯罪歴などの欠格事由に該当しないこと、そして営業保証金の供託(または保証協会への加入)による保証措置を講じること等は共通の要件です。
ただし、個人申請と法人申請では細部で次のような違いがあります。
宅建士の設置方法
法人では代表者自身が宅建士でなくても、専任の宅建士となる人材(従業員)を雇用すれば免許申請できます。個人で申請する場合は、基本的に申請者本人が宅建士資格を持ち専任宅建士となることが求められます。
申請者の範囲
法人の場合、代表取締役など役員全員や政令で定める使用人(支店長等)について欠格事由がないことを確認する必要があります。そのため、役員全員の身分証明書や登記されていないことの証明書などを提出します。個人の場合は申請者本人のみが審査対象となり、提出書類も本人に関するものが中心です。
会社設立の有無
法人で開業する場合、免許申請に先立って会社を設立(登記)しておく必要があります(株式会社や合同会社等)。一方、個人事業主として開業する場合は会社設立の手続きが不要で、税務署への開業届の提出だけで事業を開始できます。
個人事業主として宅建業を開業する場合

このトピックでは、個人事業主(個人名義)で不動産業を開業するケースについて解説します。
個人で宅建業免許を取得するための条件や手続き上のポイント、そして個人で開業することのメリット・デメリットを見ていきましょう。
なお、個人名義で宅建業を営む方もいますが、全体としては法人名義の不動産会社が多数派です。全国的にも宅建業者の約8割は法人経営で、個人で開業しているのは約2割程度と言われています。
特に地域密着の賃貸仲介など、小規模な不動産業では個人で開業している例も見られます。例えば、一人で地元の賃貸仲介業を営み、地域で信頼を得ている個人事業主も存在します。
個人で宅建業免許を取得するための条件
個人事業主として宅建業免許を申請する場合、基本的な要件は前述のとおり法人の場合と共通です。ここでは、個人ならではの留意点や必要な手続きについて整理します。
専任の宅建士の確保
個人で開業する場合、申請者本人が宅地建物取引士の資格を持ち、自ら専任の宅建士になるケースが一般的です。
事務所の設置
事業用の事務所を用意しなければなりません。自宅を事務所にする場合でも、「宅建業者」としてふさわしいスペースを確保する必要があります(契約書類や帳簿を備え付け、標識を掲示できる環境であること)。賃貸物件を事務所とする場合は、不動産業の事務所用途で使用可能か契約書の用途欄なども確認が必要です。
欠格事由がないこと
申請者本人が、宅建業法で定める欠格事由(破産して復権を得ていない、禁錮以上の刑に処され5年経過していない、暴力団関係者でない等)に該当しないことが求められます。身分証明書や登記されていないことの証明書などを取得して提出し、自身に欠格事由がないことを証明します。
営業保証金の供託または保証協会加入
免許が下りた後、営業を開始するまでに営業保証金を法務局に供託するか、保証協会に加入して分担金を納付する必要があります。金額は主たる事務所で1,000万円(供託の場合)ですが、保証協会に加入すれば大幅に軽減され、通常は本店分60万円(支店は1箇所ごとに30万円)の分担金納付で済みます。
多くの事業者は保証協会を利用します。(※免許取得後3か月以内に保証金の供託または協会加入を行わないと免許が取り消されるので注意してください。)
その他の必要書類
上記のほか、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村が発行する証明)、登記されていないことの証明書、直近の納税証明書(税務署発行)など、個人に関する各種証明書類を揃える必要があります。
個人で開業するメリット
個人事業主として宅建業を始めることには、次のようなメリットがあります。
会社設立費用が不要
法人を設立する場合に必要な登録免許税(株式会社なら約20万円)や定款認証費用などがかかりません。個人であればこれらの初期費用を節約できます。
手続きがシンプルで早い
開業にあたり会社の登記手続きが不要なため、その分スピーディーに準備が進められます。税務署への開業届を提出すれば事業を開始でき、宅建業免許も個人名義ですぐに申請可能です。
小規模・副業でも始めやすい
事業規模が小さいうちは個人事業の方が身軽です。本業のかたわら副業的に不動産仲介をするケースや、地元密着の小さな不動産屋を開く場合でも、個人であれば柔軟にスタートできます。(代表者や取引士の常駐は必須ですが。)
運営コストが低い
法人に比べ、毎年の維持費用を抑えられます。例えば法人だと毎年赤字でも均等割の法人住民税(最低7万円程度)の支払いが必要ですが、個人事業主にはこうした固定費はありません。また、従業員を雇わない限り社会保険への加入義務もないため、人件費面でもコストをコントロールしやすいです。
廃業・撤退が容易
万一、不動産業をやめる場合でも、個人事業であれば廃業届を出すだけで手続きが完了します。法人の場合は解散・清算などの手間や費用がかかりますが、個人事業主であれば事業の終了も比較的簡単です。
個人で開業するデメリット
一方で、個人名義で宅建業を営むことには以下のようなデメリットや制約もあります。
社会的信用力が低い
個人事業主よりも法人の方が対外的な信用が高い傾向にあります。不動産取引では高額な契約も多く、取引相手や顧客から「会社組織ではないと不安」と見られるケースがあります。特に金融機関から融資を受けたい場合、個人事業だと不利になることがあります。
事業拡大に限界がある
個人で営業できる範囲にはどうしても限りがあります。営業所を増やして多店舗展開する際も、個人事業主のままでは管理が難しく、人材採用においても法人に比べハンデを負う可能性があります。将来的に事業規模を大きくしたい場合は、途中で法人化を検討する必要が出てくるでしょう。
税務上のメリットが少ない
利益がある程度大きくなると、法人の方が税率面で有利になるケースが多いです。個人事業主の所得税は累進課税で最高税率が高く設定されているため、事業が軌道に乗り利益が増えてくると税負担が重くなりがちです。法人化すれば経費計上の幅が広がり、利益を分散することで節税の余地が生まれる場合があります。
事業の継続性に不安
個人名義の宅建業免許は事業主個人にひも付いているため、例えば事業主に万一のことがあれば免許は失効してしまいます。家族や従業員が後を継ぎたくても、免許を承継する制度はなく、新たに免許を取り直す必要があります(法人であれば役員交代等で事業継続が可能)。
法人(会社)として宅建業を開業する場合

このトピックでは、株式会社や合同会社など法人を設立して宅建業免許を取得し、不動産業を開業するケースを解説します。
法人で開業するための要件や、法人化することのメリット・デメリットを確認しましょう。
不動産業界では企業として事業を行う方が一般的であり、その理由についても触れていきます。現在、宅建業者(不動産会社)の多くは法人形態をとっていますが、それには上述したような利点があるためです。
法人で宅建業免許を取得するための条件
会社(法人)を設立して宅建業免許を申請する場合、基本的な要件は個人の場合と同様ですが、法人特有の準備や必要書類があります。
会社設立と登記
まず宅建業を営む会社(株式会社や合同会社等)を設立し、法務局で登記を完了させる必要があります。会社の商号に「不動産取引所」など禁止ワードが含まれていないかも確認が必要です(不適切な場合は変更しなければなりません)。
専任の宅建士の配置
法人の場合、代表者自身が宅建士の資格を持っていなくても問題ありません。ただし、各事務所に1名以上の専任宅建士を確保することは必要です。
代表者または役員の中に有資格者がいない場合は、従業員として宅建士資格者を雇用し、専任の宅建士に充てます(※業務に従事する者5名に対し1名以上の割合で宅建士を置く必要があります)。
役員等の欠格事由の確認
法人申請では、代表取締役をはじめ役員全員および政令で定める使用人(支店長等)について、欠格事由に該当しないことを証明する必要があります。
各役員の身分証明書、登記されていないことの証明書などを取得し、提出します。ひとりでも欠格事由に該当する役員がいると免許は下りません。
営業保証金の供託または保証協会加入
営業保証金制度は法人でも同様です。免許取得後、主たる事務所ごとに1,000万円(支店は1箇所につき500万円)を法務局に供託するか、不動産保証協会等に加入して分担金(本店60万円、支店30万円)を納付します。(※免許交付から3か月以内に保証金供託または協会加入の届出を行わないと免許が取消となるので注意が必要です。)
その他必要書類
法人申請では、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や定款の写し、役員の略歴書、納税証明書(法人設立初年度は不要な場合あり)などを準備します。これらに加え、専任宅建士となる者の宅建士登録証の写しや身分証明書類も必要です。
法人で開業するメリット
法人(会社)形態で宅建業を営むことには、以下のような利点があります。
社会的信用が高い
会社組織であることで、取引先や顧客からの信頼度が増します。不動産取引では高額な案件も多いため、法人格がある方が安心感を持たれやすい傾向があります。また、金融機関からの融資を受けやすくなる点も大きなメリットです。
事業の継続性・拡張性
法人は代表者や役員が交代しても会社自体は存続します。個人事業のように事業主の死亡や引退で免許が消滅することがないため、長期的な事業継続が可能です。また、支店を増やして他地域に進出する場合や、多くの従業員を抱えて事業拡大する場合でも、法人形態の方が組織的に運営しやすくなります。さらに、採用においても、会社組織の方が優秀な人材を確保しやすい傾向があります。
責任が限定される
法人が有限会社の場合、会社の債務や損害賠償責任が原則として会社財産の範囲内に限定されます。万一事業上のトラブルで多額の債務や賠償が発生した場合でも、適切に法人と個人を分けていれば、事業主個人の資産まで及ぶリスクを軽減できます。
節税や資金調達の選択肢
法人の方が経費計上や所得分散などの手段によって、税負担をコントロールしやすい場合があります。利益を社内留保したり、役員報酬として支給して所得を分散するなど、事業規模や利益に応じて柔軟な税務戦略を取りやすいです。また、株式発行による資金調達や外部投資の受け入れも法人ならではの選択肢です。
ブランド戦略
法人格を持つことで、法人名で銀行口座を開設したり契約を結んだりでき、対外的なブランドイメージを構築しやすくなります。会社のウェブサイトや名刺においても、株式会社〇〇不動産といった名称は顧客に安心感を与える材料となるでしょう。
法人で開業するデメリット
もちろん、法人化には次のようなデメリットや注意点もあります。
設立・維持にコストがかかる
会社設立には登録免許税や認証費用などまとまった資金が必要です。また、設立後も毎年、決算申告に伴う税理士費用や、赤字でも発生する法人住民税(均等割)など固定費がかかります。小規模事業の場合、この負担が利益を圧迫することもあります。
事務手続きが煩雑
法人は各種届出や帳簿の記帳義務など、個人事業に比べ事務手続きが増えます。決算報告や税務申告も複雑で、専門知識が必要です。経理・総務の体制を整える必要があり、事務管理コストがかさむ可能性があります。
社会保険の加入義務
法人を設立すると、経営者や従業員に対して厚生年金・健康保険など社会保険への加入義務が生じます(従業員がいなくても、役員報酬を支給する場合は加入対象)。保険料の事業主負担分は人件費として毎月発生するため、個人事業では不要だったコストが追加されます。
宅建士の人材確保
法人の場合、代表者自身が宅建士でないケースでは、有資格者を採用して専任宅建士に充てる必要があります。創業時から資格者を雇用することは、人件費の負担や適切な人材の確保といったハードルになる可能性があります。
撤退時の手間
事業をやめる場合、法人では解散・清算といった手続きが必要で、時間と費用がかかります。個人事業のように届出一枚で事業終了、とはいきません。
個人と法人どちらで宅建業を開業すべきか?

最後に、個人事業主と法人のどちらで宅建業を開業するのが適しているか、その判断ポイントを整理します。また、一度個人で開業した後に法人化する場合の注意点や、宅建業免許申請を専門家(行政書士)に依頼するメリットについても見ていきましょう。
開業形態を決める判断ポイント
個人で始めるか法人で始めるか迷ったときは、事業の規模や目的に応じて選択すると良いでしょう。一般的に、次のようなケースでは個人事業主として開業するメリットが大きいと考えられます。
- 副業や小規模な形でスタートしたい
- できるだけ初期費用やランニングコストを抑えたい
- 地域密着の賃貸仲介など、限られた範囲での営業を想定している
一方で、以下のようなケースでははじめから法人(会社)を設立した方が有利と言えます。
- 将来的に複数の営業所を展開したい
- 金融機関からの融資を活用して事業規模を拡大したい
- 売買仲介や不動産開発など大規模な取引を予定している
個人開業から法人化する場合の注意点
最初は個人事業で始めたものの、後に会社設立(法人化)するケースもあるでしょう。この法人成りにあたって注意すべきなのは、宅建業免許は個人から法人へ引き継ぐことができないという点です。
個人名義の免許とは別に、新たに法人名義で免許を取得し直す必要があります。その際、改めて申請手数料(知事免許で33,000円)を支払い、保証協会の分担金も法人として再度納め直す必要があります(個人で供託した営業保証金は法人では流用できません)。
免許番号も個人時代とは別の新しい番号が付与されます。場合によっては、個人の免許を一旦廃業してから法人で新規申請をする流れとなり、営業を一時中断せざるを得ないこともあります。(※自治体によっては、一定の条件下で個人免許を維持したまま法人免許の新規申請を受け付ける特例的な取扱いがある場合もあります。いずれにせよ免許自体は別物となります。)
したがって、近い将来に法人化を視野に入れている場合は、最初から法人で免許を取得する方が手続きの重複やコストの無駄がなくスムーズです。なお、法人から個人に切り替える場合(いわゆる「個人成り」)も、同様に一度法人を廃業し、新たに個人免許を取得する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
宅建業免許の申請手続きは、多くの書類準備や複雑な要件の確認が必要です。はじめての方にとって負担に感じる部分も多いでしょう。そこで頼りになるのが、宅建業免許申請に精通した行政書士です。プロに依頼すれば、手続きを円滑に進め、書類の不備による差し戻し等を防ぐことができます。
当事務所(行政書士)は奈良県・大阪府を中心に宅建業免許の新規申請を全国対応でサポートしております。当事務所にご依頼いただくメリットは次のとおりです。
宅建士資格を持つ行政書士が対応
宅地建物取引士(宅建士)の有資格者である行政書士が申請を担当します。業法の実務にも精通しており、要件のチェックから書類作成まで安心してお任せいただけます。
不動産・建設業界での経験
当事務所の行政書士は、元々不動産業や建設業の会社に勤務していた経験があります。業界の慣習や実務を踏まえたサポートが可能です。
リーズナブルで明確な料金
料金体系はわかりやすく、リーズナブルに設定しております。事前にお見積もりを提示し、追加料金なく最後までサポートいたします。
個人であれ法人であれ、必要な要件を満たして着実に準備を進めれば、宅建業への新規参入は十分に可能です。本記事の内容も参考にしながら、ご自身に最適な形態で不動産業をスタートしてください。宅建業免許の取得をお考えの方は、ぜひ専門家の力を活用してスムーズな開業を実現してください。当事務所へのご相談・お問い合わせもぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
料金表
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。
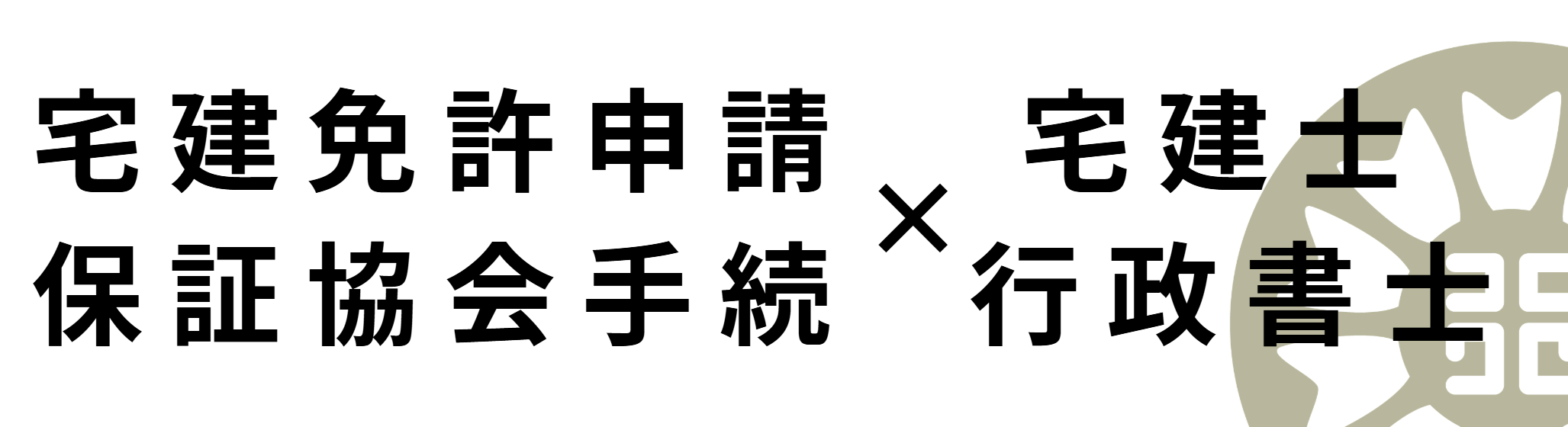
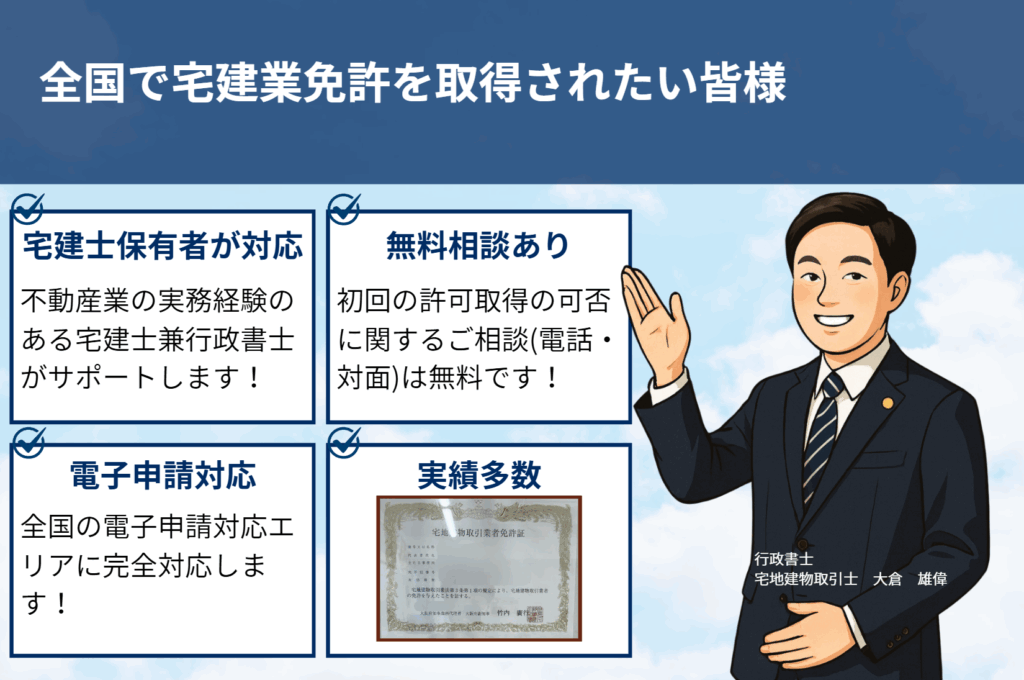
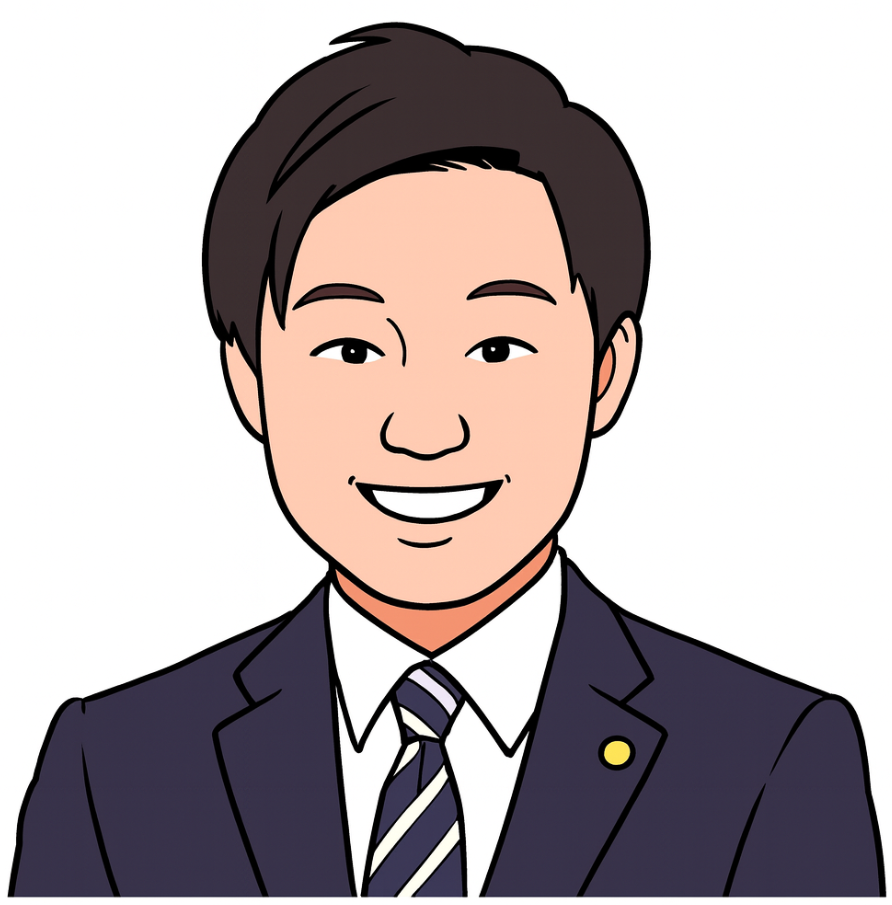
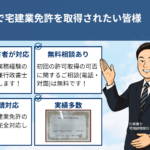
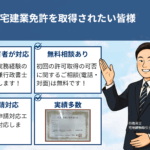
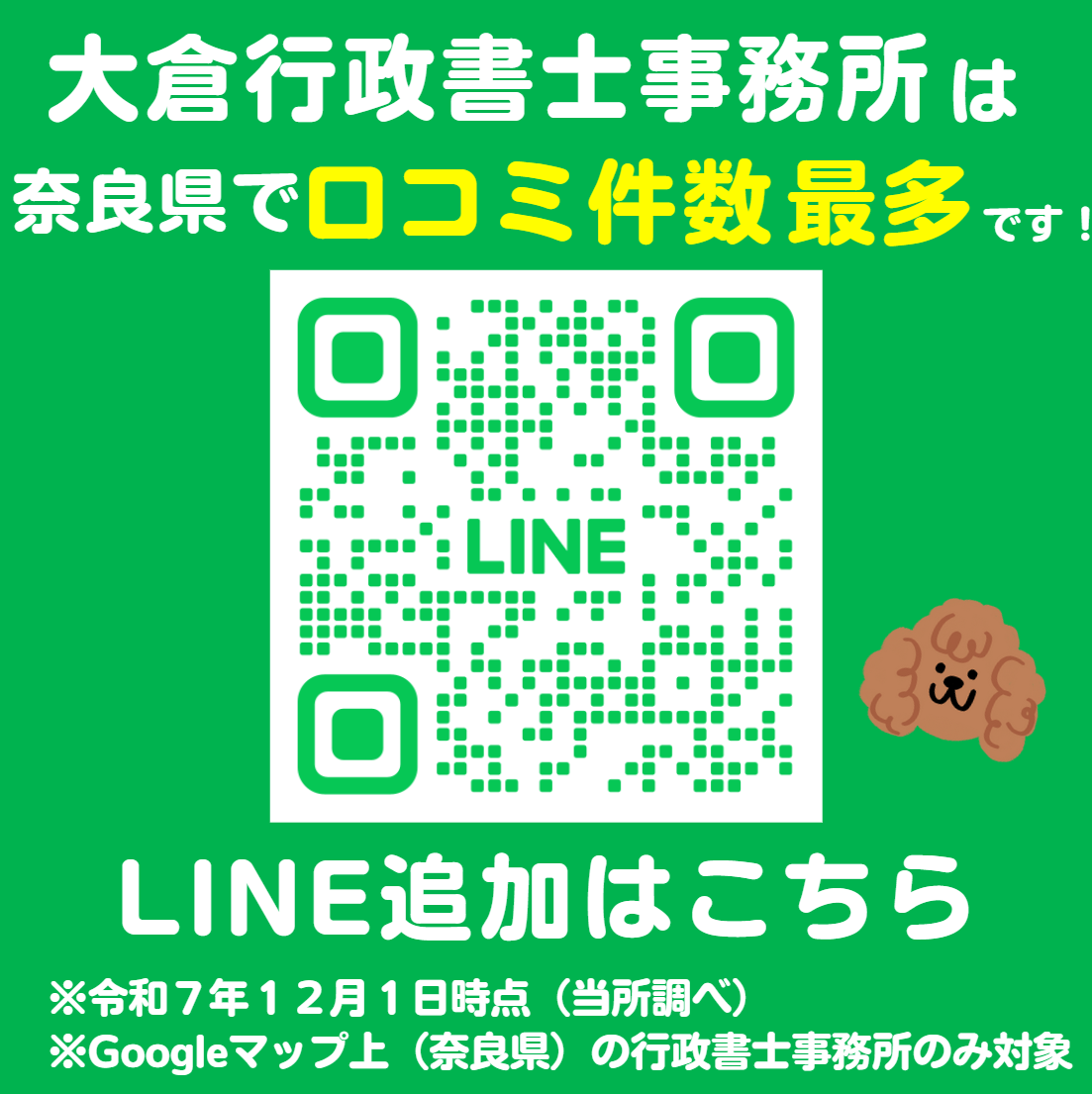
コメント