不動産業の開業を検討する際に、「宅建業免許を取りたいが専任の宅建士がいない」という壁に突き当たる方は少なくありません。
実際、事務所や資金の準備が整っていても、肝心の宅建士を確保できず開業計画が頓挫してしまうケースもあります。宅建業の免許とは、不動産の売買・交換・賃貸の媒介(仲介)や代理を業として行う際に必要となる行政許可です。
自社が所有する物件を賃貸するだけであれば免許は不要ですが、それ以外の取引を継続反復して行う場合には宅建業免許が求められます。宅建業(宅地建物取引業)の免許を取得するには、法律により事務所ごとに一定数の「専任の宅地建物取引士」(いわゆる宅建士)を設置することが義務付けられています。
この要件を満たさないと免許が下りないため、資格者不在の状況は深刻な問題です。本記事では、宅建業免許に必要な専任宅建士の設置義務やその条件、さらに資格者がいない場合にどう対応すべきかについて詳しく解説します。最後に、免許申請手続きを専門家(行政書士)に依頼するメリットもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
宅建業免許における専任宅建士の設置義務

このトピックでは、不動産業を営むにあたり必要となる「専任の宅地建物取引士」の設置義務について解説します。
宅建業法が定める専任宅建士の役割と必要性、そして事務所ごとに何人の宅建士が必要になるのかを見ていきましょう。
専任宅建士の役割と必要性
宅建業法では、不動産取引のプロフェッショナルである宅地建物取引士が重要事項の説明や契約書への記名押印などの独占業務を担うこととし、宅建業者に対し一定数の有資格者を置くよう義務付けています。
具体的には、宅建士は契約前に重要事項説明を行い、その説明書および契約書に記名・押印することが法定業務です。これにより、重要な取引事項について専門知識を持った者が責任を持って説明し、取引の適正さと安全性を確保する仕組みになっています。
専任の宅建士は各事務所に常勤し、取引の専門家として消費者保護と取引の適正化に寄与する存在です。そのため、専任宅建士がいなければ宅建業の免許を受けることはできません。不動産会社にとって宅建士は信頼の証であり、法令遵守の要でもあります。
必要な宅建士の人数(「5人に1人以上」の基準)
法律上、宅建業者は事務所ごとに「業務に従事する者」5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならないと定められています(宅建業法第31条の3)。例えば従業員が5人以下の事務所であれば宅建士は1名、6~10人なら2名、11~15人なら3名…というように、従事者数を5で割って端数を切り上げた人数が必要です。
したがって最小でも各事務所に1名以上の宅建士がいなければならず、要件を満たせない場合は免許申請が認められません。また、この人数要件には代表者や役員も「宅建業に従事する者」に含まれる点に注意が必要です。
代表取締役自身が宅建士でない場合でも免許取得は可能ですが、その場合は代表者を含め少なくとも2名(代表者+宅建士)の体制を整えなければならないことになります。なお、会社が他の事業を兼業している場合には、「宅建業に従事する者」の数を算定する際に業務比率を考慮する必要があります。
代表者が無資格でも開業できる?
前述の通り、会社の代表者が宅地建物取引士の資格を持っていなくても宅建業免許の取得自体は可能です。多くの新規業者では代表者自身が宅建士試験に合格しているケースもありますが、資格が無い場合は従業員や共同経営者などから専任宅建士となる人材を確保すれば問題ありません。
ただし、代表者が宅建士ではない場合は実質的に最低2人以上での開業が必要です。代表者本人も「従事者」に数えられるため、代表ともう1名の宅建士を置いて初めて人数要件を満たせるからです。
仮に代表者1人だけで開業したい場合は、自身が宅建士の資格を取得する以外に方法はないということになります。例えば代表者と事務員1名の計2人で開業する場合、代表者が無資格なら事務員が宅建士である必要があります(2人中1人を充足)。
逆に代表者自身が宅建士資格者であれば、1人だけでも免許取得は可能です。なお、代表者が別の会社で常勤役員を務めているような場合には自身が専任者になれない可能性もあるため、その場合も有資格者の雇用が不可欠です。
宅建業免許を取得する/専任宅建士の資格要件と認定条件

このトピックでは、専任の宅建士として認められるための条件について解説します。「常勤性」や「専従性」といったキーワードがポイントです。せっかく有資格者を確保しても、これらの要件を満たさないと専任宅建士としてカウントされないため、注意が必要です。
専任宅建士に求められる常勤性
「専任の宅地建物取引士」としてカウントされるためには、まず常勤であることが求められます。常勤性とは、当該宅建業者との間に継続的な雇用関係があり、その事務所の営業時間中は原則としてそこで勤務している状態をいいます。
一般的にはフルタイム(週40時間程度)の勤務が基準とされ、他の会社や役所に常勤していないことが必要です。自治体によっては健康保険証や雇用保険被保険者証の写しを提出させるなどして、社保加入状況から常勤性を確認する運用もあります。以下のようなケースでは常勤性が認められず、専任宅建士としてカウントできません。
- 他の企業に正社員として勤務している(兼業の従業員や公務員である)場合
- 勤務時間が限られる非常勤・パートタイムである場合
- 別の職場の勤務終了後や休日のみ従事している場合
- 月に数日しか出勤しない場合
- 事務所から極端に遠方に住んでおり、常識的に毎日の通勤が困難な場合
- 大学等に在学中の学生である場合
以上のように、他の職務との掛け持ちや十分な勤務時間を確保できない場合は常勤性が認められません。専任宅建士には、その会社の通常の業務時間中に継続して従事できることが求められるのです。
専任宅建士に求められる専従性
もう一つの重要な要件が専従性です。専従性とは、その宅建業者の宅建業務に専ら従事していること、すなわち他の事業や職務を兼ねていないことを指します。特に問題になるのは兼業や副業の有無です。例えば、他の不動産会社に籍を置いている人や、他社で既に専任宅建士になっている人は認められません。
また、他法人の代表取締役や常勤役員を兼任している場合も原則不可です。士業(司法書士・行政書士など)として独立開業している宅建士も、そちらの業務に時間を取られるようでは専任とはみなされません。
ただし、同一の事務所内で行政書士業務と宅建業を営むような場合で、両方の業務を十分にこなせる体制にあると認められれば例外的に専任性が認められる可能性があります。要は、宅建業の業務に集中できるかどうかが専従性の判断基準です。
専任宅建士として認められないケース
上記の常勤性・専従性を満たさない場合はもちろん、たとえ宅建士資格を持っていても専任の宅建士として認められないケースがあります。代表的な例を挙げます。
- 宅建士の登録をしていない場合:宅建士試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」と名乗れません。合格後に各都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証(顔写真付きの資格証)を交付されて初めて業務に従事できます。つまり宅建士証を持っていない人は専任宅建士になれません。まだ登録していない場合は、2年以上の実務経験証明か所定の実務講習を経て速やかに登録手続きを行う必要があります。
- 宅建士証の有効期限が切れている場合:宅建士証は有効期間が5年間と定められており、期限が過ぎると効力を失います。有資格者を雇い入れる際には、その方の宅建士証が現在有効であるかを確認しましょう。有効期限切れの場合、更新手続きを行い新しい証の交付を受けてもらわない限り専任者にはなれません。
- 前職場の登録が残ったままの場合:他社で専任宅建士をしていた人を新たに雇用する場合、前の会社での宅建業者名簿および宅建士資格登録簿上の勤務先情報を抹消してもらう必要があります。前職での情報が残っている状態では、新しい会社で専任宅建士として登録できないため注意してください。
- 欠格事由に該当する場合:宅建業法に定める欠格要件(破産や一定の刑罰歴、暴力団関係者等)に該当する人は、宅建士資格者であっても宅建業者の役員や専任宅建士になることはできません。採用予定者については念のため確認が必要です。
このように、単に宅建士の資格証を持っているだけでは不十分で、登録状況や証明書の有効期限、さらには法律上の欠格要件にも抵触しない人物であることを確認する必要があります。
宅建業免許を取得する/宅建士資格者がいない場合の対処法

このトピックでは、社内に宅建士の有資格者が「いない」場合にどのような対策を取れるかについて解説します。新規に宅建業免許を申請したいものの、自分を含め誰も宅建士資格を持っていないというケースは実務上よくあります。そうした場合に専任宅建士を確保するための方法や、注意すべきポイントを見ていきましょう。
宅建士有資格者を新たに雇用する
もっとも現実的かつ迅速な解決策は、宅建士の有資格者を社員として雇用することです。代表者や既存メンバーに資格者がいないなら、外部から専任宅建士となる人材を迎え入れる必要があります。
具体的には、不動産業界の求人サイトに募集を出したり、知人の紹介や宅建士資格者のコミュニティに声を掛けるなどして、宅建士証を持つ人を探します。
資格者ネットワークを通じて希望に合う人材を紹介してもらえる可能性があります。雇用形態は正社員である必要はありませんが、前述の通り常勤・専従が求められるため、フルタイムで働ける人を採用しましょう。単に「資格を持っている知り合いに名義だけ貸してもらう」という形ではまず認められませんので注意してください。
場合によっては、信頼できる有資格者に役員や共同経営者として参加してもらう方法も考えられますが、いずれにせよ専任(常勤)として実態的に従事してもらう必要がある点は同じです。
なお、雇用にあたっては人件費の負担も考慮しましょう。専任宅建士を置かず一人で開業できれば人件費ゼロですが、それができない以上、開業当初から給与や社会保険料のコストが発生します。
資金計画に組み込んだ上で、信頼できる人材を早めに確保することが大切です。免許申請の際には専任宅建士となる方の宅建士証コピーや専任宅建士設置証明書、前述の誓約書などを提出して常勤・専従性を証明する必要がある点も覚えておきましょう。
自分や社員が宅建士資格を取得する
次善の策として、自分自身や社内のスタッフが宅建士の資格を取得する方法があります。宅建士試験は毎年1回(10月)実施されており、独学や予備校で勉強して合格を目指すことも可能です。もし時間的余裕があるなら、開業前に代表者自ら試験に挑戦し資格を取ってしまうのが理想的でしょう。
自分が宅建士になれば、他人に頼らず一人で免許申請ができますし、将来的な人件費負担や人材流出リスクも抑えられます。また、代表者自身が資格を持っていることは専門知識が身につくメリットにもなり、お客様からの信頼獲得にもプラスに働くでしょう。
既に従業員がいる場合には、意欲のある社員に資格取得を目指してもらい、受験費用を会社が負担するなど社内で宅建士を育成する方法も考えられます。
ただし、試験合格から免許申請までにはさらに登録手続きが必要である点に注意が必要です(前述)。試験に合格しただけではすぐに専任宅建士としてカウントできません。また試験は合格率15%前後と難易度が高いため、誰も資格を持っていない状態で合格を待ってから起業する場合、開業時期が遅れるリスクもあります。
違法な名義貸しに頼らないこと
「資格者がいないので、とりあえず名義だけ貸してもらおう」という発想は絶対に避けてください。宅建士資格者に対し報酬を払って名前だけ専任者として登録し、実際には勤務してもらわないという行為は名義貸しと呼ばれ、宅建業法違反の重大な不正行為です。
近年は申請時のチェックも厳格化されており、雇用実態のない専任宅建士で免許を受けることはまず不可能です。内部告発などで発覚するケースもあり、リスクが高すぎるため絶対にやめましょう。
実際、各都道府県の公表する監督処分状況を見ると、「専任宅建士の未設置」を理由とした業務停止処分事例が毎年のように確認されています。
また、正規に免許を取得できた後も、専任宅建士が欠けた状態で営業を続けることはできません。専任者が退職や病気で不在になった場合、2週間以内に新たな専任宅建士を補充する義務があります。
しかし、わずか2週間で新しい専任宅建士を見つけるのは実際問題として容易ではありません。宅建士資格自体の保有者は数多くいても、登録を済ませてすぐに勤務できる人となると非常に限られるためです。
そのため、専任宅建士が1名だけの体制で開業する場合は、普段からその方に長く勤めてもらえるよう良好な関係を維持し、待遇面にも配慮しておくことが大切です。
可能であれば、リスクヘッジとして複数の有資格者を確保しておくと安心でしょう。もし補充が間に合わなければ、新規の取引契約を締結することは禁止され、最悪の場合は業務停止処分につながります。免許の有効期間中に専任者不在のままにしておくと更新もできず免許失効という事態になりかねません。
免許証番号も新規取得扱いとなり、()内の更新回数が1に戻ってしまうなど、業歴の信用面にも影響が及びます。免許取得時だけでなく、その後も継続的に要件を満たすよう人員体制には十分注意しましょう。
宅建業免許を取得する/当行政書士に依頼するメリット
このトピックでは、宅建業免許の申請手続きを専門家に依頼するメリットについて説明します。当事務所を含め行政書士などの専門家に依頼すれば、要件の確認から書類作成、役所への届出までスムーズに進めることが可能です。
役所との折衝・調整も含めて任せられるため、ご自身が何度も窓口に足を運ぶ必要もありません。経験豊富な行政書士に任せれば書類不備による申請却下や手戻りを防ぎ、最短での免許取得が期待できるでしょう。特に当事務所のように宅建士資格を持つ行政書士がサポートする場合、不動産業界の実務知識も活かしたきめ細かな対応が期待できます。
宅建士資格を持つ行政書士が担当
当事務所にご依頼いただく最大のメリットは、行政書士自身が宅地建物取引士の有資格者である点です。単に手続きの代行をするだけでなく、宅建業法や宅建士の役割について深く理解した者が対応いたします。
専任宅建士の設置要件に関するご相談や、必要書類(誓約書・雇用証明など)の準備についても、法律と実務の両面から適切にアドバイス可能です。宅建士試験に合格していない行政書士に依頼する場合と比べても、宅建業界特有の専門用語や事情をスムーズに共有できるため安心です。
建設・不動産業界での経験に基づくサポート
当事務所の担当者は、もともと建設業や不動産業の会社に勤務していた経歴を持っています。不動産取引や建設業界の現場を熟知しているからこそ、実務に沿った申請サポートが可能です。
例えば、事務所要件のチェックや、他業種を兼ねる場合の専任性の留意点など、机上の知識だけではなく現場感覚を踏まえたアドバイスを提供できます。さらに、都道府県ごとに申請時の提出書類や運用が微妙に異なる点にも対応可能です。
明確でリーズナブルな料金設定
行政書士に依頼すると高額な費用がかかるのでは?と心配される方もいるかもしれません。当事務所では明確でリーズナブルな料金体系を心がけており、事前にお見積もりを提示して納得いただいてから手続きを進めています。
複雑に見えがちな報酬設定もシンプルなプランでご提示しますので、安心してご依頼いただけます(最新の法改正情報にも精通しています)。宅建業免許申請に関する相談は全国対応(電子申請対応可能な場合のみ)で承っており、奈良県・大阪府をはじめ近畿圏の方はもちろん、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
プロに依頼することで、煩雑な書類作成や役所対応に手間取ることなく、本業の準備に専念していただけます。
宅建業免許申請は当事務所にお任せください

宅建業免許の申請では、専任の宅建士の確保が避けて通れない重要条件です。資格者がいない場合は、早めに有資格者を採用するか、自ら資格を取得する計画を立てる必要があります。手続きや要件に不安がある方は、当事務所にご相談ください。万全の準備で開業に臨みましょう。
専任宅建士の要件をクリアして、ぜひスムーズに宅建業免許を取得し、不動産ビジネスのスタートを切り、新たな一歩を踏み出しましょう。
お問い合わせ
料金表
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。
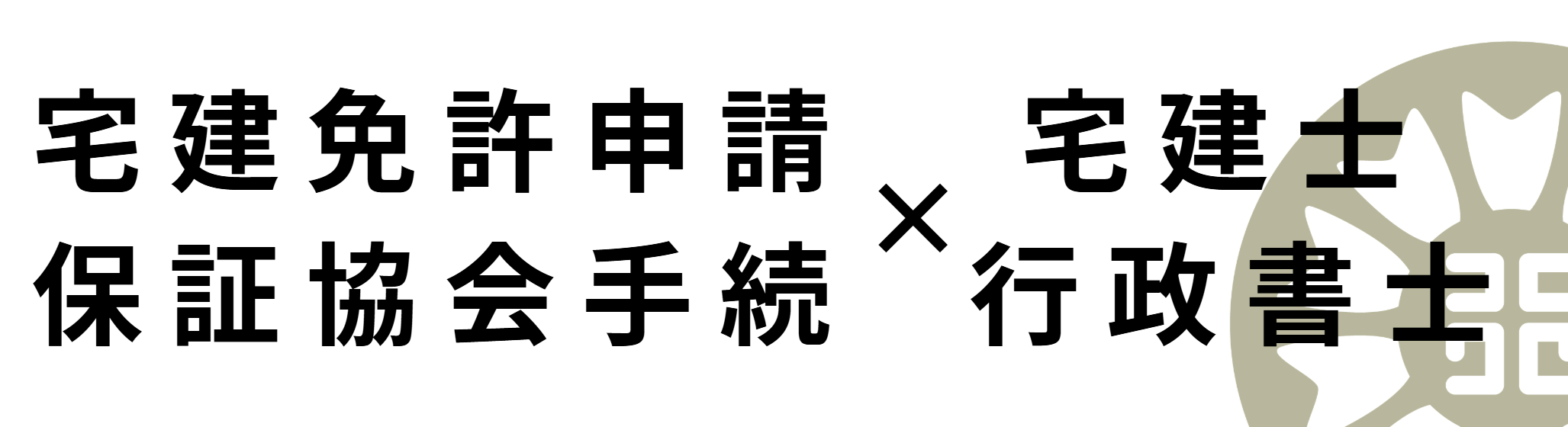
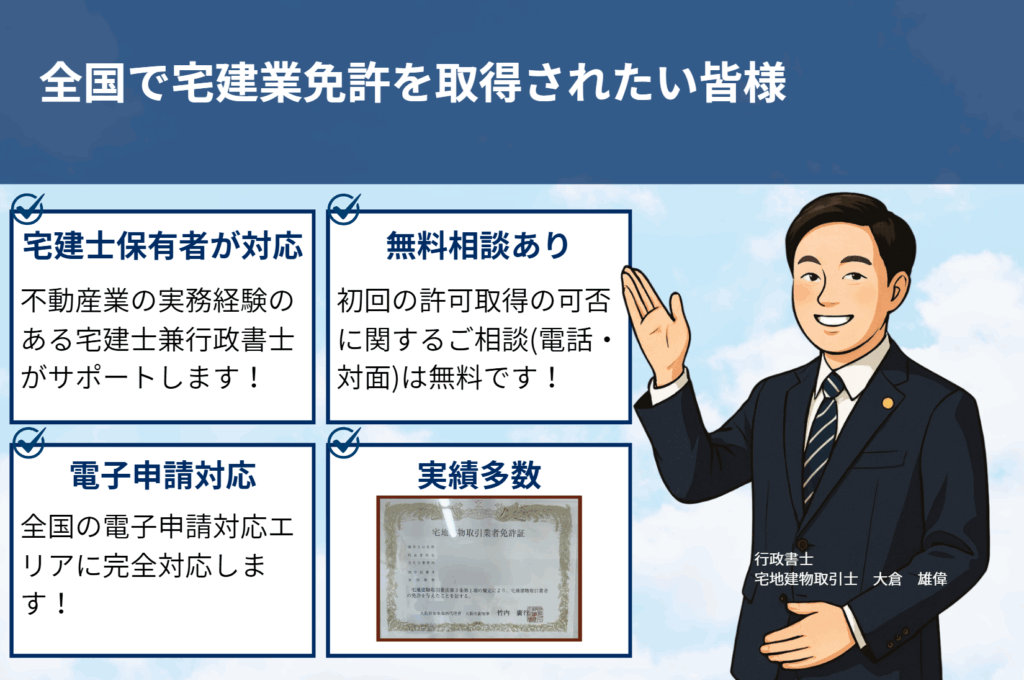
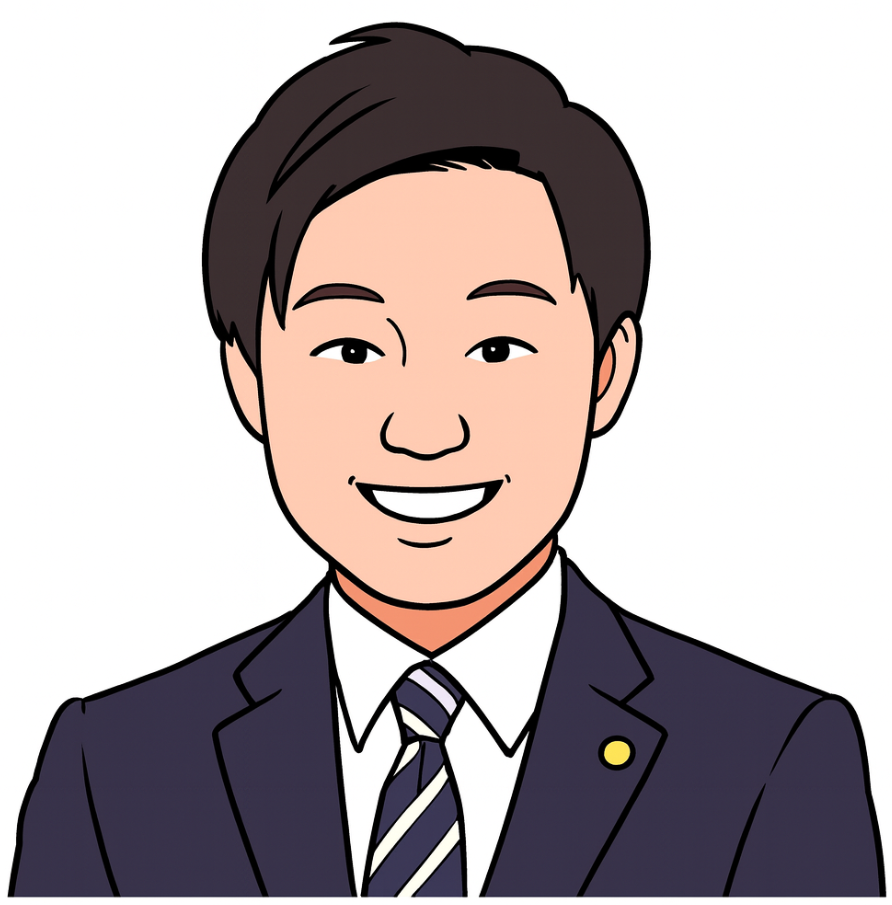
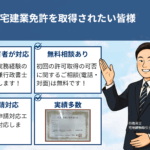
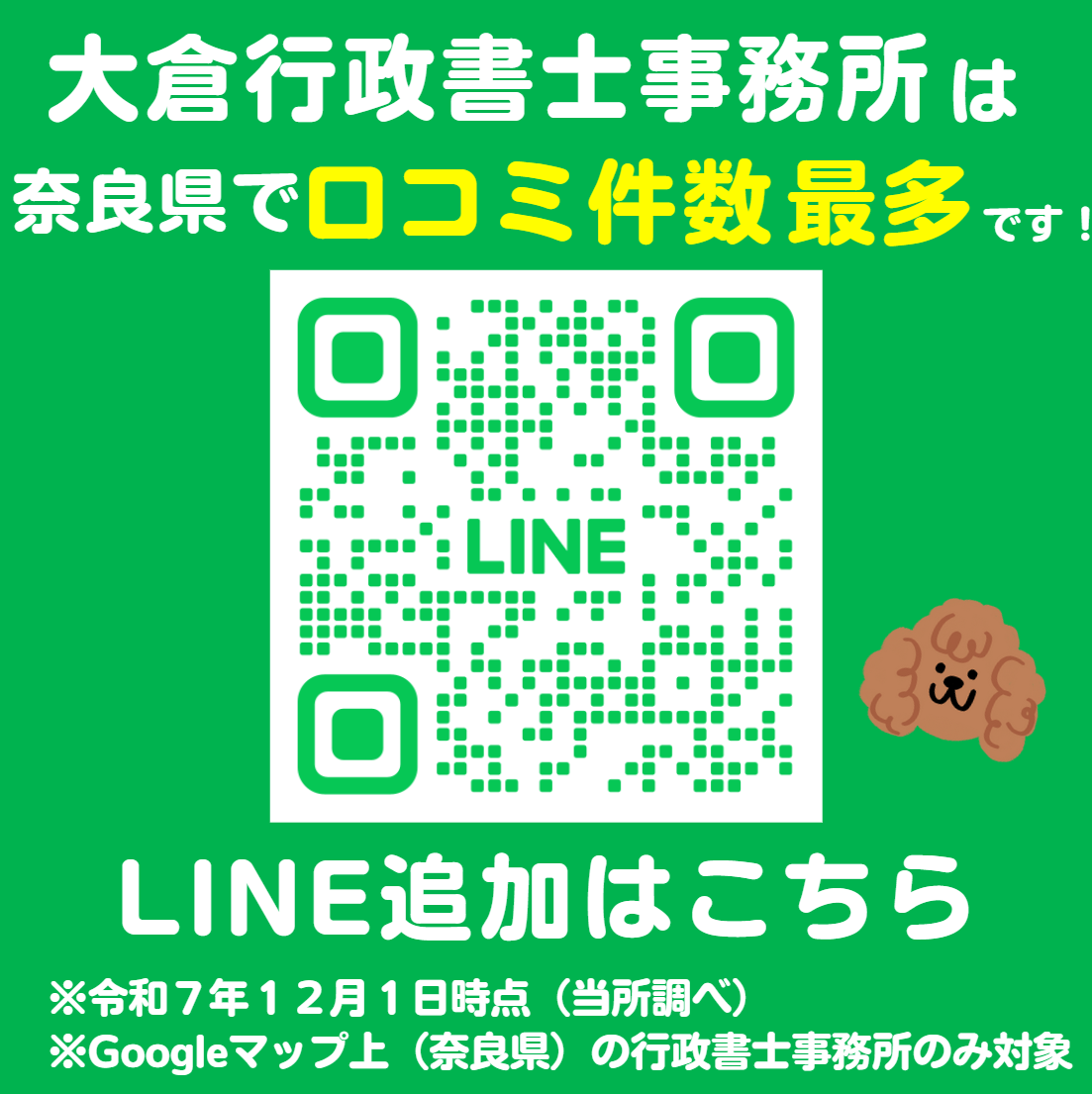
コメント