奈良県で宅地建物取引業免許(宅建業免許)を申請する際、「代表者」「政令で定める使用人」「専任の宅地建物取引士」の3つの要件は、審査上の重要なポイントになります。
これらの条件を満たしていない場合、免許が下りなかったり、更新時に不受理となるケースもあります。本記事では、奈良県庁での実務運用に沿って、それぞれの要件を丁寧に解説します。
奈良県の宅建業免許申請/代表者の要件
宅建業の免許申請者が法人の場合、「代表取締役」や「代表理事」などの代表者が、実際に事務所に常駐していることが基本要件となります。
代表者が常駐とは?

「常駐」とは、社会通念上、通常の勤務時間帯に事務所に在籍し、宅建業に関する意思決定や業務執行を行える状態を指します。つまり、単に登記上の代表取締役であるだけでは足りず、実際に事務所で日常的に業務を行っていることが必要です。
ポイント
出張・外出があるのは構いませんが、恒常的に他社勤務・兼務などで不在が続く場合は「常駐」とはみなされません。
代表者が常駐できない場合
代表者が常駐できない場合、宅建業法施行令第2条の2に基づき、「政令で定める使用人」を置く必要があります。この政令使用人が、実質的にその事務所の責任者として業務を統括します。
代表者が他の法人の役員を兼ねている場合も、勤務形態によっては免許が認められない場合があります。特に以下のケースでは注意が必要です。
| 区分・代表者の勤務状況 | 政令使用人の設置義務 |
| 代表者が事務所に常駐 | 任意(政令使用人不要) |
| 代表者が常駐できない | 政令使用人の設置が必須 |
| 代表者が他法人の役員を兼務 | 勤務形態によっては政令使用人の設置が必要 |
奈良県の宅建業免許申請/政令で定める使用人とは?

宅建業法上の「政令で定める使用人」とは、単なる従業員や事務員ではなく、代表者から契約権限を委任された責任者を指します。つまり、その事務所において宅地建物取引業の契約を締結する権限を持つ者です。実際の例でいえば、支店長・営業所長・支配人などがこれにあたります。
政令使用人が必要となる場合
政令で定める使用人の設置が必須となるのは、次のようなケースです。
| 申請形態 | 設置要否 |
| 個人業者で代表者が常駐 | 任意(不要) |
| 個人業者で代表者が常駐しない | 必須(設置がないと免許不可) |
| 法人で代表取締役が常駐 | 任意(不要) |
| 法人で代表取締役が常駐しない | 必須(設置がないと免許不可) |
| 従たる事務所に代表取締役が常駐 | 本店に政令使用人を設置すれば免許可 |
| 本店に代表者が常駐、支店に従業員のみ常駐 | 支店に政令使用人の設置が必要 |
ポイント
政令使用人は、「常時勤務していること(常勤性)」が求められます。他の会社の常勤役員を兼務している場合や、通勤できない遠方に居住している場合は要件を満たしません。
政令使用人の権限
政令使用人は、代表者の代理として次のような権限を持ちます。
- 宅地建物取引契約の締結
- 重要事項説明の実施(宅建士資格がある場合)
- 業務全般の統括・管理
- 所属従業員の監督責任
そのため、形式的な名義貸しや「形だけの設置」は認められません。奈良県庁では、勤務実態の確認のために事情聴取や書面提出を求めることがあります。
奈良県の宅建業免許申請/専任の宅地建物取引士の設置要件

宅建業の事務所には、従業者5名につき1名以上の「専任の宅地建物取引士」を設置することが義務付けられています(宅建業法第31条第1項)。代表者自身が宅地建物取引士であっても、その人数にカウントされます。
「専任」とは?
専任宅地建物取引士とは、その事務所に常勤し、宅建業務に専従している取引士をいいます。この「専任」には次の2つの条件があります。
| 条件 | 内容 |
| 常勤性 | 通常の営業時間にその事務所に勤務していること。副業や他法人の常勤職員でないこと。 |
| 専従性 | 他の業務や職務に従事せず、宅建業務に専念していること。 |
たとえば以下のような場合は「専任」とは認められません。
- 他の法人の役員を兼務している
- 自身の別事業(飲食店経営など)に常時従事している
- 公務員や会社員など他の職に就いている
- 遠方に居住し、通勤が現実的でない距離にある
専任宅建士の配置義務
宅建業を行う事務所では、以下のルールで専任宅建士を配置する必要があります。
| 区分 | 配置義務 |
| 各事務所(本店・支店など) | 従業者5人につき1人以上 |
| 案内所・展示場など(法50条第2項に該当) | 1名以上の専任宅建士を配置 |
注意
支店・営業所にも専任の宅建士が必要です。本店だけに設置しても全体をカバーすることはできません。
新規申請時の注意点
新規で免許を申請する際、専任宅建士は「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が未登録であること(前勤務先が残っている場合は削除手続きが必要)が必要です。
登録が残ったまま申請すると、「専任」要件を満たさないとして受理されません。この場合は、前勤務先の都道府県に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出し、削除の受付控えを添付します。
奈良県外で登録している宅建士の方は、登録都道府県での変更受付控え(写し)を添付することで証明可能です。
奈良県の宅建業免許申請/勤務形態・実態の確認について
奈良県では、代表者や専任宅建士・政令使用人の勤務実態を確認するため、事情聴取や勤務表、委任状などの提出を求める場合があります。もし、代表者が常駐していない、宅建士が他の仕事をしている、政令使用人が形式的であるといった場合には、免許が下りないことがあります。
実務でよくあるトラブル例
| 事例 | 結果・対応 |
| 代表取締役が別法人の社長も兼ねており、ほとんど不在 | 常駐要件を満たさないため不可。 |
| 支店に宅建士を置かず、本店宅建士が兼務 | 不可。各事務所ごとに専任配置が必要。 |
| 政令使用人を置いたが実際は名義貸し | 聴聞対象、免許取消しの可能性。 |
| 宅建士が他県登録のまま勤務開始 | 資格登録変更をしていないため受理されず。 |
| 自宅兼事務所で生活空間と未分離 | 事務所要件違反により補正・再提出を指示。 |
まとめ:3つの人員要件が宅建業免許の柱
奈良県で宅建業免許を取得するための人員要件は、以下の3つが柱です。
| 区分 | 主な要件 | 注意点 |
| 代表者 | 事務所に常駐し、業務執行が可能 | 不在時は政令使用人を設置 |
| 政令使用人 | 契約権限を持ち、常勤で勤務 | 名義貸し不可・勤務実態が必要 |
| 専任宅地建物取引士 | 常勤・専従・資格登録が正しいこと | 各事務所に配置義務あり |
行政書士によるサポートのすすめ

これらの要件は、法律だけでなく奈良県庁の実務運用によっても判断されます。
形式的に条件を整えても、写真・勤務証明・ヒアリングで否認されるケースが少なくありません。
行政書士に依頼するメリット
- 勤務実態・事務所形態の事前確認
- 代表者や宅建士の勤務証明書類の整備
- 奈良県庁との事前相談・書類提出代行
- 法令・条例に即した正確な申請
宅建士資格を有する行政書士が対応すれば、要件確認から書類整備、免許申請の受理まで一貫したサポートが可能です。
奈良県で宅建業免許を申請予定の方へ

大倉行政書士事務所(奈良県生駒市)では、「代表者・政令使用人・専任宅建士」の要件診断から申請書作成まで、完全サポートいたします。
無料相談も受付中です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
料金表
料金プラン
◆ 保証協会加入手続き代行込み
知事免許申請
¥99,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フル対応
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥155,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・保証協会加入手続き代行
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
◆ 保証協会加入手続きなし
知事免許申請
¥88,000
(税込・法定費用別)
- ・宅建業免許申請代行
- ・電子申請対応
- ・書類作成・提出代行
- ・申請後フォロー込み
大臣免許申請
¥195,000
(税込・法定費用別)
- ・複数都道府県対応
- ・電子申請フルサポート
- ・全国オンライン対応
- ・申請後フォロー込み
【法定費用・実費について】
- ・知事免許:収入証紙 33,000円
- ・大臣免許:登録免許税 90,000円
- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)
※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。
【関連・参考記事】
>宅地建物取引業免許を申請される方への手引き
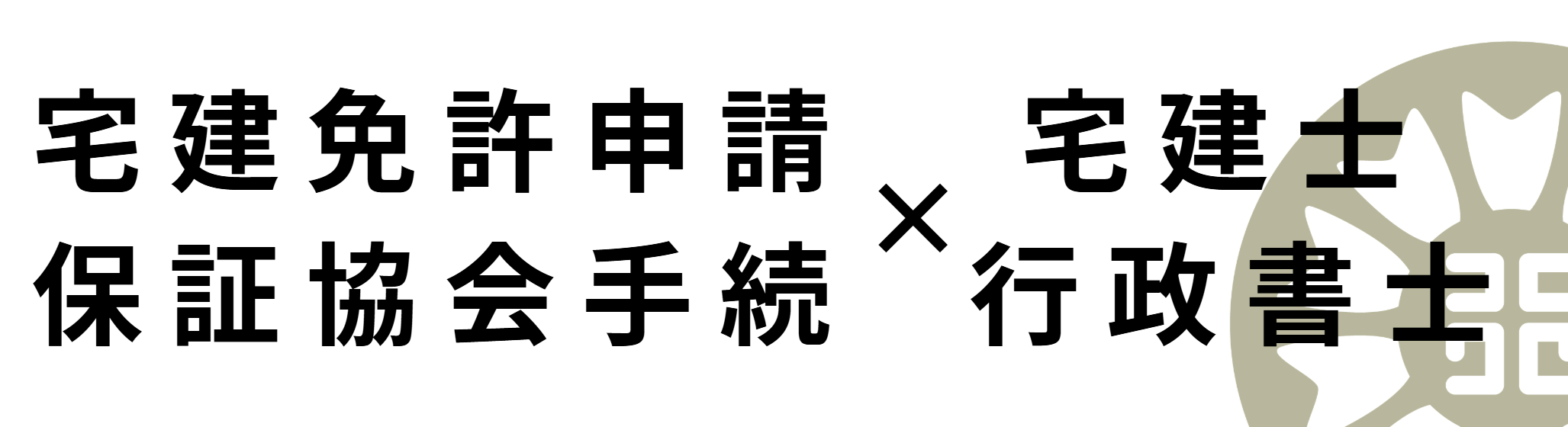
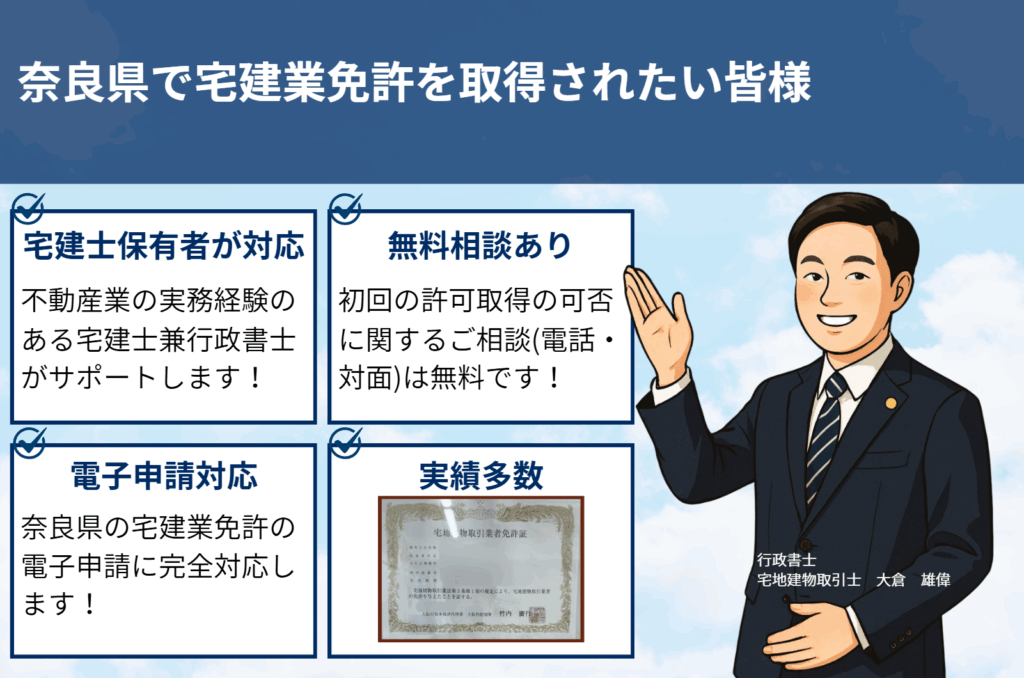
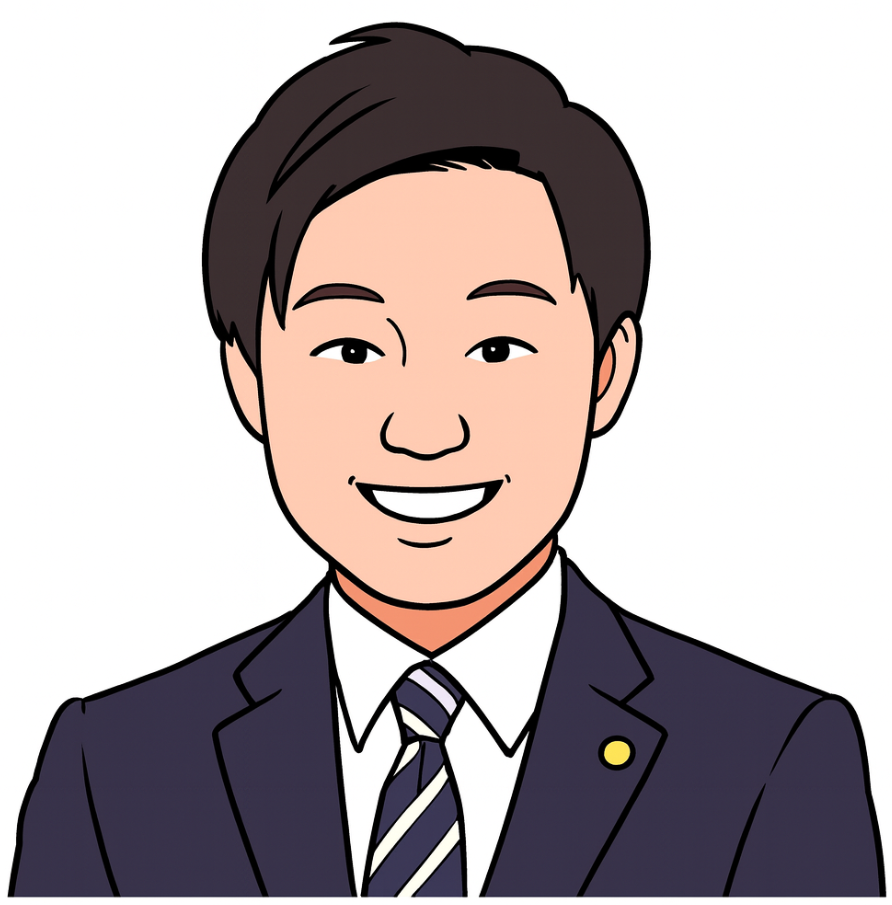
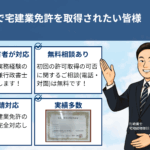
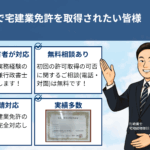
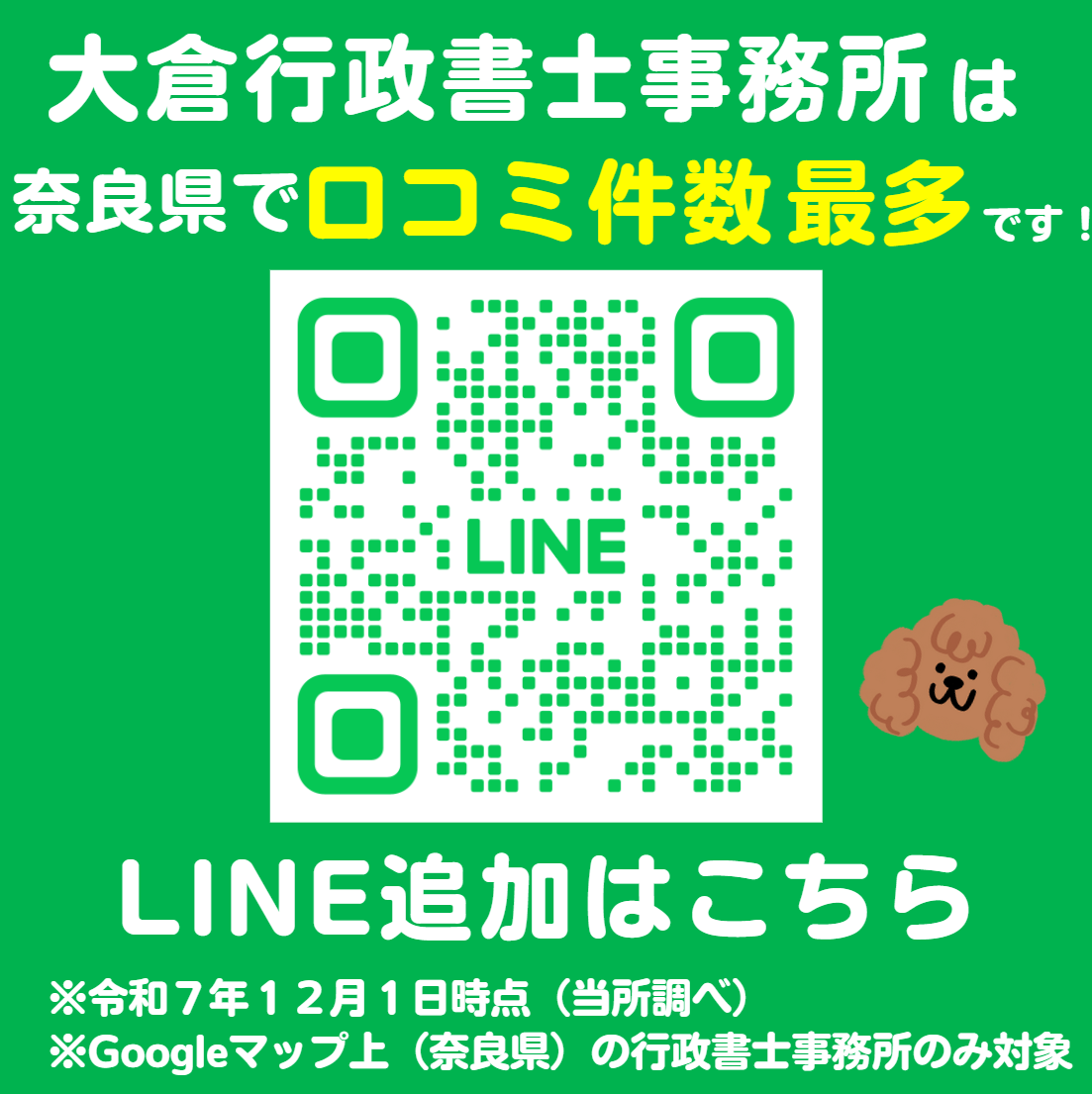
コメント