パソコン教室を開業するにあたっては、特定商取引法(特定商取引に関する法律)の規制を理解しておくことが重要です。とくに、長期にわたり高額な受講料を受け取るようなパソコン教室は、同法における「特定継続的役務提供」に該当し、さまざまなルール遵守が求められます。
本記事では、初心者の事業者向けにパソコン教室と特定商取引法の関係をわかりやすく解説し、必要な書面の整備や注意点を説明します。また、行政書士として、概要書面や契約書面の作成をどのようにサポートできるかについても触れ、適法かつ安心な教室運営のお役に立てればと思います。
パソコン教室と特定商取引法

このトピックでは、特定商取引法の概要と、パソコン教室がなぜその規制対象となるのかを説明します。
さらに、事業者として最低限理解しておくべき基本ルールについても解説します。
特定商取引法とは何か
特定商取引法とは、消費者トラブルが起こりやすい特定の取引類型について、事業者側に一定の規制を課し、消費者を保護することを目的とした法律です。訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など様々な取引が対象ですが、パソコン教室のようなサービス業も含まれます。
同法では、長期・継続的にサービスを提供する契約で高額の対価を伴うものを「特定継続的役務提供」と定義し、特別なルールを定めています(役務の目的は身体の美化や知識・技能の向上だが、その成果が確実でない有償サービスを指します)。
パソコン教室が規制対象になる理由
パソコン教室は、まさに「知識・技能の向上」を目的とした継続サービスであり、受講に時間がかかる一方でその成果(スキル習得)が保証されないという特徴があります。高額な受講料を前払いしたものの思うような指導が受けられない、といった消費者トラブルを防ぐため、パソコン教室はエステや語学教室などと並んで特定商取引法で規制される7種のサービスの一つに指定されています。つまり、一定の条件を満たすパソコン教室の契約は同法のルールに従わなければなりません。
事業者として理解すべき基本的なルール
パソコン教室が特定継続的役務提供に該当する場合、事業者は特定商取引法に基づきいくつかの重要な義務を負います。主なルールとしては、契約前後に所定の書面を交付する義務、契約後8日以内のクーリング・オフ(無条件解約)の容認、そして期間途中であっても中途解約に応じる義務があります。
さらに、広告や勧誘において虚偽や誇大な表示をすることが禁止されており、誤解を招く説明によって消費者に不利益を与えてはならないとされています。これらのルールを理解し遵守することが、健全な教室運営の前提となります。
パソコン教室が「特定継続的役務提供」に該当する場合
ここではパソコン教室が法律上「特定継続的役務提供」に当たるケースの条件と具体例、および該当した場合に事業者が果たすべき義務について説明します。
特定継続的役務提供の定義
「特定継続的役務提供」とは、特定商取引法第41条で定められた取引類型の一つです。これは前述の通り、美容や語学習得など消費者の心身に関わる目的(美しくなる、技能が上達する等)のために、一定期間継続して提供される有償サービスで、その成果が確実ではないものを指します。
政令で指定されたエステティックサービス、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚紹介サービス、そしてパソコン教室など7種類のサービスが該当します。パソコン教室は「電子計算機やワープロの操作方法の教授」としてこの中に含まれており、対象条件を満たせば特定継続的役務提供として規制を受けることになります。
【関連記事】
>特定継続的役務提供
該当する条件と具体例
パソコン教室のどういった契約が特定継続的役務提供に該当するのでしょうか。法律上は、契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える受講契約がこれに当たります。
例えば、6か月間のコースで受講料合計10万円のパソコン教室は、この条件を満たす典型例と言えます。契約金額には入会金や授業料のほか教材費や関連商品の代金も含まれるため、受講に必要な費用を合計して判断します。
なお、これらの条件を満たしていれば、対面で教室に申し込んだ場合でも規制の対象となります(店頭での契約であっても特定商取引法が適用されます)。事業者は、自社の提供形態がこれらの条件に該当するかどうかを確認しておく必要があります。
該当した場合の事業者の義務
パソコン教室の契約が特定継続的役務提供に該当する場合、事業者は特定商取引法に定められた以下の義務を履行しなければなりません。
書面の交付義務
契約を結ぶ前に契約内容の概要を記載した「概要書面」を交付し、契約締結後は遅滞なく契約内容を明示した「契約書面」を交付する必要があります。
概要書面には事業者情報(名称・住所・電話番号等)、役務の内容、期間、対価総額、支払時期・方法、クーリング・オフや中途解約の条件などを記載することが定められています。契約書面には契約日や契約担当者名なども含め、最終的な契約条件を明記します。
クーリング・オフへの対応
消費者(受講者)は契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、理由を問わず契約を解除(クーリング・オフ)できます。事業者はクーリング・オフの申し出があれば速やかにこれに応じ、すでに受け取った金銭があれば全額返金しなければなりません。
中途解約への対応
クーリング・オフ期間経過後も、消費者からの途中解約(中途解約)の申し出に応じる義務があります。この場合、事業者は提供済みのサービスの対価を差し引いた残額から、所定の解約料を控除して返金します。解約料には法律で上限が定められており、パソコン教室の場合、役務提供開始後なら未提供分残額の20%か5万円のいずれか低い額が上限です。(役務提供開始前であれば1万5千円が上限)
したがって、高額な違約金や返金拒否などはできず、法律の範囲内で精算する必要があります。以上のように、特定継続的役務提供に該当するパソコン教室では、契約時の書面交付から解約時の対応まで細かな義務が課される点に注意が必要です。
パソコン教室が「特定継続的役務提供」に該当しないケース
ここでは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当てはまらないパソコン教室の例と、その場合に事業者が注意すべき点について解説します。契約形態や料金設定によっては、特定商取引法の規制対象外となるケースもありますが、消費者への誤解を防ぐ配慮が必要です。
単発・短期間の講座の例
特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たらない典型例として、短期間または単発で完結するパソコン講座が挙げられます。例えば、1日限りのセミナーや1ヶ月程度で終了する集中講座、受講料が5万円以下の短期コースなどは契約期間・金額のいずれも基準を超えないため、特定継続的役務提供には該当しません。
こうした契約であれば、特定商取引法上のクーリング・オフ制度や書面交付義務は適用されず、基本的には双方の合意した契約条件(民法等の一般ルール)に従って運営されます。ただし、短期間の講座であっても契約内容の説明不足によるトラブルは起こり得るため、事前の説明は丁寧に行うことが望まれます。
料金体系による判断の違い
パソコン教室の提供形態によっては、料金体系や契約方式を工夫することで特定継続的役務提供に当たらないケースもあります。例えば、月謝制(都度払い)で契約期間を定めず、受講者がいつでも自由にやめられるような方式であれば、個々の契約は1ヶ月単位となり「2ヶ月を超える契約」には該当しないと解釈されます。
また、コースを細分化し、1回あたりの契約期間・金額を基準以下に設定する方法も考えられます。ただし、形式的に契約を分割していても、実質的には長期一括契約と同様であれば、消費者から疑念を持たれたりトラブルになる可能性があります。
料金割引などで実質的に長期継続を前提とする場合は慎重に検討する必要があります。重要なのは、契約内容をわかりやすく提示し、受講者に誤解なく同意してもらうことです。特定商取引法の適用を免れることばかりを優先せず、透明性のある契約形態を心がけましょう。
誤認防止のための表示や説明
特定継続的役務提供に該当しない場合でも、消費者に誤解を与えない表示・説明が不可欠です。法律上のクーリング・オフ適用がない短期講座であっても、その旨(例:「契約後のキャンセルは原則できません」等)を事前にきちんと説明しておけば、後々のトラブルを防げます。
逆に、適用外だからといって説明を怠り、受講者が不利益を被った場合には、消費者契約法など他の法律によるクレームリスクも生じ得ます。広告の段階でも、あたかも誰でも短期間で簡単に習得できるかのような誇大な表現や、「今だけ」「絶対上達保証」等の過度な謳い文句は避け、実際のサービス内容に即した正確な情報を伝えましょう。
これは特定商取引法の適用がある場合の禁止事項であると同時に、適用外の場合でも事業者として守るべき誠実な対応です。結局のところ、受講者との信頼関係を築くためには、契約前に十分な情報提供を行い、不明点を残さないことが大切なのです。
行政書士による特商法書面の作成サポート
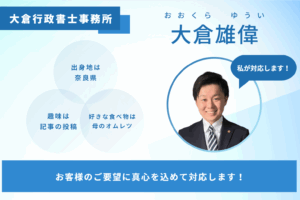
最後に、特定商取引法に対応するために準備すべき書面のポイントと、行政書士に依頼するメリットについて解説します。複雑な法律要件を満たした契約書類の作成や、違反リスクの軽減に役立つポイントを確認しましょう。
概要書面と契約書面の違いと作成ポイント
特定商取引法に基づく概要書面と契約書面は、それぞれ交付するタイミングと記載内容が異なります。概要書面は契約締結前に交付するもので、契約の概要(サービス内容や期間、料金、解約権など)を記載した説明資料です。
契約書面は契約締結後に交付される正式な契約内容の書面で、契約日や契約担当者名まで含めた詳細が記載されます。双方に共通して記載すべき事項も多く、例えば事業者の情報、役務内容・期間、支払金額・方法、クーリング・オフや中途解約に関する条項などが挙げられます。
特に、消費者が注意すべき点であるクーリング・オフ可能期間は赤枠・赤字で明示する決まりがあります。また、書面の文字サイズも8ポイント以上など細かな規定があり、法律の定める事項を漏れなく盛り込むことが重要です。
これらの書面を作成する際は、法律用語の理解や規定項目の洗い出しが必要になります。万一記載漏れや不備があると、後述するようにクーリング・オフ期間の延長や行政処分のリスクにつながります。そのため、専門知識を持つ行政書士等に依頼して、適法な書式を整えることが推奨されます。
違反リスクと罰則
前述の義務を怠った場合、事業者にはさまざまなリスクや罰則が生じます。まず、書面の交付遅れや記載不備があると、消費者は適切な書面を受け取ってから8日間はいつでもクーリング・オフできるため、本来なら権利行使期限を過ぎた後でも契約解除を申し出られる可能性があります。さらに悪質なケースでは、消費者庁や都道府県から業務改善指示や業務停止命令等の行政処分が科されることもあります。
特定商取引法違反には刑事罰も規定されており、例えば概要書面や契約書面を交付しなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。(特商法第71条)法人が違反した場合はさらに重い罰金(違反内容に応じて最大で数億円規模)も定められているため注意が必要です。(同法第74条)
また、誇大な広告や不実な説明で契約させる行為も処罰の対象となり、もし威圧や欺瞞によって消費者がクーリング・オフを断念していた場合には、期間経過後でも解除が認められます。違反による信用失墜や顧客クレーム対応のコストも無視できません。こうしたリスクを避けるためにも、法定の義務を確実に履行することが肝要です。
行政書士に依頼するメリット
以上のように、パソコン教室の運営には多くの法的留意点がありますが、そこで頼りになるのが行政書士のサポートです。行政書士は契約書類の作成や官公署提出書類のプロであり、特定商取引法に関する書面作成にも精通しています。以下に、行政書士に依頼するメリットをまとめます。
書面作成の専門知識
前述した概要書面・契約書面のように、法律で細かく定められた書類を一から自力で作成するのは容易ではありません。行政書士に依頼すれば、必要事項を漏らすことなく盛り込んだ書面の雛形を作成してもらえます。特にクーリング・オフや中途解約条項について、法律に即した適切な表現で明記してくれるため安心です。
トラブル予防
行政書士はこれまでの知見から、どのような契約条項や説明が不足するとクレームにつながりやすいかを理解しています。書面作成の段階でそうした点を補強し、消費者に誤解を与えない契約内容とすることで、将来的なトラブルを予防できます。結果として、違反リスクの低減や顧客満足度向上につながるでしょう。
最新情報の提供
法令は改正されることがあり、特定商取引法も例外ではありません。例えば2023年の改正では、消費者の承諾を条件に契約書面等を電子メール等で提供できるようになりました。行政書士に相談していれば、このような最新の制度変更にも対応した書面・手続のアドバイスを受けることができます。
本業に専念できる
複雑な法律対応を専門家に任せることで、事業者は本来の授業内容の充実や集客といった本業に専念できます。煩雑な書類作成や法令チェックに追われる負担が軽減され、精神的にも安心して事業運営できるでしょう。
このように、行政書士のサポートを受けることは、特定商取引法の遵守と円滑なパソコン教室運営の両立に大いに役立ちます。必要書面の整備や法的手続きをプロに任せ、安心して受講生にサービス提供できる環境を整えていきましょう。
当事務所に依頼する3つのメリット
- 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。 - 実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。 - 最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 | 55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
- お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。 - お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。 - 契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。 - 追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。 - 書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。 - 書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

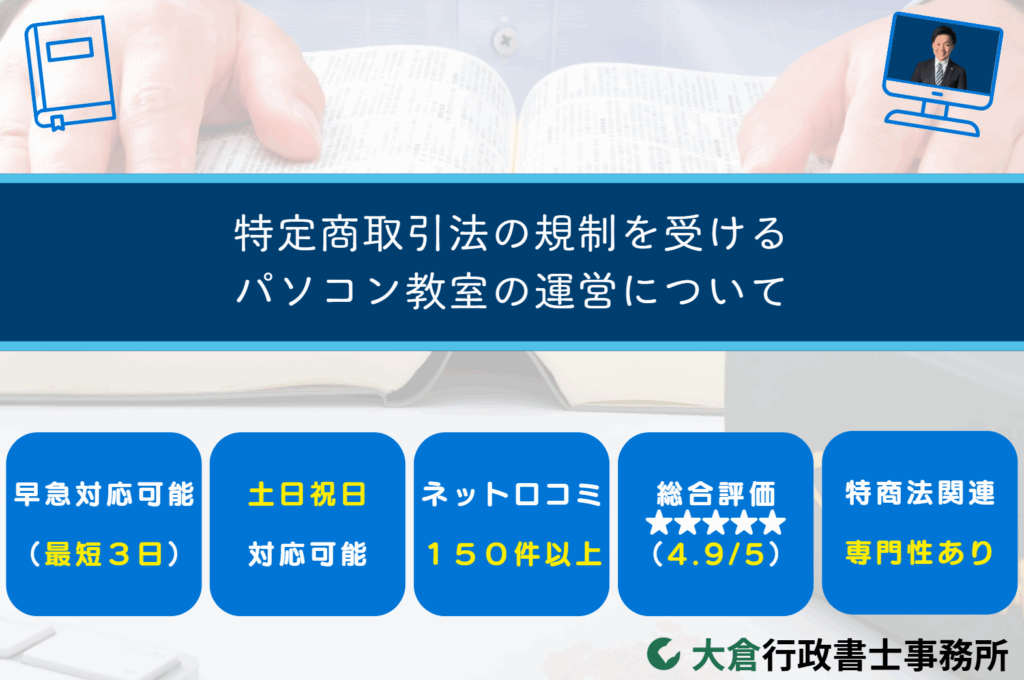

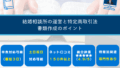

コメント