エステサロンの新規開業や事業拡大を目指す方にとって、「特定商取引法(特商法)への対応」は避けて通れない課題です。長期コースや高額プランを提供する場合、特定継続的役務提供に該当して概要書面や契約書面の交付義務が生じる可能性があります。
加えて、契約後のクーリングオフ対応や途中解約時の精算、広告表示や勧誘方法のルールなど、不安要素も多いでしょう。結論から言えば、「期間」と「金額」の要件を満たすエステ契約は特商法の規制対象となり、契約前後に所定の書面交付が必須です。
本記事では、エステサロン運営者が押さえるべき適用判断の基準、書面に盛り込むべき事項、交付・保存の実務手順、そしてクーリングオフや中途解約への対応方法や広告・勧誘上の注意点まで、わかりやすく解説します。
行政書士としての専門知識を踏まえ、書面作成や社内体制整備についても具体的なアドバイスを提示しますので、最後までお読みいただき、自社のリスク回避にお役立てください。必要に応じて書面の設計や契約オペレーション構築のご相談も承ります(電話・LINE・フォームにてお気軽にお問い合わせください)。
エステと特定商取引法の該当性判断

エステサロンのサービス契約が特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当するかどうかの判断基準について解説します。エステは法律で指定された7類型の一つですが、適用となる典型的な要件(契約期間や対価額)と、その判断フローを示します。
また、都度払いや物販セットなどのグレーケースではどのように考えるべきか、安全側の運用指針を紹介します。最後に、もし該当した場合に事業者に課される主な義務(書面交付やクーリングオフ等)の全体像を俯瞰します。
該当類型の全体像と判断フロー
エステティックサービス契約は、特商法で規制される「特定継続的役務提供」の7つの指定役務の一つです(他に語学教室、家庭教師、結婚紹介等があります)。しかし、すべてのエステ契約が直ちに対象になるわけではありません。特商法の規制対象となるには、契約内容が以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 契約期間が1ヶ月を超えること
- 契約金額(総額)が5万円を超えること
この両方を満たした場合、そのエステ契約は「特定継続的役務提供」に該当し、特商法上の書面交付義務やクーリングオフ制度等の規制対象となります。
逆に言えば、期間が1ヶ月以内で総額5万円以下の契約であれば、特商法の特別な規制(概要書面・契約書面の交付義務やクーリングオフ適用)は及びません。
例えば、「3ヶ月間の痩身コース・料金15万円」といった長期かつ高額な契約は明確に該当します。一方、「1回完結の施術(期間1日)・料金10万円」は金額は超えますが期間が1ヶ月未満のため対象外です。
また、「2ヶ月有効の回数券・料金3万円」は期間は長いものの金額が5万円以下なので対象外となります。このように期間条件と金額条件の両面から判断します。
判断フローとしては、まず提供するサービスが指定役務(エステ等)に当たるか確認し、その上で契約形態が一定期間を超える継続サービスか、支払総額が一定額を超えるかをチェックします。
エステサロンではコース契約や回数チケット、月額制プランなど継続利用を前提としたメニューが多いため、概ね期間要件はクリアします。次に入会金・化粧品代等も含めたお客様の支払総額を計算し、5万円を超えるようなら特商法適用を念頭に置く必要があります。
契約書の作成前にこれら要件を社内で確認するルールを整え、該当すれば後述の書面交付などの手続きを確実に実施しましょう。なお、店頭で締結する契約であっても要件を満たせば規制対象となる点に注意が必要です(訪問販売等でなく店舗契約でも適用されます)。
グレーケース(ハイブリッド型・セット販売)
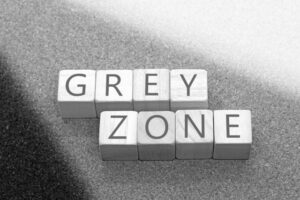
現場では、契約形態がはっきりしないグレーゾーンも存在します。例えば商品販売+役務提供のセット契約や、サロン機器のレンタル併用など複合的なサービス提供です。判断に迷う場合のポイントと、安全側の対応策を見てみましょう。
物販を伴う場合
エステ契約時に関連商品(化粧品やサプリ等)をまとめて販売するケースがあります。この場合、サービス契約部分が前述の期間・金額要件を満たせば特定継続的役務提供とみなされる可能性が高いです。
商品代金も含めて総額5万円超であれば契約全体として規制対象と考え、書面交付などの対応をしておく方が安全です(特商法ではエステ契約の付随商品を「関連商品」と位置付け、契約解除時には商品も一緒に解約できるルールになっています)。
都度払いと見せかけた継続
一見「毎回都度払いで契約を更新するから1ヶ月超の契約ではない」と説明する業者もいます。しかし、実態として同じ顧客と自動的・継続的に契約を繰り返す仕組み(例:3週間ごとの短期契約を自動更新)は、実質的に長期契約と判断される可能性があります。
形式上1ヶ月以内でも、契約書に「特に申し出がない限り更新」等の条項がある場合は実質1ヶ月超の契約とみなされかねません。対策として、自動更新制にするなら特商法対応を前提にし、そうでなければ更新時に必ず新規契約として締結し直すなど明確な運用にしましょう。
回数券・サブスク
回数券は一定の有効期間が設定されるはずです。有効期限が1ヶ月を超える回数券で総額5万円超なら対象になります。もし有効期限が記載されていない場合、それは期限の定めがない=無期限と解釈され、当然1ヶ月超とみなされます。
また、月額制サブスクリプションは終了時期が決まっていない継続契約です。いつでも解約可であっても、契約時に期間の上限なく提供を約している以上、初回契約時点で期間要件を満たすと考えるのが無難です(仮に1ヶ月単位の単発契約を毎月結ぶ仕組みであれば対象外ですが、自動継続の場合は注意が必要です)。
機器レンタル付きプラン
痩身機器を家庭向けにレンタル提供しつつ、月々サロン施術も行うようなプランもあります。このような複合契約も、サービス提供部分が長期・高額なら特商法の趣旨からいえば規制対象と考えるべきでしょう。物品の貸与部分だけで見れば単独では特商法対象外かもしれませんが、契約全体として消費者保護を図る必要があります。
以上のグレーケースでは、「法律上グレーだからやらなくてよい」ではなく、リスク管理の観点で安全側に振ることが重要です。つまり、少しでも該当の可能性があるなら必要な書面交付や説明義務を果たす運用をお勧めします。
仮に法の適用外だった場合でも、書面を交付して丁寧に説明しておくことはトラブル予防に役立ちます。一方、適用されるのに怠った場合は後からクーリングオフ延長など不利益を被る恐れがあります。契約形態に迷う場合は専門家に相談し、「該当と想定して対応する方がリスクが低い」と心得てください。
特定商取引法のエステ契約に該当した場合に生じる主な義務一覧

エステ契約が特商法の特定継続的役務提供に該当すると判断された場合、事業者には以下のような主な義務・ルール遵守が課されます。
ここで全体像を把握し、詳細は後続トピックで掘り下げます。
概要書面の交付義務(法第42条)
契約を結ぶ前に、契約内容の概要を記載した書面(概要書面)をお客様に交付しなければなりません。これは事前説明書の役割を果たし、サービス内容や料金等を紙面で説明するものです。
契約書面の交付義務(法第42条)
契約成立後は、速やかに契約内容を明記した書面(契約書面)を交付する義務があります。契約証書として、お客様に手渡し(または適法に電子交付)します。
クーリングオフ制度の適用(法第48条)
契約後でも一定期間(8日以内)は無条件で契約解除が可能です。事業者はこれを妨げてはならず、対象契約ではクーリングオフについて書面に明示しなければなりません。
中途解約への対応義務(法第49条)
クーリングオフ期間経過後も、消費者は将来に向かって契約を解約(途中解約)できます。事業者側は提供済みサービスの対価および所定の違約金のみを請求可能で、法律で定められた上限額を超える違約金は受領不可・超過分は返還義務があります。
誇大広告等の禁止(法第43条)
サービス内容や効果について、事実と違う表示や著しく優良・有利と誤認させる表示は禁止されています。広告宣伝では適正な表示を心がける必要があります。
不適切な勧誘行為の禁止(法第44条)
契約締結の勧誘に際し、虚偽の説明をしたり重要事実を故意に告げないこと、あるいは威圧的な言動で困惑させることは厳禁です。顧客を追い込むような過剰勧誘は法律違反となります。
前受金の保全・書類閲覧
前払い方式で高額な役務提供を行う場合、事業者は自社の財務状況を示す書類(貸借対照表や損益計算書等)を準備し、求めがあれば消費者に閲覧させる義務があります。
また契約書面には前受金の保全措置を講じているか記載項目があります(※実際に保全措置を取ること自体はエステ業界では努力義務に近いですが、特に大規模・高額前払いを受け入れる場合は検討が必要です)。
行政処分・罰則の可能性
以上のような規制に違反すると、業務改善指示や業務停止命令等の行政処分の対象となり得ます。一部の悪質な違反には罰則(罰金刑等)も規定されています。法令遵守は事業継続の大前提と認識しましょう。
ざっと挙げただけでも多くの義務がありますが、これらは消費者との健全な関係を保つためのルールです。適切に対応していればお客様の信頼にもつながります。次章から、特に重要な「概要書面・契約書面」と「クーリングオフ・中途解約」、そして「広告・勧誘規制と社内体制」について順に具体的に見ていきます。
概要書面・契約書面の必須記載と作成実務
特商法で交付が義務付けられる概要書面と契約書面について、その目的の違いと必須記載事項を解説します。エステサロン向けに何をどう書けばよいのか、具体例を挙げながら説明します。
また、2023年の法改正による電子交付・電子契約への対応ポイントにも触れ、紙媒体での保管と電子データでの保存管理方法についても実務的な視点でアドバイスします。書面不備によるトラブルリスクを減らし、適法かつスムーズな契約手続きを実現しましょう。
概要書面—交付タイミングと必須記載
概要書面とは、契約前に交付する書面で、お客様に契約内容の重要事項を事前に書面で説明するためのものです。エステサロンでは一般にカウンセリングやプラン提案の場面で、「それではこのコースで契約します」という直前にお渡しするイメージになります。
交付のタイミングは法律上「契約の締結前」とされていますので、署名・押印をもらう前に必ず手渡ししましょう。口頭説明だけでなく書面を交付することで、後から「聞いていない」「説明と違う」といったトラブルを防ぐ狙いがあります。
概要書面の必須記載事項は法令で細かく定められています。エステ契約の場合、主に以下の項目です。
事業者の表示
サロンの名称(屋号)、所在地、電話番号。法人の場合は代表者名も記載します。連絡先としてお客様が書面で確認できるよう明記します。
役務の内容
提供するエステサービスの内容を具体的に記載します。例えば「フェイシャルエステ(クレンジング・マッサージ・パック)」や「痩身エステ(○○機器による施術)」等、契約対象の施術コースを特定できるよう書きます。
関連商品がある場合
契約にあたって購入が必要な商品があるなら、その商品名・種類・数量を記載します。例えば「家庭用美容器1台」「施術用ジェル×2本」等です。
エステでは化粧品やサプリメントなどをセット販売することがありますが、それらがコース受講の前提になっている場合はここに明記が必要です。
役務の対価
エステサービス自体の料金およびその他お客様が支払う必要がある金銭の概算額を記載します。コース料金のほか入会金、商品代、手数料など全て含めた契約総額を書きます(不確定な場合は見込み額や計算式を示すことも可)。
「権利の販売価格」と表現されることもありますが、要はお客様負担額の総計です。
支払時期・方法
上記金額をいつ、どのように支払うかを記載します。「契約時に現金一括」「施術毎に店頭支払い」「カード払い(3回分割)」など具体的に書きます。分割払いやクレジット契約の場合はその旨も明示します。
役務提供期間
契約するサービスの提供期間を記載します。契約開始日と終了日、または「〇ヶ月間」「〇年〇月まで有効」など期間を特定します。回数券なら利用可能期間、月額プランなら契約単位(例:1ヶ月単位で自動更新等)を示します。
クーリングオフに関する事項
契約後8日以内は書面または電子書面で契約解除(クーリングオフ)できること、およびその方法を記載します。一般的には「本契約は契約書面を受領した日を含め8日間は書面(郵送または電磁的記録)により無条件で契約解除できます。その際、お客様に費用負担は生じません」等と書きます。後段の契約書面でも重複して記載しますが、概要書面にも明記が必要です。
中途解約に関する事項
クーリングオフ期間経過後でも途中解約が可能であること、その際の精算方法や違約金のルールを記載します。
例えば「提供済みサービスの料金相当額と、未提供分の10%(上限2万円)の違約金をご負担いただきます」等、法律に沿った範囲で具体的に書いておくと親切です(詳細は後述の中途解約ルール参照)。
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
もしお客様がクレジット払い(割賦払い)を利用する場合、割賦販売法に基づき一定条件下でクレジット支払いの停止を主張できる権利が消費者にあります(抗弁権の接続)。その旨を一文記載します。
前受金の保全に関する事項
事業者が前受金の保全措置(保証契約や保険契約など)を講じている場合は、その内容を記載します。多くのエステサロンでは特段の保全措置を取っていないと思いますので、その場合は「なし」と記載します。
例えば一部の大手で銀行に預託金を積んでいる場合は「〇〇信託に営業保証金預託」等と書きます。
特約があるときはその内容
標準の契約条件とは別に特別な取り決め(特約)を設ける場合、その内容を記載します。例えば「○ヶ月以内に中途解約する場合は○○のサービス分は返金対象外とする」等、個別の条件があれば明示します。
ただし消費者に不利な特約は無効となる恐れがありますので、内容は慎重に検討してください。
以上が概要書面に最低限記載すべき事項です。実際の様式としては、箇条書きでこれら項目を網羅したひな形フォーマットを用意し、契約内容に応じて数字や商品名などを書き込めるようにすると便利です。
エステの場合、コース毎の料金表や施術内容一覧を添付資料として渡すこともありますが、概要書面本文にも契約するコースの要点を必ず書き込みましょう。
また、概要書面は基本的にお客様に控えとして渡すものですので、2部用意して1部はお客様へ交付し、もう1部をお客様の署名付きで事業者側が保管する形が望ましいです(署名までは義務ではありませんが、受領の証拠としてもらっておくと安心です)。
交付時には単に手渡すだけでなく、「重要事項が書かれておりますのでご確認ください」と声をかけ、お客様が目を通す機会を作りましょう。後々の紛争時には、この概要書面に記載があるか否かが判断材料になります。
例えば「聞いていない」と言われても、「書面でお渡しし説明しています」と反証できるので、きちんと記載・交付すること自体がリスクヘッジとなります。
契約書面—成立要件と不備リスク
契約書面とは、契約成立後に交付する書面で、正式に契約内容を確認・証拠化するものです。いわば契約証書であり、双方の合意内容が詳細に記載されています。概要書面と重複する事項もありますが、法律上はこちらにもれなく記載することが求められます。
契約書面は契約締結後遅滞なく交付する決まりですので、通常は契約手続きを終えたその場でお渡しします。お客様には大切に保管してもらうよう伝えましょう。
契約書面の必須記載事項は以下の通りです(概要書面と共通する部分には★を付しています)。
★役務(権利)の内容
契約したエステ施術の内容を改めて明記します。概要書面と同様、「フェイシャルエステ〇〇コース(◯回)」等具体的に書きます。必要商品の有無も記載(「関連商品:〇〇クリーム2個」など)。
★役務の対価・支払う金銭の額
契約総額を正確に記載します。こちらは最終確定金額となります(税金や手数料含めた総計)。また、内訳(コース料金○円、商品代○円、入会金○円等)を明示すると親切です。
★支払時期・方法
実際の支払条件を記載します。例えば「本日現金○円支払い済、残額○円は翌月から6回分割でクレジット払い」等、確定した支払スケジュールを書きます。クレジット会社名や分割回数なども記載するとよいでしょう。
★役務提供期間
契約したサービスの提供期間(契約有効期間)を記載します。開始日・終了日を特定し、「全○回の施術を○年○月○日までに提供する」等と書きます。開始日については契約日と同じ場合もありますし、「初回施術日は○年○月○日」と個別に定めるケースもあります。
★クーリングオフに関する事項
概要書面と同様に、8日以内の無条件解約可であることを明記します。契約書面では特に赤枠・赤字でその旨を強調して記載するよう求められています(法定書式のルール)。
実際には契約書の末尾近くに「〈クーリング・オフについて〉本契約は契約書面受領日を1日目として8日間は書面または電子メール等で解除できます。(中略)本項は赤枠・赤字で記載」などと書きます。
★中途解約に関する事項
これも概要書面同様記載します。契約書面では例えば「8日間のクーリングオフ期間経過後でも、お客様は将来に向かって本契約を解約できます。
その際の精算は提供済みサービス料金○円+違約金○円(未提供役務残額の○%、上限○円)」等と、より具体的に条項として書く形になります。法律で定める上限額以上は請求しない旨を必ず契約条件に盛り込んでください。
事業者の表示
事業者名、住所、電話番号、代表者氏名(法人の場合)を記載します。【概要書面では冒頭に記載しましたが、契約書面でも改めて書きます】。これらはクーリングオフ通知の送り先としてお客様に周知させる意味もあります。
契約担当者の氏名
契約の締結を担当したスタッフの氏名を記入します。これは概要書面にはない項目です。誰が勧誘・契約手続きを行ったか記録するためで、将来トラブルになった際の責任所在を明確にする意味もあります。必ずフルネームで記入しましょう。
契約締結の年月日
契約を実際に締結(サイン)した日付を記載します。クーリングオフ期間計算の起点にもなる重要日付です。その場で記入し、お客様にも確認してもらいます。
購入が必要な商品の種類・数量
関連商品がある場合、その品名・数量を記載します(概要書面と同様)。契約書面では実際に購入するものを確定して記載します。
★割賦販売法の抗弁権接続
クレジット利用の場合の支払停止抗弁権について記載します(概要書面同様)。契約書面でも省略せず書きましょう。
前受金の保全措置の有無・内容
事業者が前受金保全を行っているか、その有無と内容を記載します。多くの場合「無(保全措置なし)」となるでしょうが、例えば倒産防止のための保証保険に加入しているなら「〇〇社の前払金保証サービス加入(保証限度額○○円)」等と書きます。
関連商品販売業者の表示
エステの関連商品を別業者が販売する形になっている場合(例えばサロンは仲介で実際の販売者がメーカー直販等)、その販売業者の氏名・住所・電話・代表者名等の情報を記載します。自社で販売する場合は不要です。
特約の内容
特別な取り決め事項があれば記載します(概要書面と同様)。特約を設ける場合、消費者の契約解除権を不当に害するような内容は無効になりますので、法律の範囲内で合理的なものに留めてください。
上記に加え、特商法の規定で「書面をよく読むべきこと」を赤枠赤字で注意書きすることも求められています。
特定商取引法とエステ:電子交付・電子契約・保存

近年のデジタル化の流れを受け、特定商取引法でも書面交付の電子化が認められるようになりました。ただし、電子交付を行うにはいくつか厳格な条件があります。また、社内での契約書類の保存管理についても電子化時代に対応した仕組みづくりが必要です。
この項目では、電子契約への対応ポイントと、契約書類の保管実務について解説します。
電子交付の条件
2023年の法改正により、事前の顧客の承諾を得た場合に限り、概要書面や契約書面を電子的な方法(電子メール送信やウェブ上の電磁的記録提供など)で交付することが可能となりました。
ただし、電子交付であっても書面交付と同等以上に確実に内容を伝達することが求められます。主なポイントは次の通りです。
事前の承諾取得
お客様が電子交付に同意していることが必要です。通常は契約手続きの前に「契約書類を電子メール等でお送りしてもよろしいですか?」と確認し、承諾を明示的にもらいます。この同意は証拠が残る形で取得しましょう。
再閲覧性の確保
お客様が受け取った電子書面を後日いつでも閲覧できる状態にしておく必要があります。具体的には、PDFファイルをメール添付で送る場合はお客様自身が保存すればOKです。
しかし、ウェブシステム上で提示する場合は「マイページでいつでも閲覧・ダウンロードできるようにする」等の対応が必要です。一度きりしか見られない形式だと要件を満たしません。
紙面希望時の対応
お客様が希望すれば紙の書面で交付する義務は残っています。電子交付の同意は強制できませんので、電子が嫌だと言われたら従来通り紙を渡しましょう。
また、一度電子交付に同意したお客様でも「やはり紙でも欲しい」と言われた場合は、速やかに紙を提供するのが望ましいです。
メール等の送付記録
電子交付を行った場合、いつ・どの方法で・どのアドレスに送信したか等の記録を残しておきましょう。万一「受け取っていない」というトラブルになった際に、送信ログが証拠になります。開封確認機能や、Webの場合はアクセスログなども活用したいところです。
全店統一と旧版破棄
複数店舗を運営する場合、契約書式は全店で統一することが望ましいです。法改正対応などで変更があった際は、全店舗一斉に新様式へ切り替え、旧様式は使えないように回収・破棄します。
店舗ごとに古い書面を使い続けてしまうと、どこかで法定事項漏れが起こるかもしれません。社内通達や研修等で周知徹底しましょう。
電子交付や電子契約は効率的ですが、「承諾取得」「再閲覧性」というポイントを守らなければ違法扱いとなるリスクもあります。実務上は無理に電子化せず、お客様の層に応じて適切な方法を選ぶと良いでしょう(高齢層が多ければ紙の方が安心、といった判断)。
いずれの場合も、契約書類は適切に保存し、いざという時に取り出せるようにしておくことが肝心です。特商法対応の電子化について不安がある場合は、無理せず専門家に相談しながら進めましょう。
特定商取引法とエステ:クーリング・中途解約・返金精算の設計

エステ契約におけるクーリングオフと中途解約の制度、および返金精算の方法について解説します。契約後8日以内であれば無条件解約できるクーリングオフの具体的な運用(期間の数え方、通知方法、例外事項など)や、期間経過後の途中解約時に事業者が請求できる金額の上限(提供済み役務の対価+一定の違約金)を分かりやすく説明します。
また、実際に解約申し出があった際の返金手続きフローや、クレーム対応の社内プロセスについても触れ、円滑かつ公正に対応するためのポイントを紹介します。
クーリングオフ実務
クーリングオフとは、契約後に一旦冷静に考え直すための制度で、特定商取引法では特定継続的役務提供契約について8日間の無条件解約期間が定められています。
エステサロンの契約でも、該当する場合はお客様は契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず一方的に契約解除が可能です。では、その具体的な手順や注意点を確認しましょう。
期間の起算
クーリングオフ期間の数え方は、「契約書面を受領した日」を1日目として8日間です。例えば契約書面を4月1日に渡したら、4月8日までがお客様のクーリングオフ権利行使期間になります(4月8日消印有効)。
通知の方法
お客様がクーリングオフを行うには、事業者あてに書面または電磁的記録で解除の意思表示を行います。一般的にはハガキや封書で通知されることが多いです(その際、確実に証拠を残すため特定記録郵便や簡易書留・内容証明郵便で出されることがあります)。
2023年以降は電子メール等による通知も認められていますが、メールの場合は送信日時や内容が証拠として残るよう、お客様に保存をお願いするのが望ましいです。いずれの方法でも、8日目までに発信していれば有効と解されます。
事業者の対応義務
クーリングオフの通知を受け取ったら、事業者側はただちに契約解除の手続きを取ります。引き止めや妨害は厳禁です。お客様が既に支払った代金があれば全額を速やかに返金します。具体的な返金フローは次項で述べますが、基本的に違約金や手数料は一切請求できません。
役務提供と費用負担
クーリングオフは無条件解除ですので、たとえ8日以内に一部サービスを提供済みでも、お客様はその対価を支払う必要がありません。例えば契約2日後に1回施術を受けていても、クーリングオフすればその1回分も含め全額返金です。
関連商品を既に渡している場合は、事業者負担で回収します。お客様が消耗品(健康食品や化粧品など)を使用済みの場合、その分はクーリングオフ対象外となる例外規定もありますが(商品の価値が著しく減少した場合)、基本的に提供済みの役務・商品の代金も含めてお客様負担ゼロになると考えておいてください。
期間延長事由
法律では、お客様が「事業者に騙されたり威圧されたりしてクーリングオフできなかった場合」には、8日を過ぎてもクーリングオフ可能と定めています。つまり、不実告知や威迫による誤認・困惑があった場合は無期限にクーリングオフの期間が延長されるのです。
悪質な勧誘を行えば、いつまでも解約されるリスクがつきまとうということです。また、そもそも契約書面を渡していなければ期間は進行しません。書面不備のまま8日過ぎても、お客様は「正式な書面もらってないから今からでもクーリングオフする」と主張できます。これらの点からも、適正な勧誘と契約書面交付がどれだけ重要かわかります。
通知先の指定
クーリングオフ通知を送る宛先は契約書面に記載された住所・担当部署となります。誤って違う住所に送られた場合などトラブルになりますので、契約書面には正確な事業者住所を記載し、社内でも郵便の受け取り漏れがないよう注意しましょう(内容証明などは不在だと郵便局保管になりがちなので、管理を徹底します)。
顧客対応
お客様から「クーリングオフしたい」と電話等で問い合わせがある場合、即座に手続きをご案内しましょう。書面での意思表示が必要とはいえ、電話口で拒否したり渋ったりすると後で揉める元です。
「ご連絡ありがとうございます。ご郵送でもメールでも結構ですので、○月○日までに解除の旨をご送付ください。受領しましたら速やかにご返金いたします」といった対応が望ましいです。
事業者側としてクーリングオフは痛手に感じるかもしれませんが、法律で保証された消費者の権利ですので真摯に受け止めましょう。むしろ、クーリングオフが発生しないよう契約前にお客様に十分納得いただくことが最大の防止策です。
強引に契約を取ってもほとんどキャンセルされては意味がありません。前項までの書面交付・説明をしっかり行い、お客様が冷静に判断できる環境を整えることが、結果的にクーリングオフ件数の低減につながります。
エステと特定商取引法:解約と違約金上限

クーリングオフ期間を過ぎた後でも、お客様は「将来に向かって」契約を解除(中途解約)することが認められています。
これは、残りのサービス提供を止める代わりに、事業者に一定の賠償金(違約金)を支払って契約を終了するものです。
エステ契約では、法律で中途解約時に請求できる金額の上限が細かく定められており、事業者はそれ以上の金銭を受け取ることはできません。具体的には以下の通りです。
役務提供開始前の解約
契約後、クーリングオフ期間も経過したが一度も施術を受けないまま解約する場合、事業者が請求できるのは「契約の履行のため通常要する費用」として政令で定められた額のみです。エステの場合はその額が2万円と定められています。
したがって、お客様がサービス開始前に解約した場合は、最大2万円までを違約金等として受け取れます。それ以上に前受金をもらっていたら、差額は返金する必要があります。
役務提供開始後の解約
既に一部でも施術を提供した後に解約する場合は、事業者は以下の2つを合計した金額を請求できます。
提供済み役務の対価
これはお客様がすでに受けた施術の料金相当額です。例えば10回コースで2回利用済みなら、その2回分の料金を通常価格換算で算出します(契約総額から按分計算する方法が一般的です)。
違約金
未提供の役務について発生する事業者側の損害に対する賠償金ですが、法律上上限額が決まっています。エステ契約では「未提供分の役務残額の10%」または「2万円」のいずれか低い額が上限です。
つまり、残りサービス代金の10%が2万円を下回る場合はその10%額、10%額が2万円を超える場合でも請求できるのは2万円までとなります。
| (例)総額30万円・20回コースで、10回利用後に解約するケースを考えます。残り10回の未提供分金額は15万円(仮定)。この10%は1万5千円です。2万円との比較で低い方は1万5千円なので、違約金は1万5千円まで請求可能です。
提供済み10回分の料金は15万円分をいただき、未提供分15万円のうち1万5千円を違約金としていただけます。よってお客様への返金額は残額15万円−違約金1.5万円=13.5万円となります。契約時に前払いで30万円全額受領していた場合、事業者は提供済み分15万円+違約金1.5万円=16.5万円を手元に残し、残り13.5万円を返金する計算です。 |
中途解約条項の整備
前述のとおり、契約書にはこの解約時の清算方法を記載します。法定上限を超える違約金設定は無効ですので、契約約款でも「違約金は未履行残額の◯%(上限◯円)」と明記しておきましょう。
稀に「途中解約一切不可」「残金は返金しない」などの約款を見かけますが、これらは特商法に反し無効となります。
違約金以外の費用
事業者によっては「解約手数料」「返金事務手数料」と称して別料金を請求したいかもしれません。しかし、それらも違約金と同様に扱われるため、合計して上記上限を超えることは許されません。「違約金ではなく手数料だから別枠」という言い訳は通用しませんので注意してください。
提供済み役務の対価
提供済み分については当然お客様も支払う義務がありますが、その算定は合理的に行います。例えば、通常1回あたりの単価を契約総額から按分計算する方法が一般的です(総額÷総回数=1回単価)。
事業者が恣意的に「既提供分は定価換算で○○円だから高額」などと計上するとトラブルになります。契約時に「中途解約時の清算方法」を明示することでお客様の理解も得られやすくなります。
返金の義務
お客様から前受金を預かっている場合、中途解約時には計算の結果過剰分を返金しなくてはなりません。すぐに返金できないと信用を損ないますので、十分なキャッシュフローを確保し、返金原資を常に用意しておくことが肝心です。
エビデンスの確保
中途解約精算を巡って「何回利用したか」「いつ解約を申し出たか」で揉めることがあります。防止策として、来店履歴や施術カルテ、契約者とのやり取りをしっかり記録しておきましょう。
施術毎にサインをもらう来店カードを活用したり、予約システムで履歴を保存するのも有効です。また、解約の申し出が電話であった場合は日時と対応者をメモし、後日書面でも解約の意思確認をしておくと確実です。
まとめると、中途解約時の事業者取り分はかなり限定されていることを認識しましょう。顧客からすれば良心的な制度ですが、事業者にとっては「大きく儲けを削られる」場面です。
だからといって解約をゴネたり認めない態度をとると、かえって消費者センター等に訴えられ悪印象となります。法律に則った範囲で速やかに対応し、残金を返すべきものは返すことが、結果的にトラブルの早期解決につながります。
エステと特定商取引法:返金・苦情対応フロー
実際にお客様からクーリングオフや中途解約の申し出があった際、事業者側で適切に処理することが重要です。ここでは、返金対応の具体的なフローと、クレーム発生時の社内対応手順について整理します。
あらかじめ標準的なプロセスを決めておくことで、現場のスタッフも落ち着いて対処でき、二次トラブルを防止できます。
返金・解約処理の基本フロー
申出の受付
お客様からの解約・返金依頼を受け付けます。来店・電話・メール・郵送など経路は様々ですが、いずれの場合も速やかに担当者に伝達される仕組みを作りましょう。受付時には契約者名、契約日、申し出日を記録します。
本人確認
解約手続きを進める前に、お客様ご本人からの申し出であることを確認します。対面なら間違いないですが、電話やメールの場合、契約時に登録の電話・メールか、氏名・住所等で照合します。不正な第三者からの申出でないか留意しましょう。
契約内容の照合
社内の契約台帳や管理システムで、そのお客様の契約内容を確認します。契約書控えを取り出し、コース内容・支払金額・利用履歴・特約事項などを把握します。これにより、何を精算すべきか全体像が掴めます。
返金額の計算
前項のルールに従い、提供済みサービスの料金と違約金(必要な場合)を算出します。具体的には、「契約受領金額-(提供済み分料金+違約金)」が返金額となります。
クーリングオフなら提供済み有無に関わらず全額返金、中途解約なら上記算式で計算します。計算結果はダブルチェックし、誤りがないようにします。
お客様への説明
算出した返金額とその内訳をお客様に伝えます。電話や対面であれば口頭で、「○○様は○回ご利用済みですので、その分○円をご負担いただき、未利用分○円のうち違約金○円を差し引いて○円をご返金いたします」と丁寧に説明します。
メールや書面で連絡する場合も、同様に内訳を記載して理解いただけるようにします。ここで疑問や異議が出れば、記録を示しながら誠意を持って説明し、納得いただくことが大切です。
返金の実行
合意した返金額を速やかに返金します。現金払いだったなら指定口座への振込、クレジット決済なら取り消し処理または振込対応など、適切な手段で行います。
振込の場合は送金控えを保管し、日付と金額を記録しておきます。法律上「速やかに返金」とあるので、できれば申し出から1週間以内、遅くとも2週間程度で完了させたいところです。
完了報告と記録
返金処理が終わったら、お客様に「解約手続きが完了しました」旨を連絡します。書面で完了通知書を郵送するのも丁寧です。
苦情・トラブルへの対応
解約以外にも、サービスに対するクレームや勧誘時のトラブル報告などが起こり得ます。これらに適切に対応することも重要です。
苦情受付の体制
お客様からの苦情を受け付ける窓口を明確にし、スタッフ全員に共有しておきます。初期対応をアルバイト任せにすると火に油を注ぐケースもあるため、店長やマネージャーが直接対応するようルール化すると良いでしょう。
LINE公式アカウントや専用フォームで24時間受付け、翌営業日に責任者が連絡する仕組みも有効です。
初期対応
苦情を受けたら、まず傾聴と謝意が基本です。お客様の話を遮らず最後まで聞き、「ご不快な思いをさせ申し訳ございません」と一旦お詫びを伝えます。
その上で事実確認し、可能な解決策を提示します。例えば「施術結果に不満」という苦情なら、再施術の提案や一部返金など、相手の要望も踏まえて柔軟に検討します。
威迫・過量勧誘の指摘
もし「スタッフに無理やり契約させられた」「威圧的だった」といった勧誘トラブルの苦情があれば、これは重大です。
すぐにクーリングオフ等の権利行使を案内し、謝罪の上で速やかに契約解除・返金する方向で対応しましょう。再発防止策(当該スタッフの指導等)も伝えると、お客様の怒りも和らぎます。
二次被害防止
クレーム対応でさらにお客様を怒らせてしまう「二次被害」は絶対避けねばなりません。よくあるNG例は、スタッフが感情的に言い返したり、責任逃れしようと言い訳ばかりすることです。こうした対応は口コミや消費生活センター相談につながり、信用失墜の原因になります。
クレーム対応マニュアルを整備し、「絶対にしてはいけない対応」「推奨される対応例」を事前教育しておきましょう。特に電話応対の口調や言葉遣い、解決策の提示方法などはロールプレイング訓練も有効です。
苦情記録と改善
受けた苦情は内容・日時・対応結果を必ず記録し、社内で共有します。どんな苦情が多いのか分析し、サービス改善に活かしましょう。例えば「勧誘がしつこい」という声が複数あれば勧誘方法の見直しを検討すべきですし、「予約が取りにくい」という不満があれば予約枠拡充を考える等、PDCAサイクルで運用改善に繋げます。
苦情はネガティブなものですが、それをヒントにサービス向上できれば将来的なトラブル減少と顧客満足度向上に資します。
エステと特定商取引法:勧誘・広告表示・運用体制の実装

特商法への対応は、書面交付や解約対応だけではなく、日頃の勧誘方法や広告表示、そしてそれを支える社内体制にも及びます。
ここでは、エステサロンが守るべき広告・宣伝上のルールや、店頭での勧誘・説明における注意事項を整理します。
また、違反を防ぐための社内教育や監査の仕組みについても提案します。来店前の広告から、契約時のやりとり、契約後のフォローに至るまで、一貫して法律を遵守しつつ顧客満足を高めるための実装ポイントを見ていきましょう。
広告・Web表示の留意点
顧客が最初に目にする広告やウェブサイトの表示にも、特商法をはじめ様々なルールがあります。誇大な広告は法律で禁止されていますし、景品表示法など他の法律とも絡む領域です。ここでは特にエステ業界で注意すべき広告表示のポイントを挙げます。
体験価格・期間限定表示
集客のために「初回体験○円!」や「今月限定半額」等の表現を使うことがあります。この場合、本当に限定なのかを明確にしましょう。常に初回○円でやっているのに「今だけ」と煽ると、不当表示(有利誤認)になる恐れがあります。
期間限定なら具体的な期限を示し、誰が見ても検証可能な形にします(例:「◯月◯日までの契約限定」)。
回数・総額の明示
エステは回数や期間によって料金が変わるため、広告には総額と回数をセットで表示しましょう。例えば「月額1万円」とだけ書くと、何ヶ月必要か分からず誤認を招きます。
「6ヶ月総額6万円(月々1万円)」など、条件をきちんと伝えます。総額表示義務(消費税込み価格の表示)にも留意が必要です。
ビフォーアフター写真
施術効果を示すためによく使われますが、これは実際の典型例でなければなりません。過度に修正したり別人のような写真を使うと、事実と相違する表示と見なされます。
また個人差が大きいものなので、「※効果には個人差があります」等の断り書きを添えると誠実です。医療広告規制ほど厳しくはないですが、不可能な効果を暗示しないよう注意します。
医療的効能のNGワード
エステはあくまで美容サービスであり、医療行為ではありません。「治療」「治す」「〇〇症に効く」等の医療効果を謳う表現はアウトです。
例えば「脂肪を溶解する」「永久脱毛保証」なども医療行為を想起させるのでNGです(永久脱毛は医療機関しかできません)。「サイズダウン例:ウエスト-5cm(当社調べ)」くらいに留め、断定的な表現を避けましょう。
著しい優良誤認
特商法第43条では、「実際より著しく優良・有利と誤認させる表示」を禁じています。例えば「世界一痩せるエステ」「絶対にリバウンドしません!」などは明らかに行き過ぎです。
また「当社比○○%アップ」等、根拠不明なデータも注意です。広告表現は根拠を持って説明できる内容に限定しましょう。
料金の表示方法
前述の通り、税込総額表示が原則です。分割払い可能ならその旨記載しつつも、まず総額を大きく表示します。また「商品代別」「オプション別」など追加費用がある場合は見落とされない場所に書いておきます。
お客様が後で「聞いてない」と言いがちな点(入会金・ローン手数料など)は、広告段階から示すくらいが親切です。
自動継続の明示
定期コースやサブスクの場合、「自動更新されます」「解約しない限り継続課金されます」といった重要事項をきちんと表示します。小さな注釈にせず、プラン説明の本文中に明記するぐらいが望ましいです。
おとり広告の禁止
極端に安いプランを大きく宣伝し、来店後に「そのプランはもう終了したので高額プランに…」という手法は信用を失います。実際には用意する気がない安価商品を釣り餌にするおとり広告は景品表示法でも禁止です。誠実な広告で集客し、その後も誠実に説明するという一貫性が重要です。
広告は一方的な情報発信ゆえ、法律遵守だけでなく顧客目線で誤解がないかをチェックすることが大切です。自社で作成した広告文も、第三者に読んでもらって「不明点はないか」「期待させすぎていないか」を確認すると良いでしょう。悪意なくても違反になることもありますので、常に正直で透明性のある表現を心掛けてください。
勧誘・説明オペレーション
お客様が実際に来店してから契約に至るまでの勧誘・説明プロセスも、特商法の規制対象です。ここでは、店舗でのカウンセリングから契約締結までの間に留意すべき事項をまとめます。
過量勧誘の禁止
特商法では、しつこく勧誘を続ける行為も禁止されています。例えばお客様が「今日は契約しません」と明言したのに何度も引き止める、長時間返さない等は過量勧誘とみなされ違法です。
相手の意思表示を尊重し、「ぜひご検討ください。またご連絡お待ちしています」と潔く切り上げる勇気も必要です。
威迫・困惑行為の禁止
契約させるために威圧的な態度や言動をとるのは言語道断です。大声で畳みかける、人格を否定するような発言(「このままじゃ恥ずかしいですよ」等)は絶対NG。
また、帰ろうとするのを妨げたり、クレジット申込を書くまで解放しない等も違法です。常に相手の自由意思を尊重しましょう。
不実告知・事実不告知の禁止
嘘をついて契約させる(不実告知)ことはもちろん、都合の悪い事実を故意に隠す(事実不告知)ことも禁止です。例えば「この効果は学会で証明済み」とデタラメを言ったり、逆に「クーリングオフできる」ことをわざと説明しないのはアウトです。
聞かれなくても重要事項はこちらから積極的に説明する姿勢が求められます。
書面を用いた説明
先述の概要書面を交付する際、ただ渡すだけでなく読み合わせを行うと理解度が高まります。重要ポイント(期間・総額・解約条件など)は口頭でも強調し、「こちらに書いてある通り、8日以内なら無条件解約できます」と指差し確認するような丁寧さが理想です。
署名前の再確認
契約書へ署名をいただく直前に、「最後に内容をご確認ください。ご不明点はございませんか?」と再確認の時間を設けましょう。お客様自身にもう一度書面を読み返してもらい、納得の上で署名いただくことで、「説明不足」を原因とするトラブルは激減します。急かさず、お客様のペースに合わせることが大切です。
複数スタッフによるチェック
可能であれば、勧誘担当者とは別のスタッフ(店長等)が契約直前に同席し、「重要事項のご説明は全てお聞き及びでしょうか」と軽く確認すると安心です。これを嫌がるお客様はいませんし、万一担当者が何か抜けていてもカバーできます。
過大な約束をしない
勧誘時に「絶対痩せます」「絶対シミが消えます」といった結果保証を口にしないことも肝心です。後で結果が出なかった場合に「話が違う」と揉める原因ですし、そもそも不実告知に当たりかねません。
「個人差がありますが、◯◯様の場合◯kg減を目指しましょう」等、あくまで目標・目安として伝えます。理想像を語りすぎず、現実的な線を守ることで、顧客期待値を適切にコントロールします。
要するに、正直かつ丁寧な説明こそが最良の勧誘方法です。強引に売り込まなくても、内容に納得したお客様は契約してくださいますし、その方がクーリングオフもされにくいのです。スタッフには法律遵守を徹底させ、同時に「お客様に寄り添った提案」というホスピタリティ精神を養うよう教育しましょう。
特定商取引法とエステ:FAQ(よくある質問と回答)
最後に、エステサロンの特商法対応に関してよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。疑問点の解消にお役立てください。
Q1.都度払いでも特商法の規制対象になりますか?
A.基本的に都度払い(1回ごと単発利用)であれば、特定継続的役務提供には該当しません。特商法の規制対象は「長期かつ高額な継続サービス契約」ですので、その都度単発で契約・支払いを完結させる場合、期間も金額も要件を満たさないからです。
ただし注意点として、形式的に都度払いに見えても実質は継続契約になっているケースです。例えば「毎月自動予約が入るメンバーシップ制」などは都度払いでも継続提供の契約と評価されかねません。
純粋にお客様が来たい時だけ来て1回分だけ払うというスタイルなら特商法上の書面交付義務等はありませんが、契約書を交わさなくても利用規約等で権利義務は明確にし、トラブル防止に努めることをお勧めします。
Q2.エステの回数券や月額制サブスクプランはどのように扱えばいいですか?
A.回数券は、まとめ買いで後日複数回利用する典型的な継続サービスです。利用期間が1ヶ月を超え、かつ総額5万円超となる場合は特商法の規制対象となります。
たとえ都度チケットを消費する形でも、一括前払いで複数回受ける権利を購入している以上、契約時に概要書面・契約書面を交付し、クーリングオフ等のルールを適用する必要があります。
月額制サブスクについても、自動更新型で長期間継続する前提なら同様に規制対象と考えるべきです。初月無料や月額低料金から始まるプランでも、お客様がそのまま継続すれば結果的に高額になり得ますので、契約開始時に特商法対応をしておくのが安全です。
ただし、例外的に「1ヶ月単位の契約を毎月お客様が更新する形式」であれば各契約ごとに期間1ヶ月以内となり対象外とも解釈できます。しかし実務上そこまで区切って運用するのは煩雑ですし、万一認識違いがあるとトラブルになります。
Q3.書面の電子交付は具体的にどこまで認められているのでしょうか?
A.2023年6月以降、特商法の書面交付義務については電子的方法での提供が一定条件下で認められています。概要書面・契約書面ともに、事前に消費者の承諾を得ていれば、例えばメールでPDFを送信する形での交付が可能です。
また、電子サインによる契約締結もOKとなりました。ただし、電子交付した場合も紙で交付した場合と同等の効力・内容が求められる点に注意が必要です。例えば、契約書面のクーリングオフ欄は赤枠・赤字で記載する決まりですが、電子契約の場合もPDF上でそれを実現する必要があります。
また、お客様が希望すれば紙の交付にも応じるべきです。現状では「電子でもOKだが細かい要件が多い」ため、完全電子化に踏み切れていない事業者も多い印象です。
Q4.中途解約時の違約金は具体的にどのくらいまで取れるのでしょう?
A.エステ契約の場合の違約金上限は、繰り返しになりますが提供開始前2万円、提供開始後は未提供役務残額の10%か2万円の低い方となります。これは法律で上限が決まっており、契約書でそれ以上高く設定しても無効です。
たとえば50万円のコース残額がある段階で解約されても、10%は5万円ですが上限2万円なので2万円までしか頂けません。逆に残額10万円なら10%は1万円ですからその範囲内で請求可能です。
要するに、最大でも2万円程度と覚えておけば概ね間違いありません。また、提供済みの施術分はその対価を頂けますが、それも最初に取り決めた計算方法で公正に算出する必要があります。注意:違約金以外の名目でお金を取ること(解約手数料など)は、実質的に違約金とみなされ、合計額で上限を超えると違法ですので避けましょう。
Q5.途中でコース変更や追加契約をした場合、改めて書面を交付する必要がありますか?
A.必要です。コース追加やプラン変更は、お客様にとって契約内容の重要な変更ですから、基本的には新規契約と同様の手続きが必要と考えてください。
例えば既存コースにもう10回追加する場合、追加分について新たな概要書面・契約書面を交付し、クーリングオフ等の権利もその追加契約に対して発生します。また、当初契約を変更して総回数や金額を修正する場合も、変更契約書を作成して双方署名するのが望ましいです。
そうしないと、後から「追加分は聞いてない」「前の書面に書いてないから無効では?」といった争いになりかねません。一度交わした契約を変更する際も書面主義を貫くのがトラブル予防の鉄則です。
Q6.未成年者や高齢者と契約を結ぶ際に配慮すべきことはありますか?
A.未成年者(民法改正後は18歳未満)は、原則として保護者の同意なく契約すると後で取り消されるリスクがあります。特に高校生以下のお客様の場合、必ず親権者の同意書または同席を求めるようにしましょう。
18歳・19歳は成年ですが、社会経験が浅いため極力慎重に説明し、必要なら家族と相談する時間を与えるなど配慮します。また契約書に生年月日欄を設け年齢チェックをすることも有効です。
高齢者の場合、判断能力に不安があるケースも考えられます。契約内容を噛み砕いて説明し、理解いただけたか確認することが大切です。場合によってはご家族に説明を一緒に聞いてもらうのも良いでしょう。また、高齢のお客様は後日クーリングオフを忘れてしまう可能性もあるため、契約後フォローコールを入れて内容再確認する等のケアも考えられます。いずれにせよ、判断力が十分でない可能性のある方との契約は慎重にというスタンスで、無理な勧誘は厳禁です。
Q7.外国語しか話せないお客様や通訳を介した契約の場合、どのように説明を確実にすればいいですか?
A.日本語が通じない、あるいは不自由なお客様と契約する際は、言語の壁を取り除く配慮が必要です。理想的には、契約書類と概要書面をそのお客様の母国語に翻訳した版を用意し、それを使って説明・署名してもらうことです。
難しい場合は、信頼できる通訳を介して全内容を逐一説明します。このとき、通訳者にも契約内容と法定説明事項を正しく理解させておく必要があります。お客様には通訳を通じてでもクーリングオフや解約条件まで確実に伝わったか確認しましょう。
また、後日の証拠として、例えば「英語版の概要書面を確かに交付した」「通訳者〇〇氏立会いのもと説明した」等、契約書に一筆添えておくのも有用です。言葉のハンデが原因でトラブルになるケースもありますので、外国語対応マニュアルを用意し、できれば主要言語の書面テンプレートも備えておくと安心です。
エステ契約による特商法書面の作成はお任せください

エステサロンの特定商取引法対応について、概要から実務ポイントまで網羅的に解説してきました。適用要件の判断、概要書面・契約書面の整備、クーリングオフや中途解約の処理、広告・勧誘の留意点、社内体制の構築と、多岐にわたる内容でしたがご参考になりましたでしょうか。
法令を遵守し適切に運用することで、顧客との信頼関係が強まり、健全なサロン経営につながります。当事務所では、「概要書面・契約書面のドラフト作成+電子交付運用設計」といったパッケージサービスもご提供しております。実際の店舗オペレーションにフィットした形で契約書類を作成し、運用チェックリストの作成まで包括的にサポートいたします。
初回相談(30分程度)は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。お電話、LINE、フォームのいずれからでもご相談可能です(平日10:00〜18:00受付)。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁
※本記事の内容は2025年現在の法令に基づく一般的な解説です。法律やガイドラインは改正されることがありますし、個別のケースで対応方法が変わる場合もあります。本記事で述べた事項も将来的に変更となる可能性がある点ご了承ください。また、具体的な事案に適用する際には専門家による個別相談をお勧めします。当事務所も随時ご相談を受け付けておりますので、エステサロンの特商法対応でお困りの際はお気軽にお声掛けください。ご一緒に万全の体制を整えてまいりましょう。

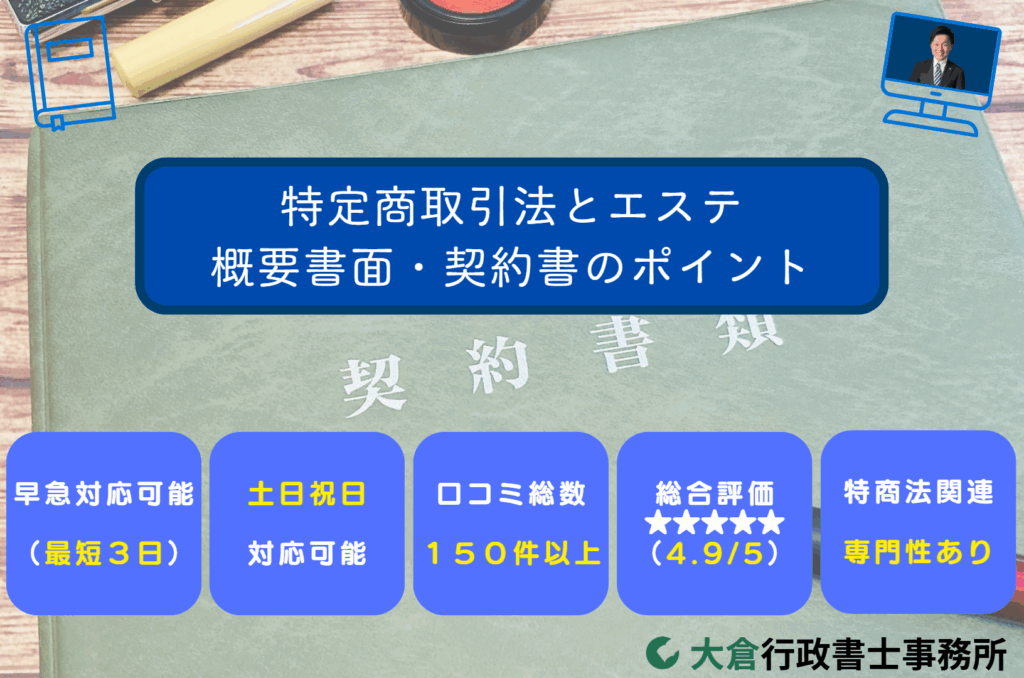
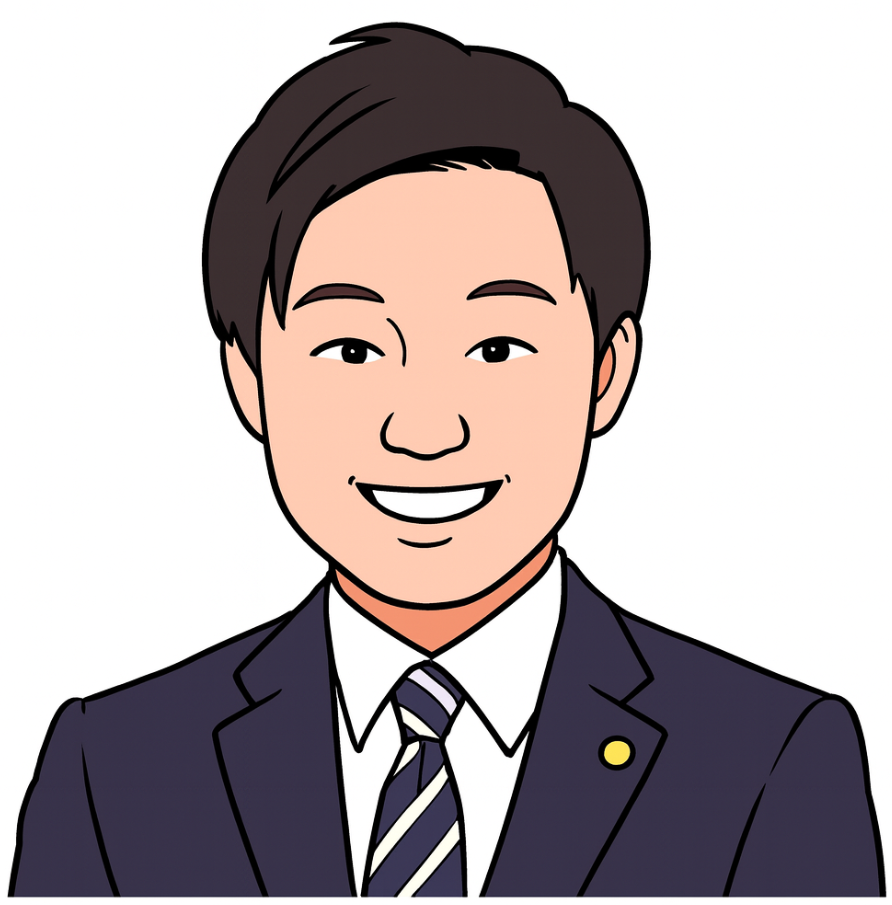
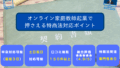
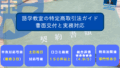
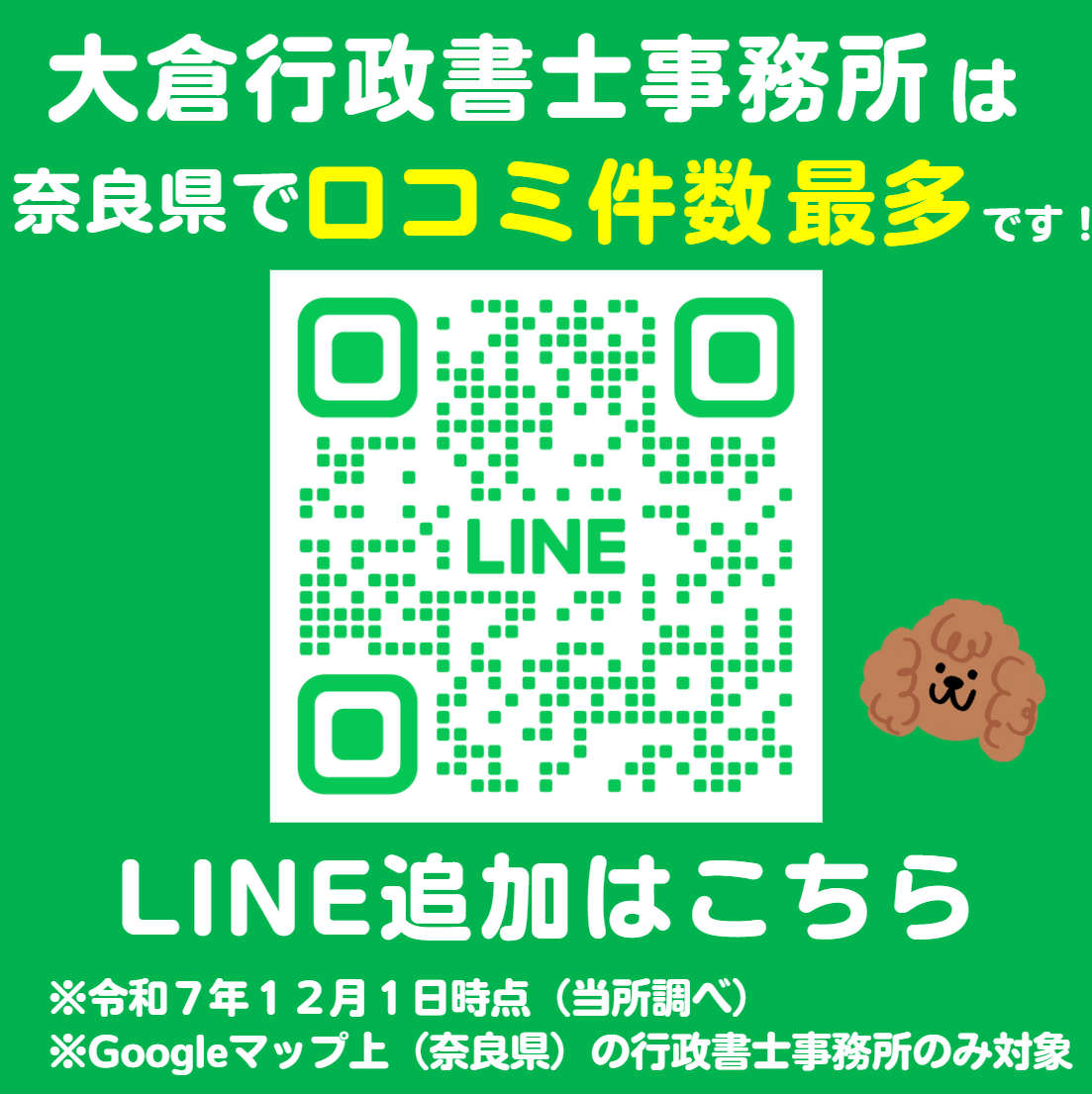
コメント