語学教室(英会話スクール等)の契約内容によっては、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。
これは長期・高額サービスに適用される消費者保護規制で、語学教室も例外ではありません。該当する場合、契約前後に概要書面・契約書面の交付や契約後一定期間のクーリング・オフ対応などが義務付けられます。
「うちの教室は特商法の対象?」「何を準備すればいい?」と不安な事業者も多いでしょう。本記事では、語学教室運営者が押さえるべき特商法対応のポイントを解説します。該当有無の判断基準から必要書面の作成・交付、クーリングオフ・中途解約への対応、社内体制整備まで網羅し、違反時リスクと防止策も具体的に提示します。
法令を正しく遵守すれば、生徒との信頼関係を築きトラブルを防げます。逆に違反すれば行政処分(業務停止命令等)や契約無効・返金要求といったリスクがあります。そうならないためにも、本記事で実務対応策を把握し、必要に応じ専門家のサポートも活用してください。
語学教室と特定商取引法:該当性の判断軸と基本概念

このトピックでは、特商法における特定継続的役務提供の定義と、語学教室がこれに該当する典型パターン、判断時の着眼点(サービス内容・契約期間・対価額)を解説します。また、スタジオ型(月謝制)やサブスク型、回数券型など多様なモデルにおける該当可能性と、そのグレーゾーンについても触れます。
特定継続的役務提供とは何か(語学教室)
まず「特定継続的役務提供」とは、特定商取引法で指定された長期・高額なサービス取引を指します。現在、エステサロンや家庭教師、結婚相手紹介など計7種類のサービスが指定されており、語学教室もその一つです。
英会話スクール等の語学指導サービスは、このカテゴリに含まれる代表例とされています。語学教室が特定継続的役務提供に該当するかは、契約の期間と金額の条件で判断されます。具体的には「契約期間が2ヶ月を超え」かつ「契約金額(入学金や教材費含む)の総額が5万円を超え」ている場合に対象となります。
例えば6ヶ月コースで一括料金10万円といったケースは明確に該当します。なお、レッスン形態(対面/オンライン)に関係なく、これらの条件を満たせば特商法の規制対象となる点に注意が必要です。またチケット制や月会費制(サブスク型)でも、有効期限が2ヶ月超なら期間要件を満たすため規制対象となります。
なぜ語学教室などに特別な規制があるかというと、こうした長期・高額契約は消費者トラブルが生じやすいからです。語学力の上達という成果が契約期間内に得られるか不確実な面もあり、過度な勧誘や不適切な契約条件による被害が起こりやすい分野とされています。
そのため法律で事前説明書面の交付や契約解除ルール(後述)を義務づけ、消費者保護を図っているのです。
【関連記事】
>特定継続的役務提供について
語学教室で該当しやすい契約類型
語学教室のビジネスモデルには様々な形態がありますが、特商法の対象となりやすい契約類型として長期一括プランと前払制が挙げられます。例えば6ヶ月〜1年間のコースをまとめ契約し、総額で数十万円の受講料を前払いするケースは典型的です。
実際、語学スクール業界では一括で高額受講料を設定する例が多く、この基準(2ヶ月超・5万円超)を満たしやすい傾向があります。
フランチャイズ本部モデルでも注意が必要です。大手英会話教室チェーンなどでは、標準的なコース設計が特商法の規制対象に該当する場合がほとんどです。フランチャイズ加盟校であっても、各教室は本部が定める契約期間・料金体系に沿って営業します。
そのため加盟者(オーナー)は、本部提供の契約書類テンプレートやルールに従い、法定の書面交付や手続きを確実に実施する責任があります。
また、オンライン受講と通学レッスンの併用といったハイブリッド型サービスも普及しています。これも契約期間と費用総額が基準を超えれば規制対象です。たとえば「週1回の対面レッスン+オンライン学習サポートを12ヶ月利用で総額○○万円」といったプランは典型的でしょう。
回数券型の語学教室も要注意で、10回分のレッスンチケットに6ヶ月の有効期限がある場合などは、その有効期限が提供期間と見なされ2ヶ月を超えるため特商法が適用されます。逆に有効期限が設定されていないチケットも期限無し=期間無制限と解釈され、やはり対象となると考えられます。
該当/非該当の境界線とリスク
すべての語学教室サービスが特商法の対象になるわけではありません。契約期間が2ヶ月以内または総額5万円以下であれば、法的には特定継続的役務提供に該当しません。
例えば月謝制で毎月払いの形式や、一回完結の短期講座などは法律上の規制対象外となります。ただし対象外の場合でも、契約内容を明示するなど基本的な配慮は重要です。特に個人で小規模に行う場合、あえて長期コースを設けず月謝制(都度払い)にすることで特商法の適用を受けない形態とすることも一法です。ただし、規制対象外であっても契約条件の明示やトラブル防止策は欠かせません。
一方、自社サービスが特商法に該当するにも関わらず、誤って対象外と思い込んで対応を怠るリスクは見過ごせません。例えば契約期間3ヶ月・総額10万円のコースで書面交付をしなかった場合、後日消費者からクーリング・オフを主張され契約無効となるケースも実際に起こり得ます。
法定書面を交付していなければ、書面を受け取った日から8日以内というクーリング・オフ期間が進行しないため、契約後1ヶ月以上経過してからでも無条件解約が認められてしまいます。
その結果、受講料は全額返金となり、事業者にとって大きな損失です。さらに行政処分や社名公表等による信用失墜のリスクも生じかねません。特商法の該当可否に少しでも迷ったら、専門家に相談して適切な対応策を講じることが安全策と言えるでしょう。
語学教室と特定商取引法:概要書面・契約書面の要件と作成実務
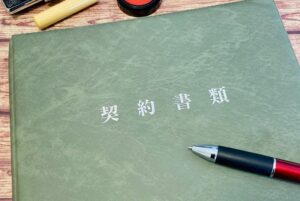
このトピックでは、語学教室で義務付けられる概要書面・契約書面の記載要件と作成ポイントについて解説します。
書面交付義務の趣旨や狙いを押さえつつ、両書面に必ず含めるべき事項を整理します。
さらに、書面の電子交付の可否や交付タイミング(申込前/契約時)の注意点、記載漏れによる契約トラブル(無効・取消のリスク)の事例にも触れ、確実な書面整備のポイントを示します。
概要書面の必須記載事項
特定継続的役務提供に該当する語学教室では、契約申込みを受ける前に概要書面(契約概要)を交付する義務があります。
概要書面とは契約に関する重要事項を事前に書面で示すもので、消費者が内容を十分理解した上で契約を検討できるようにする目的があります。法律で定められた必須記載事項は多岐にわたりますが、主な項目は次のとおりです。
- 事業者の表示:運営会社・教室の名称(法人は法人名と代表者名)、住所、電話番号等の連絡先
- 役務内容・提供期間:提供する語学サービスの詳細と契約期間
- 必要商品の有無:教材や機器など購入が必要な場合、その商品名・種類・数量
- 役務対価・総額費用:受講料や入会金など契約に係る総額費用(概算)
- 支払時期・支払方法:料金の支払タイミング(例:一括前払い、毎月分割)と方法(現金、カード等)
- クーリング・オフに関する事項:8日間の無条件解約権の説明(後述)
- 中途解約に関する事項:契約途中で解約する際のルールや精算方法(後述)
- 割賦販売法に基づく抗弁権:クレジット払いを利用する場合に、一定条件下で支払停止ができる権利に関する表示
- 前受金の保全状況:役務開始前に多額の前払い金を受け取る場合、その保全措置(信託や保険加入)の有無と内容
- 特約がある場合の詳細:標準契約と異なる個別の取り決めがあれば、その内容
以上が概要書面に最低限記載すべき事項です。語学教室向けのポイントとして、教材費や検定試験料など別途発生し得る費用は漏れなく盛り込みましょう。例えば「オンライン教材利用料」や「試験対策講座の追加料金」等を後出しするとトラブルのもとです。
また、サービス内容の説明では「週◯回レッスン」「総時間数◯時間」など具体的に明示し、誤解を招く表現(例:「必ずペラペラに話せる」等の断定的表現)は避けます。概要書面を適切に用意・交付することで、消費者に安心感を与えるとともに、後日の「聞いていない」を防ぐ効果があります。
契約書面の必須記載事項と条項例
受講申込を承諾し契約が成立した後は、速やかに契約書面(正式な契約書)を交付しなければなりません。契約書面には、前述の概要書面記載事項に加えて、契約の確定内容や当事者情報を盛り込む必要があります。主な必須記載事項は次のとおりです。
- 役務内容・期間:契約したサービス内容の詳細と提供開始日・終了日
- 対価総額・内訳:支払総額および内訳(金額、税金、手数料等)
- 支払時期・方法:代金の支払スケジュール(例:契約時に一括/毎月○日までに月謝支払等)と方法(振込、クレジット等)
- 事業者情報:事業者名(法人は代表者名も)、住所、電話番号(概要書面と同様)
- 契約担当者:契約手続きを担当したスタッフの氏名
- 契約年月日:契約が成立した日付
- 商品の明細:教材など購入が必要な商品の種類・数量(およびそれを販売する他業者がある場合はその業者の情報)
契約書面は単なる一覧ではなく、正式な契約書として条項形式で作成するのが一般的です。例えば「第◯条(契約の成立)」「第◯条(役務の提供とスケジュール)」「第◯条(料金と支払方法)」「第◯条(クーリング・オフ)」「第◯条(中途解約と精算方法)」「第◯条(教材・機器の取り扱い)」「第◯条(個人情報の取扱い)」「第◯条(不可抗力)」「第◯条(合意管轄・準拠法)」「第◯条(通知の方法)」「第◯条(電磁的交付に関する合意)」…といった見出し例が挙げられます。
これらを盛り込みつつ、前述の法定事項を網羅するよう条文を構成します。特にクーリング・オフや中途解約に関する条項は法律に沿った内容でなければ無効となるため注意が必要です。
また、契約書面交付時には未成年者契約への対応にも留意しましょう。受講者が未成年の場合、原則として親権者の同意署名を得た上で契約締結すべきです(民法上、未成年者契約は取り消され得るため)。
契約書には保護者同意欄を設けるなどの対応が望ましいでしょう。さらに、交付した契約書は社内でも控えを保管し、万一消費者から再交付の求めがあれば速やかに写しを提供できる体制を整えておくことも実務上重要です。
契約書面は契約内容の最終確定版であり、双方が署名または記名押印して正式な契約書とするケースもあります(電子契約の場合は電子署名等)。いずれにせよ、交付が遅れないよう迅速に発行し、その日付がクーリング・オフ期間の起算日となる点にも注意してください。先述のとおり、法定書面の交付遅れはその分だけ消費者が契約を解除できる期間を長引かせる結果となります。
電子交付・オンライン契約の運用注意
書面交付は原則紙で手渡しや郵送で行うものとされていますが、近年は消費者の事前同意を条件に電磁的方法(電子データ)で交付することも認められつつあります。ただし、その運用には厳格な条件と注意点があります。
まず、電子交付を行うには交付手段を事前に説明し、消費者から同意を得る必要があります。例えばメール上で「契約書類の電子交付に同意します。」と連絡をしてもらう等の手続きが考えられます。(☑では不可とされる場合があります。)この同意なしに一方的にメール送信するだけでは、法的には「書面交付」と認められない恐れがあります。
また、消費者側で電磁的記録を保存できる形式で提供することも条件です。閲覧に専用アプリが必要な形式や、一時的にしか見られない形式は避け、PDFファイルやメール本文など一般的な形で提供します。
以上のように、電子交付・オンライン契約は便利な反面、適法に行うための運用体制を整えないと「書面を交付した」扱いにならないリスクがあります。特にクーリング・オフ期間の起算などに影響するため、電子で交付した日時や方法を明確に記録し、万一紛争になった場合に立証できるよう備えておくことが重要です。十分な体制がない場合は無理に電子化せず、確実な紙交付で対応することも検討しましょう。
語学教室と特定商取引法:販売方法・クーリング・オフ・中途解約
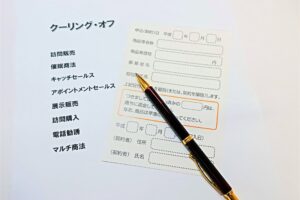
このトピックでは、勧誘・販売方法ごとに異なる規制や注意点、そして契約後のクーリング・オフ手続きと中途解約の実務対応について解説します。店頭での対面契約から訪問勧誘、電話営業、オンライン申込みまで、形態別の禁止行為や表示義務を整理し、その後にクーリング・オフ制度の起算日・通知方法や中途解約時の精算計算を具体例とともに説明します。
勧誘方法ごとの禁止行為と表示義務
語学教室の契約勧誘は、対面(店頭や訪問)、電話、インターネットなど様々な形で行われ得ます。それぞれの勧誘形態で特定商取引法上のルールや禁止行為が定められているため、適切な対応が必要です。
まず共通して契約の勧誘に際して、禁止されている行為として、次のことが挙げられます。
- 実際と異なる虚偽の事実を告げること(例:「絶対に上達する」「あと1日で申込締切」など事実と異なる説明)
- 不利益な事実を故意に告げないこと(例:クーリング・オフ可能なことを黙っている、解約条件を説明しない)
- 相手を威圧して困惑させること(例:帰りたいと言っているのに引き留める、高圧的な口調で契約を迫る)
これらは訪問勧誘や電話勧誘はもちろん、店頭での対面営業であっても禁止されています。特に「必ず短期間で話せるようになる」といった断定的な表現で消費者を誤認させる表示や、過度な勧誘で退店を妨げる行為は厳に慎むべきです。
表示義務については、主に通信販売(オンライン申込み)のケースで重要になります。自社サイトでコース申込を受け付ける場合、特定商取引法に基づく表記ページを設置し、事業者名・代表者・所在地・連絡先・料金や支払い方法・役務提供時期などを明示することが求められます。
また、ウェブ上の広告や申込み画面でも、料金の総額(税・教材費等含む)や契約期間、解約条件など重要情報をわかりやすく表示しなければなりません。申し込み最終確認画面で利用規約や契約条件を確認させるなど、消費者が誤認しない工夫が必要です。
電話勧誘の場合は、電話口で営業を開始する際に事業者名や勧誘目的を名乗る義務があります(いきなり商品の説明に入らない)。相手が興味を示さない場合は速やかに電話を切り上げ、以後不要な連絡を繰り返さない配慮も求められます。
訪問による勧誘でも、相手方が迷惑だと意思表示したら速やかに退出するなど、相手の自由を侵害しないことが大前提です。
さらに、広告段階では有利誤認表示(実際より極端に安く見せる等)も禁止されています。割引キャンペーンを宣伝する際は適用条件を明記し、追加費用がかかる場合もきちんと注記しましょう。違反すると業務停止等の行政処分対象にもなり得るため、勧誘方法に応じた適切な表示と説明を徹底することが大切です。
クーリング・オフの起算・方法・例文
語学教室の契約では、契約書面を受け取った日(交付日)を1日目として8日間は理由を問わず契約を解除できるクーリング・オフ制度があります。
例えば契約書面を4月1日に受領した場合、4月8日まで(当日消印有効)に手続きを取れば無条件で解約可能です。8日目が土日祝でも期間延長はなく、カウント方法は「受領日を含めて8日」です。
ただし事業者が契約書を交付していなかった場合は期間が進行しないため、後日でもクーリング・オフが認められる点は前述の通りです。
通知方法は書面(郵便)でも電磁的記録(Email等)でも構いません。一般的にはハガキや内容証明郵便で通知することが推奨されます。郵便で送る場合、差出人(消費者)の氏名・住所、契約日時、契約内容(「◯◯コース受講契約」など)を明記し、「本書到達をもって契約をクーリング・オフにより解除いたします」といった文言を記載します。以下は通知書の簡易な例です。
|
クーリング・オフ通知書(例) 令和◯年◯月◯日 ◯◯語学教室 御中 私は◯年◯月◯日に貴社と締結した◯◯語学コースの入会契約について、特定商取引法第48条に基づきクーリング・オフを行使し、契約を解除いたします。
|
書面を郵送する際は、内容証明郵便や簡易書留、特定記録郵便等を利用し発送記録を残すことが望ましいです。Email等の電磁的通知で行う場合も、送信日時や送信内容を保存しておきましょう(送信済みメールを保存・印刷する、送信履歴のスクリーンショットを取得する等)。
なお、クーリング・オフを行った事実について、事業者側でも社内記録を残しておきましょう。誰からいつ通知が来て契約解除処理をしたか、返金日などを管理し、後日の問い合わせに備えることも信頼維持の観点で重要です。
中途解約の算定ロジックと返金
クーリング・オフ期間を過ぎても、サービス提供期間中であれば中途解約(途中退会)が認められています。消費者から解約の申し出があれば、事業者は速やかに応じ、所定の金額を清算して返金しなければなりません。
中途解約時に事業者が受講者に請求できる金額(違約金等)は法律で上限が定められており、計算方法は契約の進行度によって以下のようになります。
サービス開始前に解約
語学教室の場合、契約履行前であれば一律1万5千円が事業者の請求できる上限額です。つまり開講前にキャンセルになった場合、事務手数料等として最大1万5千円まで差し引いて残額を返金し、それ以上は請求できません(1万5千円より少ない実費しかかかっていなければ、その実費相当額のみ請求可能です)。
サービス開始後に解約
既にサービス提供が始まっている場合、事業者が受講済み分の対価を差し引き、さらに残りの未受講分に対して違約金(解約料)を請求できます。ただしその違約金は「契約残額の20%」または「5万円」のいずれか低い額が上限です。契約残額とは未受講分の料金総額を指します。
具体例で考えてみましょう。例えば「6ヶ月総額12万円(毎月2万円×6ヶ月)のコース」を契約し、3ヶ月終了時点で中途解約するケースでは、まず提供済み3ヶ月分の受講料6万円を差し引きます。
残り未受講分も同じく6万円です。この契約残額6万円の20%は1.2万円となり、5万円との比較では小さい方の額が上限となります。したがって事業者が請求できる違約金は1.2万円までです。
結果として、受講者には未受講分6万円から違約金1.2万円を控除した4.8万円が返金されます。もし契約時に12万円全額を前払いしていたなら、事業者は6万円+1.2万円=7.2万円を自社収入として残し、残り4.8万円を返金するわけです。
このように、中途解約では消費者に過度な負担とならないよう清算方法が法律で画一的に定められています。契約書面にもこの解約金算定方法を明記し、消費者が事前に理解できるようにしておく必要があります。
また、中途解約の申し出を受けたら返金はできるだけ速やかに行い、教材の返却手続きなども円滑に進めましょう(返品送料は事業者負担が望ましいです)。万一、規定以上の違約金を定めていたり返金を渋ったりすると、特商法違反として行政指導や差止請求の対象となる可能性があります。法律の範囲内で公正な精算を行うことが、顧客との信頼維持にも繋がります。
語学教室と特定商取引法:運用体制の構築・社内教育・実務フロー

このトピックでは、特商法対応を継続的に確実に行うための社内運用体制の構築方法や、スタッフ教育・実務フローについて解説します。法定書面のテンプレート管理・改定フローの整備から、申込受付、書面交付、書類保管、クレーム対応までの標準策定、さらに行政からの問い合わせや顧客クレーム発生時の対応手順についても紹介します。
これにより、組織として安定したコンプライアンス運用が可能となります。
標準オペレーション雛形
語学教室で特商法に対応するためには、契約に関する一連の業務手順を社内で統一しておくことが有効です。以下に典型的な流れの例を示します。
- 事前判定:新規の受講申込みがあったら、まず契約予定内容が特定継続的役務提供に該当するかを確認します(契約期間・料金の確認)。該当する場合は、以下の手続きを厳守します(非該当の場合も契約内容の説明や書面交付は怠らないことが望ましい)。
- 重要事項の説明・概要書面交付:申込を正式に受け付ける前に、概要書面を用いて契約条件を説明します。サービス内容、期間、料金、クーリング・オフ等の重要事項を口頭および書面で丁寧に案内し、消費者から内容理解と申込意思を確認します。概要書面は控えをとり、交付日を記録しておきます。
- 契約締結・契約書面交付:消費者が申込みを決めたら、正式に契約書を取り交わします。必要事項を記入の上、双方が署名または押印します。事業者側は契約書面をその場で交付し、日付・担当者名等を記載漏れなく記入します。契約書面交付日=クーリング・オフ期間の起算日となるため、交付日を明確にしておきます。
- 役務提供開始準備:初回レッスン日等のスケジュールを双方で確認し、教材の配布やオンラインシステムの案内など、サービス提供の準備を行います。先に教材等を渡す場合は、クーリング・オフ期間内であれば返却され得ることを想定しておきます。
- クーリング・オフ対応:契約書面交付から8日間はクーリング・オフ期間です。期間中に解約の申し出があった場合の受付担当者(窓口)を決め、即座に対応できるようにします。電話で連絡が来た場合でも、「書面での手続きが必要」など形式を案内しつつ失礼のないよう対応します。申し出があったら日付を記録し、速やかに返金処理や教材回収手配を行います(手順については前述のとおり)。
- 書類・記録の保管:契約関連書類(申込書、概要書面控え、契約書コピー、クーリング・オフ通知控え等)は、社内で一定期間保管します。少なくともクーリング・オフ期間経過までは容易に参照できるようファイリングし、電子データ化できるものはスキャンして保存しておきます。
- サービス提供と途中解約受付:クーリング・オフ期間が過ぎた後は役務提供を継続します。万一、期間中に受講者から途中解約(中途退会)の希望が出た場合は、所定の違約金計算に基づき返金額を算出します(前述の計算式を参照)。
- アフターフォローと苦情対応:受講終了後や解約後も、問い合わせ対応や苦情処理の体制を整えておきます。特に返金処理の遅延や説明不足によるクレームが起きないよう、最後まで丁寧に対応します。必要に応じて上長や専門家に相談し、適切な解決を図ります。
以上が一連の標準フローの例です。これらをマニュアル化し、新人スタッフにも共有しておくことで、誰が対応しても一定水準のコンプライアンス対応が担保されます。
社内教育と点検チェックリスト
特商法対応を確実にするには、スタッフへの教育と定期的な点検が欠かせません。まず、契約手続きを担当するスタッフ全員に対し、特商法の基礎知識(概要書面・契約書面の目的や交付タイミング、クーリング・オフ制度、中途解約ルールなど)を周知徹底します。
新人研修時にマニュアルを用いて説明し、実際の交付手順を経験させると良いでしょう。ロールプレイ形式でお客様への説明練習を行い、重要事項の伝え漏れがないようトレーニングします。
また、社内チェックリストを作成し、定期的(例えば毎月または四半期ごと)に以下の項目を点検します。
- 書面記載事項の網羅性:最新の概要書面・契約書面テンプレートに法定事項が漏れなく含まれているか。法改正や料金改定があった際にテンプレートを更新し忘れていないか。
- 勧誘・申込時の対応:概要書面を申込前に必ず交付しているか、重要事項の説明漏れはないか。勧誘時の不適切なトーク(「絶対成果が出る」等)をしていないか。
- 契約書面の記入・交付:契約日や担当者名を含め契約書面の必要項目を漏れなく記入しているか。交付した日付を記録し、顧客にも認識させているか。契約書面控えは確実に保管されているか。
- クーリング・オフ/解約対応:クーリング・オフの問い合わせがあった際の社内フローは適切か(窓口担当の周知、受け付けた日時の記録方法、上長報告の迅速化など)。中途解約の違約金計算シート等を備え、金額算出ミスがないようにしているか。
- 広告表示の点検:Webサイトやパンフレットに掲載している料金・サービス情報が最新で正確か。特定商取引法に基づく表示ページに必要事項が記載されているか。誇大な表現や重要事項の脚注隠しなど不適切な表示がないか。割引キャンペーン情報が古いまま放置されていないか。
- 書面の版管理・改定履歴:概要書面・契約書面のひな型に改定があった場合、古い様式を誤って使い続けていないか。テンプレートの改定履歴を管理し、社内の共有フォルダ等で最新版本のみ使用する運用になっているか。
- 再交付依頼時の対応:万一顧客から契約書の紛失による再発行依頼があった際の手順を整備しているか。本人確認の上で速やかに写しを交付するフローが周知されているか。
このチェックリストに基づき、定期的に社内の点検や上長による監査を行えば、違反リスクの早期発見と是正につながります。また、新しいキャンペーンを開始する際やサービス内容を変更する際も、その都度チェックリストを用いて特商法上問題がないか確認すると安心です。
スタッフ全員がコンプライアンス意識を持ち、適切な対応が習慣化するよう継続的な教育と点検を続けましょう。
行政対応・トラブル未然防止
万一、特商法に関して行政から問い合わせや調査があった場合には、迅速かつ誠実に対応することが重要です。自治体の消費生活センターや監督官庁から書面照会を受けた際は、期限までに必要資料(契約書面の写しや説明資料等)を提出し、指摘事項があれば速やかに是正します。
行政指導(改善指示)を受けた場合は真摯に受け止め、再発防止策を講じた上で報告しましょう。改善命令に従わなかったり悪質な違反を続けたりすれば、業務停止命令や社名公表といった厳しい処分に発展しかねません。また、違法な勧誘行為等を放置すると、適格消費者団体から差止請求を起こされるリスクもあります。そうなる前に自主的に改善する姿勢が大切です。
顧客からのクレームや相談にも、初期対応が肝心です。苦情が寄せられたら、まずは話を傾聴し、事実関係を確認します。その上で、「ご不便をおかけし申し訳ございません」「詳細を調査し早急に対応いたします」等、丁寧な姿勢で応対します。
特に契約や解約に関するトラブルでは、感情的な対立を避け、契約書に記載のルールを冷静に説明しつつ、可能な限り相手の納得を得られる解決策を検討します。現場の担当者レベルで対応が難しい場合は、上長や専門家へエスカレーションするルールをあらかじめ決めておき、ワンマン対応による拗れを防ぎます。
発生したトラブルやヒヤリハット事例は、必ず記録に残し社内共有しましょう。一件一件は小さなクレームであっても、類似の指摘が複数あれば契約説明の資料を改善するなど再発防止策に繋げられます。
定期ミーティングで苦情事例を振り返り、「なぜ起きたか」「防ぐにはどうするか」をチームで検討します。例えば「○○の説明が分かりにくかった」「メール対応が遅れ不信感を与えた」等の教訓を洗い出し、マニュアルや研修内容に反映させます。
語学教室向け書面整備は専門行政書士にお任せください

特定商取引法に基づく概要書面・契約書面の設計から作成、運用整備まで、当事務所(行政書士)が一括サポートいたします。煩雑な法定書面の準備やクーリング・オフ対応策の構築も、豊富な実績を持つ専門家にご相談ください。初回60分の無料相談を実施中で、全国どこからでもオンライン(Zoom等)で対応可能です。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁
よくある質問
Q1.短期コース(2ヶ月以内や総額5万円以下)でも特商法の対象になりますか?
A1.契約期間が2ヶ月以内、または支払総額が5万円以下のコースであれば特定継続的役務提供には該当しません。
したがって概要書面の交付義務やクーリング・オフ制度も法定では適用されません。ただし対象外の場合でも、契約条件を明示した書面を交わしておくことが望ましいです(トラブル防止のため)。
Q2.オンラインのみの語学講座でも書面の交付は必要ですか?
A2.はい。レッスン提供方法がオンラインでも、契約期間と金額が基準を超えていれば特商法の規制対象です。
したがって概要書面・契約書面の交付義務やクーリング・オフ制度も同様に適用されます。書面は郵送のほか事前同意を得て電子メール等で交付することも可能ですが、適切な運用手順が必要です。
Q3.未成年の生徒と契約する際の注意点はありますか?
A3.未成年者(18歳未満※)との契約は、親権者の同意を得て締結することが重要です。民法上、未成年者が親の同意なく結んだ契約は後から取り消せるためリスクがあります。実務上は、契約書に保護者署名欄を設ける、申込時に同意書を提出してもらう等の対策をとりましょう。
Q4.企業研修など法人相手の契約にもクーリング・オフは適用されますか?
A4.いいえ。特定商取引法は消費者(個人)保護の法律ですので、法人が契約当事者となる企業研修や団体向け講座契約は対象外です。
クーリング・オフや中途解約の制度はあくまで消費者向け契約に適用されるため、法人契約には適用されません。ただし法人契約でもトラブル防止のため、解約条件等を契約書で明確に定めておくことが望ましいでしょう。
Q5.契約書類を紙ではなくメール等の電子データで交付しても問題ないですか?
A5.消費者が事前に同意すれば電子交付も可能になりましたが、一定の要件を満たす必要があります。メール送信前に同意取得を済ませること、PDF等消費者が保存できる形式で送ること、改ざん防止措置(編集禁止設定やタイムスタンプ付与等)を講じることなどが求められます。
要件を満たさない交付は「書面交付」と認められないリスクもあるため、確実に実施できない場合は紙交付で対応する方が無難です。
Q6.「途中解約不可」「返金しない」という特約を付ければ解約に応じなくてもいいですか?
A6.いいえ。そのような特約を付けても法的に無効です。特定継続的役務提供では法律で中途解約権が保障されており、事業者が一方的に「退会不可」「返金なし」と定めることは許されません。
契約書には法律に沿った解約条件を定める必要があり、仮に上記のような条項を書いても効力を持たないので注意してください。
Q7.契約前の無料体験レッスンにも特商法上のルールは関係しますか?
A7.無料体験そのものは金銭の支払いを伴わないため、特定商取引法のクーリング・オフ等は直接には適用されません。ただし、その後本契約の勧誘につなげる場合は勧誘行為規制の対象になります。
例えば体験レッスン後にその場で契約を迫れば訪問販売的な扱いとなり、不適切な勧誘をすれば特商法違反となり得ます。本契約の申込みは落ち着いた環境で検討できるように促し、体験時にも契約条件の重要事項を正確に伝えるなど、誠実な対応を心がけましょう。


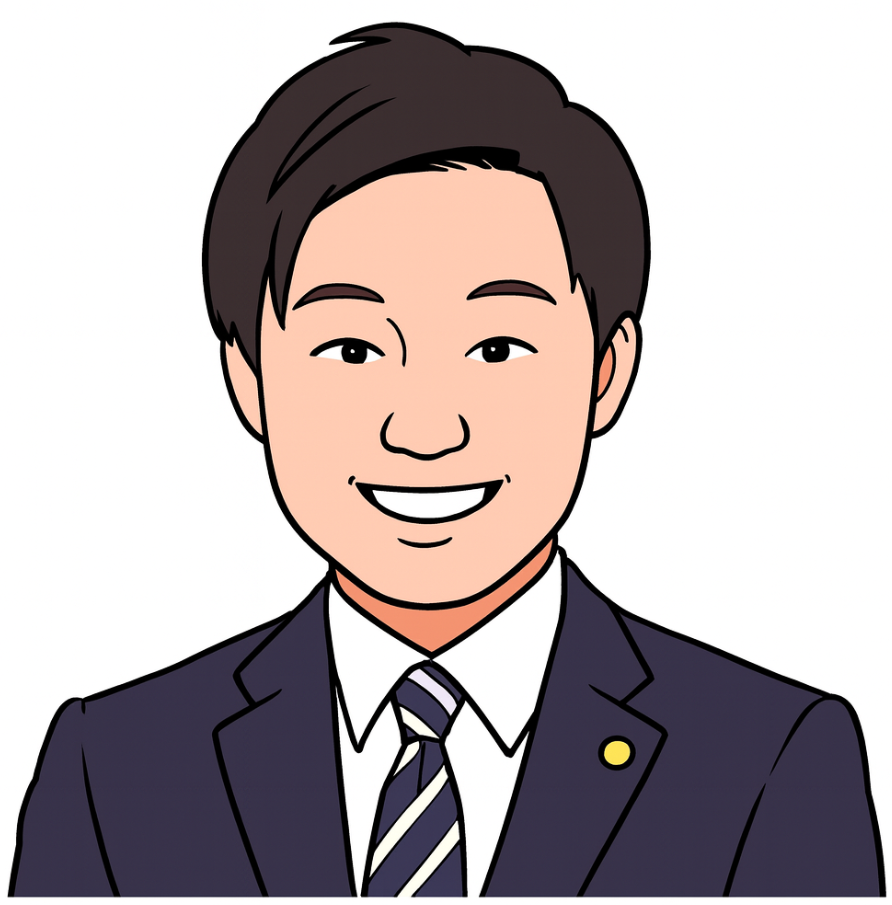
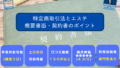
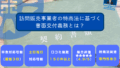
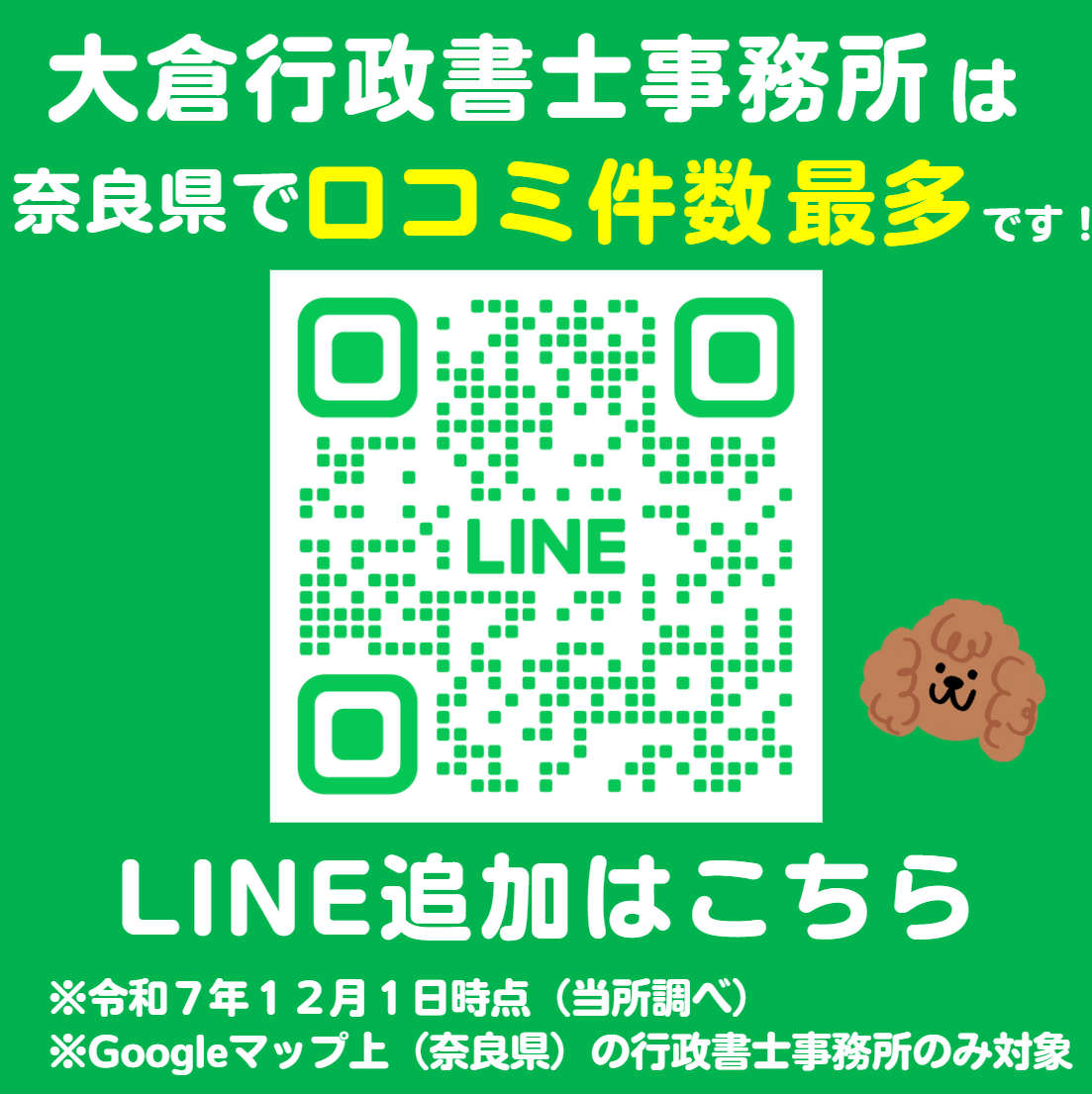
コメント