訪問販売は、店舗を介さずに行われる取引であるため、消費者が不意に勧誘を受けやすく、契約内容を十分に理解しないまま契約してしまうトラブルが後を絶ちません。
このような被害を防ぐため、特定商取引法では訪問販売を行う事業者に対し、氏名や販売目的の明示、契約内容を記載した書面の交付など、複数の義務を課しています。本稿では、その中核となる書面交付義務の内容と実務上のポイントを詳しく解説します。
訪問販売とは

訪問販売とは、法律上「営業所や代理店などの一定の場所以外で行われる販売活動」および「特定の顧客に対して行う取引」を指します。つまり、店舗や事務所といった常設の販売拠点ではなく、消費者の自宅や勤務先、あるいは路上などで商品やサービスを勧誘・販売する形態がこれに当たります。
代表的なものが、自宅を突然訪れて商品を売り込む、いわゆる押し売りです。このような訪問販売では、消費者が不意を突かれた状態で勧誘を受けるため、心理的な圧力がかかりやすく、冷静な判断が難しくなります。
結果として、本来は購入する意思がなかったのに、その場の雰囲気に押されて契約してしまうケースもあります。
さらに、販売者が実体の乏しい事業者である場合、購入後に連絡が取れなくなる、返品や返金に応じてもらえないといったトラブルも起こりやすくなります。常設店舗を持たない業者が「売り逃げ」を行う危険性も否定できません。
このような背景から、訪問販売は一般的な店舗販売よりもトラブルリスクが高いと考えられています。そのため、法律(特定商取引法)は訪問販売に特有の規制を設け、事前の情報提供・契約書面の交付・クーリング・オフ制度などを義務化することで、消費者の保護と取引の公正を図っているのです。
訪問販売にあたらない場合
訪問販売に該当する取引であれば、特定商取引法に基づきクーリング・オフ制度が適用され、不当な勧誘があった場合には契約の取消しも可能となります。
しかし、そもそもその取引が「訪問販売」にあたらなければ、これらの救済制度を利用することはできません。したがって、まず自社の販売方法が訪問販売に該当するかどうかを正確に把握しておくことが重要です。
営業所・代理店等で行われる取引
特定商取引法上の「訪問販売」とは、事業者の営業所・代理店など、法令で定められた一定の場所以外で行われる取引を指します。裏を返せば、営業所や代理店など、通常の営業拠点で契約が行われた場合には訪問販売には該当しません。
ここでいう「営業所」とは、実際に営業活動が行われている場所を指します。例えば、アパレル業であれば商品を展示・販売している店舗、エステ業であれば施術サービスを提供しているサロン等が「営業所」にあたります。
また「代理店」とは、「代理商」として他の商人のために継続的・反復的に契約の代理や媒介を行う者をいいます。したがって、単発的に販売を行うだけの者は代理商には該当せず、その販売場所は「代理店」とはみなされません。露店や一時的な催事販売などがその典型です。
経済産業省令で定める場所(展示販売等)
さらに、特定商取引法では「その他の経済産業省令で定める場所」も営業所と同様に扱われます。具体的には、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。
- 販売期間が2日以上継続していること
- 消費者が自由に商品を選べるよう、陳列が行われていること
- 販売のための固定的な設備(展示会場など)を備えていること
これらの条件を満たす展示会や見本市での販売は、形式上はホテルや体育館などの「臨時会場」であっても、営業所での取引と同等に扱われ、訪問販売には該当しません。
一方で、販売期間が短時間にとどまり(例えば数時間だけ開催される展示販売など)、上記要件を満たさない場合は、「店舗販売」とは認められず訪問販売として特商法の規制を受けることになります。
実務上の判断ポイント
したがって、次のような取引は「訪問販売にあたらない」と判断されます。
- 常設店舗や営業所で契約が締結された場合
- 代理店(代理商)の営業拠点で継続的に販売が行われている場合
- 展示会場などで複数日にわたり販売が行われ、商品が常設的に陳列されている場合
これに対し、短期の展示販売・臨時イベント販売・単発的な出張販売は、訪問販売に該当する可能性が高く、特定商取引法上の書面交付義務やクーリング・オフ規定の対象となります。
このように、「営業所等以外での販売」と「営業所等での販売」との線引きは、取引の場所の性質・期間・継続性によって判断されます。形式的な名称ではなく、実態に即して判断することが肝心です。
訪問販売事業者の書面交付等の義務

訪問販売は、店舗での対面販売と異なり、消費者が十分な情報や判断の余裕を持たないまま契約に至るケースが少なくありません。そのため、特定商取引法では、訪問販売を行う事業者に対して次のような明確な説明義務と書面交付義務を課しています。
- 事業者の身元・目的等の明示義務
- 一定事項を記載した書面の交付義務
これらの義務は、消費者に「誰が・何のために・どのような内容で契約を持ちかけているのか」を正しく認識させ、誤解や不信感を防ぐために設けられたものです。
氏名・目的の明示義務
訪問販売では、取引相手が初対面である場合がほとんどであり、消費者から見れば「誰が来たのか」「どこの会社なのか」が分かりにくい状況にあります。
このため販売員は、勧誘を始める前に、まず自分の氏名や事業者名、そして訪問の目的を明確に伝えることが法律上求められています。
- 個人事業主であれば、自身の氏名または商号を正確に名乗る。
- 法人の場合は、登記された正式な会社名を明示する(略称・屋号のみでは不可)。
- 続けて「本日は化粧品の販売にお伺いしました」など、販売目的を明言する。
これらは単なるマナーではなく、勧誘を開始する前の義務です。訪問販売員がインターホン越しに話す場合であっても、同様に自らの氏名や目的を明確に伝えなければなりません。
中には、警戒心を和らげようと「名前は後で言います」「説明だけさせてください」といった対応を取るケースもありますが、これは法の趣旨に反します。たとえ丁寧な態度であっても、身元や目的を明かさないまま会話を進めること自体が違反行為にあたる可能性があります。
書面交付義務(申込書面・契約書面)
訪問販売を行う事業者は、販売業者または役務提供事業者として、消費者に対して取引内容を明記した書面を交付する義務を負います。この書面には、次のような事項を記載しなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名及び商品の商標又は製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
これらの情報は、消費者が契約内容を理解し、判断できるようにするための基本情報です。
特に重要なのが「クーリング・オフ(契約の申込み撤回・解除)」の記載です。これを明確に告知しないと、消費者が権利を行使できず、後々「返品できない」「聞いていた条件と違う」といった紛争が起きやすくなります。
書面の体裁にも規定があり、一定の大きさの文字を用いること、および赤枠内に「内容をよく読むように」等の注意文を赤字で記載することが求められています。これは、契約内容の重要性を視覚的に示し、読み飛ばしを防止するための工夫です。
申込書面と契約書面の違い
訪問販売における書面には、交付のタイミングによって次の2種類があります。
申込書面
消費者が契約の申込みを行った際に、直ちに交付しなければならない書面。申込み内容(商品・価格・数量など)を具体的に記載し、消費者に控えを渡すことで誤解を防ぎます。
契約書面
契約が正式に成立した後、遅滞なく交付する書面。最終的な契約条件を明確に記載し、双方の合意内容を文書で確認するためのものです。
このように二段階で書面交付を義務付けているのは、申込みと契約の間で条件が変更されることを防ぐためです。(申込と契約を同時に行う場合には契約書面のみで可です。)なお、「直ちに」は申込時点、「遅滞なく」は契約当日もしくはその翌々日程度までと解されます。
訪問販売の現場では、わずかな説明不足や書面不備が重大なトラブルにつながることがあります。「名乗る・説明する・書面を渡す」という一連の行為は、事業者にとって単なる形式ではなく、法的な信頼の礎です。
これらの義務を丁寧に履行することで、消費者の理解と安心が得られ、結果的に事業者自身を守ることにもつながります。
訪問販売契約におけるクーリング・オフ制度

訪問販売によって締結された契約は、消費者にとって突然の勧誘や心理的圧迫のもとで判断を迫られる場合が多いため、特定商取引法は「クーリング・オフ制度」を設けて消費者の保護を図っています。
クーリング・オフの行使期間と起算点
訪問販売のクーリング・オフは、契約書面を受け取った日(交付日)を含めて8日以内であれば、消費者が一方的に契約を解除できる制度です。例えば8月1日に契約書面を受け取った場合には、同月8日までにクーリングオフの通知を行えばクーリングオフが可能です。
この期間内に消費者が「契約をやめたい」という意思を示せば、理由のいかんを問わず契約を無条件で解除することができます。事業者は、すでに受け取った代金を全額返還し、商品を引き取る義務を負います。
また、契約書面に記載漏れや日付の誤りがあると、消費者側から「書面が不備であった」と主張され、クーリング・オフ期間が延長されるリスクがありますので注意しましょう。
訪問販売事業者が書面交付義務に違反した場合の法的影響

訪問販売を行う事業者には、消費者に対して特定商取引法に定められた内容を記載した書面(申込書面・契約書面)を交付する義務があります。この義務を怠ったり、形式的には交付していても記載内容が不完全であったり虚偽の事項が含まれている場合には、法律上「書面交付義務違反」として扱われます。
書面不備とクーリング・オフの延長
特に注意すべきは、書面交付義務の違反がクーリング・オフ期間の起算点に直接影響するという点です。クーリング・オフは「契約書面を受け取った日を含め8日間」と定められていますが、もし書面が交付されていなかったり、法定の記載事項が欠けていた場合は、起算日が発生しない=クーリング・オフ期間がいつまでも始まらない扱いになります。
たとえば、契約書面に「クーリング・オフが可能である旨」や「通知方法」「期間の明記」が抜けていると、書面交付そのものが無効とみなされ、消費者は契約日から何ヶ月経過していてもクーリング・オフを行使できる状態が続きます。
つまり、事業者が書面不備を放置した場合、契約の安定性が永久に担保されないリスクを負うことになるのです。
行政実務上も、書面不交付や記載漏れが判明すると、監督官庁(主に経済産業局や消費者庁)から是正を求められることがあります。単なる手続ミスであっても、事実上のクーリング・オフ無期限状態を招くおそれがあるため、事業者としては書面内容を常に最新・完全な状態に保つことが不可欠です。
行政処分の可能性
書面交付義務違反が認められ、それにより消費者の利益を害するおそれや取引の公正が損なわれるおそれがある場合、経済産業大臣(または委任を受けた都道府県知事)は、事業者に対して必要な行政処分を行うことができます。
行政処分の内容は違反の程度に応じて段階的に行われます。
- 指導・勧告
軽度の違反に対し、是正措置や改善命令を促す。 - 業務停止命令
悪質な場合には、最大1年以内の営業停止を命じる。 - 公表・再発防止命令
社会的影響が大きい場合には、違反事実が公表される。
行政処分が行われると、実務上は「行政指導の履歴」として残り、以後の許認可・営業活動に悪影響を及ぼすこともあります。
とくにフランチャイズ・委託販売など多店舗展開型の事業では、1社の違反が全体の信頼低下を招くため、連鎖的リスクに注意が必要です。
刑事罰の適用(特商法第71条等)
書面交付義務違反は、行政処分にとどまらず、一定の場合には刑事罰(罰金や拘禁刑)の対象にもなります。特定商取引法では、次のような場合に罰則が科される旨を明記しています。
- 書面を交付しなかった場合
- 法定の記載事項を欠いた書面を交付した場合
- 書面に虚偽の内容を記載して交付した場合
実務的な防止策
書面交付違反を防ぐには、以下のような管理体制が有効です。
法定記載事項のチェックリスト化
契約書・申込書のテンプレートにチェック欄を設け、営業担当者が交付前に項目を一つずつ確認する仕組みを整える。
バージョン管理と監査
法改正ごとに書面の最新版を更新し、古いフォーマットの使用を禁止。定期的に書類監査を行う。
教育・研修の実施
営業担当者・代理店向けに、書面交付義務やクーリング・オフ制度に関する研修を行い、違反リスクを具体的に理解させる。
以上のように、法律に基づいた正確な書面を作成し、確実に交付・保存する体制を整えることが、クレーム防止と企業防衛の両立につながります。
訪問販売における禁止行為とは

訪問販売は、消費者が十分な情報を持たないまま営業担当者から勧誘を受けるという取引形態の特性上、誤認や心理的圧力による契約トラブルが発生しやすい傾向があります。そのため、特定商取引法では事業者が行ってはならない「禁止行為」を明確に定めています。
これらの行為を防止することが、訪問販売の公正性を保ち、消費者との信頼関係を維持するうえで不可欠です。
不実の告知(虚偽説明による勧誘)
実際の事実と異なる内容を消費者に伝えて契約を結ばせる行為は、典型的な禁止行為です。たとえば、販売員が消防署や自治体の職員を装い、「家庭には消火器の設置が義務付けられています」などと虚偽の説明をして商品を販売する行為は、不実の告知に該当します。
また、契約上はクーリング・オフできる取引であるにもかかわらず、「この商品はクーリング・オフの対象外です」などと誤った説明をする行為も同様に違法です。
故意による重要事項の不告知
重要な事実を故意に伝えないことも禁止されています。ここでいう「重要事項」とは、契約判断に影響を与えるような情報、たとえば商品の欠陥、使用制限、保証条件、耐用年数などです。
たとえば、販売する機械が「半年で動作不良を起こす可能性が高い」と分かっていながら、その事実をあえて隠して販売する行為は典型例です。
不告知行為は「積極的なウソ」ではないため軽視されがちですが、黙っていたこと自体が違法行為とみなされる点に注意が必要です。また、誤解を招く沈黙(例:質問されてもあえて話題をそらす、あるいは都合の悪い情報をぼかす)も不告知と評価される可能性があります。
威迫行為(脅し・威圧的勧誘)
威迫行為とは、脅迫に至らないまでも、消費者を心理的に圧迫して不安や恐怖を感じさせ、契約を結ばせたり、クーリング・オフの行使を妨げるような言動を指します。
たとえば、「今契約しなければ損をする」「上司が怒るから今すぐ決めてほしい」「クーリング・オフしたら損害賠償になる」といった言動は、明確な脅迫ではなくても威迫に該当します。
このような勧誘は、消費者の自由意思を奪う行為として厳しく処罰されます。また、威迫によってクーリング・オフを妨げた場合には、クーリング・オフ期間の起算が延長される(=期間が無期限になる)ため、事業者にとってもリスクが極めて大きい点に留意が必要です。
夜間・執拗な勧誘行為
消費者の生活を脅かすような夜間訪問や過度な勧誘も禁止されています。代表的な違反事例は次のとおりです。
- 夜遅く(おおむね午後8時以降)に自宅を訪問して勧誘する行為
- 長時間にわたる説得・居座りによる勧誘
- 病気・高齢・障害などで判断力が低下している人に対する強引な販売
- 消費者の生活状況や経験に照らして著しく過大な量の商品を勧誘する行為
- 消費者の経済力・知識・必要性を無視した過剰販売
これらはいずれも、消費者に精神的負担や生活被害を与える行為として厳しく規制されています。特に高齢者宅を中心とした夜間訪問は、地域によっては警察・自治体に通報されるケースもあり、事業者としての社会的信用を大きく損なうおそれがあります。
特定商取引法における禁止行為の多くは、「消費者の自由意思と平穏な生活を守る」という理念に基づいています。訪問販売を行う際には、単に法律違反を避けるという姿勢ではなく、「誠実な情報提供」「適切な勧誘方法」「明確な契約手続き」を徹底することで、消費者との信頼を築くことが最も重要です。
訪問販売による特商法書面の作成はお任せください

訪問販売を行う際には、特定商取引法に基づく申込書面・契約書面の作成と交付が義務付けられています。
これらの書面は単なるフォーマットではなく、記載内容・交付タイミング・体裁要件まで法律で厳格に定められています。
不備があるとクーリング・オフ期間が無期限となるなど、重大なリスクにつながるため注意が必要です。
私は行政書士として、特商法に準拠した書面・運用体制の整備をサポートしています。特に次のような事業者様は、早めの書面整備をおすすめします。
- 訪問販売・出張営業・展示販売を行っている事業者様
- 初めて訪問販売を始める個人事業主・中小企業様
- クーリング・オフ対応を正しく明記した契約書を作成したい方
- 現行の契約書・申込書が特商法に適合しているか確認したい方
- 書面の電子化(メール・PDF等)に対応したい事業者様
書式の作成から、交付・保管・説明体制の設計まで、法令準拠で実務的な支援を行います。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面(申込書面)や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際の業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面(申込書面)および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

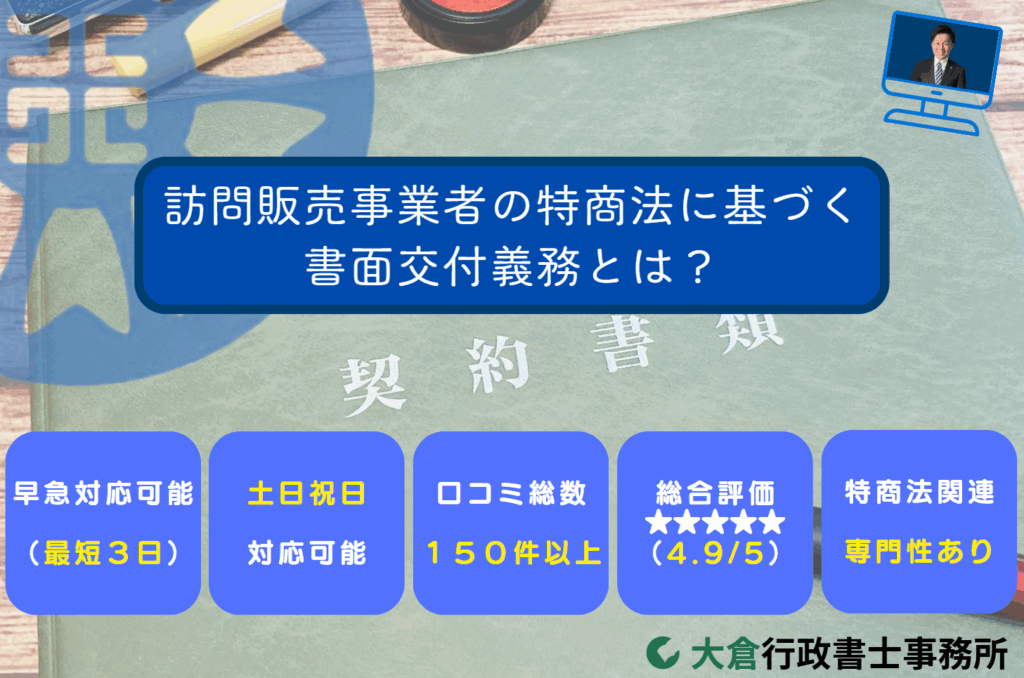
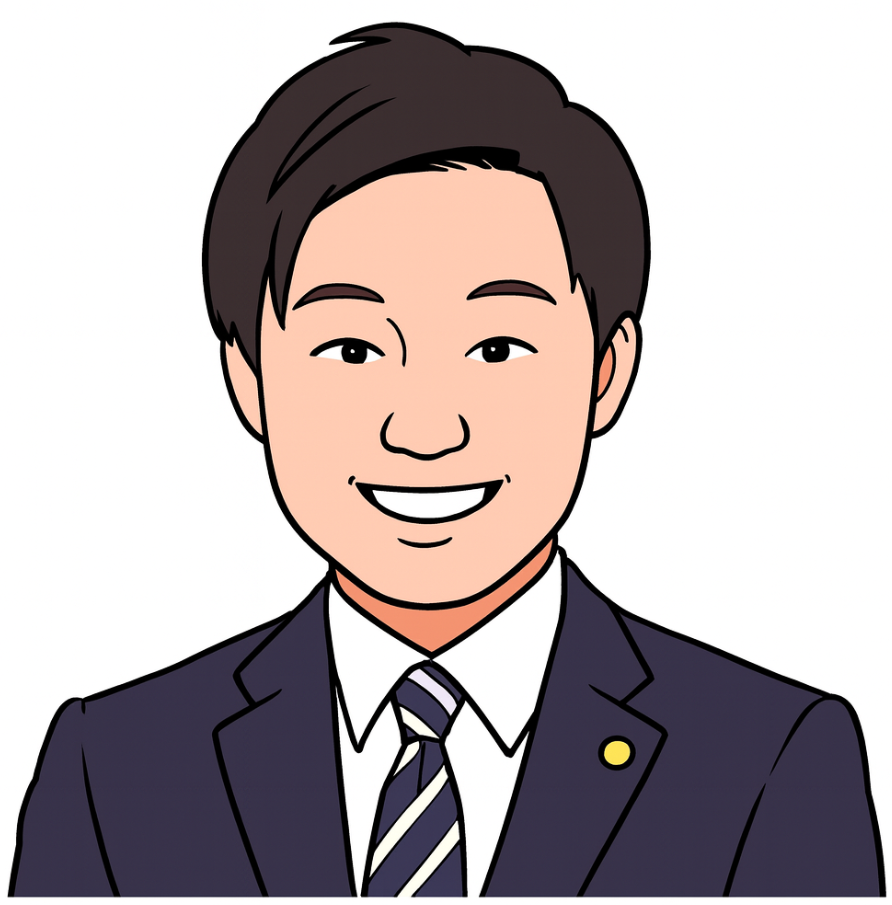
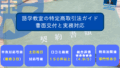
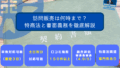
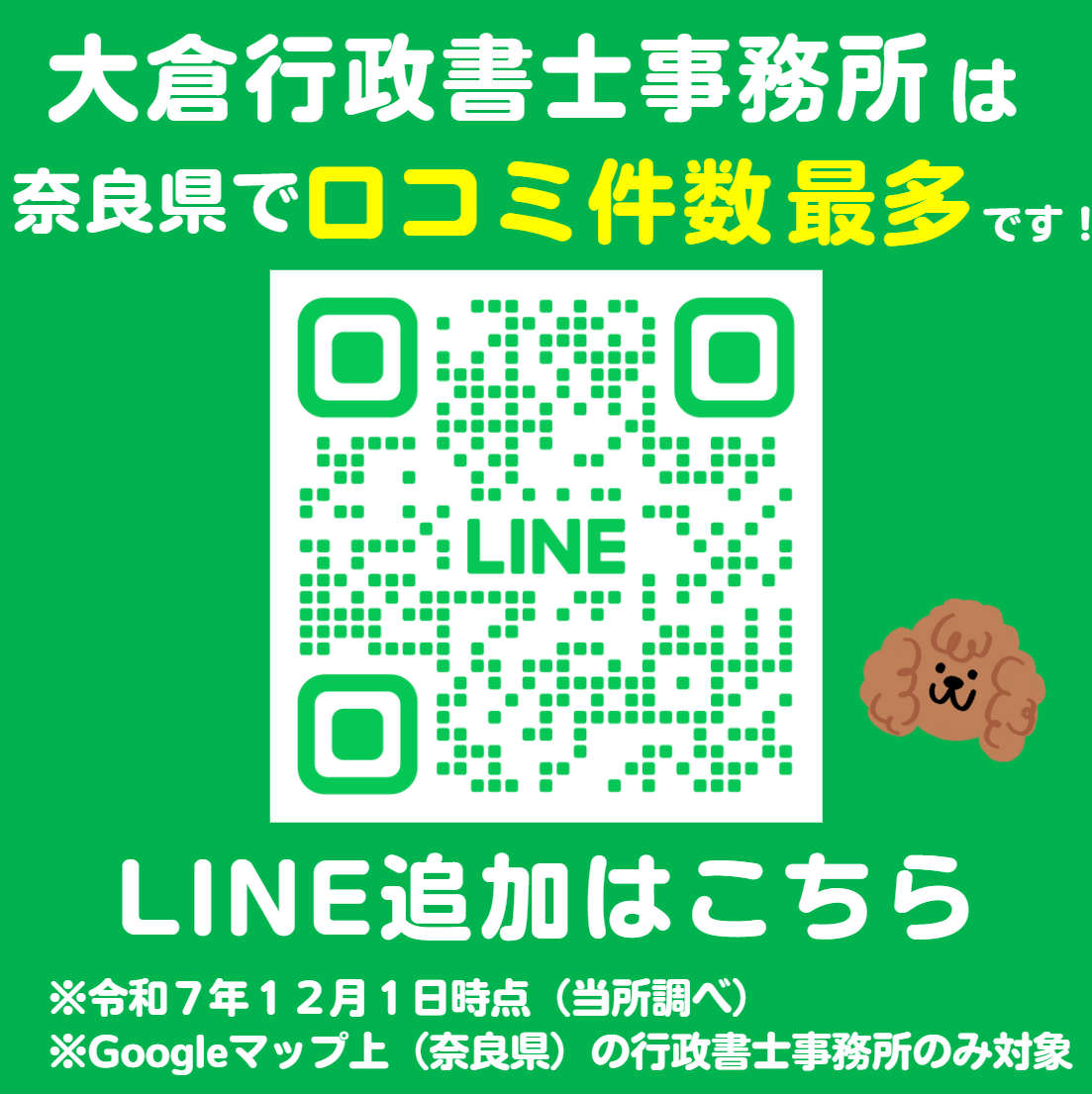
コメント