訪問販売を行う事業者にとって、「どの時間帯まで訪問して良いのか」「契約時にどんな書面を渡す必要があるのか」は悩みの種でしょう。
特に早朝や夜遅くの訪問が法律に抵触しないか、契約時の申込書面・契約書面の交付義務を怠るとクーリング・オフ等で不利にならないか、不安に感じている方も多いはずです。
本記事では、特定商取引法(特商法)や各種ガイドライン等の最新情報に基づき、訪問販売の適切な勧誘時間と書面交付義務について行政書士がわかりやすく解説します。
法律で明確に定められている事項と、ガイドラインや実務上の慣行・注意点を区別しながら説明しますので、読むことで「訪問販売は何時まで可能か」が理解でき、契約書類の不備によるトラブルも防止できるようになります。
また、記事末では適法かつ安心な営業フロー構築のポイントも紹介します。当事務所では特商法に関する書面作成、運用フロー整備のご相談も承っております。ぜひ最後までご覧いただき、自社の営業活動にお役立てください。
訪問販売の「適切な時間」と法的根拠

このトピックでは、訪問販売を行う際の「適切な訪問時間」について、法律上どのような規定があるかを整理します。
特定商取引法に訪問時間の明確な規制があるのか否かを確認し、自治体ごとの迷惑防止条例や業界ガイドラインで示される夜間訪問の扱いも紹介します。
そのうえで、実務的に何時頃までの訪問が望ましいか、クレームを避けるための社内ルール策定について解説します。法令上のルールとマナー・実務上の基準を切り分けて把握し、適切な営業時間帯の設定に役立てましょう。
特商法の枠組みと“時間規制”の位置付け
まず、特定商取引法(特商法)に訪問販売の時間帯を制限する直接の条文は存在しません。法律上は「○時以降の訪問禁止」といった明文規定はなく、訪問販売そのものは原則として時間帯を問わず行えます。
ただし、特商法第7条では不適切な勧誘行為への行政処分規定があり、その委任を受けた施行規則において「迷惑を覚えさせるような仕方」での勧誘が問題視されています。
つまり、訪問時間帯について法律は具体的な数値を定めていないものの、相手にとって迷惑となる時間帯での訪問勧誘は違法な勧誘方法とみなされ得るのです。
特商法の解釈指針として消費者庁が発出した通達(こちら、平成25年2月20日付)では、「『迷惑を覚えさせるような仕方』とは正当な理由なく不適当な時間帯(例えば午後9時から午前8時まで等)に勧誘することが該当する」と示されています。(p15)
この例示から、夜9時以降や早朝8時前の訪問は正当な理由なく行えば消費者に迷惑を及ぼす典型例と考えられていることがわかります。
要するに、法律上明確な時間の線引きは無いものの、「一般常識に照らして非常識な時間帯」の訪問は特商法違反(禁止行為)と判断され、行政指示や業務停止命令等の対象になり得ます。
なお、特商法第3条の2では消費者が勧誘を受ける意思が無いことを示した場合の再勧誘禁止も定められています。深夜など非常識な時間帯に一度訪問して断られた後、改めて日を改めて訪問することも避けるべきでしょう。
以上より、「訪問販売は何時まで可能か?」について法は明示しないものの、少なくとも夜9時~朝8時の訪問は極めてリスクが高いと言えます。
自治体条例・ガイドライン・通達の確認
訪問販売の適切な時間については、国の法律以外に自治体の条例や業界のガイドラインも参考になります。各自治体には「迷惑防止条例」や「消費生活条例」等により、訪問勧誘に関する独自の規制を設けている場合があります。
事業者は営業エリアの都道府県・市区町村の条例やガイドラインを事前に調査し、自社の訪問販売が違法・不適切とならないよう確認しましょう。特に、大都市圏では消費者トラブル防止の観点から夜間訪問への苦情も多いため、行政から注意喚起が出ている場合があります。
実務的な“適切な時間”設定と社内ルール化
法令上の規制と社会通念を踏まえ、実務的には何時頃までの訪問が適切かを考えてみます。一般的に、早朝(午前9時前)や夜間(午後8~9時以降)は訪問を避けるのが無難です。
例えば住宅街では夕飯時~就寝前の時間帯に突然訪問されると不快に感じる人が多く、実際クレームやトラブルに発展しやすい時間帯です。
また、季節によって日没時間が変わる点にも配慮しましょう(冬場は17時でも暗くなり訪問を嫌がられやすいため、終了時刻を早めに設定する等)。
また、訪問時には必ず最初に名乗りと目的告知(特商法第3条義務)を行い、「この時間にお伺いして大丈夫でしたか?」と一言断る姿勢も大切です。
仮に相手が忙しそうであれば無理に長居せずパンフレットを渡す程度に留め、「改めてご都合の良い日時に訪問しましょうか?」と提案するなど柔軟に対応します。
消費者から「帰ってください」「興味ありません」と明確に拒絶された場合は、即座に勧誘を切り上げて退出することが法律上もマナー上も求められます(その場での継続勧誘・後日の再訪問は禁止)。
こうした対応を徹底することで、「しつこい営業だ」「非常識な時間に来られて迷惑だ」という苦情を予防できます。社内教育を通じて各担当者に適切な訪問時間帯の判断基準を共有し、違反時のペナルティも定めておくと良いでしょう。
結果的に、節度ある時間帯での訪問は顧客からの信頼向上にもつながり、将来的なビジネスチャンス拡大にも寄与すると言えます。
訪問販売に必要な「書面」総論(申込書面・契約書面)

このトピックでは、訪問販売における書面交付義務について総合的に解説します。
訪問販売では契約に際し「申込書面」と「契約書面」という2種類の書面交付が事業者に義務付けられており、それぞれ交付のタイミングや必須記載事項が法律で定められています。
ここでは申込書面と契約書面の趣旨と役割、交付すべきタイミング、記載しなければならない項目を整理します。また、これら書面の不備があった場合のリスク(契約の取消や行政処分、クーリング・オフ期間延長など)についても言及し、書面交付義務違反が招く重大な結果を確認します。
申込書面の要件(交付タイミング・必須記載事項)
申込書面とは、訪問販売において消費者が契約を申し込む段階で事業者から交付される書面の通称です(法律上は「契約の申込みの内容を明らかにした書面」と表現されています)。
特商法では、事業者がお店以外の場所(訪問先)で消費者から契約の申込みを受けた場合には、その場で直ちに一定の事項を記載した書面を渡す義務があると定めています(法第4条)。これは消費者に対し、誰とどんな契約を申し込んだのかをきちんと書面で確認させるためのルールです。
通常、営業担当者がお客様から契約申込書にサインや押印をもらったら、その写し(控え)を申込書面としてすぐに手渡します。
もし営業員だけではその場で契約を確定できず、一旦申込みだけ受けて後日会社で審査・承諾する場合でも、申込みを受けた時点で「申込内容を書面で交付」する義務があります。
つまり「本申込みを受け付けました」という記録と契約条件の概要を記載した書面を即座に渡す必要があるわけです。この申込時交付の書面を、本記事では便宜上「申込書面」と呼びます。
申込書面に記載すべき事項は特商法施行規則で具体的に定められており、契約書面の場合とほぼ共通です。主な必須記載事項は以下のとおりです
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名及び商品の商標又は製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
以上が最低限盛り込まれるべき情報です。
特にクーリング・オフに関する注意書きは赤枠で囲み赤字で明瞭に表示することが義務付けられています。申込書面では契約は未成立ですが、将来的に契約が成立した場合に備えてこれら情報を漏れなく伝える必要があります。
用紙のスペースが足りない場合は別紙を添付し、「別紙も含めて申込書面の一部である」ことを明記した上で同時に交付しなければなりません。営業担当者は書面記載欄に漏れなく正確に記入し、記載漏れや誤記載がないよう注意しましょう。
もし申込書面の内容に不備や誤りがあると、後々契約トラブルになったり、法的にも書面交付義務違反とみなされるリスクがあります(この点については後述します)。
契約書面の要件(交付タイミング・必須記載事項)
契約書面とは、訪問販売の契約が成立した際に事業者が消費者に交付する書面です(法律上は「契約の内容を明らかにした書面」)。特商法第5条により、訪問販売で契約を締結したときは事業者は遅滞なく契約書面を交付する義務があります。
多くの場合、商談中に消費者が購入の意思を示し契約合意に至れば、その場で契約成立となり、営業員は直ちに契約書面を作成して交付します。
これは先に渡した申込書面と基本的に同内容ですが、契約成立日などを追加し正式な契約証書として位置付けられるものです。(申込と契約が同時である場合には契約書面のみで良いとされています。)
消費者は後日内容を見返すことで契約条件を確認できますし、事業者にとっても契約書面は社内管理用の控えとして保存し、万一の紛争時には証拠資料となります。したがって、契約書面には双方が交わした合意内容を忠実に反映させなければなりません。
実務上、商品の購入約款やサービス利用規約といった細かな条項がある場合、契約書面と一体でそれら約款類も消費者に交付する必要があります。
契約書面上に「別紙〇〇約款も本契約の一部です」と明記し、実際に約款を添付交付すれば、書面交付義務を満たしつつ詳細条件を網羅できます。この処置により用紙の制約を超えて必要事項をすべて伝達可能です。
不備・違反のリスク(取消・行政処分・返金対応)
申込書面・契約書面の交付義務に違反すると、事業者には重大なリスクが生じます。まず法律違反による罰則です。特商法では書面不交付や不備のある書面交付をれっきとした違法行為と位置付けており、6カ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則規定があります。
実際に罰則適用となるケースは悪質な場合に限られますが、行政処分(指示や業務停止命令)の前提にもなるため注意が必要です。たとえば申込書面をまったく渡さなかったり、契約書面にクーリング・オフの記載がなかったりすれば、それだけで特商法違反と認定されます。
訪問販売の行政処分事例でも、「契約書面に必要事項の記載が欠けていた」「交付すべき時期に書面を交付しなかった」ことが指摘されるケースが後を絶ちません。つまり、書面交付のルール違反自体が行政処分・刑事罰の対象となり得ることを強く認識しましょう。
【関連記事】
>訪問販売事業者の特商法に基づく書面交付義務とは?
書面不交付のクーリングオフ(契約解除)のリスク
書面不備がある場合、消費者はクーリング・オフ期間が進行しないという強力な保護を受けます。法律ではクーリング・オフ期間(8日間)は「書面を受け取った日から」起算すると定められています。
もし「書面を受け取っていない」または「書面の内容が不十分」であれば、消費者は契約内容を十分認識できていないとみなされます。そのためいつまででもクーリング・オフできるとされています。
極端な例を言えば、本来8日を過ぎていても1年後でも、書面不備がある限り一方的に契約解除(申込み撤回)されうるのです。これは事業者にとって大きな経営リスクとなります。
また、クーリング・オフ期間を過ぎても書面不交付を理由に契約そのものの無効や取消しを主張され、代金の返還や損害賠償請求を受ける可能性もあります。
以上を踏まえ、事業者は書面交付義務の履行に万全を期すことが肝要です。不交付・不備を防ぐために、次のような対策が考えられます。
訪問販売の運用フローとトラブル予防(クーリング・オフ対応を含む)

このトピックでは、訪問販売における現場での運用フローを最適化し、消費者とのトラブルを防止するためのベストプラクティスを紹介します。訪問準備から勧誘、契約成立、書面交付、アフターフォローに至る一連の流れを整理し、各段階で気を付けるべきポイントをまとめます。
また、クーリング・オフが発生した場合の実務対応について具体的な手順を解説します。
契約フロー(訪問前→勧誘→成約→交付→アフター)
訪問販売の現場における一連の流れを整理すると、以下のようになります。
訪問前準備
ターゲットリストの精査と訪問計画の策定を行います。飛び込み訪問であっても無作為に回るのではなく、過去にクレームのあった地域や「訪問販売お断り」の貼り紙がある家は避けるなど、事前の確認しておきましょう。
また、訪問予定時刻が非常識にならないようスケジュール管理します(前述の社内ルールに従う)。パンフレットや契約書類一式、名刺、身分証、会社パンフレット等を忘れず携行し、清潔感のある服装で臨みます。
訪問・勧誘開始
消費者宅を訪問したら、インターホン越しでも構いませんので第一声で名乗りと目的を伝えます。「こんにちは、〇〇株式会社の営業担当△△と申します。本日は○○のご案内で伺いました。」といった具合です。法律上、この氏名等の明示は勧誘に先立って必ず行わねばならない義務です。
訪問先の反応を確認し、怪訝そうであれば「お時間よろしいでしょうか?」と伺いを立てます。相手が話を聞く意思を示した場合のみ玄関先で説明を始めます。
勧誘意思の有無を確認する努力義務(特商法第3条の2)も踏まえ、無理に家に上がり込んだりドアを塞いだりせず、相手のペースに合わせます。
また、商品パンフレットや契約約款など、説明に必要な資料は見やすい形で提示し、虚偽・誇張のないよう誠実に商品説明を行います。
勧誘中盤
消費者が興味を示した場合でも、契約を急かすような強引さは禁物です。長時間に及ぶ勧誘も迷惑行為となり得ますので、常識的な範囲(目安として1時間程度)で切り上げるよう心掛けます。
相手が迷っている様子なら、「いったんお考えいただきましょうか?」と提案し、後日改めて訪問の約束をするのも手です。消費者が契約意思がないと表明した場合、決して食い下がってはいけません。その場で勧誘を即座に終了し、すみやかに退出します。
ここで「今回だけ特別ですから!」などと粘ったり、「買う気があって呼んだんだろう?」等と威圧するのは絶対にNGです。相手に不安や迷惑を感じさせた時点で特商法違反(困惑させる勧誘の禁止)となる可能性があります。
契約成立・書面交付
消費者が購入の意思を固め「お願いします」と契約する旨を示したら、契約手続きに移ります。用意していた契約書(申込書)に必要事項を記入し、消費者から署名(または押印)をもらいます。
記入漏れがないよう項目を一つずつ確認しながら進め、口頭でも要点を復唱して誤認を防ぎます。「本日は○○の商品を△△円でご契約、支払方法は□□、お届けは○月○日予定で承りました」といった具合です。
契約内容に相違がないことを双方確認したら、申込書面(申込書面)をその場でお客様に手渡します。さらに契約が確定した場合には契約書面を作成し、こちらも遅滞なく交付します。
多くの場合、申込書の控えがそのまま契約書面を兼ねますので、一式まとめてお客様に渡せばOKです。ここでクーリング・オフの説明も必ず行いましょう。
契約書面のクーリング・オフ欄を指差しながら、「本日から8日以内でしたら無条件で契約解除できます。その際はここに書いてある方法でご連絡ください」と丁寧に伝えます。書面には赤枠で注意書きが印刷されていますが、口頭でも補足することで消費者の安心感につながります。
「もちろん良い商品なので気に入っていただけると思いますが、ご不明点が出ましたらご連絡ください」と付け加えるのも良いでしょう。なお、契約成立時に現金を受領する場合は領収証を発行します。
代金の受け取りはクーリング・オフの妨害にならない範囲で法的に問題ありません(受領しても8日以内解除可能)。
しかし、心理的には「お金を払ったからもう撤回できないのでは?」と誤解させないよう、「※契約解除時には全額ご返金しますのでご安心ください」と一言添える配慮も考えられます。
アフターフォロー
訪問販売では契約して終わりではなく、その後のフォローも重要です。商品をすぐ渡した場合は改めてお礼を述べ、使用方法や保証書の説明など必要事項を案内します。商品引渡しやサービス提供が後日の場合、納期や開始日を再確認し、確実に履行してください。
クーリング・オフ期間中の対応も慎重さが求められます。期間内にお客様から問い合わせがあれば迅速に対応し、「解約したい」といったニュアンスがあれば手続方法をきちんと案内します。
間違っても「今キャンセルすると違約金がかかりますよ」などと嘘を言って引き止めるような行為は絶対にしてはいけません(それ自体が違法です)。
以上の流れをマニュアル化し、全営業スタッフに共有しておくことが有効です。訪問前の準備チェックリストから契約締結時のセリフ例、アフターフォローの手順まで網羅した社内マニュアルを整備し、常に現場で参照できるようにします。
各ステップで「ここで必ず○○する」「○○は禁止」と具体的に記載しておけば、新人でも漏れなく対応できますし、仮に現場担当者が独断で逸脱行為をしてしまっても「会社としては違反防止策を講じていた」ことの証明にもなります。
訪問販売は何時まで?まとめ
この記事では、訪問販売における適切な勧誘時間の設定から、申込書面・契約書面の交付義務、クーリング・オフ対応まで、包括的に解説してきました。
これらは、いずれも消費者の信頼を得るために不可欠な要素です。適法に営業することはトラブルを避け企業の信用を守るのみならず、お客様との長期的な関係構築にも寄与します。ぜひ本記事の内容を参考に、自社の訪問販売のルールや書面の運用を見直してみてください。
訪問販売による特商法書面の作成はお任せください

当事務所では、特定商取引法に基づく申込書面・契約書面の作成サポートを行っています。
訪問販売の適法・円滑な運用に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
適切な契約書類の整備と運用フローの確立によって、安心して営業活動に専念できるよう全面的にお手伝いいたします。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面(申込書面)や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際の業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面(申込書面)および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

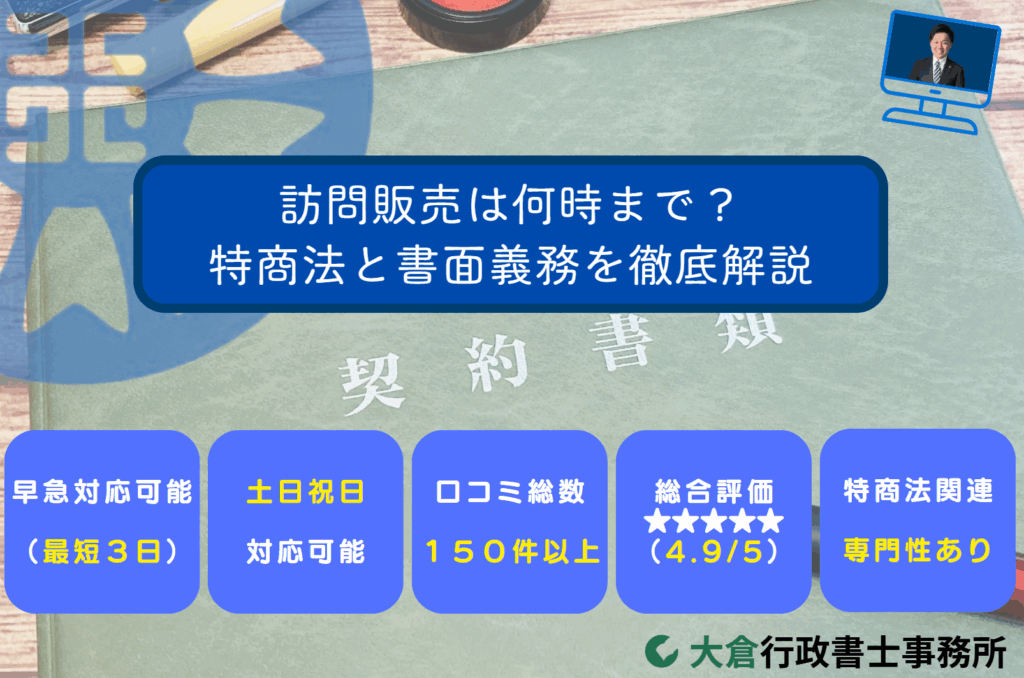
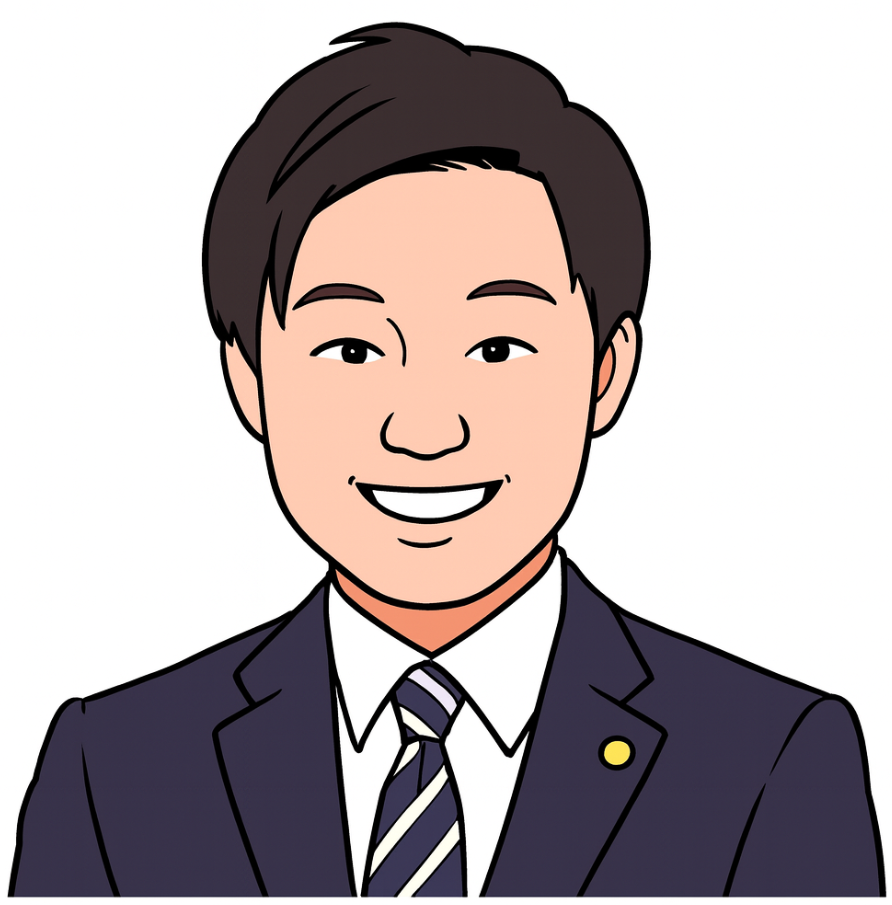
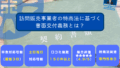
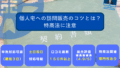
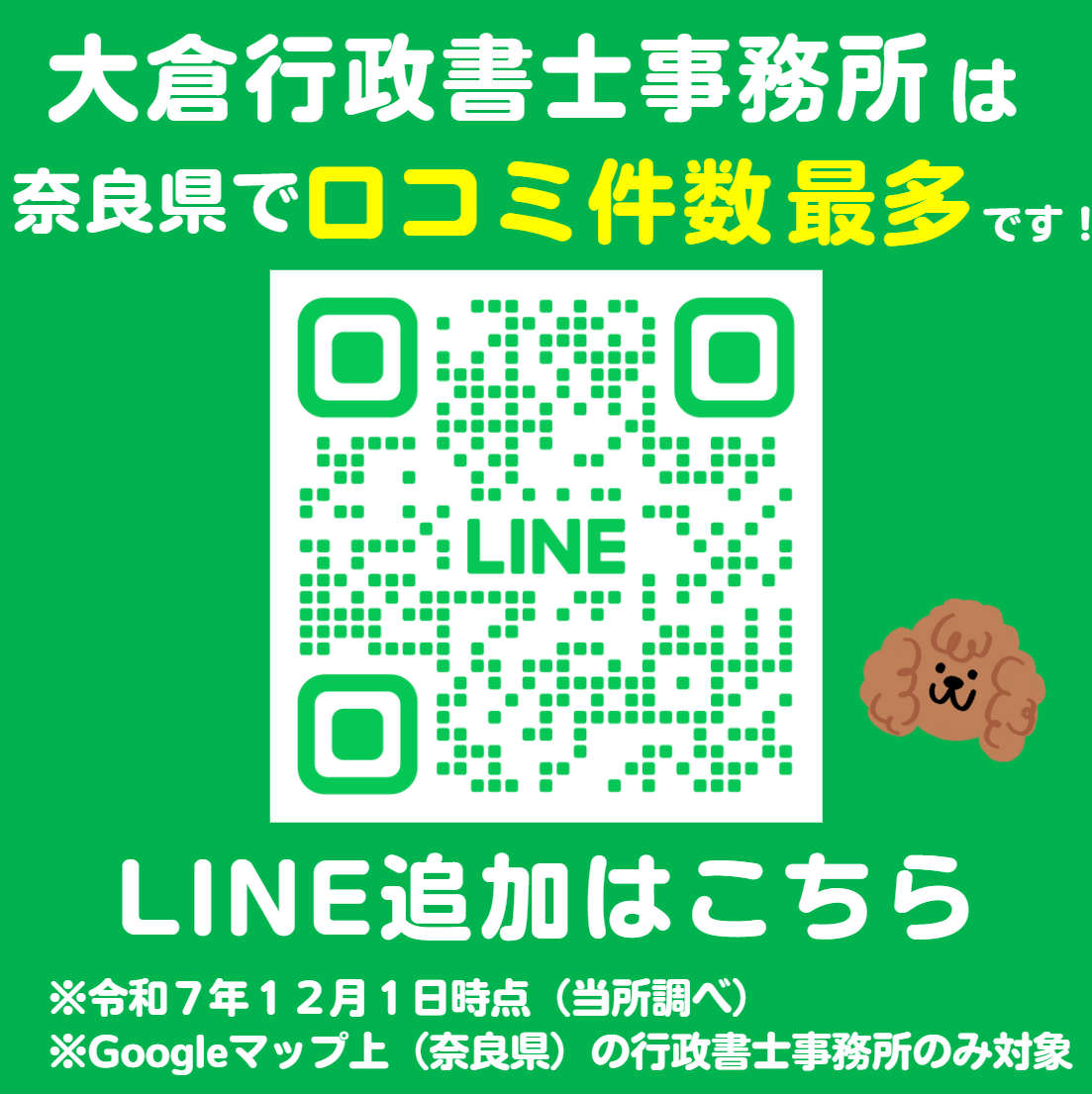
コメント