訪問販売は、健康食品や美容製品、住宅リフォームなど様々な業界で活用される営業手法です。個人宅を直接訪問して商品やサービスを紹介できる貴重な機会ですが、初対面の相手に信頼してもらうのは簡単ではありません。
本記事では、個人宅での訪問販売で成果を上げるためのコツを徹底解説するとともに、行政書士の視点から特定商取引法(特商法)による重要なルールにも触れていきます。訪問販売を行う事業者には、法律で定められた義務があり、違反すればクーリングオフ(無条件解約)をされてしまったり行政処分・罰則の対象ともなり得ます。
成功のポイントと法令遵守の両面を押さえ、健全かつ効果的な訪問販売営業を目指しましょう。
個人宅への訪問販売で成果を上げるコツ

このトピックでは、個人宅への訪問販売を成功させるためのコツを紹介します。第一印象の作り方からお客様への接し方、断られた場合の対応まで、基本的なポイントを押さえることでお客様からの信頼を得やすくなり、契約率向上につながります。訪問販売は「数×改善」の世界とも言われ、地道な工夫と努力が成果に直結します。
第一印象で信頼をつかむ
訪問販売において第一印象は想像以上に重要です。玄関先やインターホン越しのわずか数秒で「この人は信頼できるか」が判断されます。そのため、以下の点に気を配りましょう。
- 清潔感のある身だしなみ:服装や髪型、靴まで清潔に整え、爽やかな印象を与えます。名刺や社名を提示する際にもきちんとした所作を心がけましょう。
- 笑顔と丁寧なあいさつ:ピンポンを押す前に一度深呼吸し、柔らかな笑顔を作ります。ドアが開いたら明るい声で挨拶し、はっきりと自分の名前と会社名を名乗ってください。最初のひと言で「感じの良い人だ」と思ってもらえるかが勝負です。
- 姿勢と言葉遣い:相手に威圧感を与えないよう、背筋を伸ばしつつも腰を低くして話します。敬語を適切に使い、丁寧で礼儀正しい態度を示すことで「この人なら安心だ」と感じてもらえます。
第一印象で信頼をつかむことができれば、話を聞いてもらえる確率が格段に上がります。「見た目9割」とも言われる営業の世界で、まずは信頼される土台を築きましょう。
お客様の話に耳を傾ける
訪問販売というと「セールストークで売り込む」イメージがありますが、実は“話す”より“聞く”姿勢の方が大切です。商品説明ばかりを一方的にするのではなく、以下のポイントを意識してお客様の声に耳を傾けましょう。
- ニーズのヒアリング:お客様の生活状況や悩み、ニーズを質問して引き出します。「どんな点にお困りですか?」などと問いかけ、相手が話しやすい雰囲気を作りましょう。
- 共感と相づち:お客様が話している間は決して遮らず、適度に相づちを打ったり「おっしゃる通りですね」などと共感を示します。自分の話をちゃんと聞いてくれる営業には心を開きやすくなります。
- 提案はニーズに沿って:お客様の話を十分に聞いた上で、そのニーズに合った形で商品やサービスの提案を行います。用意したトークスクリプトはあくまで型と捉え、相手の反応に応じて柔軟にアレンジしましょう。
無理に説得するより、お客様自身が「それなら必要だ」と納得できるような説明を心がけます。
「この営業は自分の話をちゃんと聞いてくれる」と感じてもらえれば信頼関係が生まれ、押し売りしなくても自然と契約に近づきます。傾聴の姿勢こそが訪問販売成功の鍵と言えるでしょう。
断られた際の対応と学び
どんなに努力しても、訪問販売では断られることが当たり前です。大切なのは断られた後の対応で、これが次のチャンスにつながるかどうかを左右します。断られた際は以下を心がけましょう。
- 断られ方を分析:ただ落ち込むのではなく、「なぜ断られたのか?」を振り返ります。例えば「タイミングが悪かった」「興味はあるが予算がない」など、断りの理由から次回の改善点を見出します。断られ方にも必ずヒントがあるものです。
- 丁寧な後処理:断られた場合でも、笑顔でお礼を伝えましょう。「本日はお時間ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします」と一言添えると、印象が格段に良くなります。最後の態度次第で、「感じの良い営業だったな」と記憶に残り、後日のアプローチで成果に結びつく可能性もあります。余談ですが、筆者は自宅を購入する際に、SUUMO様を利用して複数業者に話を聞きましたが、ある住宅会社は自社で購入しないことが分かった途端にLINEの既読も付かなくなったこともあり、印象は当然よくはなかったです。
- 記録と振り返り:訪問結果を必ず記録し、社内で共有・分析しましょう。断られた理由やお客様の反応をメモしておけば、次回訪問時の参考になります。また、日々の営業後に「良かった点・悪かった点」を振り返る習慣をつけてください。同僚や上司にフィードバックを求めるのも効果的です。
訪問販売は「数×改善」の積み重ねです。断られるたびに学びを得て、自身のトークや対応をブラッシュアップしていく人こそが最終的に成功を掴みます。どんな断りも次につなげる糧と捉え、前向きに取り組みましょう。
個人宅への訪問販売における特商法のルール
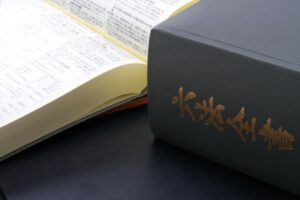
このトピックでは、訪問販売を行う事業者が守るべき特定商取引法上のルールを解説します。特商法は消費者を保護し公正な取引を促すため、訪問販売に対して様々な規制を設けています。営業テクニックだけでなく、法律で定められた義務を正しく理解・遵守することが、長期的に信頼される事業運営には欠かせません。
不適切な勧誘や書面交付漏れは契約解除や行政処分に直結しかねないため、ここで主要なポイントを押さえておきましょう。
勧誘時の義務と禁止事項
訪問販売でお客様宅を訪問した際、事業者(販売員)は勧誘の冒頭で果たすべき義務があります。まず、事業者の氏名(または名称)と訪問の目的(契約締結の勧誘であること)および取扱商品等の種類を告げなければなりません。
いきなり商品の説明を始めるのではなく、「○○会社の△△と申します。本日は◯◯(商品カテゴリー)のご案内で参りました」のように、身分とセールス目的を明示しましょう。このように名乗ることで、お客様に「誰が何のために来たのか」を最初にきちんと伝えることが法律上求められています。
さらに、勧誘に先立ちお客様が話を聞く意思があるか確認する努力義務も課されています。例えば「少しお時間よろしいでしょうか?」などと尋ねて、相手の都合や意向を確かめることが望ましいでしょう。
もし消費者が「興味がない」「必要ないです」など契約する意思がないことを示した場合、それ以上その場で勧誘を続けることは禁止されています。また、後日改めて訪問して再勧誘することも同様に禁止です。
一度断られたらすぐに引き下がり、粘ったり日を改めて押しかけたりしないよう注意してください。しつこい勧誘は法律違反であるだけでなく、消費者からの信頼を失い社会的信用を損なう行為でもあります。
なお、特商法では訪問販売時の不当な行為についても明確に禁止事項を定めています。例えば以下のような行為は違法となります。
- 事実と異なる説明で消費者を勧誘する(商品の効果や契約条件について嘘をつく)
- 重要事項を故意に告げないで契約させる(不都合な点を隠して契約を急がせる)
- 威迫行為(大声や恫喝で恐怖心を与え、契約を迫る)
- 勧誘目的を隠して呼び出した場所(自宅以外の喫茶店等)で契約を迫る(いわゆるキャッチセールス・アポイントメントセールス)
- 夜間遅くに訪問したり、長時間居座って執拗に説得したりする
- 消費者が通常必要としない過大な量の商品を売りつける(高齢者に使い切れない量の健康食品を購入させる等)
これらはいずれも消費者の生活や意思決定の自由を脅かす行為であり、特商法によって厳しく規制されています。特に夜間(概ね午後8時以降)の訪問はトラブルになりやすく、地域によっては警察や自治体への通報案件にもなります。事業者として社会的信用を失わないためにも、誠実で適切な勧誘を徹底しましょう。
【関連記事】
>訪問販売は何時まで?
書面交付義務とクーリング・オフ制度
訪問販売で商談が進み、契約の申込みや契約の成立に至った場合、事業者には書面を交付する義務があります。具体的には、お客様が契約を申し込んだ際には「申込書面」を、契約が正式に成立した際には「契約書面」をそれぞれ渡さなければなりません。
これらの書面には取引内容を明記し、後述するクーリング・オフ等に関する事項も記載する必要があります。書面交付は単なる形式ではなく、お客様に契約内容を理解・確認してもらうための法的に重要なプロセスです。
特にクーリング・オフ制度については注意が必要です。特商法では、訪問販売で契約した消費者に対し、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる権利(クーリング・オフ)を認めています。
訪問販売の契約の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者は理由を問わず一方的に契約を解除可能です。例えば8月1日に契約書面を渡したなら、8月8日までに書面またはメール等で解除の意思を伝えれば契約は白紙撤回できます。
事業者側は受け取った代金をすみやかに全額返金し、商品を引き取る義務があります。重要なのは、書面を正しく交付していないとこの8日間の起算が始まらない点です。もし交付すべき書面を渡していなかったり、書面にクーリング・オフの告知や日付の記載漏れがあると、法律上「書面を受け取ったことにならない」扱いとなります。
その場合、たとえ契約日から何ヶ月経過していても、お客様は「書面不備」を主張して契約をクーリング・オフできてしまいます。つまり、事業者にとって書面交付義務を怠ることは、クーリング・オフ期間が無期限に延長されるリスクを生むのです。
さらに言えば、仮に「もうクーリング・オフ期間は過ぎましたよ」などと誤った説明をして消費者を惑わせた場合、後から発覚すればやはり契約解除を許容されるだけでなく、悪質な場合は行政処分の対象にもなり得ます。
特商法は消費者保護のための法律ですから、正しい書面交付と公正な対応を徹底することが、お客様とのトラブル防止と信頼構築に直結します。
違反した場合のリスク
特商法に定められた義務や禁止事項に違反すると、事業者は様々な法的リスクを負います。まず、前述のとおり書面の不備はクーリング・オフ期間の無期限延長を招き、消費者からいつでも契約解除される可能性があります。
加えて、特商法違反を行った事業者には行政当局からの処分が科されることがあります。具体的には、消費者庁や経済産業局からの業務改善指示や業務停止命令、悪質な場合は役員の業務禁止命令などが発せられる場合があります。これらは事業継続に重大な支障を来す措置です。さらに一部の悪質な違反行為については刑事罰(罰金刑等)の対象ともなり得ます。
法令違反のペナルティも深刻ですが、同時に見過ごせないのが信用失墜のリスクです。不適切な勧誘や違反行為は口コミや報道を通じて瞬く間に広まり、顧客だけでなく地域社会からの信頼を失います。
特に高齢者宅への夜間訪問や執拗な勧誘は、近隣住民や自治体から警察に通報されるケースもあります。一度「悪質業者」のレッテルを貼られてしまうと、事業継続は困難になるでしょう。特商法の多くの規制は「消費者の自由な意思と平穏な生活を守る」理念に基づいています。
法律違反さえしなければ良いという姿勢ではなく、誠実な情報提供・適切な勧誘・明確な契約手続きを徹底することで消費者との信頼関係を築くことが、結果的に事業者自身を守ることにつながります。
以上のように、特商法を遵守することは単に罰則を避けるためだけでなく、顧客満足度の向上や事業の健全な発展にも直結しています。法律を正しく理解し、コンプライアンスを徹底した営業活動を行いましょう。
個人宅への訪問販売における申込書面とは?

このトピックでは、訪問販売で用いる「申込書面」について解説します。申込書面とは、お客様が契約の申込み(注文)を行った際に事業者が交付する法定書面のことです。訪問販売では契約プロセスが対面で行われるため口頭説明だけでは行き違いが生じる恐れがありますが、申込書面を交付して内容を書面化することで認識のズレや誤解を防ぐ役割を果たします。
ここでは申込書面を渡すタイミングや記載事項、その作成・交付上の注意点を説明します。
申込書面の交付タイミングと目的
申込書面は、消費者(お客様)が契約を申し込んだその場で直ちに交付しなければならない書面です。訪問販売でお客様が「それを購入します」と意思表示をしたら、営業担当者はすぐに申込書面を作成してお客様に控えとして渡します。
申込書面には、申込みを受けた商品・サービスの内容や数量、代金等の具体的な事項が記載されます。これはお客様にとって、どの商品をいくらで申し込んだのかを書面で確認できる控えとなります。
申込書面交付の目的は、お客様が契約内容を十分理解した上で申し込めるようにすることです。不意打ち的な訪問販売では、その場の雰囲気で契約してしまい後から「聞いていない話があった」というトラブルが起こりがちです。
申込書面を交付することで、契約に申し込んだ内容を改めて文章で示し、お客様自身にも確認してもらえます。口頭説明だけでなく書面を残すことで、「確かにこの商品をこの価格・条件で申し込みましたね」という共通認識を事業者と消費者の間で持てるわけです。
申込書面は言わば契約申込の明細書であり、お客様への丁寧なフォローであると同時に、事業者を後日の紛争から守る役割も果たす重要書面です。
申込書面に記載すべき主な事項
申込書面には、特商法で定められた一定の記載事項を漏れなく記載する必要があります。主な項目は以下の通りです。
- 商品・役務の内容:申し込まれた商品名やサービス内容、その型式や権利の種類など。例えば健康食品なら商品名と内容量、リフォームなら工事内容の概要などを具体的に書きます。
- 販売価格・対価:商品の代金やサービス料金(税込金額)。割引等がある場合は適用後の価格を明記し、総額がひと目で分かるようにします。
- 数量:商品の個数やサービス提供回数など、申し込まれた数量。
- 代金の支払時期・方法:いつまでにどのように代金を支払うか(現金一括・分割払い・振込期限等)。分割払いの場合は支払回数や各回の金額も記載します。
- 商品の引渡時期・役務提供時期:商品をいつ納品するか、サービスをいつ開始・実施するか。例:「○月○日までに宅配便で発送」や「契約日から◯週間後に工事開始」等。
- 事業者の氏名・住所・連絡先:販売業者(会社名や代表者名)、住所、電話番号。お客様から問い合わせやクレームができるよう、連絡先は正確に。勧誘・契約担当者の氏名:実際に訪問対応した営業担当者の氏名。
- 申込日:契約の申込みを受け付けた年月日。
- クーリング・オフ等の権利に関する事項:後述する契約解除(クーリング・オフ)の方法や期間について。特にクーリング・オフ可能な旨とその手続き方法は赤枠・赤字で明示しなければなりません。
上記は主な項目ですが、この他にも契約解除に関する特約がある場合はその内容、商品に瑕疵(欠陥)があった場合の対応について定めがあるならその内容なども記載します。
要するに、契約の重要事項は全て盛り込む必要があるということです。申込書面の段階でしっかり情報提供しておくことで、お客様が後から「聞いていない」「知らなかった」となるリスクを減らせます。法律上も申込書面の記載事項は細かく規定されていますので、テンプレートを作成する際は漏れのないようチェックリストを活用しましょう。
申込書面作成・交付の実務ポイント
申込書面を適切に運用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。交付は申込を受けた後「直ちに」です。特商法上、「直ちに交付」とは申込を受けたその場ですぐという意味です。
お客様から申込みの意思表示を受けたら、その日のうちどころか会話が一段落した時点で即座に書面を手渡す必要があります。書類を用意していなかったり後日郵送するような対応では義務を果たしたことになりません。
訪問前にあらかじめ基本事項が印字された申込書面フォーマット(用紙)を用意しておき、現場で日付や商品名・価格などを書き込んで交付するのが一般的です。
契約未成立の場合でも交付
申込書面はあくまで「申込み」を受けた段階で渡す書面です。したがって、その場で契約が確定していなくても、お客様が「申し込みます」といった時点で交付義務が生じます。
例えばクレジット審査等が残っている場合でも、一旦申込書面は発行しておき、後日契約不成立となった場合にはその旨をお客様に連絡する対応を取ります。
申込と契約が同時の場合
訪問販売では申込から契約締結までがほぼ同時に行われるケースもあります。その場合、申込書面を省略して契約書面のみ交付すれば足りるとされています。(契約書面については次のトピックで記述します。)
法律上、申込と契約が同時なら2段階の書面交付を一度で済ませても構わないという扱いですが、実務上は申込書兼契約書のような形で作成し、契約成立前後で書面内容に矛盾がないよう注意しましょう。
申込書面と契約書面の2段構えにしている場合は、申込時点での約束と契約確定時の条件が食い違わないよう整合性をとることが重要です。
記載漏れ厳禁
前述の通り申込書面の記載事項には法定項目があります。一つでも欠けると交付義務違反となり、契約無効主張や行政処分のリスクが生じます。特にクーリング・オフに関する記載漏れは重大で、書面交付そのものが無効と見なされかねません。
作成時には最新の法規に基づく様式か確認し、必ず複数人でチェックする体制を作りましょう。
お客様への説明
申込書面を渡す際、「こちらが本日お申し込みいただいた内容になります。後ほど契約書面もお渡ししますのでご安心ください」など一言添え、書面をよく読むよう促すことも大切です。
申込書面は法律上の義務であると同時に、お客様に安心感を与えるツールでもあります。「書類なんて面倒」と敬遠せず、信頼獲得のチャンスと捉えて丁寧に対応しましょう。
個人宅への訪問販売における契約書面とは?

最後に、訪問販売で交付する「契約書面」について説明します。契約書面とは、その名の通り契約が正式に成立した後にお客様に渡す書面で、最終的な契約内容を明確に示すためのものです。訪問販売では口頭合意だけで終わらせず、書面によって双方が合意した内容を確認・保存することが義務付けられています。
本トピックでは、契約書面を交付するタイミングと役割、記載すべき事項、そして契約書面作成・交付の際の実務上のポイントを解説します。
契約書面の交付タイミングと役割
契約書面は、契約が正式に成立した後に遅滞なく交付しなければならない書面です。訪問販売では申込みから契約確定まで時間差がほとんどない場合も多いですが、一般的には申込書面交付後、社内手続きや顧客の最終同意を経て契約成立となり、その直後に契約書面を交付する流れになります。
法律上「遅滞なく」とは明確な時間の定義はありませんが、通常契約当日中か遅くとも翌日から翌々日までには渡すことが求められます。現場で即契約書面を作成できるよう準備しておくことが理想です。
契約書面の役割は、最終的な契約条件を紙に残すことにあります。申込段階から条件が変更された場合(値引き交渉の結果価格が変わった等)は、その最終合意内容が契約書面に反映されます。
双方の合意内容を文章で確認することで、「言った言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。またお客様にとって契約書面は大事な契約の証拠であり、後からゆっくり読み返して内容を再確認できる安心材料でもあります。
契約書面をしっかり交付することは、事業者にとっては法的義務であると同時に、お客様へのアフターフォローでもあるのです。
契約書面に記載すべき主な事項
契約書面に記載すべき事項は基本的に前述の申込書面とほぼ共通しています。商品・サービス名、数量、価格、支払方法、引渡時期、事業者情報、担当者氏名、契約日など、契約内容のすべてを網羅的に記載します。
特に契約書面は最終合意内容を示すものですから、申込段階から変更があった点(値引き後の価格や追加サービスなど)は漏れなく反映させなければなりません。申込書面では仮の予定だった事項(工事日程等)が確定した場合は、その確定内容を記載します。そして契約書面でも最重事項と言えるのがクーリング・オフに関する明示です。
契約書面には「契約の申込みの撤回・解除に関する事項」、つまりクーリング・オフ可能である旨と具体的な方法・期限を必ず記載します。この記載は赤枠で囲み赤字で強調することが法律で求められており、例えば「本契約は書面受領日を含め8日間は無条件で解除できます。解除の際は書面(ハガキ等)または電子メールで○月○日(8日目の日付)までに通知してください。」といった内容を目立つように書きます。
加えて「重要事項につき必ずお読みください」といった注意喚起文も赤字で記載する決まりです。文字の大きさも8ポイント以上(官報と同程度)で印刷する必要があり、細かい字でこっそり書いておくようなことは許されません。
契約書面は契約の最終版と言える書類です。お客様との合意事項を一つ残らず明記し、法定記載事項の漏れがないよう十分注意しましょう。記載漏れや誤記があると、前述の通りクーリング・オフ期間が延長されるなど大きなリスクとなります。
契約書面作成・交付の実務ポイント
契約書面についても、実務上押さえておきたいポイントがあります。契約書面は「遅滞なく」交付が原則です。訪問先で契約が成立したなら、その場で契約書面を作成しお渡しするのが望ましいでしょう。
後日郵送ではタイムラグが生じ、万一郵送中に8日間が経過するとトラブルの元です。現在ではタブレット等で契約内容を入力し、その場でプリンター印刷して交付するケースも増えています。難しい場合でも当日中の郵送手配を行い、できるだけ早くお客様の手元に届くようにします。
以上のように契約書面の適切な交付は、消費者保護の最後の砦であると同時に、事業者自身の信頼を高める行為でもあります。「契約書をきちんと渡してくれたので安心できた」という声も多く、お客様満足度向上につながります。
法律に則った正確な契約書面を交付し、お客様との健全な信頼関係を築いていきましょう。
【関連記事】
>訪問販売事業者の特商法に基づく書面交付義務とは?
訪問販売による特商法書面の作成はお任せください

訪問販売を行うにあたり、特定商取引法(特商法)に則った「申込書面」および「契約書面」の適正な作成と交付は、事業運営の信頼性を支える基盤です。書面の不備や不交付は、クーリング・オフの無期限延長や行政処分のリスクに直結し、事業者にとって重大な経営リスクとなり得ます。
行政書士として、当職はこうした訪問販売事業者様の法令遵守と実務支援を専門的にサポートしております。特に、以下のようなご相談・ご依頼に対応しています。
- 最新法令に対応した申込書面・契約書面の作成
特商法の改正動向をふまえた適正様式をご用意し、事業内容や取扱商品(健康食品、美容機器、住宅リフォームなど)に応じてカスタマイズいたします。 - クーリング・オフ要件を満たす記載内容の確認
赤枠・赤字・フォントサイズなど、形式要件を正確に反映した文言整備を行い、トラブルの芽を事前に摘みます。 - 行政対応の備え・顧客トラブル予防のためのアドバイス
消費者センターへの申出・行政指導が入る前に、予防的措置として書面整備・営業トーク点検を実施することができます。
「書面の作成まで手が回らない」「自社の書式が法的に問題ないか不安」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。
特定商取引法に強い行政書士として、安心して営業できる訪問販売体制づくりを丁寧にお手伝いさせていただきます。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面(申込書面)や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際の業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面(申込書面)および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

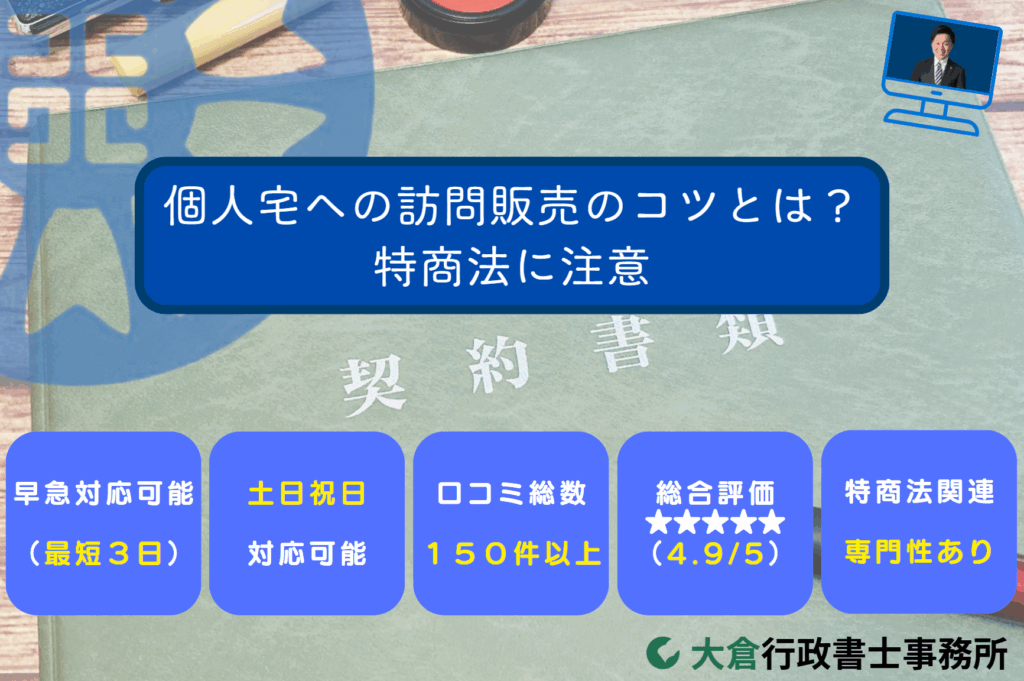
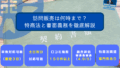
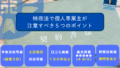
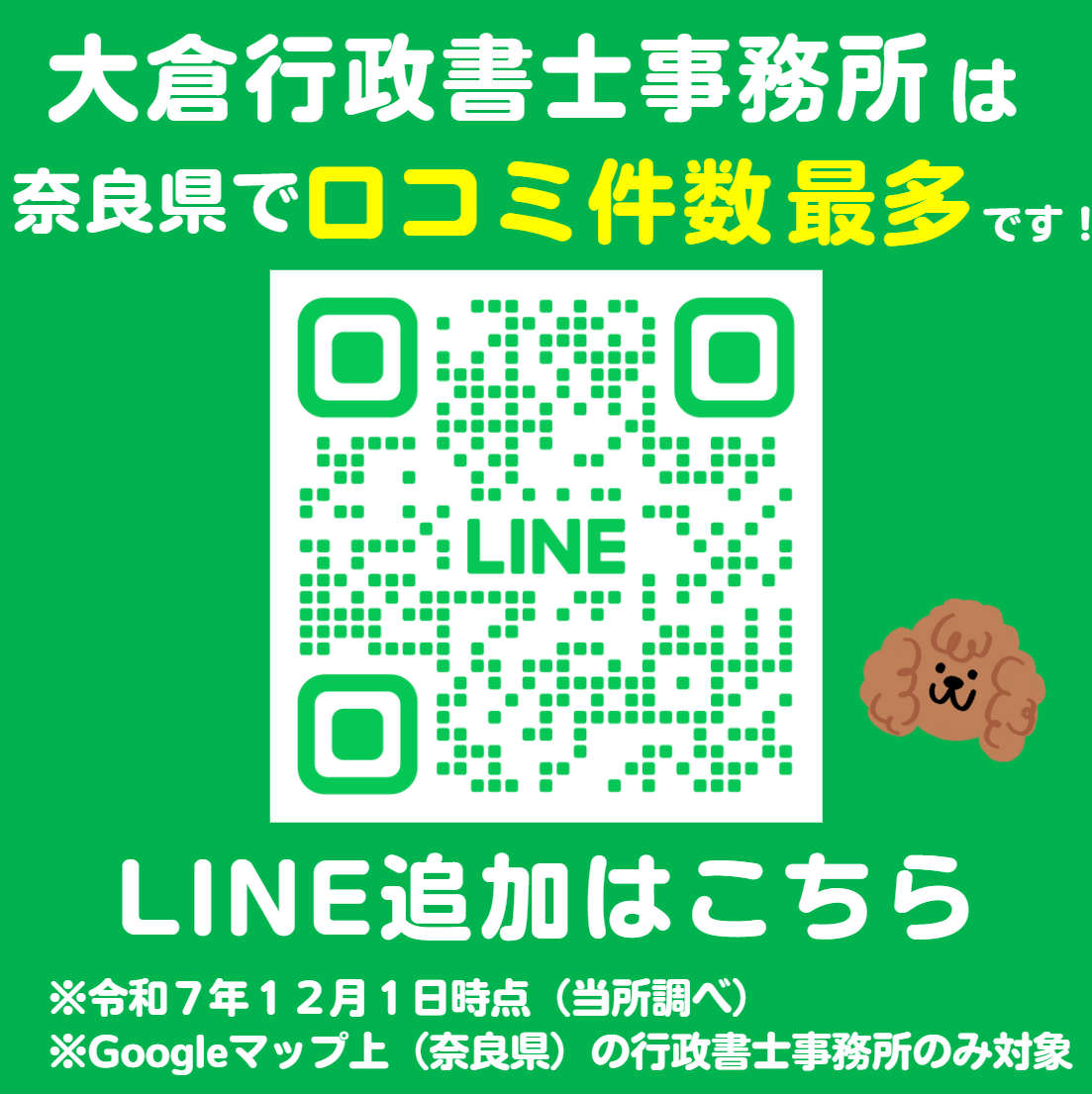
コメント