特定商取引法(特商法)は、訪問販売や通信販売など消費者トラブルが発生しやすい取引を規制する法律です。
多くの方は訪問販売の「クーリング・オフ」で名前を聞いたことがあるかもしれませんが、特商法ではそれ以外にも事業者側に様々な義務が課されています。
個人事業主であっても、自社の事業内容によっては特商法の規制対象となります。しかし現実には、「小規模だから大丈夫」「法律は知らなかった」として、特商法上の義務を果たさずに契約を結んでしまうケースが少なくありません。
本記事では個人事業主が特商法で注意すべき5つのポイントを特商法を専門業務の一つとして扱う行政書士が解説します。
特定継続的役務提供事業者や訪問販売事業者に課せられる書面交付義務を中心に、法を遵守するために知っておくべき重要事項を確認しましょう。なお、特商法は個人事業主にとっても決して他人事ではありません。それでは早速、具体的な注意点を見ていきましょう。
個人事業主でも特商法の規制対象になる

このトピックでは、個人事業主も特定商取引法の対象となり得ることを説明します。特商法は特定の取引形態に着目して定められており、企業形態の大小を問いません。つまり、相手が消費者であれば、個人経営の事業者であっても法律を守る義務があります。
特商法による規制は事業者の規模ではなく取引の類型で決まるため、小規模事業者も例外ではないという点を認識しましょう。個人事業主も例外ではないことをしっかり押さえておきましょう。
特商法が適用される「事業者」とは
特商法における「事業者」とは、商品やサービスを提供して収益を得る者を指します。その中には株式会社などの法人だけでなく、フリーランスや個人事業主も含まれます。営業規模や社員数に関係なく、消費者相手の取引であれば特商法は個人事業主にも適用されるのです。
例えば、一人でエステサロンを運営している場合や、自宅から通信販売を行っている場合でも、取引内容が特商法の定める類型に該当すれば規制の対象となります。
個人事業主が特に該当しやすい取引類型
個人事業主が関わる可能性の高い特商法の取引類型として、訪問販売と特定継続的役務提供の二つが挙げられます。訪問販売とは、店舗や事務所といった常設の営業所以外の場所(顧客の自宅や職場、公園など)で商品やサービスの契約を行う販売形態です。
代表的なのが、自宅を突然訪れて商品を売り込む、いわゆる押し売りです。このような訪問販売では、消費者が不意を突かれた状態で勧誘を受けるため、心理的な圧力がかかり冷静な判断が難しくなります。
結果として、本来は購入する意思がなかったのに、その場の雰囲気に押されて契約してしまうケースもあります。例えば、高齢者宅に営業員が突然訪れ、高額な布団や浄水器を契約させてしまうといった事例が後を絶ちません。
一方、特定継続的役務提供とは、長期間にわたり継続的なサービスを高額の対価で提供する取引を指し、エステサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、美容医療などの7種類の役務が現在指定されています。
これらは個人経営で開業する例も多く、知らないうちに特商法の規制対象となっていることがあります。具体的には「サービス提供期間が2ヶ月を超え、かつ契約総額が5万円を超えるような契約」を扱う事業者が該当します(エステ・美容医療は契約期間1か月超かつ金額5万円超、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスは期間2か月超が基準)。
例えば、個人でヨガ教室を開き数ヶ月単位のコース契約を結んでいるケースや、プライベート英会話レッスンを数十万円のパッケージで販売するケースなどがこれにあたります。
個人事業主であっても、こうした長期サービスの提供契約を結ぶ場合は特定継続的役務提供事業者として特商法のルールに従わなければなりません。
なお、契約期間が2ヶ月以内であったり総額5万円以下の場合は特定継続的役務提供には該当しません。例えば1ヶ月だけのお試しコースや低額な単発サービス契約であれば、特商法のこの類型には当たらない点も覚えておきましょう。
【関連記事】
>特定継続的役務提供
消費者相手の取引は原則すべて対象
特商法は消費者保護を目的としているため、取引の相手が個人の消費者であれば基本的に同法の適用範囲に入ります。ただし、事業者同士の取引(B2B取引)や店舗内で完結する通常販売など、一部適用除外も存在します。
重要なのは、「自分は個人事業主だから特商法は関係ない」という誤解をせず、提供するサービスや販売方法によって自社が該当する法律上の義務を正確に把握することです。
なお、消費者が自ら「事業者」として契約した場合にはクーリング・オフ適用外になるケースもありますが、販売側がそれを誘導し契約書上で業務用取引と偽るような行為は違法となります。
特定継続的役務提供事業者と訪問販売事業者のチェック

このトピックでは、ご自身の事業が特商法上どの類型に当たるか確認するポイントを解説します。
個人事業主の場合、特に特定継続的役務提供事業者または訪問販売事業者に該当するかどうかが重要です。
これらに該当すれば、契約時に交付すべき書面など特商法ならではの義務が発生します。自社がこれらの事業者に該当する場合、特商法上の義務が生じることを忘れないでください。
特定継続的役務提供事業者とは
前述の通り、特定継続的役務提供とは長期間にわたり高額なサービス提供を約束する取引です。この類型に該当する事業者は、エステや語学教室等を運営している場合が典型です。
具体的には「サービス提供期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約」を扱う事業者が対象となります。例えば、個人でヨガ教室の○ヶ月コース契約を販売しているケースや、プライベート英会話レッスンを数十万円のパッケージで提供しているケースなどが該当します。
個人事業主であっても、こうした長期・高額サービスを提供する契約を結ぶ場合は特定継続的役務提供事業者として特商法の規制に従う必要があります。
訪問販売事業者とは
訪問販売事業者とは、消費者の自宅やオフィス、公道など、店舗以外の場所で対面勧誘を行い契約を締結する販売者を指します。たとえば個人で浄水器を持って住宅地を回り直接販売する場合や、アポイントを取ってオフィスに出向きコピー機リースの契約を取るようなケースも訪問販売に含まれます。
「自分は小さな事業者だから飛び込み営業の法律なんて関係ない」と思いがちですが、規模に関係なく訪問販売の形態を取る以上は特商法の対象です。なお、展示会やイベント会場での一時的な販売でも、状況によっては訪問販売と見なされる場合があります。
念のためチェックしておきましょう。また、街頭で声をかけ喫茶店等に同行して契約させるキャッチセールスや、電話等で事前に約束を取り付けて訪問するアポイントメントセールスも訪問販売の一種として規制されます。
自社が該当するか確認する方法
自分のビジネスが特商法上のどの類型に該当するか判断に迷う場合は、経済産業省や消費者庁が提供するガイドラインやQ&Aを参照すると良いでしょう。
例えば、消費者庁が公開する「特定商取引法ガイド」には、各取引類型の詳細やQ&Aが掲載されていますので、一度目を通しておくとよいでしょう。経済産業省のホームページにも、中小事業者向けの特商法解説資料やパンフレットが公開されていますので活用しましょう。
また、当事務所を含め行政書士など専門家に相談すれば、自社が特定継続的役務提供事業者や訪問販売事業者に当たるかどうかを的確にアドバイスしてもらえます。まずは自社の営業形態と契約内容を整理し、法律上の位置づけを明確にすることが、適切な対応の第一歩です。
個人事業の内容に応じて交付すべき書面が異なる

このトピックでは、特商法で義務付けられる書面交付について、事業類型ごとの違いを説明します。特定継続的役務提供と訪問販売では、消費者に交付する書面のタイミングや種類が異なります。それぞれのケースで何をいつ渡す必要があるのかを理解し、漏れのないように備えましょう。
自社の取引形態に応じ、必要な書面を適切に交付することを徹底しましょう。
特定継続的役務提供:概要書面と契約書面
エステやスクール事業など特定継続的役務提供に該当する契約では、契約前と契約後の二段階で書面交付義務があります。
まず契約締結前に、その契約の概要を記載した「概要書面」をお客様(消費者)に渡さなければなりません。概要書面には、事業者の名称・住所・電話番号、サービス内容、料金や支払方法、提供期間、クーリング・オフや中途解約に関する事項など、契約の重要事項が記載されます。お客様が契約内容を十分理解した上で判断できるよう、事前に書面で情報提供するのが目的です。
そして契約締結後は、遅滞なく契約内容を明示した「契約書面」を交付します。契約書面には最終的な契約条件がすべて明記され、概要書面に記載した事項に加えて、契約を担当したスタッフの氏名や契約日なども含まれます。
契約書面は言わば正式な契約書の控えであり、消費者が後から内容を確認できるようにするためのものです。概要書面・契約書面ともに、クーリング・オフの方法や期間を赤枠で囲み赤字で明記する、文字サイズは8ポイント以上にする、といった細かなルールも定められています。
さらに、特定継続的役務提供では契約期間中であっても消費者は契約を途中で解除(中途解約)することが可能であり、その際事業者が請求できる違約金や損害賠償には上限が定められています。例えばエステや語学教室の場合、未提供サービスの代金残額の20%か5万円のいずれか低い額を上限として解約手数料を設定する決まりになっています。
訪問販売:申込書面と契約書面
訪問販売では契約プロセス上、申込み時と契約成立時の二回に分けて書面交付義務が課されます。まず、消費者が商品購入やサービス契約の申込みをした際には、その場で直ちに「申込書面」を交付しなければなりません。
申込書面には、申込内容を具体的に示すため、商品やサービスの名称、数量、金額、申込日などを記載し、消費者に控えとして渡します。こうすることで「申し込んだ内容の控えが手元に残らない」「口頭の約束と違う契約を結ばれてしまった」といった誤解やトラブルを防ぐ効果があります。
次に、契約が正式に成立した後は、やはり遅滞なく「契約書面」を交付します。訪問販売における契約書面も、最終契約内容の明示と双方の合意事項の確認が目的です。記載項目は特定継続的役務提供の場合と似ていますが、訪問販売特有の項目として商品の引渡し時期や瑕疵担保責任(初期不良等に対する販売者の責任)に関する定めなども含まれます。
なお、申込みと契約を同時に行う(申込書にサインして即契約成立する)場合には、契約書面のみ交付すれば申込書面は省略可能です。ただし、その場合でも契約書面は申込時点で直ちに渡すことが望ましいでしょう。
書面に記載すべき主な事項
概要書面・申込書面・契約書面と名称は違いますが、いずれの書面にも基本的に以下のような重要事項を記載する必要があります。
- 事業者情報:屋号・氏名(法人名)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名(個人事業主の場合でも、屋号だけでなく自身の氏名や住所を記載しなければなりません(自宅住所を書くことに抵抗があっても、省略は認められません)。)
- 商品・役務内容:提供する商品やサービスの具体的な内容や品質、型番など
- 価格や支払条件:商品価格やサービス料、契約総額、代金の支払時期・方法(分割払いの場合はその旨)
- 提供時期や期間:商品の引渡予定日、サービス提供期間や契約期間
- クーリング・オフ等:契約の解除・撤回ができる権利(クーリング・オフ)の有無や行使方法、期間
- 中途解約:長期契約の場合の途中解約や返金のルール
- 特約事項:その他特別な合意事項があればその内容
これらの情報はすべて消費者が契約を判断する上で欠かせない要素です。書面交付義務は単なる形式ではなく、消費者に契約内容を正しく伝えトラブルを防ぐための法律上の仕組みだと理解しましょう。
なお、2022年の法改正により、消費者の承諾を条件に契約書面等を紙ではなく電子データ(電子メール送付やウェブ上での提示など)で交付することも可能になりました。ただし、電子交付を行う場合は事前に所定の手続きを踏み承諾を得る必要があります。
知らずに特商法違反?個人事業主に多い落とし穴

このトピックでは、特商法の知識不足から起こりがちなミスや、それによる影響について説明します。
個人事業主の場合、「法律の存在自体を知らなかった」「必要な書面を用意せずに契約してしまった」というケースが珍しくありません。
実際、消費者庁や国民生活センターには「契約書類を渡されていない」「口頭の説明と契約内容が違う」といった相談が寄せられており、その背景には事業者側の知識不足があると指摘されています。
しかし、無知であっても違反は違反です。ここでは、ありがちな落とし穴とそのリスクを見ていきます。知識を身につけ、違反を未然に防ぎましょう。
書面交付忘れ・不備は頻発している
特商法の書面交付義務は細かい規定が多いため、十分な知識がないまま事業を始めた場合に見落としがちです。例えば、個人でエステサロンを開業した人が契約時に口頭説明だけで契約書類を交付していなかったり、訪問販売を副業で始めた人が申込控えを渡さず契約してしまったりといったケースが見受けられます。
また、書面自体は渡していても記載すべき事項が欠けている(クーリング・オフの方法を書いていない、事業者の連絡先を明示していない等)場合も、法律上は「書面を交付していない」ものと扱われます。
忙しさや手間を理由に法定書面を省略・簡略化してしまうことは、後々大きなトラブルを招く原因となり得るのです。実際に、特商法をよく知らないままエステサロンやスクールビジネスを始め、後から消費生活センターへの相談等で自らの違反に気付く個人事業主も見受けられます。
書面を渡さないとクーリング・オフ期間が延長
特商法違反が消費者との契約に直接影響する具体例として、クーリング・オフ期間の延長が挙げられます。本来、訪問販売や特定継続的役務提供の契約では、契約書面を受け取った日を含め8日間は無条件解除(クーリング・オフ)が可能です。
しかし、事業者が適切な契約書面を交付しなかった場合、この8日間のカウントが始まらず、消費者はいつまでも契約解除できる状態が続いてしまいます。つまり、書面を交付していない限り、1ヶ月後でも1年後でも「契約をやめたい」と言われるリスクが残るのです。
さらに、契約書面にクーリング・オフに関する記載漏れがあるような場合でも同様に期間が延長されます。事業者にとって、売上が確定しない不安定な状況が続くことになりかねません。例えば、あるエステサロンでは契約書にクーリング・オフの記載を欠いたため、利用者から契約日から半年以上経過した後に契約解除を求められ、支払済み代金の全額返金に応じざるを得なくなったケースもあります。
営業停止や罰則の可能性も
特商法の規定に違反すると、消費者との契約リスクだけでなく行政上・刑事上の制裁を受ける可能性もあります。消費者からの苦情や通報があれば、監督官庁である消費者庁や都道府県は調査を行い、悪質な場合には業務停止命令などの行政処分が下されることがあります。
また、特に悪質な違反(意図的に書面を交付しない、虚偽の説明で勧誘した等)については、特商法第71条に基づき罰金刑等の刑事罰が科されるケースも想定されます。
なお、書面交付義務違反をはじめ特商法違反には刑事罰の規定もあり、例えば書面を一切交付しなかった場合には6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります(特商法第71条)。
特商法を遵守して安全・安心な経営を
特商法をしっかり守って事業を継続するために、個人事業主が取るべき対策を説明します。現在すでに営業している方も、今一度自社の契約実務を見直し、法令違反がないかチェックしましょう。法令遵守は事業の信頼基盤です。万が一未対応の義務があれば、早急に改善することが求められます。
契約書類の整備と見直し
まず取り組みたいのは、自社で使用している契約関連書類の点検です。特商法に基づく概要書面・申込書面・契約書面を交付すべき事業者である場合、法定の記載事項が漏れなく盛り込まれているか確認しましょう。
テンプレートをネットで入手して使っている場合は、その内容が古かったり不十分な可能性があります。例えば、クーリング・オフの説明文言が最新の法改正に対応していなかったり、自社の取引形態に合わせた特約の記載が抜けていたりすることもあります。
定期的に書面の内容をアップデートし、法律の要求水準に合致しているかをチェックすることが重要です。もし既に法定書面を交付せずに契約を結んでしまっているお客様がいる場合には、後からでも正しい書面を交付して説明することが望まれます。
それによりクーリング・オフ期間が新たに起算されますが、解除権が無期限に存続するリスクを放置するよりは得策でしょう。
社内ルール・教育の徹底
特商法の遵守は書類さえ整えば終わりではありません。実際に消費者対応を行う現場でも、法律に沿った行動を徹底する必要があります。個人事業主とはいえ、スタッフを雇っている場合や代理で営業活動をする人がいる場合には、社内ルールや研修を通じてコンプライアンス教育を行いましょう。
具体的には、訪問販売であれば「勧誘開始前に氏名と目的を告げる」「申込書面を必ず手渡す」といった手順をマニュアル化し、新人にも周知徹底します。法定書面の交付漏れがないよう、チェックリストを用いるのも効果的です。
なお、スタッフを雇わず1人で営業している場合でも、法定手続きを怠らないようチェックリストを作成したり、契約時の段取りをあらかじめ決めておくことは有効です。
あわせて、虚偽の説明や威圧的な勧誘をしないこと(不実告知・威迫行為の禁止)など、特商法で禁じられている行為についても周知徹底しましょう。組織として継続的に取り組むことで、うっかりミスによる違反を防ぐことができます。
専門家の力を借りて安心対応
特商法は改正が定期的に行われており、直近では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者に求められる対応も変化しています。
最新の法律動向を把握し、自社の書類や手続きに反映させるのは容易ではありません。こうしたとき、行政書士などの専門家に相談することは有効な手段です。
行政書士は特商法の書面作成や届出手続にも精通しており、事業者が常に適法な状態で営業できるようサポートしてくれます。例えば、行政書士であれば、法定記載事項を網羅した契約書類の作成代行や、特定商取引法に関する各種届出手続きのサポートなどを通じて事業者を支援できます。
自力では見落としがちなポイントもプロの目でチェックでき、安心して本業に集中できるでしょう。「法令遵守に不安がある」という方は、一度専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
まとめ:個人事業主が特商法で注意すべき5つのポイント
- 個人事業主も特商法の対象-ビジネス規模に関係なく遵守義務がある
- 自社の事業類型を確認-特定継続的役務提供や訪問販売に該当するかチェック
- 契約時の書面交付-事業内容に応じて概要書面/申込書面と契約書面を忘れず交付
- 法定書面の不備に注意-書面交付漏れはクーリング・オフ延長や罰則のリスク
- コンプライアンス徹底-書類整備や教育・専門家活用で特商法を遵守
なお、本記事では個人事業主に特に関係が深い訪問販売と特定継続的役務提供に絞って解説しましたが、特商法には他にも通信販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)など複数の取引類型があります(通信販売にはクーリング・オフ規定がありません)。
それぞれ事業者に課されるルールが異なるため、自社の営業形態に合わせて確認しておくことも重要です。
法を遵守することは、トラブルを未然に防ぎ、顧客からの信頼を得るためにも不可欠です。適切な知識と準備で、安心・安全な事業運営を心がけましょう。
個人事業主の特商法書面作成はお任せください

特定商取引法の遵守は、「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。
法律を守っているつもりでも、書面の記載漏れ・旧様式の使用・誤った説明など、個人事業主の方が見落としやすいポイントは非常に多くあります。
当事務所では、特定継続的役務提供・訪問販売など、事業内容に応じた特商法書面の作成サポートを専門業務として扱っております。とくに次のようなお悩みをお持ちの方に最適です
- 自分の事業が特商法の対象になるのか判断できない
- 概要書面・申込書面・契約書面の違いが分からない
- ネットのテンプレートを使っているが正しいか不安
- クーリング・オフや中途解約の記載方法が分からない
- 法改正(電子交付など)に沿った最新の書面を整えたい
- 書面の整備をしたいけれど、何から手をつければいいか分からない
そんな方こそ、専門家に任せていただくことで負担が大幅に軽減されます。特商法に基づく書面作成は、当行政書士が得意とする分野の一つです。
特商法対応でお悩みの個人事業主の皆様は、どうぞお気軽にご相談ください。事業の安心・信頼を守るために、全力でサポートいたします。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく概要書面(申込書面)および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面(申込書面)や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際の業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
|
⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成
⑵契約手順の説明書
|
55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
|
⑶電子交付対応
|
22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
|
⑷延長相談
|
22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面(申込書面)および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

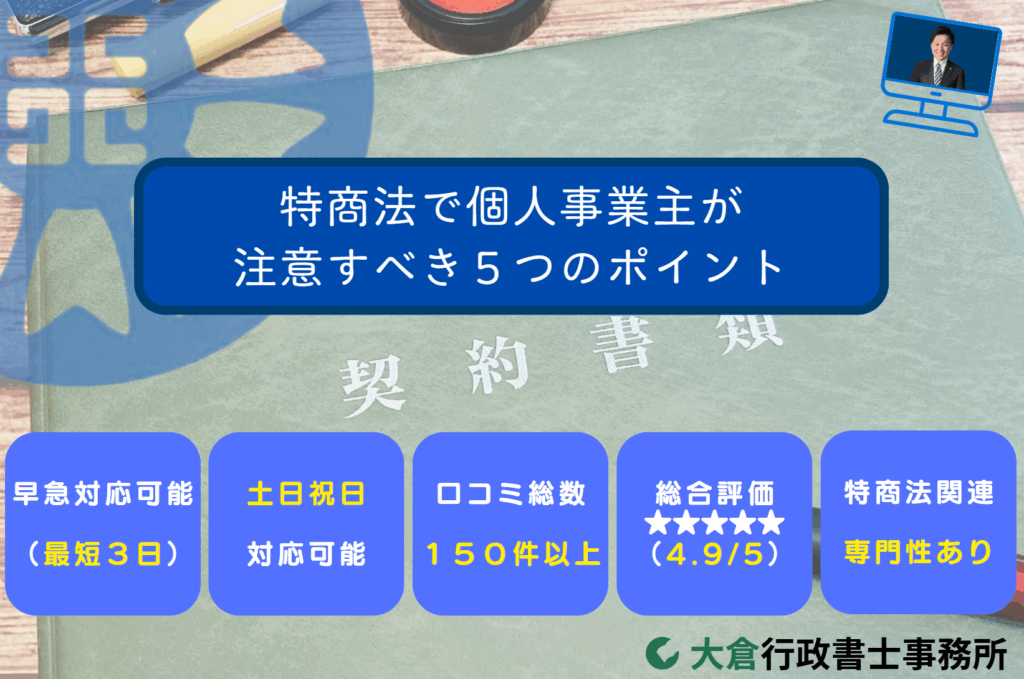
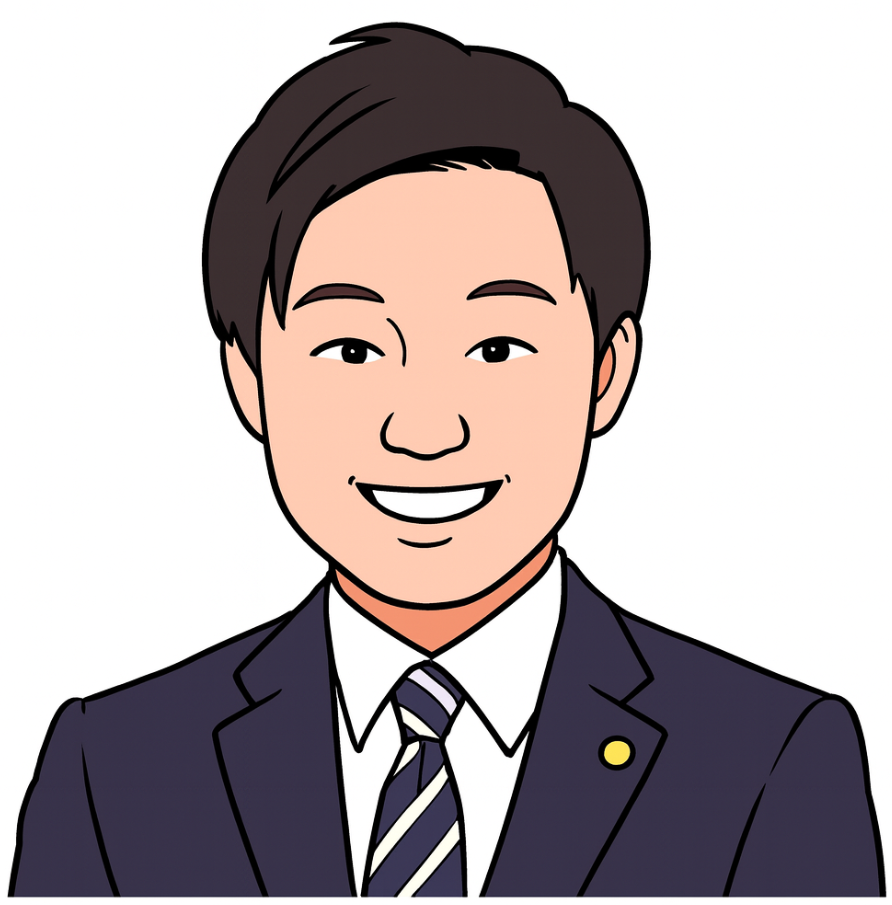
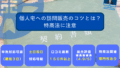
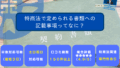
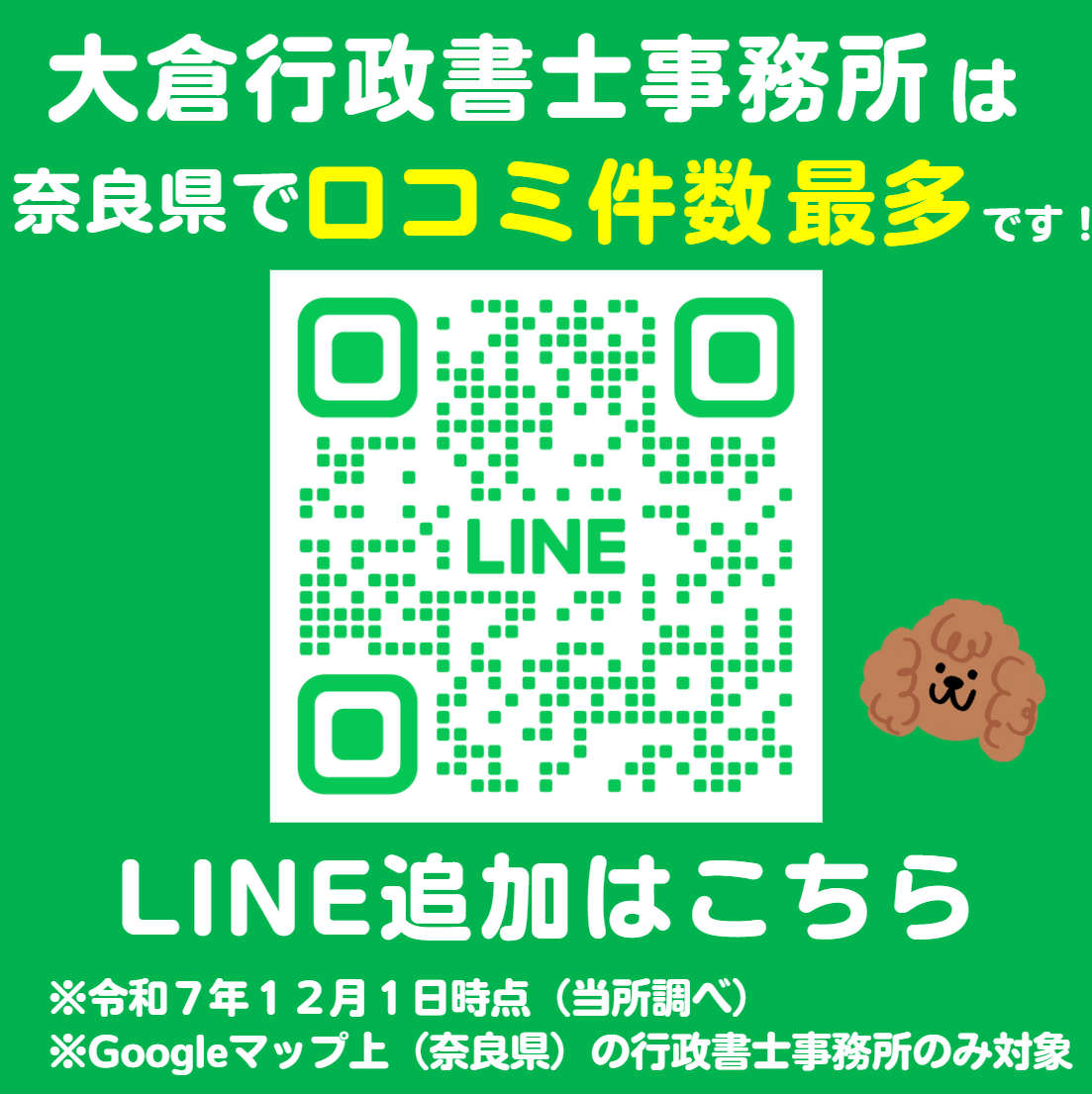
コメント