連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法やネットワークビジネス)に該当するビジネスを新たに開始する際には、特に注意が必要です。例えば、情報商材(ノウハウ教材など)の販売に会員紹介を組み合わせた副業モデルや、健康食品・化粧品の会員販売ビジネスなどは連鎖販売取引の典型例です。
特定商取引法では、この連鎖販売取引において契約前に概要書面、契約締結後に契約書面を消費者に交付することが義務付けられています。これらの書面を適切に交付しなければ、加入者からクーリングオフ(無条件解約)されるリスクが生じるほか、行政処分や罰則の対象にもなり得ます。
また、令和3年改正により、これらの書面は消費者の承諾を条件に電子交付することも可能になりました。本記事では、行政書士の立場から、特商法が規制する連鎖販売取引の概要と必要書面の内容、電子交付のポイント、そして書類作成を行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
連鎖販売取引とは?その要件と対象事例

このトピックでは、特定商取引法上の連鎖販売取引の定義や要件、および対象となる典型的なビジネス例について解説します。連鎖販売取引とは、一言でいえば商品やサービスの販売組織をピラミッド状に拡大していくマルチレベルマーケティング(MLM)のことです(俗にマルチ商法やネットワークビジネスとも呼ばれます)。
法律上は、特定の利益と負担を伴う取引として定義されており、商品等を介した合法的な取引ではありますが、消費者保護の観点から厳しい規制が適用されています。このトピックでは、その法的定義と要件を整理し、どのようなビジネスが該当するのか事例を交えて説明します。
連鎖販売取引の定義と仕組み
連鎖販売取引は特定商取引法第33条で規定されており、簡単に言えば「参加者が他者を次々と勧誘し、商品やサービスの販売組織を連鎖的に拡大する取引」を指します。その成立要件は法律上、以下のように整理できます
- 商品や役務の販売を業とすること(権利の販売やサービス提供も含む)
- 参加者が他の者に商品の再販売や販売のあっせん等を行う仕組みであること
- 勧誘の際に「他人を紹介すれば報酬が得られる」といった特定利益によって誘引していること
- 取引条件として入会金や商品購入など1円以上の特定負担を参加者に課していること
これらの条件を満たす場合、そのビジネスは連鎖販売取引に該当します。例えば「この会に入会すれば商品を割引価格で買えて転売で儲かる」「友人を勧誘すれば紹介料がもらえる」などと勧誘し、契約時に登録料や商品代金を支払わせるような仕組みは典型的です。
連鎖販売取引自体は法律で直ちに禁止されているものではありませんが、組織が拡大するにつれ末端会員が利益を得にくくなることや、高額な初期費用を支払わせるケースが多いため、特商法で厳しく規制されています。
なお、商品を介さずお金の出資だけで会員を増やすねずみ講(無限連鎖講)は別の法律で全面的に禁止されており、違反すれば刑事罰の対象となります。マルチ商法(連鎖販売取引)は商品・サービスの提供を伴うため合法ではありますが、違法な勧誘方法や書面交付義務違反があれば行政処分や契約解除のリスクが生じる点に注意が必要です。
| 特定商取引法第33条(定義) この章並びに第五十八条の二十一第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。 |
情報商材販売を含む典型的な例
連鎖販売取引で扱われる商品・サービスの種類は様々ですが、化粧品や健康食品は古くから典型例として知られています。例えば「毎月1万円の健康食品を購入し、さらに購入者を紹介すれば一人につき月5千円の報酬が得られる」というような副業案件は、まさに連鎖販売取引に該当する契約形態です。
このような商品販売と会員紹介を組み合わせたビジネスでは、紹介者が増えなければ十分な収益を得られない構造であり、実際には上位の一部会員しか利益を得られないため被害が生じやすいと指摘されています。
近年では手口が巧妙化し、「ネットワークビジネス」「コミュニティビジネス」などと称して一見マルチ商法と分からないように勧誘したり、SNSやオンライン広告を通じて人と直接会わずに誘うケースも増えています。
情報商材(オンラインサロンや投資ノウハウ教材など)を高額で販売し、会員を紹介するとキックバックが入るといったインターネット起業系のマルチ商法も登場しており、デジタルコンテンツであっても前述の要件に当てはまる勧誘スキームであれば特商法の規制対象となる点に注意しましょう。
個人事業主にも適用される理由
連鎖販売取引に関する規制は、取引相手が個人事業主であっても適用されます。特定商取引法では保護対象を「消費者」に限らず「無店舗で商品販売等を行う個人」(つまり店舗を持たない個人事業主)まで含めており、会員を「代理店」「フランチャイズ加盟店」などと呼び契約形式を取り繕っても、実態が連鎖販売取引に該当すれば特商法の規制から逃れることはできません。
例えば、自社の商品販売を外部の個人事業主に委託する代理店契約を結んでいた場合でも、その契約内容が前述のマルチ商法の特徴を備えていれば連鎖販売取引とみなされ、相手方(代理店)は契約後にクーリングオフによる解除を行える可能性があります。
実際に、名目上は「代理店契約」でも実態がマルチまがいであれば特商法違反を指摘され行政処分に至るケースも起こり得ます。取引相手が個人事業主であっても、事業者として特商法上の義務(後述する書面交付や禁止行為の遵守など)を確実に履行する必要がある点に注意しましょう。
連鎖販売取引で事業者に課せられる義務

連鎖販売取引を行う事業者には、勧誘方法の禁止行為や広告表示義務など様々なルールが課されています。なかでも重要なのが契約時の書面交付義務です。このトピックでは、契約前に交付すべき概要書面と契約後に交付すべき契約書面に記載すべき事項、および書面交付を怠った場合のクーリングオフや行政処分のリスクに焦点を当てます。
概要書面に記載すべき事項
概要書面とは、連鎖販売取引の契約を締結する前に事業者が相手方に交付しなければならない書類で、当該連鎖販売業の概要を記載したものです。法律で定められた概要書面の記載事項は多岐にわたりますが、主なものを挙げると以下のとおりです。
- 事業者(統括者)の氏名(名称)・住所・電話番号(法人の場合は代表者名を含む)
- 勧誘者や販売者が統括者でない場合はその販売者の氏名・住所・電話番号(法人なら代表者名)
- 商品(役務)の種類・性能・品質などに関する重要事項(権利やサービス内容を含む)
- 商品名および販売価格、引渡時期・方法その他販売条件に関する重要事項
- 特定利益に関する事項(紹介料やボーナスなど報酬の内容)
- 特定負担の内容(入会金、保証金、商品代金、研修費用等、契約時に参加者が負う金銭負担)
- 契約の解除条件その他契約に関する重要事項(クーリングオフ等のルールを含む)
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(分割払いの場合)
- 法第34条に規定する禁止行為に関する事項(不実告知や威迫行為など禁止された勧誘手法の注意書き)
概要書面は、契約の締結前に必ず交付しなければなりません。勧誘を行う段階でこの書面を相手に渡し、上記項目について十分に説明することが求められます。記載すべき事項が一つでも欠けていたり誤っていたりすると、法律上「書面を交付した」ことにはならない点に注意が必要です。
契約書面に記載すべき事項
契約書面は、連鎖販売取引の契約成立後に事業者が相手方に交付する書類で、契約内容を明らかにするものです。契約書面には概要書面の記載事項に加え、契約固有の情報を含める必要があります。主な記載事項は次のとおりです。
- 商品(役務)の種類・性能・品質に関する事項(概要書面同様)
- 商品の再販売や販売あっせんの条件に関する事項(会員が商品を再販売する際の条件など)
- 特定負担に関する事項(参加者が負担する費用の具体的内訳)
- 連鎖販売契約の解除に関する事項(中途解約や解約手続きの条件)
- 事業者(統括者)および販売者の氏名・住所・電話番号(法人は代表者名)
- 契約年月日
- 商標・商号その他特定の表示に関する事項(特定のブランド名などがある場合)
- 特定利益に関する事項(報酬プランの詳細)
- 特定負担以外に参加者が負う義務があればその内容
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項(分割払いの場合)
- 禁止行為(法第34条)に関する事項(不当な勧誘行為の禁止に関する注意書き)
契約書面は、契約成立後遅滞なく交付することが義務付けられています。契約日や契約者情報など、その契約に固有の事項を漏れなく記載し、早急に相手に渡さなくてはなりません。概要書面と同様、法定事項の記載漏れがある書面では交付義務を果たしたことにならないため注意しましょう。
書面交付違反とクーリングオフ・罰則
連鎖販売取引では、法律で定められた書面を交付しなければ、相手方は契約後もいつでも契約を解除(クーリングオフ)できる状態になります。クーリングオフ期間(20日間)は、消費者が適正な書面を受領した日から起算されるため、書面を渡していなかったり記載不備があったりすると期間が進行せず、事業者はずっと無条件解約を受けるリスクを負うことになります。
また、書面にクーリングオフに関する事項を記載しなかったために契約を取り消され、場合によっては刑事事件(逮捕)に発展した例も報告されています。書面交付義務はそれだけ重要だということです。書面を交付しない、虚偽の記載をする、交付を拒むといった行為は特商法違反となり、業務改善指示や取引停止命令などの行政処分の対象となります。
悪質な場合は6か月以下の拘禁刑や100万円以下の罰金またはその併科といった刑事罰が科される可能性もあります。(特定商取引法第71条)連鎖販売取引を行う以上、法定書面の整備と適切な交付は事業継続の前提条件といえるでしょう。
特定商取引法改正で可能になった書面の電子交付

このトピックでは、特定商取引法の改正によって実現した書面の電子交付について、その概要と条件、注意点を解説します。連鎖販売取引では2023年の改正によって契約書面等を電子的に提供できるようになりましたが、電子交付を行うには消費者からの承諾取得や細かな手続きを踏む必要があります。
以下で、電子交付解禁の背景と要件、そしてメリットと注意点を見ていきます。
書面の電子交付を可能にした法改正
2021年の法改正により、連鎖販売取引に関する書面のデジタル交付が認められるようになりました。改正法は2023年6月1日に施行され、それまで紙での交付が義務だった契約書面・概要書面などを、消費者が希望すればメール送付やウェブ上での提供といった電磁的手段で交付できるようになりました。
このデジタル化により、事業者にとっては書面管理の手間削減や非対面での契約手続きが円滑になるメリットがあります。一方で、高齢者などデジタル端末の扱いに不慣れな消費者への配慮が課題と指摘されており、改正当初から利便性とリスクの双方が議論されています。
電子交付を行うための条件
もっとも、書面の電子交付を行うには、法律で定められた厳格な手続きを踏む必要があります。まず、消費者から事前に電磁的方法による提供の承諾を得なければなりません。承諾を得る前提として、事業者は書面で交付すべき重要事項(契約内容やクーリングオフ等)をあらかじめ対面等で説明し、さらに消費者が電子交付を受けるのに適した環境にあるか適合性の確認を行う必要があります。
例えば「日常的にパソコンやスマホを使用しているか」「受け取りに使う端末の画面サイズが4.5インチ以上か」といった点を確認します。これらの説明と確認を経て、消費者が電子交付に同意した場合には、その意思を書面等で承諾してもらう必要があります(口頭の同意では無効)。
事業者は消費者から承諾書を回収した後、その写しを交付し、さらに「承諾を得たことを証する書面」(控え書面)を作成して消費者に交付しなければなりません。消費者は一度承諾しても後から撤回することが可能であり、その場合は以降電子交付を行ってはいけません。
電子交付のメリットと注意点
電子交付を活用すれば、郵送の手間や紙コストを削減でき、オンライン完結の手続きを実現できるという利点があります。しかし、電子交付にあたっては消費者への配慮と法令遵守がこれまで以上に重要です。
消費者が電子より紙の方が読みやすいケースも多いため、無理に電子交付を押し付けるべきではありません。また、改正法では電子交付に関し事業者が行ってはならない行為が列挙されています。例えば、電子交付を希望しない消費者に手続きを強行したり、紙交付を選択した人に手数料を課すなどの不利益を与えたりする行為は禁止されています。
承諾を得る際に事実と異なることを告げたり、威圧的な態度で承諾させることも当然ながら許されません。これらに違反すれば特商法違反として行政処分の対象となるため、電子化による効率化ばかりを優先せず、消費者の意向を尊重した対応が求められます。
特定商取引法に精通した行政書士に依頼するメリット
最後に、連鎖販売取引にかかわる書類作成を行政書士に依頼するメリットについて解説します。行政書士は契約書や法定書面の作成を専門とする国家資格者であり、専門分野であれば特商法の最新改正にも精通しています。プロに相談することで、書面の不備によるトラブルを未然に防ぎ、安心してビジネスに取り組むことができます。以下では、行政書士に依頼する具体的な利点を見ていきましょう。
法改正にも対応し書類の不備を防止
行政書士に依頼すれば、特定商取引法や関連法令の最新動向を踏まえた書類作成が可能です。2023年の電子交付解禁のような改正にも迅速に対応でき、法律に沿った体裁・記載事項を確実に満たす書面を用意できます。素人判断で書類を作成すると、記載漏れや様式の不備によって「適法な書面を交付した」とみなされず、契約を一方的に解除されたりトラブルに発展したりするリスクがあります。
特商法関連を扱う行政書士はこうしたリスクを熟知しているため、要件漏れのない適切な概要書面・契約書面を作成し、クーリングオフの告知忘れなど重大なミスを未然に防いでくれます。
クーリングオフ等のトラブル防止とリスク軽減
行政書士に書類作成を依頼する最大のメリットは、トラブル防止にあります。不適切な書面交付は、前述のように消費者からのクーリングオフや行政処分を招きかねません。また、昨今はSNSや動画サイト等で消費者側にも法律知識が広まっており、少しでも不備があれば即座に契約解除や返金要求に発展する恐れがあります。
行政書士は特商法の規制内容を踏まえた書類整備だけでなく、ビジネスモデル自体が適法かどうかのチェックもできます。事前に専門家の目で確認しておくことで、「知らないうちに違法な勧誘をしていた」「書類が原因で信用を損なった」といった事態を避け、安心して事業運営できるでしょう。
本業に専念でき業務効率アップ
さらに、書類作成を行政書士に任せれば業務効率が向上します。煩雑な法令調査や書面作成の作業から解放され、本業である商品の開発・販売や組織運営に専念できるでしょう。特商法関連の書類は一から自作するには専門知識を要し、時間も労力もかかります。プロにアウトソースすることで、時間的コストを削減するとともに、法的に間違いのない書面を用意できる安心感が得られます。
行政書士は「街の法律家」として身近な存在ですので、わからない点があれば気軽に相談し、適切なアドバイスを受けることができます。結果として、法令遵守の徹底と事業の効率化を同時に実現できるのが行政書士に依頼する大きなメリットです。
連鎖販売取引に関する特定商取引法書面の作成はお任せください
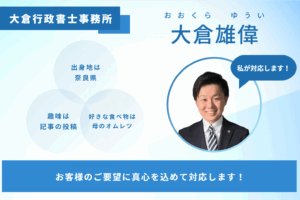
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネス)を開始する際には、特定商取引法に基づく「概要書面」「契約書面」の交付が義務付けられています。これらの書面に不備があれば、クーリングオフや行政処分、罰則のリスクを抱えることになります。
当事務所では、最新の法改正(電子交付対応など)にも対応した適法な書面を作成し、安心して事業を進められるようサポートいたします。特に次のような方はぜひご相談ください。
- 情報商材やオンラインサロンの会員紹介ビジネスを始めたい方
- 健康食品・化粧品などの会員販売モデルを運営予定の方
- 「代理店契約」「フランチャイズ契約」形式での勧誘が連鎖販売取引に当たらないか不安な方
- 概要書面・契約書面を一から作る時間や知識がなく不安な方
- 書類の不備によるクーリングオフや行政処分のリスクを避けたい方
行政書士は「街の法律家」として、事業者様が安心して取り組めるよう、確実な書面整備と法令遵守をサポートします。
当事務所に依頼する3つのメリット
法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる
特定商取引法に基づく「概要書面」および「契約書面」には、記載が義務付けられた法定項目が細かく定められており、不備があれば契約無効や行政処分のリスクが発生します。当事務所にご依頼いただければ、複雑な要件をすべて満たした適法な書類を作成でき、安心して事業運営が可能となります。
実務に沿った運用指導が受けられる
概要書面や契約書面は単に作成すればよいのではなく、どの段階で交付し、どのように説明するかが重要です。当事務所では、連鎖販売取引のビジネスモデルに合わせ、勧誘時の説明内容や契約締結の流れを具体的にご案内いたします。これにより、違反リスクの少ない運営を実現できます。
最新の法改正や実務動向に対応できる
特定商取引法は定期的に改正が行われ、近年では概要書面・契約書面の電子交付が認められるなど、事業者に求められる対応も変化しています。当事務所では法改正や最新の実務動向に基づいた書類整備と運用支援を行い、常に適法な状態を維持できるようサポートいたします。
料金表
当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。
| 内容 | 料金 | 詳細 |
| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |
77,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |
| 選択プラン | ||
| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |
※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。
手続きの流れ
当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談
まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。
お見積りのご提示
ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。
契約締結
当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。
追加質問のお伺い
書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。
書類の作成
お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。
書類の納品
完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。
以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
【関連記事】
>特定商取引法ガイド
>消費者庁

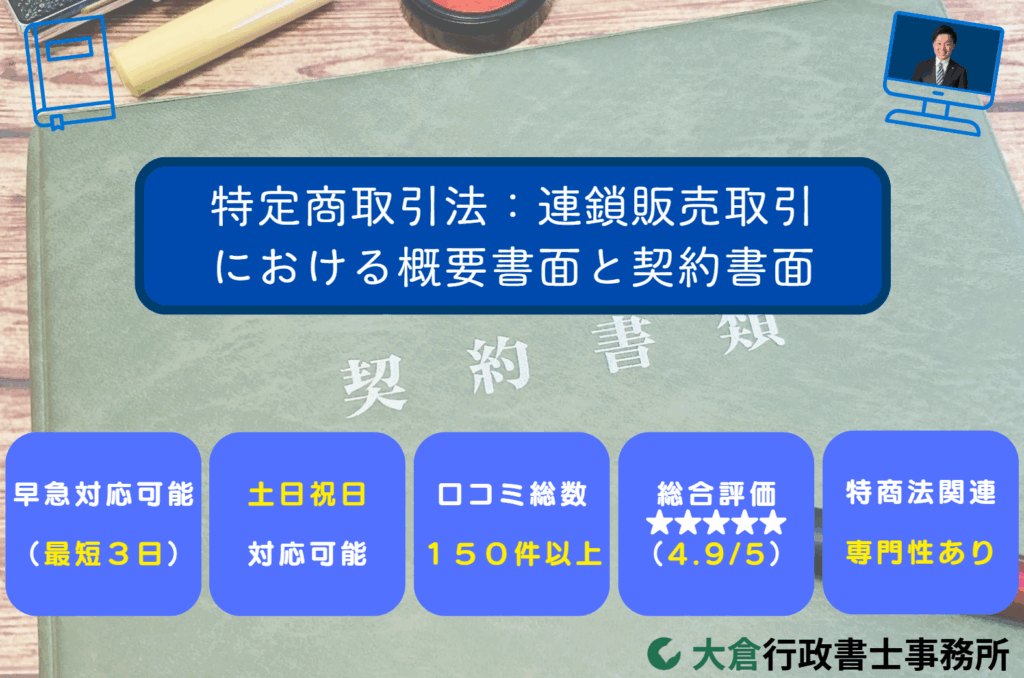
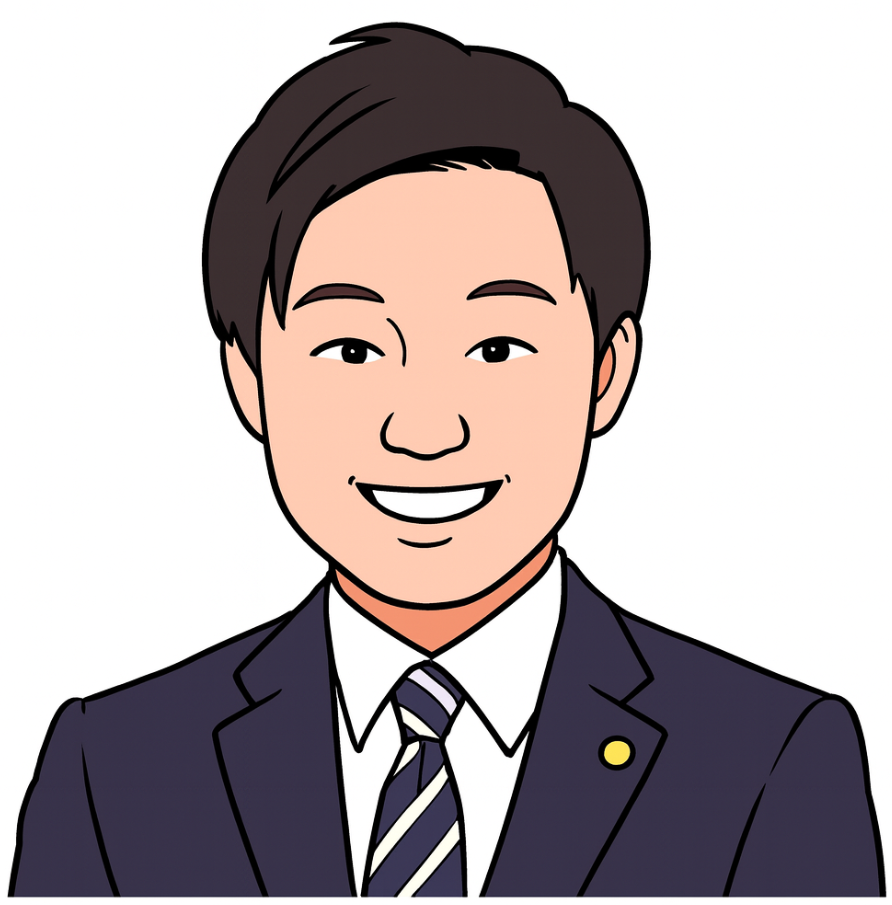
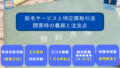
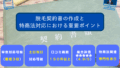
コメント