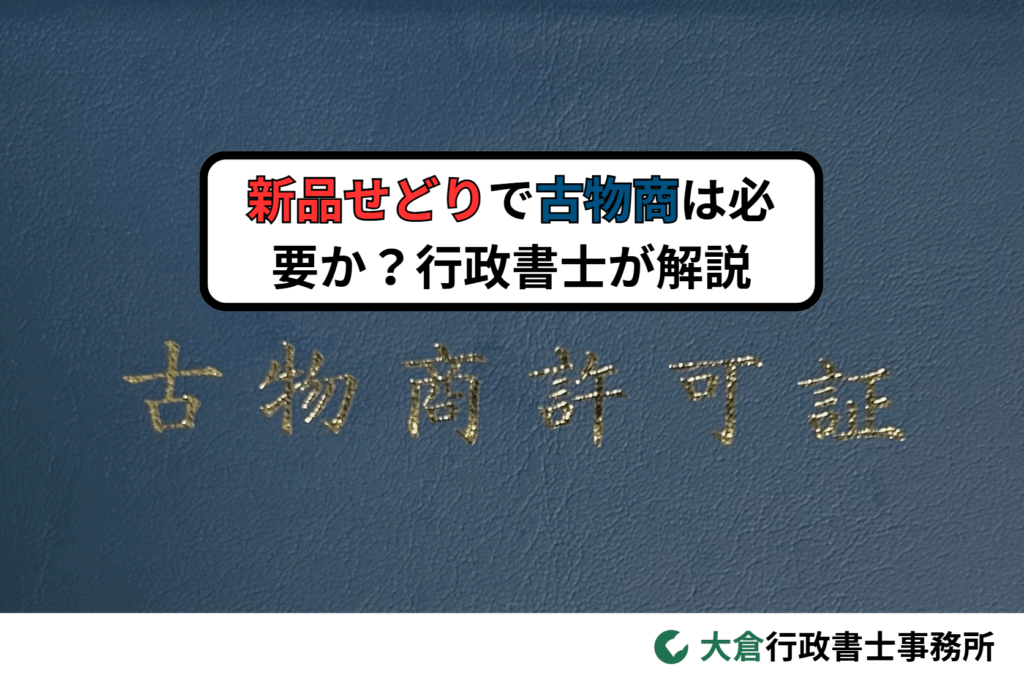新品せどりを始める際に古物商は必要かどうか、悩む方は少なくありません。副業として人気の「せどり」ですが、たとえ商品が新品であっても法律上は「古物」にあたる場合があるためです。
近年、副業解禁やネット通販の普及により、誰でも手軽に始められるビジネスとしてせどりが注目されています。しかし、関連する法規制を正しく理解せずに始めると、思わぬ違法行為につながる可能性もあります。
この記事では、新品せどりと古物商許可の関係や、その必要性・取得方法を行政書士がわかりやすく解説します。筆者(行政書士)も実際に古物商許可申請のサポートを数多く手掛けてきました。その経験から、許可取得のメリットや手続きの注意点についても触れていきます。
せどりとは何か、副業としての現状と定義

まず、せどりというビジネスの基本的な意味と現状について確認しましょう。もともと「せどり」は古本の転売から始まったと言われますが、現在では新品・中古を問わず様々な商品を扱う副業モデルとして定着しています。ここでは、せどりの定義や種類、そして主な販売チャネルと収益モデルを解説します。
せどりの語源と基本的な意味
「せどり」という言葉は、元々は古本の転売を指す業界用語に由来するとされています。古書店で本の背表紙(背)を見て価値を判断し、安く仕入れて高く売る行為を指したのが語源とされ、もとは書籍の世界の言葉でした。
その後、同様の手法が古本以外の分野にも広がり、安く仕入れて高く売る転売ビジネス全般を指す言葉として定着しました。現在では、単に安く仕入れて高く売るビジネス一般を「せどり」と呼び、インターネットを活用した副業モデルとして広く浸透しています。
【関連記事】
古物商で本の売買を始めたいなら古物商許可が必要です
新品せどりと中古せどりの違い
せどりには大きく分けて「新品せどり」と「中古せどり」の2種類があります。新品せどりは新品・未使用の商品を仕入れて販売するもので、家電やおもちゃ、限定品など店頭のセール品や在庫処分品を安く買い付け、オンラインで定価に近い価格で売るのが典型的な手法です。
一方、中古せどりは中古品を仕入れて販売する形態で、古本や中古ゲーム、古着などリサイクルショップやフリマアプリで安く仕入れ、必要に応じて清掃や動作確認をしてから再販売します。新品せどりは商品の状態にばらつきが少なく売りやすい反面、仕入れにある程度の資金が必要です。中古せどりは少ない資金でも始められますが、商品の状態チェックやクリーニングなどに手間がかかります。
せどりの主な販売チャネルと収益モデル
せどりで扱った商品は主にインターネット上のマーケットプレイスで販売されます。代表的な販売チャネルとして、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大型オンラインモールへの出品が挙げられます。
特にAmazonではFBA(FulfillmentbyAmazon)などのサービスを利用することで、小規模な個人でも在庫保管や発送を代行してもらい、全国の顧客に商品を届けやすい環境が整っています。また、メルカリやラクマなどのフリマアプリ、Yahoo!オークションなどのCtoCサイトも主要な販路です。これらは手軽に出品できますが、価格競争が起きやすく購入者対応の手間も発生します。このようなチャネルで安く仕入れた商品を販売し、その差額が利益(収益)となるのがせどりの基本的な収益モデルです。販売価格から仕入れ値と送料・販売手数料を差し引いた残額が利益になります。利益を伸ばすには、利益率の高い商品を見極めたり、販売数を増やしたりする工夫が求められます。市場価格の変動を注視し、タイミングよく売買することも大切です。
【関連記事】
eBayを個人事業主で始めるための準備
古物商許可とヤフオクの使用URLについて
メルカリで古物商を始める方法は?
新品せどりに古物商許可が必要なケース
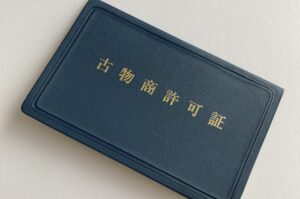
新品商品ばかり扱うから古物商許可は不要だろう、と考えている方もいるかもしれません。しかし、法律上は「新品」であっても状況によっては古物商許可が求められるケースがあります。ここでは、どのような場合に新品せどりでも古物商許可が必要になるのか、その基準と誤解されやすいポイントを解説します。
「新品」が古物とみなされる場面とは
古物営業法において「古物」とは、一度でも使用された物品、または未使用であっても一度取引された物品などを指します。つまり、たとえ新品同様に見える商品であっても、一度誰かの手に渡った時点で法律上は中古品(古物)とみなされるのです。例えば、個人から買い取った未使用品や、フリマアプリで手に入れた新品同様の商品は、外見上は新品でも法的には古物に該当します。
一方で、メーカーや正規代理店から直接仕入れた新品商品は、一度も消費者の手に渡っていないため古物には含まれません。このように、商品の流通経路によって新品であっても古物と扱われる場合があることに注意が必要です。
法的に許可が求められる基準と誤解の多いパターン
新品せどりで古物商許可が必要となるかは、そのビジネスが古物営業に該当するかどうかで判断されます。古物営業とは、平たく言えば「中古品を仕入れて売る営業行為」のことです。多くの方は「新品を買って売るだけなら中古品ではないから許可不要だろう」と考えがちですが、前述のとおり仕入れ先によっては新品でも法律上中古品となり得ます。
具体的には、一般の消費者や中古市場から仕入れた商品を転売する場合は古物営業と見なされ古物商許可が必要です。逆に、正規の小売店で購入した新品をそのまま転売する場合は仕入段階で古物を扱っていないため許可不要と解釈されます。なお、少しでも中古品を扱う可能性があるなら、あらかじめ許可を取得しておく方が安全です。許可が必要な状況にもかかわらず無許可で営業を続ければ、後述するように大きなリスクを伴います。
無許可営業によるリスクと罰則
古物商許可が必要な状況で無許可のまま営業を続けると、明確な法律違反となり深刻なリスクを伴います。古物営業法では無許可営業に対し3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則規定が設けられています。
実際に無許可で大量転売を行っていた業者が摘発された例もあり、違法な状態でビジネスを続けることは極めて危険です。また、プラットフォームの監視により無許可販売が発覚すれば、アカウント停止などの措置を取られる可能性も高いでしょう。信用面でも違反が明らかになれば顧客や取引先からの信頼を失います。せどりを安全に続けるためにも、古物商許可が必要な場合は必ず取得してから営業しましょう。
なぜ新品せどりで古物商許可を取る人が多いのか

新品だけを扱うつもりでせどりを始める場合でも、古物商許可をあえて取得する人が少なくありません。それは、ビジネスを進める中で許可を持っていた方が有利・安全と考えられる理由がいくつかあるためです。ここでは、新品せどりの方が古物商許可を取得する主な理由を見ていきましょう。
中古品との混在や仕入れ先の事情
当初は新品商品のみを扱う予定でも、ビジネスを拡大・継続していく中で中古品の取引が発生するケースは珍しくありません。例えば、在庫確保のために個人から未使用品を仕入れたり、リサイクルショップやネットオークションで掘り出し物を入手したりすることがあります。新品せどりと中古せどりが混在すれば、それは古物営業に該当しますが、事前に古物商許可を取得しておけば安心してこうした仕入れチャネルを利用できます。
また、一部の業者専用市場(業者オークション)や卸売市場では、入場や取引に古物商許可が必要となる場合もあります。許可を持っていることで、仕入れ先の選択肢が広がり、ビジネスチャンスを逃さずに済むでしょう。
許可を取得しておくことの信頼性と安全性
古物商許可を所持していること自体が、取引先や顧客に対する信頼の証明になります。許可番号を公表すれば「法令を守って営業している正規の事業者」であることを示せるため、購入者にも安心感を与えられます。
また、許可業者として定められたルール(身分証確認や古物台帳記録等)を遵守することで、盗品をうっかり仕入れてしまうリスクも減り、事業者自身の身を守ることにもつながります。総じて、許可を取得しておくことは事業の信用力向上とリスクヘッジの両面で大きなメリットがあると言えるでしょう。
【関連記事】
転売では古物商許可はいらないの?
ガンプラの転売は違法か?古物商許可があれば大丈夫
ポケモンカードの売買をもっと安心に!
古物商許可を取得してせどりを行う方法

最後に、古物商許可を実際に取得する手続きと、許可取得後に守るべきルールについて解説します。また、行政書士に依頼して申請を進めるメリットについても触れます。許可を適切に取得・活用し、安心してせどりを続けるためのポイントを確認しましょう。
許可取得の流れと申請手続き
古物商許可を取得するためには、所轄警察署での申請手続きを行う必要があります。一般的な申請から許可取得までの流れは次のとおりです。
1.必要書類の準備
申請者(個人または法人)の住民票、身分証明書(法人は登記事項証明書)、許可申請書類一式(略歴書・誓約書など)などを用意します。事前に警察署窓口や行政書士から書類の入手方法・記入方法のアドバイスを受けておくと安心です。
2.警察署への申請
営業所所在地を管轄する警察署の窓口に書類一式を提出し、申請手数料(約19,000円)を納付します。受理後、警察による審査が開始されます。
3.審査と許可証の交付
通常、申請から許可まで約40日程度の審査期間があります。問題なく許可が下りると、警察署から古物商許可証が交付されます。許可証を受領したら、営業所に古物商標識(許可票)を掲示し、正式に古物商として営業を開始できます。
許可後の管理義務と記録のつけ方
古物商許可を取得した後は、許可業者として守るべき法定義務があります。その一つが古物台帳(取引帳簿)の備付けです。取引の都度、日時や相手の氏名・住所、商品カテゴリ(13品目の区分)や品名などを帳簿に記録し、所定期間保存する義務があります。
特に個人から中古品を買い取る際は、運転免許証などで相手の本人確認を行い、その情報も記録します。また、許可証の掲示も必須であり、営業所(自宅を営業所とする場合は自宅)に許可票を見やすく掲げておかなければなりません。さらに、住所や氏名、法人の役員など許可内容に変更が生じた場合や、営業を辞める場合には、速やかに警察署へ変更届や廃業届を提出する必要があります。これらの義務を怠ると罰則の対象となる可能性がありますので注意しましょう。
行政書士による支援と全国対応のメリット
古物商許可の申請手続きは決して極端に難しいものではありませんが、書類に不備があると受理されず許可取得が遅れることがあります。こうしたリスクを避けるため、行政書士に申請を依頼するメリットは大きいでしょう。
行政書士は許可申請の経験と専門知識を有しており、書類の準備から警察署とのやり取りまでを代行します。初めて申請する方や本業が忙しい方でも、プロに任せれば確実かつ迅速に許可を取得できるのは大きな利点です。また、全国対応可能な行政書士も多く、遠方に住んでいる場合でも郵送やオンラインで依頼しサポートを受けられます。許可取得後も帳簿のつけ方や届出義務について助言を受けられるなど、継続的なサポートが得られる点も安心です。
新品せどり開始時の古物商許可申請はお任せください
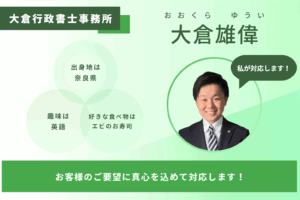
新品せどりを始めるにあたって「古物商許可が本当に必要なのか」「どのように申請すればいいのかわからない」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。当事務所では、これまでに多数の古物商許可申請に携わってきた実績があり、個人事業主の方から副業としてせどりを始めたい初心者の方まで、幅広くサポートを行ってきました。
特に新品せどりにおける古物商許可の必要性については、制度の曖昧さから誤解が生じやすく、法令違反を避けるためにも事前の確認と正確な対応が重要です。当事務所はネット上の口コミでも150件以上の投稿をいただき、総合評価は4.9/5と高い評価を得ております。こうした評価は、丁寧かつ迅速な対応、そして依頼者様の状況に合わせた的確なアドバイスが評価されている証です。特に以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
- 新品せどりを始める予定だが、古物商許可が本当に必要か判断がつかない方
- フリマアプリやネットオークションで仕入れた商品を扱う新品せどりを行いたい方
- 申請書類の書き方や添付資料の準備が煩雑で、自分での対応に不安を感じている方
- 古物商許可を取得した後の記録管理や帳簿作成に不安がある方
- せどりの規模を拡大するにあたり、安心して事業を継続できる体制を整えたい方
- 新品せどりを本業に近づけていくため、法令遵守や信頼性のある取引体制を構築したい方
新品せどりを円滑かつ安心してスタートするためには、法律面の備えが不可欠です。行政書士による支援を活用することで、複雑な手続きを確実に進め、万全の体制でビジネスに取り組んでいただけます。まずはお気軽にご相談ください。全国対応でサポートいたします。

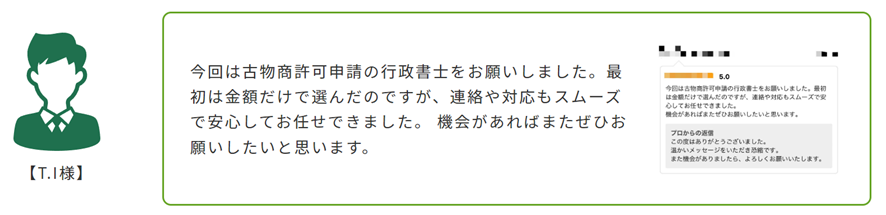

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
新品せどりで古物商は必要か?-よくある質問
Q.新品を転売するだけなのに、なぜ古物商許可が関係するのですか?
A.見た目が未使用であっても、仕入れた経路によっては法律上「一度流通した品物=古物」と判断されることがあります。たとえば個人間で譲り受けた新品やフリマで仕入れた商品は、古物扱いとなり、取引を継続的に行うなら届け出が必要です。
Q.新品せどりでは、すべて古物商の届け出が必要ですか?
A.いいえ。新品せどりでも、仕入れがメーカーや正規代理店などの場合は、古物営業に該当しないため、許可は不要です。ただし、仕入れ先が個人や中古市場であると古物となるため、ケースによって判断が分かれます。
Q.フリマアプリで仕入れた未使用品も古物商の対象ですか?
A.はい。フリマで手に入れた商品が未使用品でも、一度個人の所有物になっていれば「古物」と見なされるため、販売目的なら古物商の許可が必要になります。
Q.新品しか扱わない予定ですが、今後のために許可を取っておいた方がいいですか?
A.将来的に中古品を取り扱う可能性がある、あるいは仕入れ先が広がる予定がある場合には、あらかじめ許可を取得しておくのが安全です。ビジネス展開の柔軟性が高まります。
Q.個人で細々と新品を売るだけでも古物商許可は取るべきですか?
A.規模よりも「継続性と営利目的かどうか」で判断されます。個人であっても反復継続して販売する意思がある場合は、法律上の営業にあたるため、届け出が求められます。
Q.新品せどりを副業として始めるのに、古物商登録をしても問題ありませんか?
A.問題ありません。副業でも本業でも、古物営業法の適用対象であれば、必要な届け出を済ませておくことで合法的に運営できます。副業であっても申請可能です。
Q.古物商の許可証があれば、中古せどりも同時に始められますか?
A.はい。一度古物商許可を取得すれば、新品・中古を問わず、条件を満たす商品を合法的に販売できます。せどりスタイルの幅も広がるため、有効な手段です。
Q.新品せどりで古物商の番号を持っていると、信頼性は上がりますか?
A.はい。許可を得ていることは、法令遵守と健全な運営を示す証となり、購入者や取引先に安心感を与えるポイントになります。
Q.古物商の番号はどこで表示すればよいですか?
A.オンラインで取引を行う場合には、販売ページや出品者情報の欄に許可番号と公安委員会名を記載するのが一般的です。
Q.古物商許可を得た後、どんな管理が必要になりますか?
A.主に「取引帳簿(古物台帳)」の記録、本人確認や標識の掲示などが義務となります。行政書士から指導を受けながら整備する方法もあります。
Q.申請してからどれくらいで許可が下りますか?
A.警察署の審査期間は通常40日程度とされています。地域や書類の状況によって変動しますが、書類が揃っていれば特に問題なく許可が得られます。
Q.自宅でせどりをする場合でも古物商の届け出は可能ですか?
A.はい。自宅を営業所として届け出ることは可能です。必要に応じて、大家や管理会社からの使用承諾書が求められることがあります。
Q.行政書士に依頼した場合の費用はどのくらいですか?
A.地域や内容により異なりますが、目安として申請代行の報酬は4万円〜6万円程度が一般的です。全国対応している事務所も多いため、オンライン完結も可能です。
新品せどりで古物商は必要か?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、新品せどりと古物商許可の関係や、その必要性・取得方法を行政書士がわかりやすく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
第1章:せどりの基礎と種類、流通手段の概要
せどりとは元々古書の転売を指していた言葉で、現在ではネットを活用した仕入れ販売ビジネス全般に用いられます。新品商品を対象とする手法と、中古品を扱う形態に大別され、それぞれにメリットとデメリットがあります。Amazon、フリマアプリ、オークションサイトなどが主要な販売経路となり、差額利益を得ることが基本的な収益構造です。
第2章:新品を扱っていても認可が求められるケース
一見未使用に見える商品でも、取引の履歴があれば中古品と判断され、届出が必要になることがあります。個人や二次流通市場から仕入れた新品風の商品を再販する行為は、法律上の中古品売買に該当する可能性があります。正規店で購入した新品商品の再販売は認可不要ですが、判断基準を誤ると、重大な法令違反とみなされ、刑事罰の対象になることもあるため注意が必要です。
第3章:なぜあえて届出をする人が多いのか
新品せどりに取り組む人の中には、将来的な事業拡大や仕入れルートの多様化に備えて早めに許可を取得するケースが増えています。取引先の幅が広がり、仕入れチャネルの制限がなくなるためです。また、許可を持っていることが顧客や取引プラットフォームに対する信頼性の裏付けにもなります。業者市場での入場資格やモールでの出品条件にも影響することから、事業戦略として取得する動きが見られます。
第4章:許可取得の実務とその後の運用体制
営業の許可を得るためには、居住地を管轄する警察署への書類提出が求められます。申請時には必要な資料を揃え、手数料の納付を行った上で審査を受けることになります。許可が下りた後は、帳簿の作成や身分確認といった管理義務が発生します。行政書士へ依頼すれば、書類作成から提出までの手続きを一括で代行でき、遠方でも対応が可能です。取得後の維持管理においても、専門的な助言が受けられるため、安心して事業を継続できます。
【関連記事】
大阪府警「古物商許可申請」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/ninkyoka/1/1/kobutsu_shinki/3684.html