古物商としての活動を拡大したり、新たな取り組みを始める際には、追加申請が必要となることがあります。追加申請には、営業所の追加、行商の開始、取り扱う古物の区分の追加、そしてホームページの開設など、さまざまなケースがあり、これらの変更を適切に行うためには、事前の準備と正確な手続きが求められます。
こちらの記事では、古物商の追加申請が必要となる具体的なケースやその手続きの流れ、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。これにより、スムーズに手続きを進め、古物商としての活動を確実に拡大するための参考にしていただければ幸いです。
古物商の追加申請が必要となるケース

まず、こちらの記事でいう古物商の追加申請とは、古物商許可申請内容の追加等の変更のことであり、以下では、「追加申請」と表記させていただきます。
追加申請は主に次の内容が多いです。
- 営業所の追加
既存の営業所に加えて新たに別の営業所を開設する場合、追加申請が必要です。 - 行商の実施
店舗以外での行商を行う場合も、「行商しない」から「行商する」へ変更をする必要があります。 - 取り扱う古物の区分の追加
取り扱う古物の種類を増やす場合も、古物商の変更が必要です。これにより、新しく取り扱う品目について売買を行えるようになります。 - ホームページの開設
古物商としてのホームページ等を利用して、古物営業を展開するためには、変更の届出が求められます。
これらの変更に対しては、必要に応じて補正書や変更届を提出し、正確かつ迅速に対応することが求められます。
古物商の追加申請を検討する際の状況
古物商の追加申請を検討する際には、以下の2つのケースが主に考えられます。
申請が受理された後(標準処理期間中)の追加申請
この場合、追加申請は「補正書」によって対応することが求められます。
補正書とは何か?
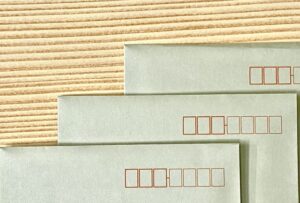
補正書は、既に提出された申請内容に対して、修正や変更を加えるための書類です。申請が受理されてから標準処理期間中に内容の変更や追加が必要となった場合、補正書を提出することで、修正が可能になります。補正書の書式は、各都道府県警察署によって異なる場合がありますが、基本的には自由形式で作成することができます。
警察署のウェブサイトに補正書のフォーマットが掲載されていることもありますが、基本的にはどのような書式でも提出が可能です。
補正書に記載すべき内容
補正書には、以下の内容を明確に記載する必要があります。
- 申請した日付
いつ申請を行ったのかを明記します。 - 申請した内容
どのような内容で申請したのかを具体的に記載します。 - 変更する旨
申請内容にどのような修正や変更が必要であるかを示します。 - 変更部分の詳細
どの部分を変更するのかを明確に表示します。 - 変更後の内容
修正や変更後の新しい申請内容を正確に記載します。
補正書の提出方法
補正書は郵送でも提出することができますが、正確で迅速な対応を確保するためには、できる限り警察署の窓口で直接提出することが推奨されます。例えば、奈良県警の補正書の書式(奈良県警補正書のサンプル)を他の府県で使用する場合には、書類内の「奈良県公安委員会殿」をご自身の管轄の公安委員会に訂正して使用してください。
補正書では対応できない場合
ただし、申請が受理されてから一定期間が経過している場合や、変更内容が大きい場合には、補正書ではなく、新たに許可取得後の対応を求められることもあります。このようなケースでは、標準処理期間内に補正を行う必要がありますが、事前に管轄の警察署に問い合わせを行い、必要な対応を確認しておくと安心です。
これらの手続きは、補正による追加申請を円滑に進めるために重要なポイントとなります。下記では、許可後の変更による手続について述べさせていただきます。
許可が下りた後の追加申請

許可が下りた後に行う追加申請は、補正書では対応できません。この場合、変更内容に応じて「変更届」を提出する必要があります。ここでは、許可後に追加申請が必要となる主なケースと、その手続きの流れや必要書類について詳しく説明します。
営業所を追加したい場合
- 手続きの流れ
新たな営業所を追加する際には、営業所を管轄する警察署に対し、変更の日から3日前までに変更届出書を提出する必要があります。また、営業所の追加に伴い、新たに管理者を選任する場合は、変更の日から14日以内に、計2回の変更届を提出する必要があります。 - 必要書類
(事前に提出する書類)
・変更届出書(別記様式第5号)1通
(事後に提出する書類)
・変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))1通
・変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)
・新たに選任した管理者の住民票(「本籍地」の記載入り)
・管理者の身分証明書
・管理者の略歴書
・誓約書
行商を行いたい場合
- 手続きの流れ
行商の許可に関する変更は、「行商をしない」から「行商をする」へ変更する際に必要です。この場合、変更の日から14日以内に、申請した警察署に変更届出書を提出する必要があります。 - 必要書類
・別記様式第6号その1(ア)
取り扱う古物の区分を増やしたい場合
- 手続きの流れ
取り扱う古物の区分を増やす場合も、変更の日から14日以内に、申請した警察署に変更届出書を提出する必要があります。 - 必要書類
・別記様式第6号その1(ア)
ホームページを開設した場合
- 手続きの流れ
ホームページを開設して古物商活動を行う場合、ホームページの開設日から14日以内に、申請した警察署に変更届出書を提出する必要があります。これは、古物営業に関わる情報の正確な管理と公開が必要なためです。 - 必要書類
・別記様式第6号その1(ア)
・別記様式第6号その3
・URLの使用権限が確認できる資料(参考資料)
これらの変更手続きは、古物商としての活動を適切に行うために重要です。各手続きには、それぞれ特有の要件と書類が求められますので、事前に必要な準備を整え、期限内に正確な手続きを行うことが大切です。また、申請内容や手続きに不明点がある場合は、事前に管轄の警察署に問い合わせることで、手続きが円滑に進むでしょう。
| 【関連記事】 >古物商の住所変更の方法 徹底解説 >古物商とフリーマーケット:出店に必要な手続きについて |
古物商の追加申請をする場合の注意点

古物商の追加申請を行う際には、いくつか重要な注意点を事前に把握しておく必要があります。
これらの注意点を理解し適切に対応することにより、申請手続きがスムーズに進むだけでなく、不必要なトラブルを回避することができるでしょう。
申請前の事前連絡が必要
古物商の追加申請を行う際には、申請前に必ず警察署へ事前連絡を行うことが極めて重要です。これにより、申請手続きが円滑に進むだけでなく、警察署側でも申請をスムーズに処理する準備が整えられます。事前連絡なしで突然訪問してしまうと、他の申請者と重なって待たされることや担当者が不在のことがあるため、必ず事前に連絡をしておくことをお勧めします。
事前連絡は2回に分けて行うこと
追加申請では、警察署への連絡を2回行います。
- 一回目の連絡では、追加申請に必要な書類の確認を行います。これにより、事前にどの書類を用意すれば良いのかを正確に把握することができ、申請時に書類不足や記入ミスを防ぐことができます。
- 二回目の連絡は、実際に補正や変更手続きを行う日や時間の具体的な連絡です。警察署は緊急対応が求められる業務もあるため、急に外出してしまう可能性も考慮し、事前に訪問の予定を伝えておくことで、確実に対応してもらえるようにします。事前連絡を入れることは、円滑な手続きのために非常に重要なステップとなります。
書類の記載は正確に行うこと
古物商の追加申請で提出する書類の記載は、厳密に行う必要があります。警察署が求める書類の記載内容には厳格な基準が設けられており、記入ミスや不備があると、変更が必要であり、手続きが遅れる可能性があります。そのため、記載例をしっかりと確認し、それに基づいて正確に書類を作成することが重要です。
もし、記載例を確認しても疑問点や不明な点が残る場合には、専門家である行政書士に依頼することも検討できます。行政書士に相談することで、書類の作成がよりスムーズに進み、手続きの確実性が高まります。また、記載例に従ってもわかりにくい部分があれば、行政書士のサポートを受けることで、正確な書類作成が可能となり、申請手続きが円滑に進むでしょう。
古物商の追加申請は当事務所にお任せください!
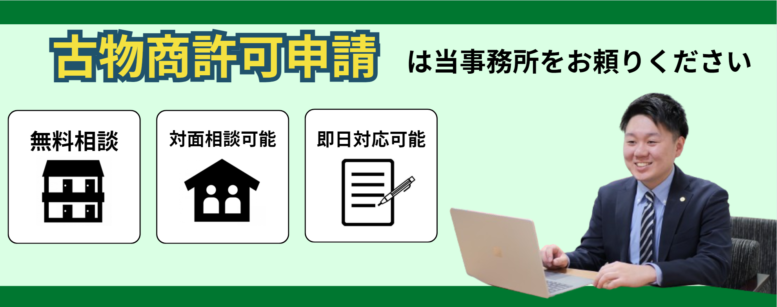
当事務所による代行サービスでは、古物商許可の取得や追加申請に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請において確固たる実績を有しています。私たちのサービスは、お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、手続き全般をお手伝いいたします。
さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

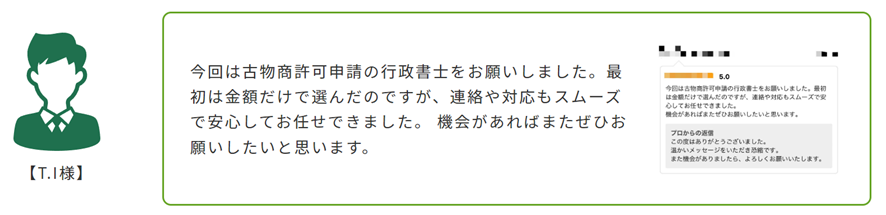

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商の追加申請をされたい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、古物商の追加申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商の追加申請 | 25,000円(税込) 【全国対応】 |
古物商の追加申請をさせていただきます。 |
| 実費 | ||
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)追加の申請件数が多い場合には、料金に変動がございます。
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商を追加申請した場合の費用や手続は?-よくある質問
Q:追加申請にかかる費用はどのくらいですか?
A:追加申請の費用は、公定書類の取得が必要な場合には数百円程度です。警察署に支払う手数料は許可証の書換が不要であればかかりません。
Q:補正書と変更届の違いは何ですか?
A:補正書は、申請が受理された後の変更や追加に対応する書類であり、申請が受理される前の変更を行うためのものです。変更届は、許可が下りた後に行う変更に対応する書類です。
Q:ホームページを開設した場合、申請は必須ですか?
A:はい、ホームページを使用して古物営業を行う場合は、14日以内に申請が必要です。これは、法律で定められている義務です。
Q:新しい営業所を追加する場合、管理者の選任が必要ですか?
A:はい、追加する営業所ごとに新たに管理者を選任する必要があります。管理者の選任には、身分証明書や住民票などの書類が必要です。
Q:申請前に警察署へ事前連絡をしないとどうなりますか?
A:事前連絡をしない場合、申請手続きがスムーズに進まない可能性があります。担当者が不在であったり、必要な書類が揃っていないといったトラブルを避けるために、事前連絡を行うことが推奨されます。
Q:区分の追加申請でよくある間違いは何ですか?
A:区分の追加申請では、取り扱う古物の種類を正確に記載することが重要です。種類を誤って記載すると、後で再度修正が必要となり、手続きが遅れる可能性があります。
Q:補正書はどのように作成すればよいですか?
A:補正書は基本的に自由形式で作成できますが、申請内容や修正箇所を具体的に記載することが求められます。書式が不明な場合は、警察署や行政書士に相談することをお勧めします。
Q:申請が不許可になった場合、再申請は可能ですか?
A:申請が不許可となった場合でも、問題点を修正して再申請することは可能です。ただし、原因を明確にし、再度の不許可を防ぐために、行政書士等に相談することを検討してください。
古物商を追加申請した場合の費用や手続は?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商の追加申請が必要となる具体的なケースやその手続きの流れ、そして注意すべきポイントについて詳しく説明させていただきました。本記事を簡潔にまとめたものを下記に記載させていただきます。
1.古物商の追加申請が必要となるケース
古物商の追加申請は、主に以下のような内容で行われます。
営業所の追加:既存の営業所に加えて新たな営業所を開設する場合には、追加申請が必要です。
行商の実施:店舗以外での行商を行う場合、「行商しない」から「行商する」へ変更するための申請が必要です。
取り扱う古物の区分の追加:取り扱う古物の種類を増やす場合も、古物商許可の変更申請が必要です。
ホームページの開設:古物営業を行うためにホームページを開設する場合、変更の届出が求められます。
2.古物商の追加申請を検討する際の状況
追加申請には、申請が受理されている場合と、許可が下りた後の2つのケースがあります。
⑴申請が受理された後の追加申請
この場合、補正書を提出することで申請内容の修正が可能です。
補正書とは?:申請内容に修正や追加が必要な場合に使用される書類です。基本的には自由形式で作成でき、申請内容の変更部分を明確に記載する必要があります。
補正書の提出方法:郵送で提出できますが、正確で迅速な対応を確保するため、警察署の窓口で直接提出することが推奨されます。
⑵許可が下りた後の追加申請
許可後の変更には、変更届を提出する必要があります。
営業所の追加:新たに営業所を開設する場合、事前に変更届出書を提出し、必要書類を準備します。
行商の開始:行商を始める際には、変更日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
取り扱う古物の区分の追加:取り扱う品目を増やす場合も同様に、変更届が必要です。
ホームページの開設:ホームページを開設して古物営業を行う場合、開設日から14日以内に変更届を提出する必要があります。
3.古物商の追加申請をする際の注意点
古物商の追加申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。
申請前の事前連絡:申請前に必ず警察署へ事前連絡を行い、手続きがスムーズに進むよう準備を整えます。
書類の記載は正確に:提出書類の記載は厳密に行う必要があります。記入ミスや不備があると手続きが遅れる可能性があるため、記載例を確認して正確に作成しましょう。
専門家への相談:記載内容に不安がある場合、行政書士に相談することで、正確な書類作成が可能となり、手続きが円滑に進みます。
| 【参考】 >大阪府警察(営業所に係る変更届出(事前届出)) >大阪府警察(変更届出(事後届出)) >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |

