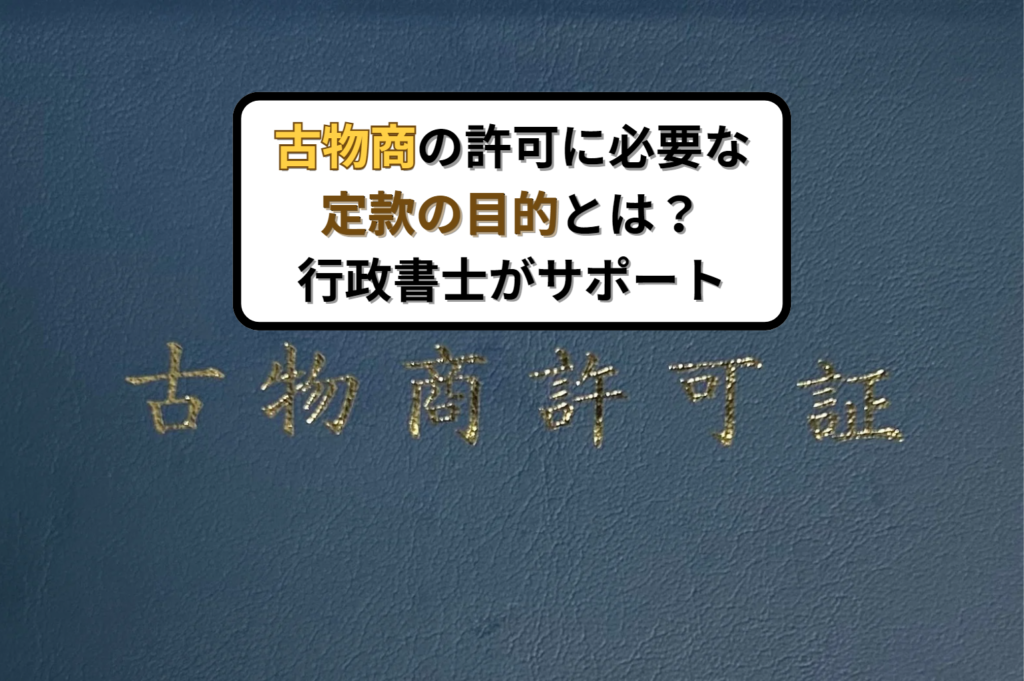法人が古物商を始める際には、最初に定款の目的に古物営業に関する内容を正確に記載する必要があります。この目的設定がないと、古物商許可を取得する際に申請が認められない可能性があるため、注意が必要です。定款は、会社や法人がどのような活動を行うかを記載した基本的なルールを示すものですが、古物商の許可申請においては、定款に特定の記載がなければなりません。
この記事では、古物商の許可申請における定款の目的設定について、そしてそれを行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
古物商の許可申請に必要な定款の目的とは?

古物商を営むためには、法人の定款に「古物営業に関連する目的」が記載されていることが求められます。定款は会社や法人が行う事業内容を明記する基本的なルールであり、許可申請の際には、目的欄に「古物営業法に基づく古物商」や「中古品の売買」、「リサイクル事業」など、古物に関連する事業内容をしっかりと記載することが必要です。
なぜ定款の目的が重要なのか?
この記載が必要な理由は、許可申請を受け付ける警察が、その会社が古物商を営む意思があることを明確に確認するためです。もし定款にこのような目的が記載されていない場合、警察はその会社が古物商としての事業を行うつもりがないと判断し、許可申請を受理しない場合があります。これにより、許可の取得が遅れる可能性があるため、古物商として事業を行う予定がある場合には、事前に定款の内容を確認し、必要に応じて目的事項を変更しておくことが非常に重要です。
商品に関する記載があれば受理される可能性
しかし、定款に「古物営業法に基づく古物商」等の具体的な記載がない場合でも、販売する商品について記載があれば、許可申請が受理される可能性があります。例えば、中古自動車を取り扱う場合、定款の目的に「自動車の売買」などの記載があれば、それは中古自動車を取り扱う意図が含まれていると解釈されることが多いです。もちろん、「中古自動車の売買」と明確に記載することが望ましいですが、商品が明確に想像できる記載があれば問題になることは少ないでしょう。
定款の変更手順
定款を変更するには、株主総会の決議が必要です。この場合、通常「特別決議」が求められます。株主の3分の2以上の賛成が必要で、決議を経た後に定款の内容を正式に変更することができます。また、定款の目的事項の変更については登記事項に該当するため、変更があった日から2週間以内に登記をすることが法律で義務付けられています。この手続きが遅れると、罰則が適用される場合もあるため、注意が必要です。登記手続きには、申請書、株主総会議事録などの必要書類を法務局に提出する必要があります。具体的な手続は以下のトピックにて解説しております。
【関連記事】
古物商の許可申請で定款に目的がなくとも受理されるケースとは?

古物商の許可申請において、定款に古物営業に関連する目的が記載されていない場合でも、申請が受理されるケースがあります。特に、登記簿謄本の目的欄に古物商に関連する内容が記載されていれば、許可申請が受理される可能性があるのです。登記簿謄本は、会社の登記内容を示す公的な証明書であり、法人がどのような目的で設立され、どのような事業を行っているかが記載されています。
登記簿謄本の目的に記載がある
古物商の許可申請では、警察は通常、定款とともに登記簿謄本の提出を求めます。理想的には、定款に「古物営業法に基づく古物商」や「中古品の売買」といった具体的な事業目的が明記されていることが望ましいです。しかし、定款にこれらの記載がない場合でも、登記簿謄本に同様の目的が記載されていれば、申請が受理されることがあります。
定款変更後の登記事項変更は義務
定款の目的事項を変更した場合、会社内部での決議にとどまらず、その内容を法務局で登記事項として変更することが法律で義務付けられています。例えば、会社が新たに「古物営業」を目的に追加した場合、その変更内容は登記簿にも反映させる必要があります。この手続きを怠ると、会社法違反となります。
定款の変更が怠られるケース
しかし、実務では、登記簿謄本の目的事項を更新する際に定款の変更を怠るケースが多く見られます。例えば、定款は設立時のまま更新されず、登記簿謄本上だけが最新の事業目的に沿っていることがあります。このような場合、警察は登記簿謄本を基に判断するため、定款に古物商に関する記載がなくても申請が受理されることがあります。
理由書を準備しておくことで申請がスムーズに
ただし、登記簿謄本に古物営業に関連する目的が記載されていても、定款にはその記載がない場合、将来的に問題が発生する可能性があるため、念のため「定款の目的事項が変わっていないことを伝える理由書」を提出することが推奨されます。これは、会社が現在の目的に基づいて事業を行っており、古物商事業を確実に計画していることを確認するための書類です。この理由書を添えることで、警察も会社が古物商を営む意思が継続していることをより明確に理解でき、申請がスムーズに進むことが予想されます。また、定款の目的事項が将来的に変更される可能性がある場合にも、その意図を事前に伝えることができるため、申請に対する信頼性が高まります。
理由書の作成のポイント
理由書の作成には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、申請者がなぜ定款を変更していないのか、そして登記簿謄本に記載されている目的事項が正確に古物商事業に関連していることを、わかりやすく説明する必要があります。また、今後定款の目的事項を変更する予定がある場合には、その予定や時期についても明確に記載すると良いでしょう。
理由書の内容が不十分であったり、曖昧であると、警察が申請に対して懸念を抱く可能性があるため、慎重な作成が求められます。このため、理由書の作成は行政書士に依頼することを強く推奨します。行政書士は、古物商の許可申請の手続きに精通しており、理由書に必要な要素を確実に盛り込むことができます。行政書士に依頼することで、形式に沿った適切な理由書を準備し、申請の成功率を高めることが可能です。
定款の目的事項変更手続きの具体的な流れ

もし既に設立した会社や法人の定款に古物商に関連する目的が記載されていない場合、その事業を開始する前に定款の目的事項を変更する必要があります。古物商の許可申請では、定款に古物商事業の目的が明確に記載されていなければ、申請が受理されないため、この変更は非常に重要です。目的事項の変更は以下の流れで行われます。
- 株主総会での決議
まず、定款の目的事項を変更するためには、株主総会を開催し、そこで古物商に関連する事業を新たな目的として追加することを決議します。株主総会での決議は通常「特別決議」と呼ばれ、株主の議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。 - 定款の修正
株主総会での決議が無事に行われた後、次に定款を修正します。この修正は、株主総会で決議された内容を基に、具体的に定款の目的事項に古物商関連の記載を追加します。たとえば、「古物営業法に基づく古物商の営業」や「中古品の売買」など、具体的な事業内容を正確に記載することが求められます。目的が曖昧だったり、古物商関連であることが不明確だと、後に許可申請が問題になる可能性があります。 - 法務局への登記申請
定款の修正が完了したら、次に法務局にて「目的事項変更の登記申請」を行います。定款の変更が行われた場合、変更内容を法務局に申請し、会社の登記簿に反映させることが法律で義務付けられています。この手続きを怠ると、登記懈怠として法的な罰則が科される可能性があります。法務局での登記申請には、次の書類が必要です。
・登記申請書:目的事項の変更を記載し、必要な情報を申請します。
・株主総会議事録:定款変更が適法に議決されたことを証明するためのものです。
・株主リスト:株主総会での議決権を有する株主のリストです。
また、登記申請には登録免許税が発生します。この税額は会社の資本金によって異なり、数万円程度の費用がかかることが一般的です。必要書類を準備し、登録免許税の納付を終えたら、申請書類を法務局に提出します。この際、書類の不備があると登記が受理されない可能性があるため、事前にすべての書類をチェックすることが重要です。 - 登記完了後の対応
法務局での手続きが完了すると、登記簿に新しい目的が反映されます。この時点で、正式に会社の目的が「古物商関連の事業」に含まれることになります。古物商許可申請の準備もこの時点から行うことができ、事業の正式な開始に向けて進めることが可能です。
なお、目的変更の登記が完了したら、新しい定款を社内で正式に保管しておく必要があります。
古物商許可に必要な書類と準備すべき手順

古物商許可を取得するためには、単に定款の目的事項を変更するだけでなく、その他多くの書類を正確に準備する必要があります。特に、法人の場合には、警察署に提出する書類の種類が多岐にわたるため、どの書類も不備なく用意することが重要です。不備がある場合、許可申請が受理されず、再提出や手続きの遅延につながる可能性があるため、注意が必要です。
以下に、法人が古物商の許可申請を行う際に必要な書類と、それに伴う準備手順を詳しく解説します。
- 古物商許可申請書
古物商許可申請書は、許可申請を行う際の基本となる書類です。申請書には、会社や申請者の基本情報、取り扱う古物の種類、営業所の所在地、管理者の情報などが記載されます。警察署が申請書を基に審査を行うため、正確な情報を漏れなく記入することが重要です。 - 住民票
法人の役員や管理者の住民票も必要です。住民票は、現住所が確認できる公的書類であり、通常は交付から3か月以内のものを提出する必要があります。また、住民票には本籍が記載されたものを求められる場合もあるため、提出前に警察署での確認を怠らないようにしましょう。 - 身分証明書(官公署発行)
身分証明書は、代表者や役員が「破産者でないこと」「被後見人ではないこと」「禁固刑以上の刑に処されていないこと」を証明する書類です。この書類も、市区町村役場で発行されます。古物商の許可申請では、申請者が信用に欠ける人物でないことを確認するために、法的な問題がないことを証明する書類が必要です。身分証明書も住民票同様、交付から3か月以内の最新のものを提出する必要があります。 - 略歴書(直近5年)
略歴書は、申請者および役員・管理者が直近5年間にどのような職歴を有しているかを示す書類です。これは、古物商を適切に営む能力や経験があるかを判断するための基準となります。職歴に不明点があると、警察から追加の説明や証明書類を求められる場合があります。略歴書には、正確な職歴や過去の雇用状況を明確に記載し、虚偽がないように記載しましょう。 - 誓約書(役員、管理者)
誓約書は、法人の代表者、役員、管理者が「法令を遵守すること」や「反社会的勢力に関与していないこと」などを誓うための書類です。これも古物商許可申請の重要な要件であり、全ての関係者が法令に基づいた健全な運営を行うことを証明するために必要です。誓約書は各役員や管理者ごとに作成し、警察署に提出します。 - 登記簿謄本
登記簿謄本は、法人の基本情報や構造を確認するための重要な書類です。登記簿謄本には、会社の設立日や事業目的、代表者名、所在地などが記載されています。古物商の許可申請では、法人の実態が確認できるように最新の登記簿謄本を提出することが求められます。登記簿謄本は法務局で取得できます。 - 定款
法人の定款も許可申請に必要です。定款には、会社の事業目的や構造、運営に関する基本的なルールが記載されており、古物商に関連する事業内容が明記されていることが重要です。もし定款に古物商関連の事業が記載されていない場合、目的変更手続きを行い、登記簿謄本にその変更を反映させたうえで申請を行う必要があります。 - URL疎明書類(必要に応じて)
インターネット上で古物を販売する場合、URL疎明書類も必要になります。これは、申請者が管理するWebサイトのURLを申告し、そのサイト上で古物の取引が行われることを証明する書類です。特に、メルカリやヤフオクなどのプラットフォームを通じて中古品を販売する場合、この書類は必須となります。また、警察が指定する方法で、Webサイトが申請者によって正しく管理されていることを証明する必要があり、サイト上に必要な情報が正確に掲載されていることも確認されます。
【関連記事】
- 古物商で必要なURL使用承諾書ってなに?取得時の注意点は?
- 古物商の許可は営業開始後から取得できるの?リスクはあるの
- メルカリで古物商を始める方法は?許可取得からURLの届出まで
- 古物商許可とヤフオクの使用URLについて
申請書類の注意点と行政書士の役割
これらの書類はすべて警察署が求める条件を満たしていなければなりません。記載内容に誤りや不備があると、申請が却下されるか、手続きが大幅に遅れる可能性があります。特に、誤解を招く表現や書類の不足は、許可申請において大きな障害となります。
そのため、申請書類の準備や作成には注意が必要で、これまでの経験や知識が求められます。このような場合、行政書士に依頼することで、書類の作成や申請手続きをスムーズに進めることができます。行政書士は、古物商許可申請に必要なすべての書類について、正確に作成する方法や注意点を熟知しており、依頼者に合わせた最適なサポートを提供します。
目的事項の変更が必要な古物商の許可申請サポートはお任せください

古物商許可を取得するためには、事業目的に関する定款の記載が非常に重要です。特に、許可申請を行う際には定款に「古物営業」に関する目的が明確に記載されている必要があります。もし、現在の定款に古物商に関連する目的が記載されていない場合、目的事項の変更が必要となります。
当事務所は、これまでに数多くの古物商許可申請のサポートを手掛けてきており、皆様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、あらゆる手続きを全面的にサポートいたします。ネット上の口コミでも150件を超える評価を頂き、総合評価4.9/5と非常に高い信頼を得ております。特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 現在の定款に古物商に関連する目的が記載されておらず、許可申請が通るか不安な方
- 目的の具体的な文言や修正方法について悩んでいる方
- 定款の目的事項の変更に関する株主総会の手続きや議事録の作成方法がわからない方
- 登記簿謄本と定款に矛盾が生じていて、許可申請に影響が出ないか心配している方
- 古物商許可申請を進める上で、複雑な書類作成や警察署とのやり取りに負担を感じている方
- インターネット販売を行うために必要な書類の準備や申請手続きに不安を感じている方
当事務所は、経験に基づいた的確なアドバイスと手厚いサポートを提供し、複雑な定款変更手続きから古物商許可申請まで一貫して対応いたします。ぜひ、古物商許可の取得に向けた手続きを当事務所にお任せください。

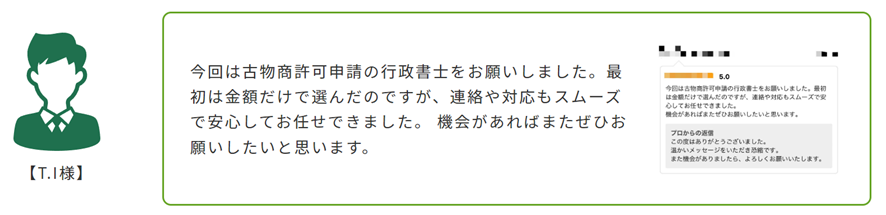

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 目的変更登記と古物商許可 【丸投げ】 |
100,000円(税込) | 目的変更登記と古物商許可申請です。提携の司法書士と協力して登記から許可までサポートします。 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
| 法務局手数料 | 30,000円(税込) | |
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
当事務所のこれまでの経験
当事務所では、これまでに複数の法人から目的事項の変更が必要な古物商許可申請のご依頼をいただいてきました。その中でも特に印象に残っている事例として、ある中古自動車販売業者の法人からの依頼です。この法人は、既に「自動車販売業」として事業を行っていましたが、古物商として中古車の買取および販売を新たに追加したいとの要望がありました。しかし、設立時の定款には古物商に関連する事業が明記されておらず、目的事項の変更が必要でした。
具体的なケースの詳細
このケースでは、法人が自動車販売業として事業を行っていたため、すでに「自動車の売買」という事業目的が定款に記載されていました。しかし、「中古車販売」や「古物営業」に関する具体的な記載が定款にないため、警察への古物商許可申請を行う前に定款の目的を変更する必要がありました。
対応したポイント
1.株主総会の決議準備まず、株主総会を開催して「中古自動車の売買」を目的に追加する決議を行う必要がありました。この際、クライアントが株主総会の準備に慣れていないことが分かっていたため、議事録の作成や招集手続きについてもサポートしました。特に、事前通知の内容を正確にし、株主の同意を得るためのポイントを丁寧に説明しました。
2.定款の変更株主総会での決議が無事に終了した後、速やかに定款の修正を行いました。この修正は、単に「中古自動車の売買」と追加するだけでなく、「古物営業法に基づく中古品の売買」や「古物の販売、買取」に関する具体的な文言を追加し、将来的に必要となる事業範囲がしっかりカバーされるようにしました。
3.法務局への申請は提携司法書士に依頼定款の変更が完了した後、法務局での登記申請については当事務所の提携する司法書士に依頼しました。司法書士は、登記に関する法律知識を活かし、迅速かつ正確に目的事項変更の登記手続きを行いました。行政書士が対応する範囲を超える部分については、信頼できる司法書士と連携することで、手続きのスムーズな進行を確保しています。
解決したポイント
このケースで特に注意を払ったのは、定款の目的事項における適切な文言の追加と、警察署が求める書類の正確な作成です。古物商に関連する文言が不十分だと、申請が受理されなかったり、追加書類を求められるケースが多いため、事前に将来的な事業の拡大も見据えて定款を修正しました。また、法務局への申請は提携の司法書士が対応することで、専門的な登記手続きがスムーズに進行しました。
古物商の許可に必要な定款の目的とは?-よくある質問
Q.古物商許可申請で定款に「古物商」や「中古品の売買」といった事業目的が記載されていないと、申請はできませんか?
A.はい、基本的には定款に「古物商」や「中古品の売買」といった具体的な事業目的が記載されていることが必要です。ただし、登記簿謄本に該当する目的が記載されている場合、申請が受理されることがあります。このため、古物商に関連する目的が定款に反映されていない場合は、定款の目的を変更する手続きが推奨されます。
Q.古物商許可申請の際に定款の目的変更を行うには、どのような手順が必要ですか?
A.定款の目的事項を変更するには、まず株主総会で特別決議を行い、その後、法務局に登記申請を行う必要があります。この手続きを完了させることで、定款に古物商関連の目的を追加することができます。
Q.定款の目的に「リサイクル事業」や「中古品の取引」といった広範な事業内容を記載しても問題ありませんか?
A.基本的には問題ありませんが、できるだけ具体的に「古物商」や「中古品の売買」といった事業内容を記載することが推奨されます。警察は許可申請を審査する際、事業の内容を具体的に把握したいと考えています。
Q.古物商許可申請に定款の目的を変更しなくても、申請は通りますか?
A.定款に古物商に関連する目的が記載されていない場合、登記簿謄本に同様の目的が記載されていれば、申請が受理されるケースもあります。しかし、将来的なトラブルを避けるため、定款に目的を明記しておくことが望ましいです。
Q.定款の目的変更後、法務局に登記申請する必要はありますか?
A.はい、定款の目的を変更した場合、その変更内容を法務局に申請し、登記簿に反映させることが法律で義務付けられています。これを怠ると、法的な罰則が科されることがあります。
Q.古物商許可申請の際、定款に記載する事業内容に制限はありますか?
A.特に制限はありませんが、古物商許可申請では、古物商に関連する事業内容を明確に記載することが重要です。
Q.登記簿謄本には記載されているが、定款に古物商の目的がない場合はどうすればよいですか?
A.登記簿謄本に古物商に関連する目的が記載されていれば、申請が受理される場合もありますが、定款の内容を確認し、必要に応じて変更しておくことが推奨されます。念のため「理由書」を提出することも有効です。
Q.古物商許可申請において、定款の目的変更はどれくらいの時間がかかりますか?
A.株主総会の開催や議事録作成、法務局への申請手続きなど、通常2、3週間ほどかかることが一般的です。手続きを迅速に進めるためには、事前の準備が重要です。
Q.定款の目的変更手続きを自分で行うことはできますか?
A.もちろん可能ですが、定款の変更手続きは法務的な知識が必要なため、専門家に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進行します。
Q.古物商許可申請において、行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.行政書士は古物商許可申請に必要な書類作成や手続きに精通しており、不備のない書類を作成することで申請がスムーズに進みます。また、申請書類にミスがあると手続きが遅れるため、専門家のサポートは非常に有効です。
Q.URL疎明書類は古物商許可申請のどのような場面で必要ですか?
A.インターネット上で古物を販売する場合、URL疎明書類が必要になります。これにより、警察がインターネットでの取引内容を確認することができ、適切な管理がなされているかを判断します。
Q.古物商許可申請に必要な「誓約書」とはどのような内容ですか?
A.誓約書は、法人の代表者や役員、管理者が法令を遵守し、反社会的勢力と関わりがないことを証明する書類です。これは、古物商許可申請の必須書類の一つです。
Q.定款の目的変更手続きに必要な費用はどれくらいですか?
A.定款の目的変更に伴う登記申請には、登録免許税として通常3万円程度の費用がかかります。その他、専門家に依頼する場合の報酬なども考慮する必要があります。
古物商の許可に必要な定款の目的とは?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商許可申請における定款の目的設定について、そしてそれを行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。
1.古物商許可に必要な定款の目的設定とは?
古物商を営むためには、定款に「古物営業に関連する目的」を記載することが求められます。定款は会社が行う事業内容を明記するもので、許可申請において重要な役割を果たします。
⑴なぜ定款の目的が重要なのか?
警察は定款の記載に基づき、古物商を営む意思があるかどうかを確認します。記載がなければ申請が受理されず、許可取得が遅れる可能性があります。
⑵商品に関する記載があれば受理される可能性
定款に「古物商」の記載がなくても、販売する商品が記載されていれば申請が受理される可能性があります。例えば、中古自動車を扱う場合は「自動車の売買」の記載でも許可されることがあります。
⑶定款の変更手順
定款の変更には株主総会での特別決議が必要で、決議後は2週間以内に法務局で登記申請を行う必要があります。この手続きを怠ると罰則が科される可能性があります。
2.定款に目的がなくとも許可が受理されるケース
定款に古物商の目的が記載されていなくても、登記簿謄本に記載があれば許可申請が受理されることがあります。
⑴登記簿謄本の役割と定款の違い
警察は定款と登記簿謄本を確認しますが、登記簿に古物商の目的が記載されていれば、定款の記載がなくても許可が受理されることがあります。
⑵定款変更後の登記事項変更は義務
定款の目的を変更した場合、法務局での登記が義務付けられています。登記を怠ると会社法違反となります。
⑶定款変更が怠られるケース
実務上、登記簿謄本が更新されていても定款が変更されていない場合があります。この場合、登記簿を基に警察が判断し、許可が受理されることがあります。
⑷理由書の準備
定款に目的がない場合は、理由書を準備して提出することで申請がスムーズに進む可能性があります。
⑸理由書の作成のポイント
理由書には、定款を変更していない理由や登記簿に記載された目的が古物商事業に関連していることを明確に説明する必要があります。行政書士に依頼することで、適切な理由書を準備することができます。
3.定款の目的事項変更手続きの流れ
古物商事業を開始する前に、定款に目的を追加する必要があります。この変更手続きは以下の流れで行います。
⑴株主総会での決議
まず、株主総会で定款の目的事項を変更するための決議を行います。この決議には3分の2以上の賛成が必要です。
⑵定款の修正
決議後、定款を修正し、古物商に関連する目的を追加します。
⑶法務局への登記申請
修正後は法務局に登記申請を行います。登記を怠ると法的罰則が科される可能性があります。
⑷登記完了後の対応
登記が完了したら、正式に古物商事業を開始できます。定款の保管や取引先への通知も行う必要があります。
4.古物商許可に必要な書類と手順
古物商許可申請には、定款の他にも多くの書類が必要です。以下はその代表的なものです。
古物商許可申請書:許可申請に必要な基本的な書類です。
住民票:役員や管理者の住民票を提出します。
身分証明書:破産者や刑罰を受けていないことを証明する書類です。
略歴書:役員や管理者の直近5年間の職歴を記載します。
誓約書:役員や管理者が法令を遵守することを誓う書類です。
登記簿謄本:法人の基本情報を確認するために提出します。
定款:古物商に関連する事業内容が記載された定款が必要です。
URL疎明書類:インターネットでの販売を行う場合、ウェブサイトに関する書類が必要です。
⑴申請書類の注意点と行政書士の役割
書類に不備があると申請が受理されません。行政書士に依頼することで、書類の準備や申請手続きをスムーズに行うことができます。
| 【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |