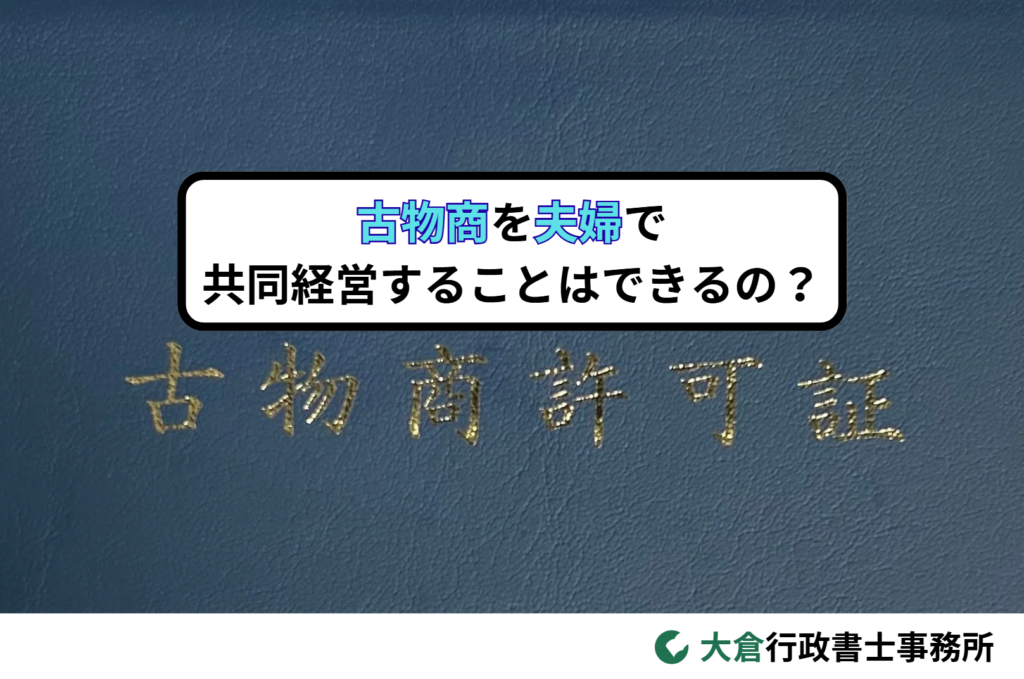古物商の経営は、近年、多様な働き方や副業の増加により注目されています。その中でも、夫婦での共同経営を検討する方からの相談が稀にあります。このように古物商を夫婦で共同経営することが可能なのか、法律上の制約や注意点はあるのかといった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、夫婦で古物商を共同経営する際の基本的な法律や規定、メリット・デメリット、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説します。古物商を始めたいと考えている方や、夫婦でのビジネスを計画している方にとって役立つ情報をお届けします。
古物商を夫婦で共同経営できるのか?

古物商の許可を取得し、夫婦で共同経営を行うことは可能です。しかし、適切な手続きを踏むことや、古物営業法に基づく規定を遵守することが求められます。ここでは、夫婦で古物商を共同経営する際に知っておきたいポイントについて詳しく解説します。
古物商を夫婦で共同経営することは可能
古物商を夫婦で共同経営することは、法律上問題ありません。古物営業法には夫婦間での共同経営を禁止する規定がないため、正しい手続きを経ることで、夫婦での経営を合法的に行うことができます。例えば、夫が古物商の許可を取得し、妻を営業所の管理者として選任するケースや、夫婦それぞれが個別に許可を取得して、共同で事業を運営するケースがあります。ただし、いずれの場合も、法的な要件を満たすことが必要です。
古物商を共同経営できる根拠
古物営業法には、夫婦で古物商を共同経営することを禁止する規定は存在しません。そのため、適切な手続きを経れば、夫婦で古物商を合法的に共同経営することが可能です。法律は個人または法人としての許可取得を求めていますが、経営形態が夫婦共同であること自体を制限する内容は含まれていません。
ただし、営業所の管理者や許可取得者は、以下の要件に該当していない必要があります。
- 破産者(復権を得ていない場合)
- 刑罰歴がある者(禁錮以上の刑や特定の犯罪で罰金刑を受け、刑の終了後5年以内の者)
- 暴力行為のリスクがある者(暴力行為を行う可能性が認められる者)
- 暴力団関係者(一定の命令や指示を受けてから3年以内の者)
- 住居が定まらない者
- 許可取消歴がある者(取消し日から5年以内の者)
- 許可証を返納した者(正当な理由がなく、返納から5年以内の者)
- 心身に問題があり、業務を適切に行えない者
これらの要件に該当しない場合に限り、営業所の管理者として選任することが認められます。
| 古物営業法第13条(管理者) 1古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。 2次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 ⑴未成年者 ⑵第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 ⑶心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの (第3項および第4項は下記で説明するため省略します。) |
管理者としての知識や経験が必要
営業所の管理者として選任する際には、「取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識や技術、経験を持たせること」が求められます。これは、古物営業法の趣旨が盗品の流通を防ぐことにあるためです。具体的には、以下のような知識や技術を管理者が持っていることが求められます。
- 古物の真贋を見分ける能力
骨董品や中古品などの正規品と偽物を見分ける基本的な知識が必要です。 - 適正な取引の知識
取引記録の作成や保存方法、法律に基づく適切な取引方法を理解していることが求められます。 - 法律遵守の意識
古物営業法や刑法、その他関連する法律についての基本的な理解が必要です。
これらの知識が不足している場合、警察が管理者としての適性を認めず、許可が受理されないことがあります。そのため、管理者となる夫婦の一方が十分な知識や経験を持つよう努めることが重要です。
| 古物営業法第13条第3項(管理者) 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 |
【関連記事】
古物商を夫婦で共同経営するメリットとデメリット
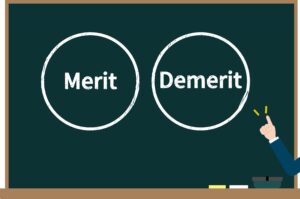
夫婦で古物商を共同経営することには、ビジネス上の大きな利点がある一方で、慎重に対処しなければならない課題もあります。ここでは、具体的なメリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット
- 連絡が取りやすい
夫婦間のコミュニケーションが円滑であるため、ビジネスにおいても意思疎通が非常にスムーズに行えます。たとえば、仕入れや販売の方針について話し合いたいときでも、家庭内で簡単に相談ができ、スピーディーに決定を下すことが可能です。日常的に顔を合わせることが多いため、メールや電話での煩雑な連絡手段を取る必要がなく、情報共有が迅速に行えます。 - 状況を把握しやすい
一緒に業務を行うことで、進捗状況や課題をリアルタイムで共有できます。例えば、どの商品が売れているのか、どの仕入れ先とトラブルがあったのかといった情報をお互いが即座に把握できるため、問題解決や戦略立案が効率的に行えます。特に、日常的に接する夫婦ならではの連携のしやすさが、経営の安定化に寄与します。 - 経理の不安が少ない
夫婦間の信頼関係が前提となるため、経理やお金の管理における不正やトラブルの心配が少なくなります。従業員に任せる場合と異なり、「お金の使途が不明」といった事態に陥る可能性が低いため、安心して経理業務を進められます。また、夫婦で経費の支出に関して相談しやすい点も大きな利点です。 - 人件費の削減
夫婦で経営することで、外部の従業員を雇用する必要がなくなり、人件費を削減できます。特に、スタートアップ時には経営資源が限られる場合が多いため、このコスト削減効果は非常に重要です。たとえば、仕入れや営業、在庫管理といった業務を夫婦で分担することで、効率的な経営を実現できます。
デメリット
- 経営のプロではない場合の不安
夫婦共に経営の知識や経験が乏しい場合、ビジネスの運営が難航する可能性があります。たとえば、マーケティング戦略や仕入れの判断が甘い場合、売上が伸び悩むだけでなく、在庫過多や資金繰りの悪化といった問題を引き起こすリスクがあります。特に、古物商は在庫管理が非常に重要な業種であるため、計画性のない運営は致命的な結果を招きかねません。 - 古物営業法の理解が必須
古物商の経営には、古物営業法をはじめとする法律や規制を遵守することが求められます。不適切な運営を行うと、許可の取り消しや罰則を受ける可能性があります。たとえば、盗品の取り扱いに関与していなくても、適切な確認手続きが行われていない場合は、責任を問われることがあります。また、許可証の更新や帳簿の管理など、法律で定められた手続きを怠ると、行政指導や業務停止命令を受けることもあります。
古物商を夫婦で共同経営する際の注意点とは

夫婦で古物商を共同経営する場合、法律を守り、適切に運営するためにいくつかの重要な注意点があります。古物営業法を遵守しないと、許可の取り消しや業務停止といった重大なペナルティを受ける可能性があるため、以下の点をしっかりと押さえておきましょう。
名前貸しで管理者とすることはできない
古物営業法では、営業所の管理者は実際に責任を持って業務を遂行できる人でなければなりません。夫婦で共同経営する場合でも、形式的に名前だけを借りて管理者として登録することは法律で禁止されています。
実務を伴わない管理者の問題点
管理者が実際に業務を行わない場合、古物営業法に違反するリスクがあります。たとえば、夫が許可を取得し、妻を管理者として登録したものの、妻が実際には業務に携わらない場合、警察の立ち入り検査などで問題視される可能性があります。管理者には、営業所での業務を適切に監督し、法律や規制を遵守する義務があり、管理者が不在の場合、業務の適正性が確保できません。また、管理者が法律に違反した場合、公安委員会から解任を勧告される可能性があります。このようなことを予防するためにも、夫婦の一方を管理者とする場合、その人がしっかりと業務に携わり、必要な知識やスキルを習得するように努めることが必要です。形式的な名前貸しはトラブルのもとになるため、絶対に避けるべきです。
古物営業法の知識が双方に必要
古物営業法では、営業所の管理者に「取り扱う古物が不正品かどうかを判断できる知識や技術」を求めています。これには、法律や規制に関する知識だけでなく、商品の鑑定や取引に関する実務的なスキルも含まれます。夫婦で共同経営を行う場合、互いに法律や実務について十分な理解を持つことが重要です。
知識不足がもたらすリスク
許可の取り消し
古物営業法に違反する行為があった場合、公安委員会によって古物商の許可が取り消される可能性があります。たとえば、不正品の取引が判明した場合や、必要な帳簿が適切に管理されていない場合などです。許可が取り消されると、再取得までに一定期間の制限がかかるため、事業の継続が難しくなります。
解任の勧告
公安委員会は、管理者が適切に業務を行えないと判断した場合、解任を勧告することができます。この勧告を無視すると、古物商としての営業自体が停止される可能性があります。
| 古物営業法第13条第4項(管理者) 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。 |
このように、夫婦共同で古物商を経営する場合に、妻を管理者として選任する場合には、古物営業法の基本的な内容や実務に必要なスキルを学ぶことが大切です。その後、実務経験を積むことで、商品の鑑定や取引記録の作成、帳簿の管理などを適切に行えるようになります。
夫婦で古物商を取得されたい方はお任せください
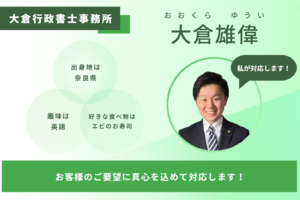
夫婦で古物商を取得し、共同経営をお考えの方にとって、許可申請や法律の理解は非常に重要です。当事務所では、これまでに数多くの古物商許可申請のサポートを行い、多くのご夫婦がスムーズに古物商事業をスタートできるようお手伝いして参りました。特に、夫婦での経営ならではのメリットを最大限に活かしつつ、古物営業法の規定を確実に遵守するためのサポートを提供しております。
当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5と高い評価をいただいております。実績と信頼に基づいたサービスで、これから古物商を始める方に安心と確実性をお届けします。許可申請の煩雑な手続きから、夫婦での共同経営における注意点のアドバイスまで、トータルでサポートいたします。
特に、以下のようなお悩みをお抱えの方はぜひご相談ください。
- 古物商の許可取得の手続きが複雑で、自分たちだけでは不安なご夫婦
- 古物営業法の理解や必要な知識の習得に自信がなく、専門家のアドバイスを必要とされる方
- 夫婦で共同経営を計画しているが、管理者選任や申請書類の作成で悩まれている方
- 過去に許可申請を断られた経験があり、再チャレンジを考えている方
- 忙しく、申請手続きに十分な時間を割けない状況の方
- 古物商としての許可取得後、日常的な法令遵守や帳簿管理について継続的なサポートを求めている方
当事務所では、これらのお悩みに対し、親身に寄り添いながら最適な解決策をご提案いたします。夫婦で古物商を始めることは、信頼関係を活かした効率的なビジネス運営が可能になる一方で、法律や手続きに関する知識が不可欠です。ぜひ私たちにお任せいただき、安心して古物商事業をスタートしてください。お問い合わせをお待ちしております。

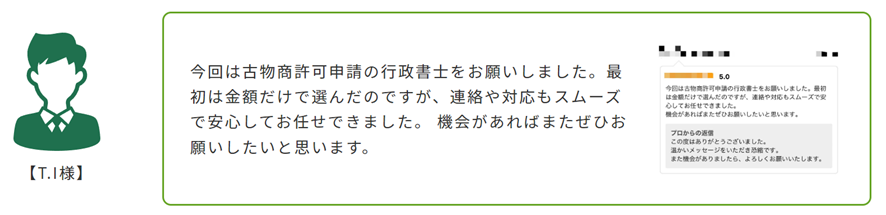

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商を夫婦で共同経営することはできるの?-よくある質問
Q.古物商を夫婦で共同経営することは可能ですか?
A.はい、古物商を夫婦で共同経営することは可能です。古物営業法には、夫婦での共同経営を禁止する規定がないため、適切な手続きを踏めば合法的に経営できます。
Q.古物商の許可を夫婦それぞれが取得する必要がありますか?
A.夫婦どちらか一方が許可を取得すれば、もう一方が営業所の管理者として従事する形で共同経営が可能です。ただし、それぞれが独立した古物商として営業する場合は、両方が許可を取得する必要があります。
Q.古物商を夫婦で共同経営する場合、どちらが管理者になるべきですか?
A.夫婦のうち、古物営業に関する知識や経験が豊富な方が管理者になるのが望ましいです。管理者には、法律に基づく責任や業務を適正に遂行する義務があるため、適性が重要です。
Q.古物商の管理者にはどのような資格が必要ですか?
A.特定の資格は不要ですが、古物営業法に基づき「取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識や技術、経験」を持つことが求められます。
Q.夫婦で共同経営する際に気を付けるべき点は何ですか?
A.名前貸しで管理者をすることはできません。また、古物営業法を遵守し、許可の取り消しや罰則を受けないよう、夫婦双方が法律や規定について十分に理解しておくことが必要です。
Q.古物商を夫婦で共同経営するメリットは何ですか?
A.夫婦間で連絡が取りやすく、意思疎通がスムーズであること、経理上の不安が少ないこと、人件費の削減につながることが挙げられます。
Q.古物商を夫婦で経営するデメリットはありますか?
A.経営経験が不足している場合、ビジネスがうまくいかない可能性があります。また、古物営業法の理解が欠けていると、法律違反やトラブルにつながるリスクがあります。
Q.夫婦間で役割分担をする際のポイントは何ですか?
A.夫婦間で得意分野を活かした役割分担をすることが大切です。たとえば、商品管理や仕入れを一方が担当し、もう一方が経理や接客を担当する形が効果的です。
Q.古物商の許可を取得するための費用はどのくらいですか?
A.許可申請の手数料は19,000円です。その他に必要書類の取得費用や、専門家に依頼する場合の報酬も発生します。
Q.古物商を夫婦で経営する場合、税務上の注意点はありますか?
A.夫婦間で収益をどのように分配するかを明確にし、適切に申告することが大切です。税理士に相談して、最適な方法を検討することをお勧めします。
Q.古物商を夫婦で経営する場合、不正品を扱わないためにはどうすれば良いですか?
A.仕入れ時に商品が盗品や偽物でないことを確認することが重要です。出品者から取引記録や身分証明書を確実に取得することで、不正品の流通を防止できます。
Q.古物商を夫婦で経営する際、許可の更新はどのように行いますか?
A.古物商許可は無期限ですが、許可内容に変更がある場合は、速やかに警察署を通じて公安委員会に届け出る必要があります。また、住所変更や管理者変更があった場合も同様です。
Q.古物商の経営に不安がある場合、どこに相談すれば良いですか?
A.行政書士に相談することで、許可取得や経営に関するアドバイスを受けられます。特に夫婦での共同経営を検討している場合は、法律や運営面での具体的なサポートを提供してもらえます。
古物商を夫婦で共同経営することはできるの?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商を夫婦で共同経営する際の基本的な法律や規定、メリット・デメリット、さらに注意すべきポイントについて詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.古物商を夫婦で共同経営できるのか?
夫婦で古物商を共同経営することは可能です。古物営業法には夫婦間の共同経営を禁止する規定がなく、適切な手続きを経ることで合法的に事業を運営できます。例えば、夫が古物商の許可を取得し、妻を営業所の管理者として選任することも認められます。ただし、管理者や許可取得者には破産者や特定の刑罰歴がある者など法律で定められた要件に該当しない必要があります。
管理者として選任された夫婦の一方には、古物営業法で求められる「取り扱う古物が不正品であるかを判断する知識や技術、経験」が必要です。知識が不足している場合、警察に受理されないこともあるため注意が必要です。
2.古物商を夫婦で共同経営するメリットとデメリット
⑴メリット
夫婦間の連絡が取りやすいため、意思決定がスムーズに行えます。日々の業務進捗や課題を共有しやすく、経理に関しても信頼関係に基づいて不正のリスクを減らせます。また、従業員を雇う必要がないため人件費を削減でき、経費の効率化が図れます。
⑵デメリット
夫婦共に経営や古物営業法についての知識が乏しい場合、事業運営が難航する可能性があります。また、法律や規制を守らない場合には許可の取り消しや罰則を受けるリスクがあります。特に、盗品の取り扱いが発覚すると重い責任を問われる可能性があるため、慎重な運営が求められます。
3.古物商を夫婦で共同経営する際の注意点とは?
⑴名前貸しは法律違反
形式的に管理者の名義を借りるだけでは法律違反となります。管理者は実際に業務を遂行し、業務の適正性を確保する責任があります。管理者が不適切な行為を行った場合、公安委員会から解任を勧告されることもあります。
⑵古物営業法の知識が必要
夫婦双方が古物営業法の基本的な内容や、商品の鑑定、帳簿の管理方法を理解している必要があります。不適切な運営は許可の取り消しにつながるため、研修や専門家の指導を受けるなどして知識を習得することが重要です。
⑶法律違反のリスク
不正品の取引や帳簿の不備など、法律に違反する行為があった場合、古物商許可が取り消される可能性があります。さらに、公安委員会による管理者の解任勧告が行われる場合もあるため、適切な運営体制を整えることが求められます。