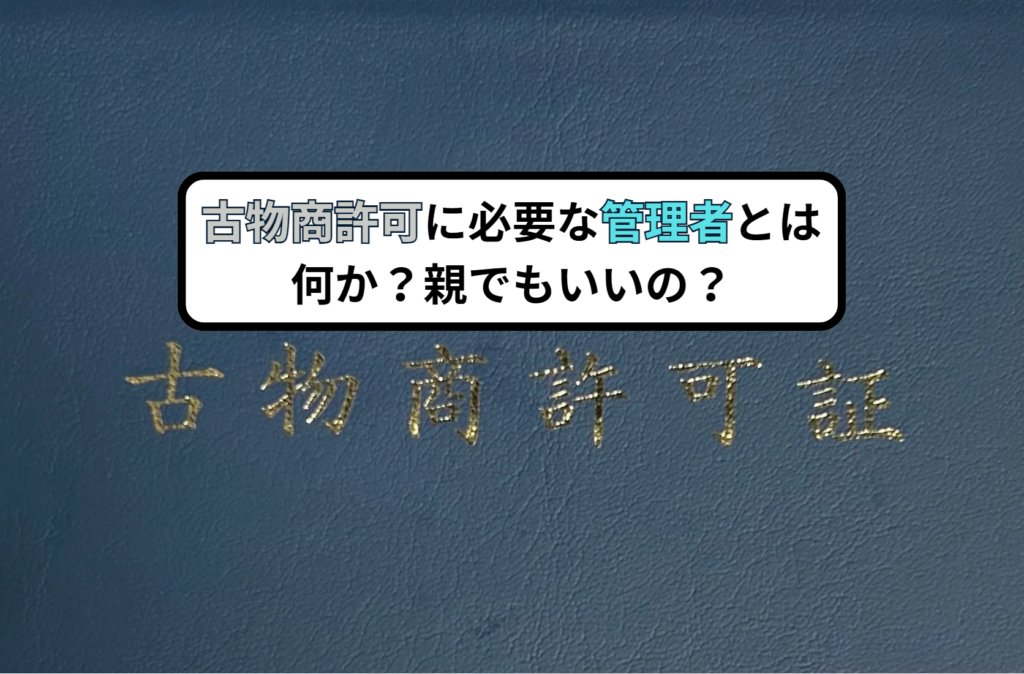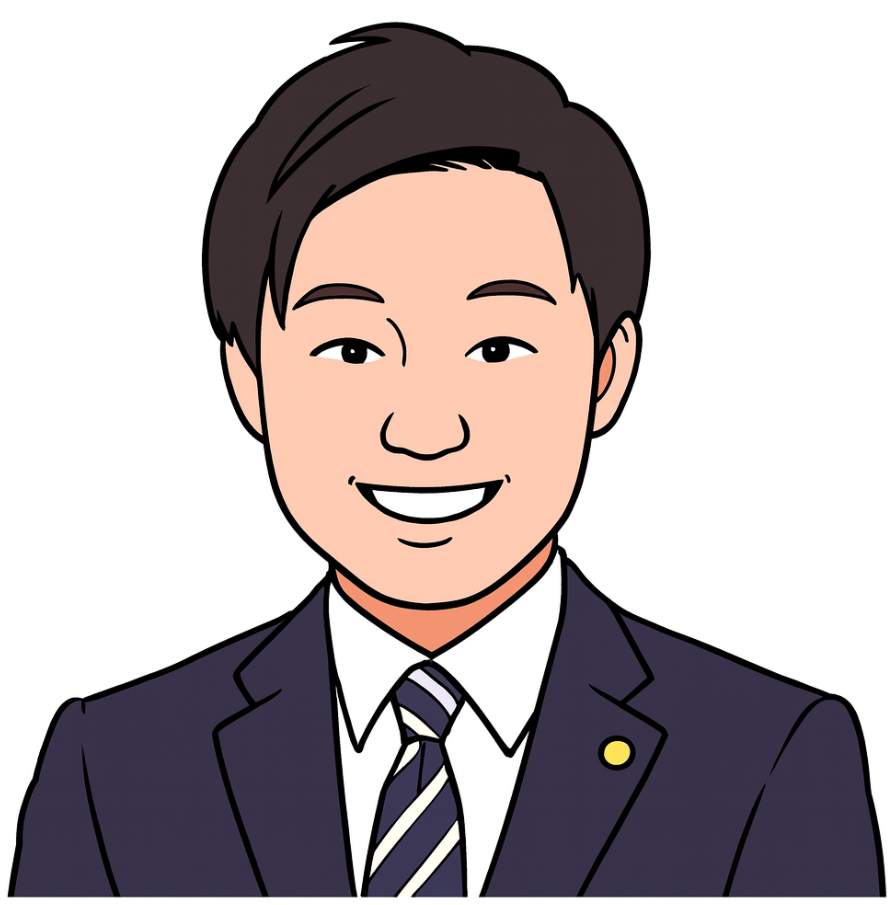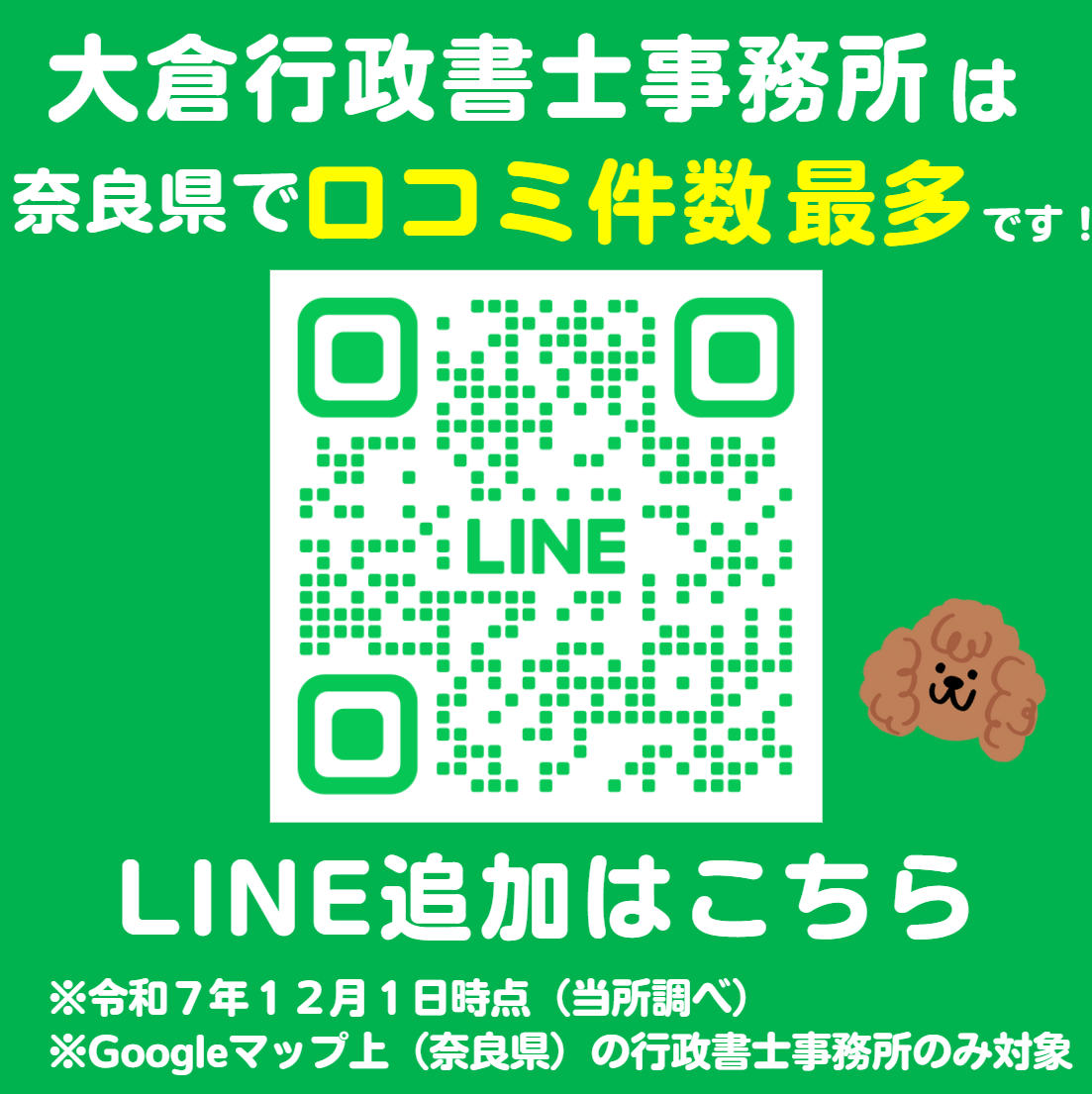古物商を営むためには、営業所の管理者を決めて、まず「古物商許可」を取得しなければなりません。管理者は、法律に基づいて業務が適切に行われるよう監督する責任を負いますが、その役割や条件、申請手続きについてはよく理解しておく必要があります。
本記事では、古物商の管理者に関する要件や、許可申請の際に管理者が注意すべきポイント、さらに手続きをスムーズに進めるための方法を詳しく解説します。
古物商では管理者が必ず必要!その要件とは

古物商許可を取得するためには、営業所ごとに「管理者」を選任しなければなりません。この管理者とは、古物営業法に基づき、営業所で行われる取引が適法に行われることを監督する責任者です。つまり、管理者は単に営業所に所属するだけでなく、日々の業務が法律に則って運営されているかをしっかり監督する重要な役割を担います。
では、この「管理者」として選任できるのはどのような人物なのでしょうか。管理者になるための条件にはいくつかの要件があります。まず、管理者は満18歳以上であり、かつ日本国内に住所を有している者でなければなりません。また、過去に刑事事件で有罪判決を受けた者や、暴力団との関わりがある者など、一定の法的制限がある者は管理者に就任することができません。詳細は次のとおりです。
古物営業法に基づく管理者の要件
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪で罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団に暴力的要求行為をすることを依頼するなどして、命令または指示を受けてから3年経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
- 営業所の通勤圏内に住んでいない者
- 他の営業所の管理者になっている者
上記以外に、管理者は業務の内容を十分に理解し、取引の法令を遵守できる能力が必要です。そのため、法律に関する基本的な知識を持ち、適切な判断を下せる人材であることが求められます。こうした条件を満たした上で、古物商許可申請の際に管理者としての登録を行います。
| 古物営業法第13条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。 |
【関連記事】
法人の古物商申請で営業所の管理者と役員の兼務は可能か

法人が古物商許可を申請する場合、営業所ごとに管理者を選任する必要がありますが、その際に「管理者が役員を兼務することができるのか?」という疑問がしばしば生じます。この点について、結論としては「可能」です。管理者は、法人の役員や代表者であっても問題ありません。
多くの法人では、代表取締役や専務などの役員が管理者を兼任するケースがあります。この場合、役員としての業務と管理者としての業務が重なるため、業務効率の向上が期待されます。特に小規模な法人や新たに設立された法人では、コスト削減や業務の一元化を図るため、代表者自身が管理者となることが一般的です。
しかしながら、法人の規模が大きくなり、営業所の数が増えると、管理者は一つの営業所に一人必要であるため、各営業所を適切に監督するのが難しくなる場合があります。特に、複数の営業所がある場合、管理体制が整っていなければ法令遵守が困難です。そのため、規模に応じて専任の管理者を各営業所に配置することが推奨されます。専任の管理者を配置することで、営業所ごとの業務管理が確実に行われ、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
また、役員と管理者を兼任する場合でも、管理者としての責任が軽減されるわけではありません。管理者は、法令に基づき業務が適法に行われることを監督する役割を担っているため、業務の適正な運営と法令遵守に常に注意を払う必要があります。法的に問題が発生した場合、管理者には厳しい責任が問われるため、十分な理解と注意が必要です。
法人の代表者と管理者を兼務する場合
上記より、たとえ1人代表の法人であっても、自分を管理者兼役員として申請することが可能です。しかし、このようなケースでは、注意が必要です。それは、法人の所在地や代表者の自宅と、営業所の場所が離れている場合です。このような場合、営業所を適切に管理できないと判断されることがあり、申請が受理されないリスクが存在します。
これまでのケースでは、営業所から自宅が車で約2時間(一般道利用)離れている場合でも申請が受理された事例がありますが、これ以上の距離がある場合、管轄の警察署などから「適切な管理ができない」可能性が高いと伝えられました。
このような距離の問題があるので、営業所の立地や管理者の居住地が適切であるか、事前に確認しておくことが重要です。以上のように、管理者として役員を兼務する場合は、管理責任と業務運営を両立させるために、事前に営業所と居住地の距離や管理体制をしっかりと確認し、管轄の警察署とも十分に相談することが大切です。
【関連記事】
古物商の管理者は家族でもいいの?適任者の選び方とは

古物商の管理者として家族を選任することは可能です。たとえば、家族経営の事業では、夫婦や兄弟などの身近な人物が管理者となるケースも少なくありません。家族が管理者に選ばれることで、信頼関係をもとに業務を進めることができる点は大きなメリットです。特に、家族経営のビジネスにおいては、外部から人材を探す手間を省くことができるため、効率的です。
しかし、家族を管理者に選任する場合でも、古物営業法に基づいた厳格な責任が伴うことを理解しておく必要があります。家族だからという理由だけで選任することは、後々問題を引き起こす可能性があるため注意が必要です。古物商の管理者には、法律を理解し、適切な判断を下せる能力が求められます。法律に詳しくない家族を管理者にすると、適切な監督ができず、結果として違法な取引に関与するリスクが高まる恐れがあります。
また、警察署に古物商許可の申請を行う際には、管理者が古物営業について十分に理解しているかが厳しく確認されることがあります。特に家族を管理者に選んだ場合、「家族だから」という安易な理由ではなく、適任者としての能力を証明できることが重要です。「なんとなく管理者がいないから親を選任した」「とりあえず家族だから選んだ」という理由では、警察によって古物商許可申請が受理されない可能性があります。
具体的な事例として、警察署での申請審査時に、家族が古物営業に関してどの程度の知識や経験を持っているか、営業活動の監督が適切に行えるかどうかを聞き取り調査されることがあります。この際、家族であっても業務内容に無知であれば、不合格となるケースもあるため、管理者の選任は慎重に行う必要があります。
さらに、古物商の管理者には、単なる「名義貸し」ではなく実際の責任が伴います。たとえば、親や兄弟に対して「名前だけ貸してほしい」というような形で管理者に選任することはしてはいけません。管理者は、古物営業法に基づいた責任者としての義務があり、違法な取引が行われた場合には、管理者自身も法的な責任を問われる可能性があります。
過去には、管理者が十分な理解を持たないまま名目上だけで管理者に選ばれ、結果として法的トラブルに巻き込まれたケースも報告されています。このようなリスクを避けるためにも、管理者としての責任をしっかり理解した上で、業務に関与できる人物を選任することが重要です。家族を管理者に選ぶことは可能ですが、その選定には慎重さが求められます。家族であっても、業務を監督する能力や法的な知識を持っているかをしっかり確認し、古物営業法を遵守できる体制を整えることが必要です。
【関連記事】
古物商許可で管理者が求められる書類

古物商許可を申請する際には、申請書に加え、申請者および管理者に関するいくつかの重要な書類を提出する必要があります。これらの書類は、申請者と管理者が古物営業法に基づいて業務を適切に管理・運営できる人物であることを証明するためのものです。特に、管理者が適切な責任を負える人物であることを示す書類の提出は必須です。
以下に、管理者に求められる主要な書類を説明します。
- 住民票:まず、管理者の住民票が必要です。住民票は、本籍地が記載され、マイナンバーの記載されていないものが必要とされています。
- 身分証明書(役所発行):役所で発行されるこの書類は、管理者が破産者、後見人、禁治産者でないことを証明するものです。
- 誓約書(管理者用):管理者は、古物営業法に基づき、営業所の業務が法令に適合して行われるように監督する責任を負います。そのため、管理者が未成年者でないか、犯罪歴が無いかなどを確認する「誓約書」の提出が求められます。
これらの書類がすべて揃っていなければ、古物商許可申請は受理されません。書類の不備があった場合、申請の進行が遅れますので、事前にしっかりと書類の内容を確認し、正確に揃えることが重要です。また、申請者と管理者が同一人物である場合には、同じ書類を複数提出する必要はありません。たとえば、法人の代表者がそのまま管理者を兼任するケースでは、住民票や身分証明書は1通提出するだけで対応可能です。しかし、誓約書については、申請者用と管理者用のものを各1通記入しなければいけません。
古物商許可申請は当事務所にお任せください
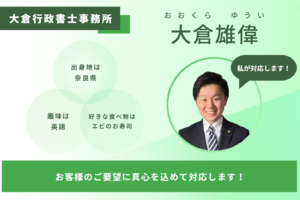
当事務所では、これまでに数多くの古物商許可申請のサポートを行い、多くのお客様から信頼をいただいております。豊富な経験に基づき、申請手続きの複雑さや古物商の管理者に関する細かな要件についても、確実に対応いたします。お客様一人ひとりの状況に応じた的確なアドバイスとサポートを提供し、許可取得までのプロセスをスムーズに進めることができます。
当事務所は、ネットでの口コミ件数が150件を超え、総合評価が4.9/5と非常に高い評価をいただいております。多くのお客様から高い満足度を得ている理由は、丁寧な対応と的確なアドバイス、そしてスピーディな手続き進行にあります。初めて古物商許可を申請する方、手続きに不安を感じている方にも安心してお任せいただけます。
特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 初めて古物商許可を申請するが、どこから手をつければよいか分からない方
- 管理者の選任に関して、家族を管理者にしてよいか悩んでいる方
- 法人申請で、役員と管理者の兼務が可能かどうかを確認したい方
- 必要書類の揃え方や、住民票や身分証明書の取得方法がわからない方
- 警察署への申請手続きが複雑で、申請がスムーズに進むか不安な方
- 過去に申請を却下されたことがあり、再度の申請で不安を抱えている方
当事務所では、お客様一人ひとりのニーズに合わせたサポートを提供し、複雑な申請手続きを分かりやすく丁寧にご説明いたします。経験豊富な行政書士が迅速に対応し、許可取得までの道のりをサポートいたしますので、安心してお任せください。

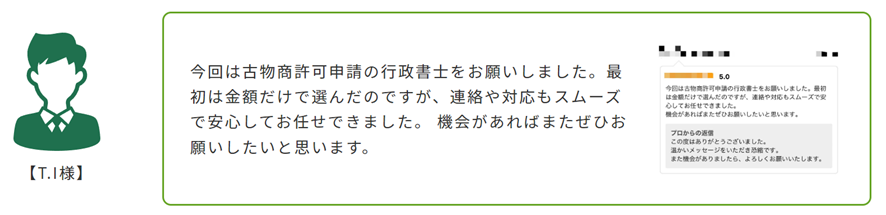

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商許可に必要な管理者とは何か?親でもいいの?-よくある質問
Q.古物商許可申請の際、管理者とは何ですか?
A.管理者とは、古物営業法に基づき、営業所で行われる取引が適法に行われるよう監督する責任者のことです。管理者は、法令遵守や業務運営の適正化を図るため、必ず選任しなければなりません。
Q.古物商許可申請で管理者は必ず選任しなければならないのですか?
A.はい、古物商許可申請では営業所ごとに管理者を選任する必要があります。これは古物営業法で義務付けられており、管理者がいないと申請は受理されません。
Q.古物商の管理者に求められる資格や要件はありますか?
A.管理者にはいくつかの条件があります。例えば、満18歳以上であり、日本国内に住所を持っていること、そして暴力団関係者や破産者でないことなどが求められます。また、法律を理解し、法令を遵守できる能力が必要です。
Q.管理者は法人の役員を兼務することは可能ですか?
A.はい、法人の場合、役員が管理者を兼任することが可能です。特に小規模な法人では、代表取締役が管理者としても役割を担うケースが一般的です。
Q.古物商の管理者を選任する際、家族を選んでも問題ありませんか?
A.家族を管理者として選任することは可能です。ただし、家族であっても法律に基づいた責任を負うため、古物商業務や法律に関する知識があるかを慎重に判断することが必要です。
Q.古物商の管理者を選任する場合、何が一番重要ですか?
A.一番重要なのは、管理者が法令遵守を理解しており、古物営業法に基づいて業務を適正に監督できるかどうかです。適任者でなければ、申請が受理されなかったり、後々トラブルが発生する可能性があります。
Q.申請者と管理者が同一人物の場合、提出書類はどうなりますか?
A.申請者と管理者が同一人物の場合、住民票や身分証明書は1通の提出で足ります。ただし、申請書類は正確に揃え、事前に不備がないよう確認しておくことが重要です。
Q.法人で複数の営業所がある場合、管理者はどうすればいいですか?
A.各営業所に管理者を一人ずつ選任する必要があります。法人が大きく、営業所が複数ある場合には、適切な管理体制を整え、法令遵守がしっかりと行える体制を確立することが重要です。
Q.古物商の管理者として選任する際、必要な書類は何ですか?
A.管理者として必要な書類は、住民票、身分証明書、そして誓約書です。これらが揃わなければ申請は受理されません。
Q.住民票にはどのような条件がありますか?
A.管理者の住民票には、マイナンバーが記載されていないものが必要です。申請の際には、役所で発行された正確な住民票を提出しましょう。
Q.管理者が責任を怠った場合、どのようなペナルティがありますか?
A.古物商の管理者は、法令違反や業務不適切に対して責任を負います。違法な取引が発覚した場合、管理者には罰則が科される可能性があるため、法令遵守が非常に重要です。
Q.管理者として未成年者を選任することはできますか?
A.いいえ、古物商の管理者として未成年者を選任することはできません。管理者は成人でなければならず、18歳以上でなければ選任できません。
Q.もし管理者を辞任したい場合、どうすればよいですか?
A.管理者が辞任する場合には、管理者の変更を管轄の警察署に届出し、新しい管理者を速やかに選任する必要があります。新たな管理者を選任しないままでは、古物商営業を続けることはできません。
Q.古物商許可申請において管理者が選任されない場合、どうなりますか?
A.管理者が選任されない場合、古物商許可申請は受理されません。管理者は法律に基づいた必須条件であり、選任しなければ営業が認められないため、必ず適任者を選出する必要があります。
古物商許可に必要な管理者とは何か?親でもいいの?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商の管理者に関する要件や、許可申請の際に管理者が注意すべきポイント、さらに手続きをスムーズに進めるための方法を詳しく解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。
1.古物商では管理者が必ず必要!その要件とは
古物商許可を取得するには、各営業所に管理者を選任する必要がある。管理者は、古物営業法に基づいて業務を監督する責任者であり、満18歳以上で日本国内に住所を有していること、過去に重大な犯罪歴や暴力団との関わりがないことなど、特定の要件を満たす必要がある。
2.法人の古物商申請で管理者と役員の兼務は可能か
管理者は法人の役員や代表者が兼務できる。特に小規模な法人では、代表取締役が管理者を兼任することが一般的だが、法人の規模が大きくなると各営業所に専任の管理者を配置する方が適切な場合もある。また、管理者と役員を兼務する際には、法令遵守の責任が軽減されるわけではない。
3.古物商の管理者は家族でもいいの?適任者の選び方とは
家族を管理者として選任することは可能だが、適切な知識と責任感が求められる。家族だからという理由だけで選ぶのは避けるべきで、古物営業に関する理解があり、監督能力を持つ人物でなければならない。名義貸しのような形で管理者を選任することは厳禁である。
4.古物商許可で管理者が求められる書類
管理者に関する必要書類として、住民票、身分証明書、管理者用誓約書などが挙げられる。これらの書類が揃っていなければ、申請は受理されない。管理者が申請者と同一人物の場合、同じ書類を1通提出すれば足りるが、誓約書はそれぞれ必要になる。