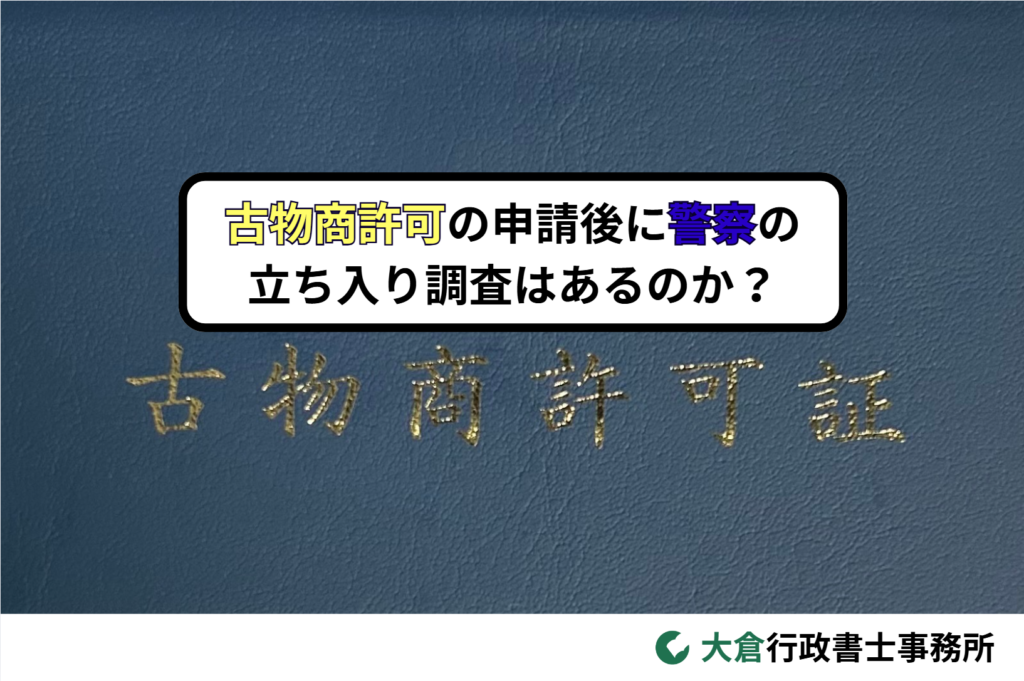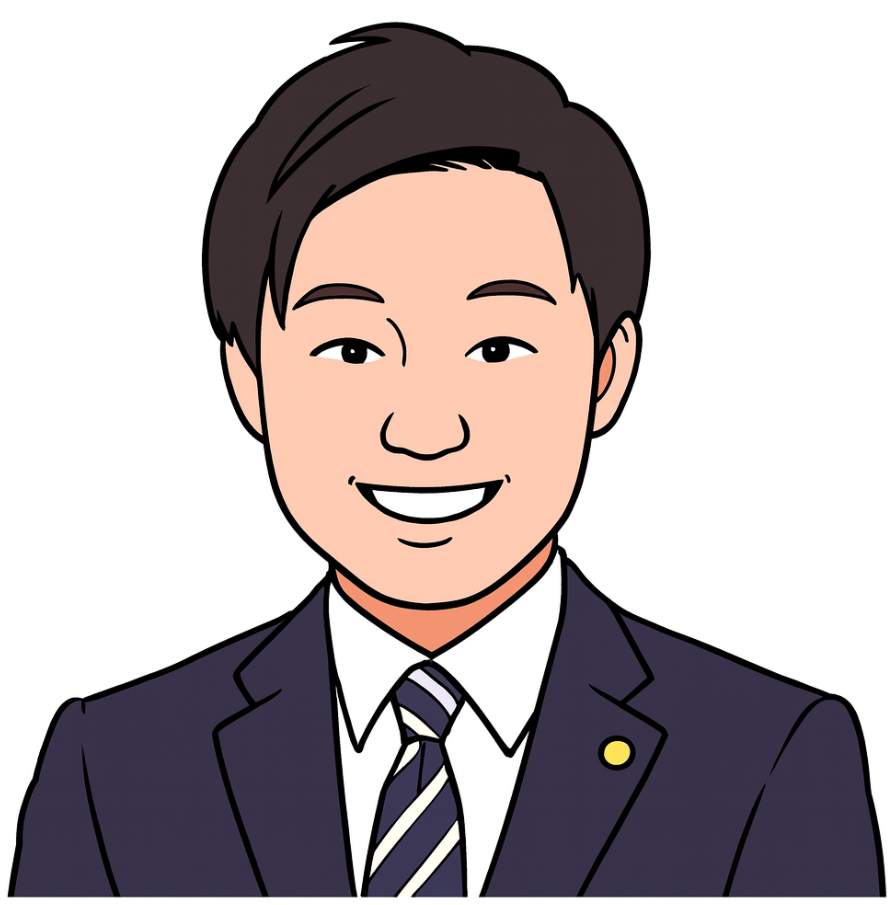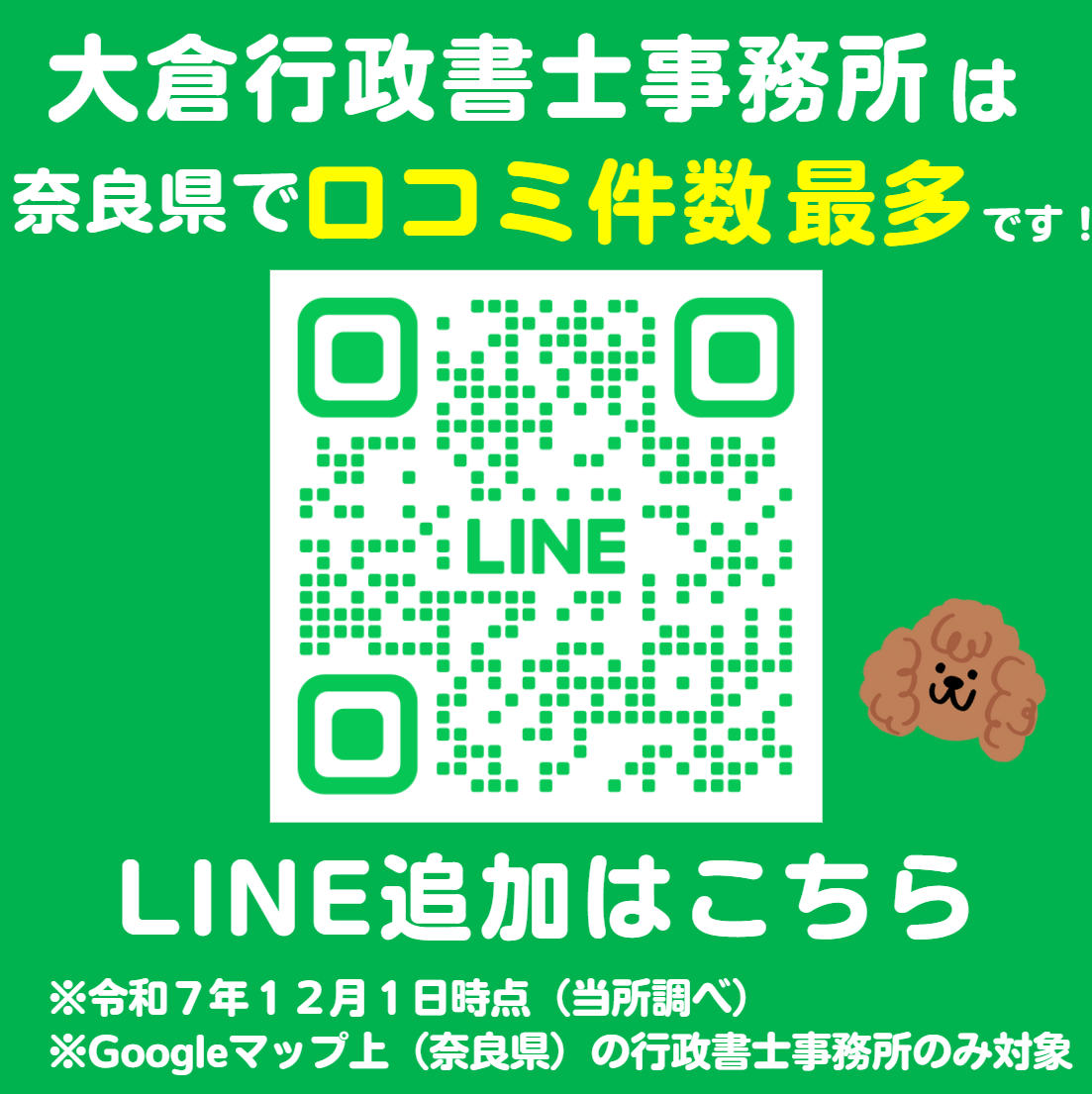古物商許可の申請後、営業所には警察による立ち入り調査が行われる場合があります。立ち入り調査は、古物商としての営業が適切に行われているか、また法律に基づいた営業が実施されているかを確認するために行われる重要な手続きです。警察が調査する項目には、申請者の欠格事由がないかや、営業所の実在確認などが含まれます。調査は、許可申請後の営業所確認に始まり、許可取得後の営業状況確認へと続きます。
この記事では、古物商がどのような調査を受ける可能性があるのか、また調査に備えた準備や、立ち入り調査への適切な対応方法について詳しく説明します。調査への理解と適切な準備は、スムーズな営業継続の鍵となり、また警察との信頼関係を築く上でも欠かせません。
古物商許可の申請後に警察の立ち入り調査はあるのか?

古物商許可申請における警察による営業所への立ち入り
古物商許可申請を行うと、まず警察による審査が行われます。この審査の目的は、申請者が欠格事由に該当していないかどうか、そして申請した営業所が実際に存在するかどうかを確認することにあります。
欠格事由とは、例えば前科がある場合や反社会的勢力との関係が疑われる場合など、法律に違反している状態で古物商許可を得ることができないとされる要因です。また、申請した営業所が実在するかも確認されます。この確認がなされる理由は、古物商としての営業が実際に行われているか、適切な管理体制が整えられているかを確認するためです。営業所の実在が確認できなければ、許可は下りません。
警察署ごとの立ち入り調査の違い
営業所の存在を確認するために、警察署が立ち入り調査を行うかどうかは、管轄する警察署ごとに異なります。例えば、大阪の場合、ほとんどの警察署では営業所の外観を調査するだけで済ませるケースが一般的です。この場合、申請者が営業所に常駐している必要はなく、外観調査が完了すれば審査が進みます。
一方で、一部の警察署では営業所内部への立ち入りが行われることもあります。このような場合、申請者は警察と打ち合わせを行い、立ち入りの日時を調整する必要があります。立ち入りが求められる場合には、必要な設備が整っていることを確認しておくと良いでしょう。
古物商許可取得後の警察による営業所への立ち入り

古物商許可が下りた後も、警察による立ち入り調査が行われることがあります。この調査は、通常、違法な販売が行われている、盗品が取り扱われているなどの通報があった場合や、不正な取引が疑われる場合に実施されます。警察による立ち入りは、古物営業法第22条に基づいて行われ、古物商はこれに応じる義務があります。(以下に条文があります。)
古物営業法第22条は、古物商が警察の立ち入り調査に協力しなければならないことを定めています。これは、適正な古物取引の維持と、盗品の流通防止を目的としています。立ち入り調査の拒否や、協力を怠ると、罰則がありますので営業を続ける上で、こうした調査に適切に対応することが求められます。
立ち入り調査の内容と対策
許可取得後の立ち入り調査では、警察は古物台帳の確認や在庫品のチェックなど、業務内容に問題がないかを確認します。古物台帳には、取引の詳細や顧客の情報が記録されており、これが適切に管理されているかが重要なポイントとなります。また、取り扱っている商品が盗品でないかも確認されるため、日頃から仕入れ先の信用性や商品の出所について注意を払う必要があります。
警察による立ち入り調査が行われた際には、台帳や在庫リストを迅速に提示できるよう、常に整った状態で保管しておくことが大切です。
このように、古物商として営業を続けるためには、警察による立ち入り調査への理解と準備が不可欠です。許可申請の段階での外観確認や立ち入り調査、さらに許可取得後の突発的な調査に備えるためには、日常から適切な管理体制を整えておくことが重要です。古物商として信頼される営業を行うためには、法令遵守と適切な対応が欠かせません。
| 古物営業法第22条(立入り及び調査) 1 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。 2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。 3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。 4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。 |
古物商許可許可後に警察の立ち入り調査は断れる?

古物商許可を取得し、営業を開始した後、警察による立ち入り調査が実施される可能性があります。これは、古物商が法令を遵守し、適切に業務を遂行しているかを確認するためのものであり、許可を受けた古物商にはこの調査に協力する義務があります。
この立ち入り調査は、古物営業法第22条に基づいて行われ、法律に明記された義務であるため、原則として断ることができません。
なぜ古物商には立ち入り調査の協力義務があるのか?
古物営業法が定める立ち入り調査の義務は、適正な古物取引を保護し、盗品などの不正商品が市場に流通しないようにするためのものです。古物商は、その業務を通じて、一般市民からの信頼を得ることが求められています。そのため、警察による監査や調査を受け入れることで、社会的な信頼を維持し、健全な営業を続けることが求められます。
このような立ち入り調査の対象となるのは、主に古物台帳や在庫品の管理体制、適切な取引記録が保管されているかといった事項です。警察は、これらを通じて古物商が法令に基づき、適正な管理体制を維持しているかを確認します。例えば、取引記録が不十分であったり、適切な保管が行われていない場合には、法令違反とみなされる可能性があるため、日常的に管理体制を整えておくことが大切です。
| 古物営業法第35条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 1 省略 2 省略 3 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 4 第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
古物商許可の立ち入り調査が行われた際の注意点とマナー

このトピックでは、警察の立ち入り調査が行われる際の事前準備の重要性、調査中の適切な対応姿勢、トラブルが発生した際の対処法について説明しています。これらを理解することで、立ち入り調査がスムーズに進むだけでなく、古物商としての信頼性を高めることができます。
立ち入り調査に備えた事前準備の重要性
警察による立ち入り調査が行われる際には、古物台帳や在庫リスト、許可証の提示など、求められる資料が複数あります。調査がスムーズに進むためには、これらの必要書類をあらかじめ整えておくことが大切です。例えば、古物台帳には取引の詳細を記録し、在庫リストには現在の保有品が正確に反映されている状態を維持しましょう。これにより、警察が求める情報を迅速に提示でき、調査の進行が滞ることを防ぎます。当事務所では、立ち入り調査時に必要な書類の整備や管理方法についてのアドバイスを行っており、万全の準備を整えるサポートを提供しています。
調査中の対応姿勢と協力的な態度
立ち入り調査が始まった際には、警察官の指示にしっかり従い、協力的な態度で対応することが大切です。警察の立ち入り調査は、古物商が法令を遵守し、適正に営業しているかを確認するためのものです。そのため、警察からの指示に従わなかったり、不適切な対応をとると、警察との信頼関係に影響を与え、営業の継続にも悪影響を及ぼす可能性があります。
調査中に質問があった場合は、できるだけ正確かつ丁寧に回答し、誠実な対応を心がけましょう。曖昧な内容については無理に答えるのではなく、「事実を確認の上でお答えいたします」といった姿勢で冷静に対応することが信頼を築く一歩となります。また、重要なのは虚偽の内容を伝えないことです。万が一、虚偽の内容を伝えた場合、古物営業法に基づき罰則が科されることもありますので、正確な情報の提供を心がけましょう。
トラブルが発生した場合の対処法と専門家のサポート
立ち入り調査中に書類の不備や記録ミスが指摘されることがあります。こうした場合には、指摘事項を素直に受け入れ、必要な改善策を即座に講じることが求められます。不備があること自体は珍しいことではありませんが、問題を早期に解決するために警察の指示をしっかりと受け止めることが大切です。
このようなミスが起きないよう、事前に古物営業法の内容を確認し、法令に従って日々の業務を行うことが重要です。法令をしっかり理解していれば、日常的な記録の取り方や書類の管理方法についても安心感が生まれ、いざというときにも自信をもって対応できます。
また、古物商許可申請を行政書士に依頼することで、一定期間のサポートが受けられる場合があります。例えば、古物商許可が下りるまでの間に、不明点を質問し、必要書類の記載方法や管理方法についても相談できるので、この期間を活用して書類の記載方法や注意点について理解を深めると良いでしょう。当事務所では、申請後も不備が起きないように、適切な書類管理や古物営業法の遵守についてアドバイスを提供し、長期的なサポートもご用意しております。
古物商許可申請は当事務所(行政書士)にお任せください

当事務所は、これまでに数多くの古物商許可申請をサポートしてきた実績があり、豊富な知識と経験に基づいた的確なアドバイスを提供しております。さらに、ネットでの口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高評価をいただいており、多くのお客様から信頼を寄せていただいています。
特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 古物商許可申請に関する書類準備や、警察による立ち入り調査の対応方法について、具体的なアドバイスが欲しい方
- 警察署ごとに異なる立ち入り調査基準についての理解を深め、適切に対処したい方
- 申請後の警察による営業所の外観調査や内部立ち入りの流れについて、不安を感じている方
- 古物商許可取得後の突発的な警察の立ち入り調査に備え、管理体制のアドバイスを受けたい方
- 古物営業法の遵守を徹底し、警察との信頼関係を保ちながら長期的な営業を目指している方
- 古物商としての信頼性を高めるため、適切な対応や警察調査への準備を専門家に相談したい方
当事務所では、古物商許可申請からその後の対応まで一貫したサポートを提供し、お客様が安心して営業を続けられるよう全力でサポートいたします。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

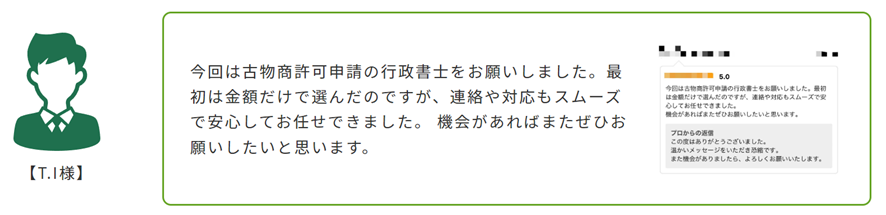

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商許可の申請後に警察の立ち入り調査はあるのか?-よくある質問
Q.古物商許可申請後、警察の立ち入り調査は必ず行われるのですか?
A.警察の立ち入り調査は必ずしも全ての古物商に対して実施されるわけではありません。特に、営業所の存在確認については、警察署ごとに外観調査だけで済む場合もありますが、内部調査が必要なケースもあります。
Q.立ち入り調査では、具体的にどのようなことが調査されますか?
A.古物商の営業が適切に行われているかを確認するため、古物台帳や在庫リストなどの書類、顧客情報、商品管理体制が調査されます。これにより、法令順守や盗品の防止が徹底されているかが確認されます。
Q.大阪の警察署では、古物商許可申請後の立ち入り調査はどのように行われることが多いですか?
A.大阪では多くの警察署で外観調査のみで済むことが多いですが、一部の警察署では内部調査が行われる場合があります。調査の内容や方法は管轄警察署により異なるため、事前に確認することをおすすめします。
Q.古物商許可取得後も警察の立ち入り調査を受けることがあるのですか?
A.はい、許可取得後も警察の立ち入り調査が行われる場合があります。不正取引や盗品の疑いがある場合には、適切に応じる義務がありますので、日頃から管理体制を整えておくことが大切です。
Q.警察による立ち入り調査を拒否することは可能ですか?
A.古物商は警察の立ち入り調査に協力する義務があります。立ち入り調査を拒否した場合、古物営業法に基づき罰則が科される可能性があるため、警察の指示には誠実に従うことが求められます。
Q.立ち入り調査が行われる際に注意すべきことは何ですか?
A.必要な書類(古物台帳や在庫リストなど)を準備し、警察の指示に従い、協力的な態度で対応することが重要です。曖昧な内容については無理に答えず、確認の上で回答すると良いでしょう。
Q.警察の立ち入り調査で虚偽の内容を伝えるとどうなりますか?
A.虚偽の内容を伝えた場合、古物営業法に基づき罰則が科される可能性があります。正確な情報提供が求められるため、回答には十分注意が必要です。
Q.古物商許可を取得するためには営業所が必要ですか?
A.はい、許可申請の際には営業所の実在が確認されます。営業所がない場合は許可が下りません。営業所が適切に管理されているかを確認するために、立ち入り調査が行われることもあります。
Q.立ち入り調査が入る頻度はどれくらいですか?
A.立ち入り調査の頻度は一定ではなく、不定期に実施されます。特に、通報があった場合や、不正な取引の疑いがある場合には、警察の調査が入ることが多くなります。
Q.立ち入り調査で求められる書類にはどのようなものがありますか?
A.古物台帳や在庫リスト、許可証の提示などが必要です。これらの書類は古物営業法で管理が義務付けられているため、日頃から整理し、提示できる状態を保つことが求められます。
Q.立ち入り調査の際、警察官に不明点を質問されても答えられない場合はどうすれば良いですか?
A.不明点があった場合は、事実確認の上で正確にお答えしますと伝えると良いでしょう。無理に回答せず、後日改めて説明する姿勢が信頼関係の維持につながります。
Q.立ち入り調査で不備を指摘された場合はどう対応すれば良いですか?
A.指摘事項については、素直に受け入れ、迅速に改善を行いましょう。指摘が改善されないと、さらなる監査が行われる可能性もあるため、適切に対応することが大切です。
Q.古物商許可の立ち入り調査に備えるため、事前に何を準備すれば良いですか?
A.必要書類の整備、在庫管理、古物台帳の適切な記載などが求められます。管理体制を整えることで、立ち入り調査にスムーズに対応できますので、日頃から準備しておくと安心です。
Q.古物商の許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.行政書士に依頼することで、許可申請時から立ち入り調査への備えまでサポートを受けられます。書類の記載方法や管理体制の整備に関するアドバイスを得られるため、安心して営業を開始できるでしょう。
Q.警察の立ち入り調査の通知は事前にありますか?
A.警察の立ち入り調査が予定されている場合は事前に通知されることもありますが、急な調査が行われる場合もあります。常に準備を整え、適切に対応できるようにしておくことが重要です。
古物商許可の申請後に警察の立ち入り調査はあるのか?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商がどのような調査を受ける可能性があるのか、また調査に備えた準備や、立ち入り調査への適切な対応方法について詳しく説明させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.古物商許可申請後の警察による営業所への立ち入りについて
古物商許可を申請すると、警察による審査が実施されます。申請者が欠格事由に該当していないか、営業所が実在するかなどが確認されます。営業所確認の方法は警察署ごとに異なり、大阪の多くの警察署では外観調査のみですが、一部の警察署では内部の立ち入りもあります。この場合、警察と日時を調整し、必要な設備が整っているか確認が必要です。
2.古物商許可取得後の警察による営業所への立ち入りについて
許可取得後も、違法行為の疑いがある場合などには警察の立ち入り調査が行われる可能性があります。この調査は古物営業法に基づいており、古物商は協力義務を負います。適正な古物取引の維持や盗品の流通防止が目的で、警察の指示に従わないと罰則の対象となることもあります。
3.立ち入り調査の内容と対策
許可取得後の調査では、古物台帳や在庫品の管理状況が確認されます。商品が適正に管理され、盗品が含まれていないことを示すため、仕入れ先の信頼性や商品の出所に注意が必要です。調査に備えて、台帳や在庫リストを整え、迅速に提出できるようにしておくことが求められます。
4.立ち入り調査に備えた事前準備の重要性
警察の調査がスムーズに進むために、古物台帳や在庫リストなど必要書類を整え、許可証も提示できるようにしておくことが重要です。当事務所では、書類整備や管理方法のサポートを提供しており、立ち入り調査への準備をお手伝いしています。
5.調査中の対応姿勢と協力的な態度
調査中は警察の指示に従い、誠実な対応が求められます。質問に対しては正確かつ丁寧に答え、事実確認をする姿勢が信頼につながります。虚偽の回答には罰則があるため、正確な情報提供を心がけましょう。
6.トラブルが発生した場合の対処法と専門家のサポート
調査中に書類不備や記録ミスが指摘された場合は、素直に受け入れ改善策を講じることが大切です。古物営業法を事前に確認し、日々の業務を法令に沿って行うことがミスの防止につながります。行政書士のサポートを受け、書類管理や法令遵守について相談することで、安心して営業を続けられる体制が整います。