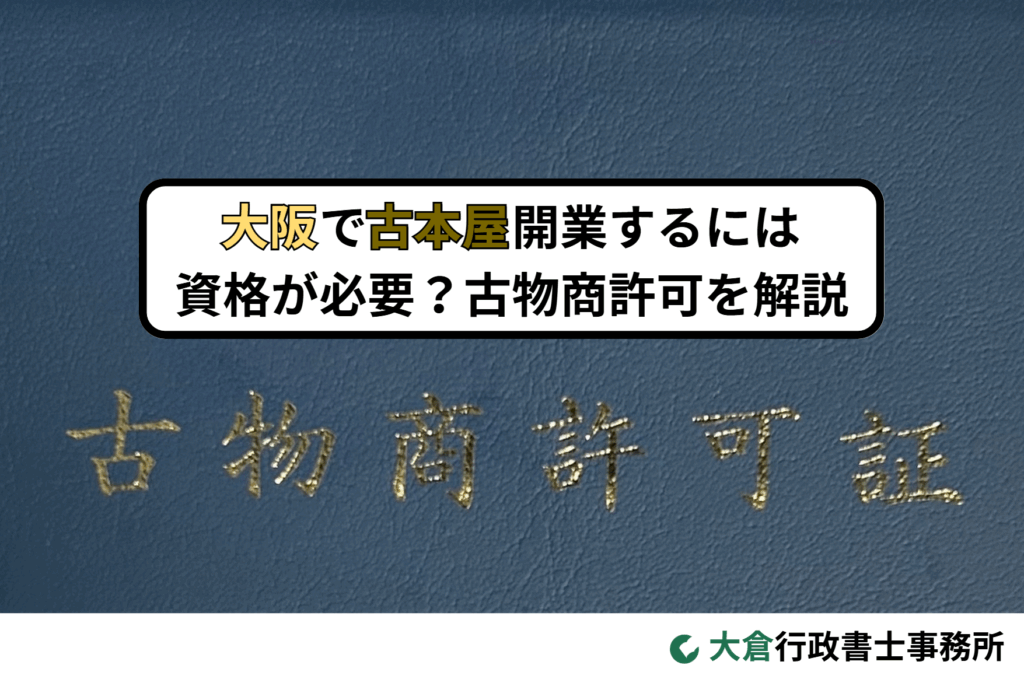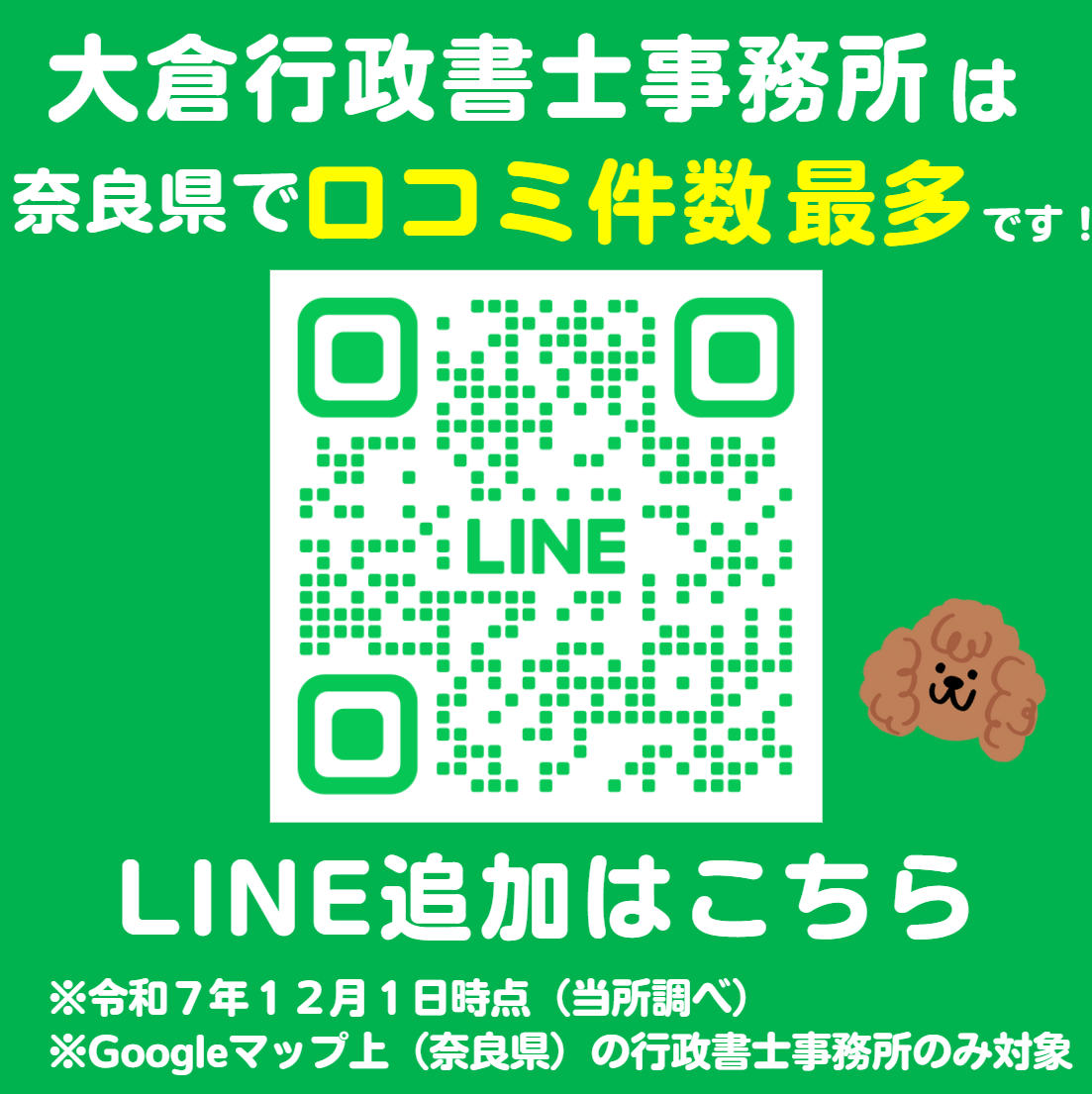「大阪で古本屋を開業したいけど、何から始めるかわからない。」このようにお考えの方は少なくありません。近年はフリマアプリやネットオークションの普及により、古本を含む中古品の転売ビジネスが副業としても人気を集めています。古本屋は好きな本に囲まれて仕事ができる魅力的なビジネスです。
古本屋は初期投資が比較的少なく始めやすいビジネスですが、その反面、法的な許可手続きをしっかり踏むことが成功への第一歩となります。
開業するには法律上クリアすべき条件がいくつかあります。結論から言えば、特別な国家資格は不要ですが、中古の本を取り扱うために「古物商許可」が必須です。
本記事では、古物商許可がなぜ必要なのか、取得する方法、そして行政書士に申請を依頼するメリットについて、大阪で開業を目指す皆さんに役立つ情報をまとめました。ぜひ最後までお読みいただき、開業準備の参考にしてください。
古本屋開業に必要な資格とは

古本屋を始めるにあたり、どんな資格や許可が求められるのでしょうか。基本的には古物商許可さえ取得すれば、法律上は誰でも古本屋を開業できます。反対に、この許可を持たずに営業することは違法となるため注意が必要です。以下では、古物商許可の必要性やその他の手続きについて説明します。
古物商許可は必須
古本屋を開業する場合、中古の本の仕入れ・販売を行うことになります。古物営業法では、中古品を転売目的で扱う事業者は古物商許可を取得しなければならないと定められています。
したがって、新刊書籍のみを扱う書店には不要ですが、一冊でも中古本を仕入れて販売するなら古物商許可が必須です。店舗販売はもちろん、フリマアプリやネットショップで継続的に古本を売る場合も対象となります。なお、許可を取得すれば古物市場(業者専用の中古品オークション)に参加できるようになるというメリットもあります。
古書業界では、業者市で希少本や大量の在庫を仕入れる機会も広がるため、許可を持っていることは仕入れルート拡大にも繋がります。
試験や特別な資格は不要
「古本屋を開くのに資格は必要?」と心配になる方もいますが、安心してください。古物商許可は警察からの営業許可であり、取得に際して難関の試験があるわけではありません。
古本屋開業自体に学歴や経験の資格条件はなく、所定の手続きを行えば基本的に誰でも許可を取得できます(後述の欠格事由に該当しないことが条件)。
つまり、司書や古書取引の資格などは必要なく、ビジネスとして成り立たせるための知識や熱意さえあれば開業可能です。ただし、本や古書に関する豊富な知識や目利きの力は、経営上の大きな強みになるでしょう。
個人事業の開業届も提出を
古物商許可とは別に、個人で古本屋を始めるなら税務署への開業届の提出も忘れないようにしましょう。開業届は事業開始から1か月以内に所轄税務署へ提出するもので、これにより正式に個人事業主として開業したことになります。
法律上の資格ではありませんが、税務上必要な手続きです。また、大阪府で開業する場合、屋号や事業内容を届け出ておくことで行政からの支援情報を得やすくなる場合もあります。まずは古物商許可の取得と開業届提出、この二つのステップを確実に踏みましょう。
【関連記事】
古物商で本の売買を始めたいなら古物商許可が必要です
なぜ古本屋に古物商許可が必要なのか

なぜ古本を扱うお店に古物商許可が求められるのでしょうか。その背景には、中古品取引ならではの社会的な理由と法律の規定があります。
ここでは古物商許可が必要とされる理由や、無許可営業のリスクについて解説します。
古物営業法による中古品取引の規制
古物商許可が必要なのは、古物営業法という法律で中古品の売買が規制されているためです。古物営業法は、盗品等の不正流通を防止し健全な中古市場を維持することを目的としています。
古本も法律上は「古物(=一度使用された物品)」に該当し、古本は古物の13品目区分の一つ「書籍類」に分類されます。そのため、営利目的で古本を仕入れて販売する営業を行う場合、事前に公安委員会(都道府県公安委員会)の許可を受けねばなりません。大阪府で開業する場合は、大阪府公安委員会の許可を所轄の警察署経由で取得することになります。
古物商許可が必要な場面
営利目的で継続的に古本を売買する場合はすべて古物商許可の対象です。例えば、大阪の店舗で古書を仕入れて販売するのはもちろん、倉庫や自宅を拠点にネット通販だけで中古本を売る場合でも許可が必要です。
副業であっても、利益を得る目的で定期的に古本を買い取り販売するなら法律上は開業とみなされます。一方、自分の読み終わった本をフリマサイトで単発で売る程度であれば事業とは言えないため許可は不要です。要するに、「ビジネスとして中古本を扱うなら許可必須、個人的な不要品処分なら不要」と覚えておきましょう。
また、古書業界では業者市で希少本や大量の在庫を仕入れる機会も広がるため、許可を持っていることは仕入れルート拡大にも繋がります。
無許可で営業するリスク
万が一、古物商許可を取らずに古本屋を営業した場合、法律違反による処罰を受けるリスクがあります。無許可営業が発覚すると、古物営業法違反で罰則が科される可能性があります(3年以下の懲役または100万円以下の罰金など)。
また、許可を掲示していない店はお客様からの信用も得られにくく、仕入れ先から取引を断られるケースも考えられます。中古書籍業界では古物商許可を持っていることが信頼の証にもなるため、リスクを避けるためにも必ず許可を取得してから営業を開始してください。
【関連記事】
古物商を持たずに営業してしまったら?
古物商を副業で取得するための手続ガイド
古物商許可の取得方法(大阪で古本屋を開業する場合)

古物商許可が必要なことは分かりましたが、実際にはどのように取得すれば良いのでしょうか。大阪で古本屋を開業する場合を想定し、許可取得の要件や申請手続きの流れを説明します。初めて手続きをする方にとって役所への申請は不安かもしれませんが、ポイントを押さえれば比較的スムーズに進められます。
許可取得の主な要件
古物商許可を申請するにあたって、まず申請者が一定の要件を満たしている必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- 申請者(または法人の役員)が成年(18歳以上)であること
- 申請者が以下のいずれにも該当しないこと(欠格事由の不存在)
⑴破産して復権を得ていない
⑵特定の犯罪で禁錮以上の刑に処され、刑期終了または執行猶予満了から5年を経過していない
⑶暴力団員またはその構成員である
⑷過去に古物商許可を取り消されてから5年を経過していない
⑸営業所となる場所を有していること(自宅を事務所とする形でも可)
これらの基本的な要件を満たせば、古物商許可の申請資格があります。なお、自宅で開業する場合は、賃貸物件なら賃貸契約書で事業用途が許可されているか、マンション等なら管理規約上問題がないかを確認しておきましょう。
学歴や職歴といった要件はないため、多くの方が該当するでしょう。ただし、古本や古書の知識が豊富であることやビジネスセンスは、経営を成功させる上で大いに役立ちます。
申請手続きと必要書類
古物商許可の申請は、営業所所在地を管轄する警察署で行います。大阪で開業するなら、店舗や事務所の所在地を所轄する警察署の生活安全課に申請書類を提出します。申請に必要な主な書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書(所定の様式)
- 略歴書(経歴を書いた書面)
- 誓約書(欠格事由が無いことを誓う書面)
- 住民票や身分証明書の写し(本人確認資料)
- 古物商許可申請手数料(大阪府の場合、19,000円の収入証紙)
書類を揃えて提出し、審査が行われます。なお、申請時には取り扱う古物の種類(区分)を選択します。古本屋の場合は通常「書籍」で申請しますが、中古ゲームソフトや雑貨など書籍以外の商品も扱う場合は、それらに該当する区分(例:道具類やその他の古物)も忘れずに申請しましょう。
審査期間は標準で約40日(営業日ベースで約1〜2か月)程度です。申請後、警察署の担当者による簡単な面談や営業所の確認が行われる場合もありますが、指示に従って対応しましょう。問題がなければ、期間経過後に公安委員会から許可がおり、晴れて古物商許可証が交付されます。
許可証は警察署で受け取り、営業所に掲示する必要があります。なお、申請の受付は平日の日中に限られるため、スケジュールに余裕を持って手続きを進めましょう。
許可取得後の遵守事項
古物商許可を取得した後は、営業者として守るべきルールがあります。特に重要なポイントを押さえておきましょう。
- 許可証の掲示
取得した古物商許可証は、古本屋の店内の見えやすい場所に掲示する義務があります。また、インターネット上で取引を行う場合は、ホームページ等に氏名(名称)・許可番号・許可公安委員会名を明示することが法律(2024年改正)で義務付けられました。
- 帳簿の備付け
古物台帳と呼ばれる取引記録簿を備え、古本の仕入れや販売の都度、日付・品目・相手先などを記録します。これは警察からの照会に応じるために必要です。
- 身分証の確認
買取を行う際には、売主の身分確認(氏名・住所・職業などの確認と記録)を行う義務があります。盗難本など不正品の流通防止のため厳守しましょう。
- 許可内容の変更届出
営業所の名称・住所変更や、取扱品目を追加する場合など、許可内容に変更が生じた際は警察署へ届け出が必要です。
以上のような遵守事項を守り、適法に営業することで、安心して古本屋を継続できます。法律を守ることはお客様の信頼にもつながります。
【関連記事】
古物商の住所変更の方法 徹底解説
古物商許可申請を行政書士に申請を依頼するメリット

古物商許可の申請は自分でも可能ですが、手続きを専門家に任せる選択肢もあります。大阪には古物商許可申請を得意とする行政書士も多く、プロに依頼することでスムーズに許可を取得できるメリットがあります。ここでは、行政書士に申請手続き代行を依頼する利点を紹介します。
複雑な書類作成も専門家なら安心
古物商許可申請では提出書類が多く、初めての方には記入内容や添付書類の準備が煩雑に感じられるでしょう。行政書士は許可申請の専門家であり、書類作成を正確かつ漏れなく行ってくれるため安心です。
自身では迷いがちな部分もプロのサポートで確実に準備できます。不備による再提出を防ぎ、一度で申請が通るよう適切に書類を整えてもらえるのは大きな利点です。
手続きがスムーズで時間短縮に
仕事をしながら副業で古本屋を始める方や、開業準備で忙しい方にとって、役所への申請手続きは時間と手間がかかるものです。行政書士に依頼すれば、警察署での手続きや役所とのやり取りを代行してもらえるため、自分の時間を節約できます。
委任状を用意すれば警察署への申請書類提出も行政書士が代理で行ってくれるので、平日に警察窓口へ出向く必要もありません。
申請に必要なやり取りや日程調整もプロに任せられるので、開業準備に専念できるでしょう。また、行政書士は申請先の大阪府警のローカルルール(地域特有の注意点)にも通じているため、つまずきがちなポイントもクリアしやすく、結果的に許可取得までのスピードが早まることが期待できます。
信頼性の向上と安心感
行政書士に手続きを依頼することは、単に楽になるだけでなく開業までの安心感にもつながります。許可取得まで専門家が伴走してくれることで、法的に漏れのない開業準備ができているという自信を持てます。
また、行政書士から古物営業の注意点や運営上のアドバイスをもらえるケースもあり、開業後のトラブル防止にも役立ちます。お客様や取引先に対しても「必要な許可を専門家の力も借りて確実に取得している」ことは信頼材料となるでしょう。
なお、行政書士へ依頼する際には報酬として5万円程度の費用がかかります。しかし、プロのサポートによって得られる安心感と時間短縮の効果を考えれば、十分検討に値すると言えます。
以上のように、古本屋開業に際して古物商許可申請を行政書士に依頼するのは、多忙な個人事業主や副業希望者にとって賢い選択と言えます。大阪で古物商許可の取得に不安がある方は、当行政書士への相談も検討してみてください。
大阪で古本屋を開業する際の古物商許可申請はお任せください
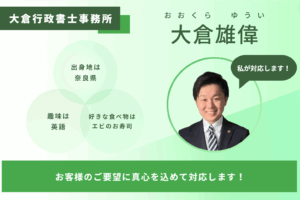
古本屋の開業には、古物営業法に基づく「古物商許可」が欠かせません。
とくに大阪府内での申請では、警察署とのやりとりや地域特有の注意点を押さえておく必要があり、初めての方にとっては不安や手間が伴う場面も少なくありません。
当事務所では、古物商許可申請に関する豊富な実績と地域対応の経験を活かし、スムーズな取得を全力でサポートしております。書類の作成から警察署とのやり取りまで、安心してお任せいただける体制を整えておりますので、はじめての方でも安心です。
特に次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。
- 古本屋を開きたいが、何から始めればよいかわからない
- 警察署に何をどう提出すればいいのか不安
- ネット販売もしたいが、必要な手続きが分からない
- 副業として自宅で始める予定だが許可が必要か判断できない
- 忙しくて申請書の作成や窓口対応に時間が割けない
ご相談はメールや電話などで対応可能です。大阪市内はもちろん、府下全域や奈良エリアにも対応しております。「安心して古本屋を始めたい」「確実に古物商許可を取得したい」とお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。開業の第一歩を、確かな手続きでしっかりサポートいたします。

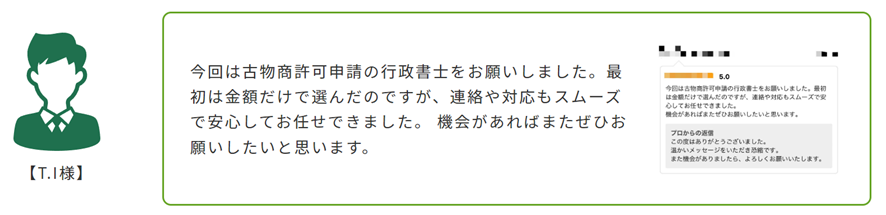

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能
古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能
当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、大阪市や大阪府をはじめ、奈良県、兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
【大阪府警】
古物商許可申請