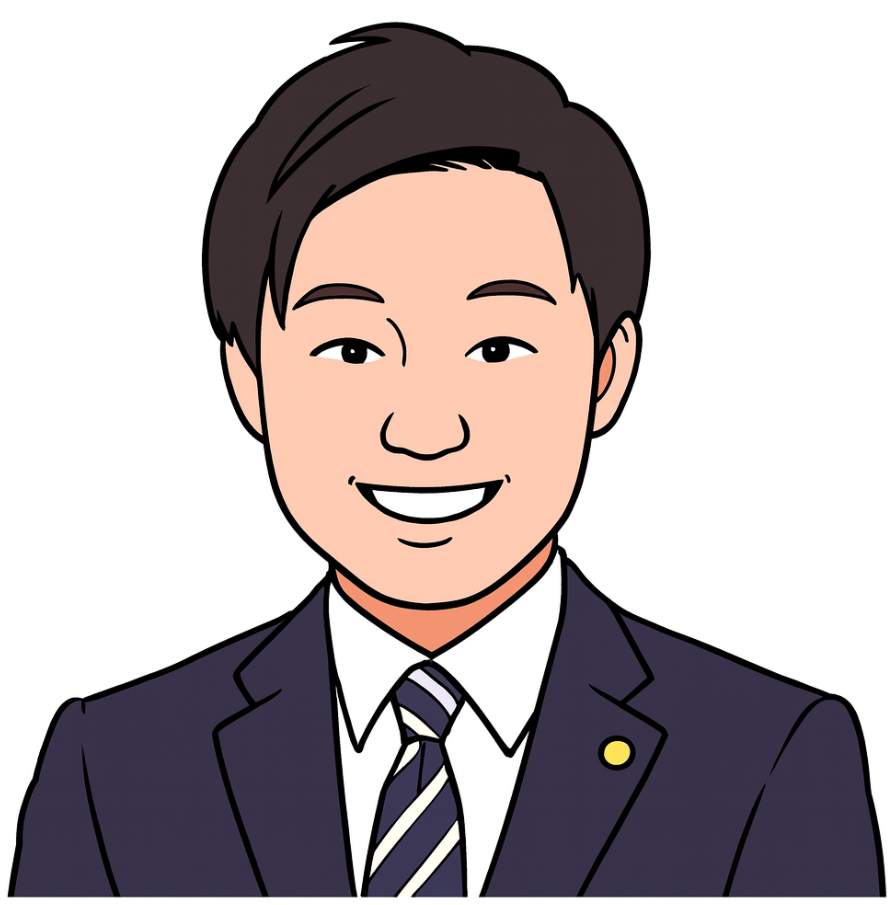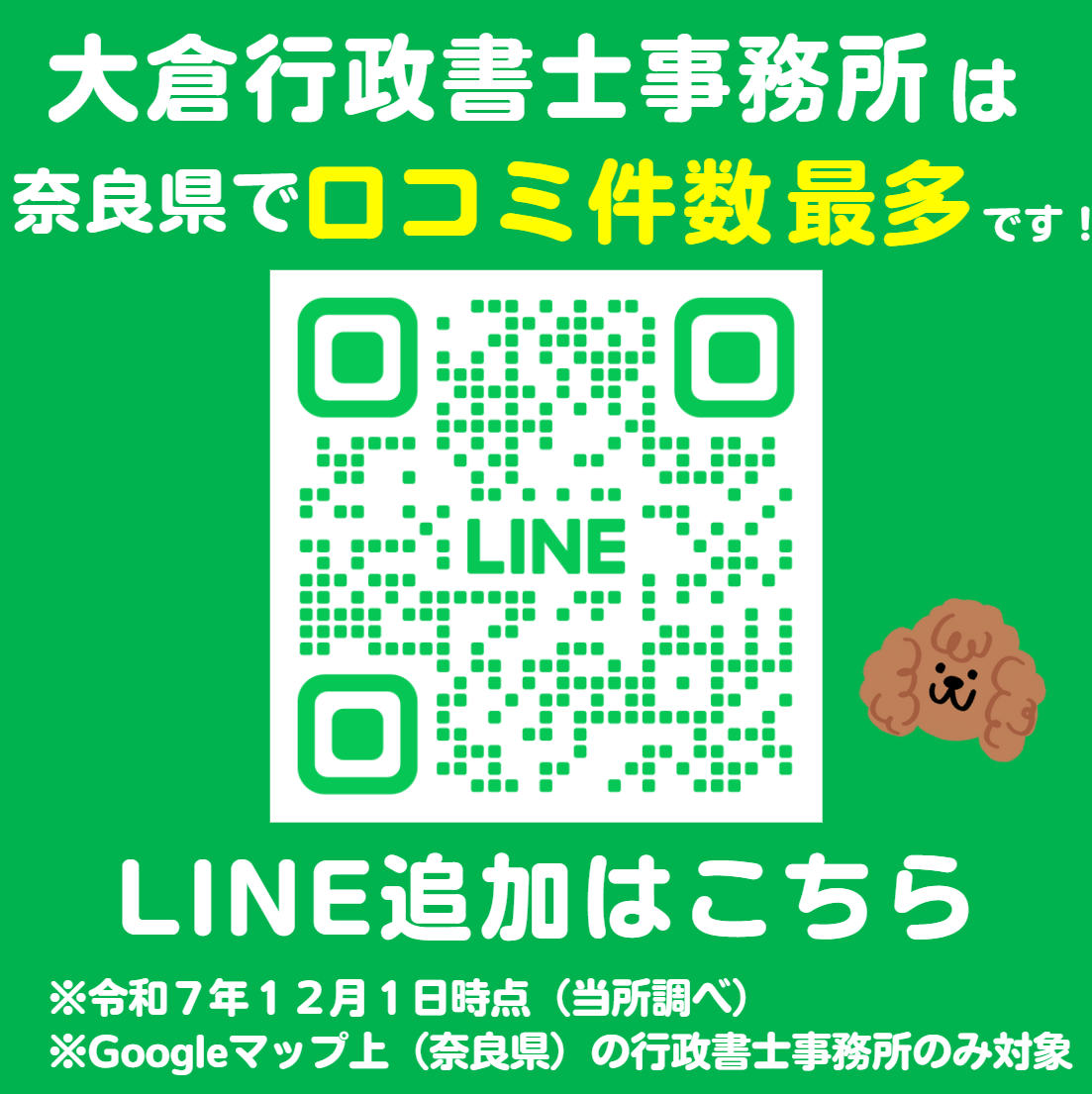古物商を法人として取得する場合、許可の取り方を知っておくことは重要なステップとなります。こちらの記事では、法人が古物商の資格を取得するために必要な手続きや書類について、詳しく解説していきます。
法人申請のプロセスを理解し、スムーズに申請が進むことを願っています。もし申請が難しいと感じた場合は、当事務所や行政書士に依頼することもできますので、ぜひご相談ください。
古物商の取り方【法人編】
下記では、個人と法人の違い、法人の種類について解説させていただきます。
個人と法人の違い
| 個人とは:個人事業主や副業として古物を扱う個人を指します。つまり、会社を設立せず、自己名義で事業を行う形態です。 法人とは:法務局に登記を行った会社や団体を指します。登記とは、法人の設立や変更、解散などを法務局に登録し、公的に認められた状態を指します。 |
法人の種類

法人とは、法務局に登記された法人格を持つ団体を指します。法人は法人格を有することにより、個人とは異なる法的に独立した存在として事業を行うことができます。現在、日本には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの主要な法人形態がありますが、その中で特に多くの法人が株式会社で占められているとされています。
実際には、株式会社が法人全体の約90%を占めているとされることから、株式会社という法人形態は非常に一般的で、皆様もよく耳にすることが多いかもしれません。
法人で古物商を取得する際の必要書類
法人で古物商を取得するには、通常個人申請で必要となる書類以上の書類が必要となります。まずは、これらの書類について述べさせていただきます。
- 別記様式第1号その1(ア)
法人の名称や所在、主に取り扱う区分、代表者の情報を記載します。 - 別記様式第1号その1(イ)
法人に代表者以外に役員がいる場合には役員の氏名、生年月日、住所等を記載します。 - 別記様式第1号その2
主たる営業所の名称、所在地、取り扱う区分(複数可)、管理者の氏名、生年月日、住所等を記載します。 - 別記様式第1号その3
その他の営業所(主な営業所以外に営業所がある場合に記載します。) - 別記様式第1号その4
インターネットホームページを用いる場合に、送信元識別符号(URL(ドメイン))を記入します。用いない場合は「用いない」記載を要します。 - 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
会社の基本事項(商号、本店、役員など)を証明するもので、法務局で誰でも取得できます。つまり、自社の証明書だけでなく、他社の証明書も取得可能です。 - 法人の定款
法人の定款は、法人の目的、組織、活動に関する基本規則をまとめた書類です。法人を設立時に必ず作成する必要があります。 - 住民票
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。 - 身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で扱っています。 - 略歴書
最近5年間の略歴を記載します。5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。 - 誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方は、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出します。 - URLの届出書
ウェブサイトを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ウェブサイト等のURLの届け出が必要です。
個人と法人で異なる書類

法人が古物商許可を申請する際には、個人が申請する書類に追加して書類が必要です。
特に、定款や登記簿謄本といった書類の追加が求められます。
個人の場合の書類
個人が古物商許可を申請する場合、申請書と申請者や管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書が主な書類となります。特に、個人の古物商許可では、添付書類の書類が申請者だけであったり、申請者と管理者のそれぞれ1通ずつ提出すれば済むことが多いです。このため、個人での申請では書類の量が比較的少なく、手続きがスムーズに進むことが一般的です。
法人の場合の書類
一方で、法人で古物商許可申請をするには、以下のような法人特有の書類が必要となります。
- 登記簿謄本
法人が古物商許可を取得する際には、「登記簿謄本」が必要です。登記簿謄本は正式には「履歴事項全部証明書」と呼ばれ、法人の設立から現在に至るまでの事項が記載されています。これは法人の基本情報を証明する重要な書類で、法務局で発行してもらうことができます。取得には通常600円の手数料がかかり、全国の法務局で入手可能です。手続き自体は、法務局で印紙を購入して申請するだけですので、比較的簡単です。 - 定款
定款は法人の設立や運営に関する基本的な規定が書かれた文書です。古物商許可申請においては、定款の内容が最新である必要があります。つまり、法人設立時に作成された原始定款ではなく、最近の株主総会や取締役会での決議内容が反映された最新の定款を提出することが求められます。申請時には「現在の内容と相違がない」といった原本証明を求められることが多いです。このため、古い定款を提出すると警察署のローカルルールにより申請が受理されない可能性があるため注意が必要です。
書類の量と準備
法人の申請では、役員全員の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要となるので、個人申請と比べて書類の量が多くなることが一般的です。これにより、書類の準備や確認に時間と手間がかかることがあります。
古物商許可を法人で取る場合の流れ

古物商の資格を法人として取得する際は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で手続きを行います。申請自体は比較的容易ですが、警察署ごとに異なるローカルルールが存在するため、注意が必要です。申請から許可取得までには通常2~3ヶ月程度の期間がかかるため、計画的に進めることが大切です。申請の流れは以下の通りです。
ステップ1: 警察署での事前相談
申請に先立ち、警察署で事前相談を実施します。これにより、必要な書類や申請手続きに関する詳細な情報を得て、スムーズな申請準備が可能となります。
ステップ2: 添付書類の準備
申請に必要な添付書類を集めます。法人の場合には個人の場合と異なり追加の書類が必要となりますので注意が必要です。
ステップ3: 申請書の記入
古物商許可申請書に必要事項を記入します。申請書には、事業内容や営業所の情報、代表者の詳細などを正確に記入することが求められます。
ステップ4: 警察署に申請書を提出
完成した申請書と添付書類を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。申請の際には、窓口での確認や質問に対応することが必要です。
ステップ5: 許可証の受領
申請が受理されると審査が行われます。審査に通過すれば、古物商許可証が発行されます。許可証を受け取った後、正式に古物商としての営業を開始することができます。
法人で古物商を取得する際の注意点
定款又は登記簿謄本の目的事項
法人が古物営業を行うためには、管轄の警察署に定款や登記簿謄本を提出する必要がありますが、これらの書類に記載する内容については十分な注意が求められます。特に「事業の目的事項」の記載に関して、以下のポイントに気を付ける必要があります。
目的事項
古物商許可を取得するためには、法人の定款や登記簿謄本に古物商の営業を行う旨の記載することが求められます。この記載により、法人が古物商としての営業範囲や区分を自由に選ぶことが可能になります。例えば、古物の売買全般を行いたい場合には、目的事項に「古物営業法に基づく古物商」のような記述が必要です。
逆に、目的に古物商に関する記載が全くない場合、法人として古物商許可が受理される可能性は低くなります。また、目的に「自動車の売買と修理」のように特定の分野のみが記載されている場合、古物営業がその分野に限定されることになります。つまり、法人が自動車以外の古物を取り扱いたい場合には、目的を変更するための登記や定款の修正が必要になります。
このように、古物商許可の取得には、定款や登記簿謄本における事業の目的の記載内容が重要であり、事前に正確に確認し、必要に応じて修正手続きを行うことが求められます。法人の目的事項の変更について下記で詳しく解説しております。
営業所から自宅が遠い場合
法人代表者が営業所の管理者となる場合、営業所と代表者の自宅が大きく離れていると、古物商営業における常駐義務を満たすことが難しくなる場合があります。例えば、代表者が和歌山に自宅を持っており、大阪で古物商を始める場合を考えてみましょう。和歌山と大阪では距離があるため、代表者が大阪の営業所に常駐するのが現実的に難しいと判断される可能性があります。このような場合、古物商許可が取得できないリスクが高まります。
しかし、代表者が大阪に住民票を移していない場合でも、営業所に通うための証明ができれば、許可が受理される場合もあります。例えば、大阪の居住地を示す書類(例えば、公共料金の請求書や賃貸契約書など)を提出し、営業所への通勤が実際に可能であることを証明する必要があります。これにより、大阪の営業所に常駐することが可能であることを示すことができます。
それでも最も確実な方法は、和歌山から大阪に住民票を移すことです。住民票を大阪に移すことで、営業所と自宅の距離に関する問題が解消され、常駐義務が果たせることが明確になります。これにより、古物商許可の取得がスムーズに進む可能性が高くなります。
個人から法人へ古物商を変更(法人成り)するには

個人事業主が古物商を営んでいる場合、法人化(法人成り)を進めることができます。法人成りにおいては、法人としての古物商許可を取得するためにいくつかの手続きや注意点があります。ここでは、法人成りのプロセスと留意点について詳しく解説します。
法人成りとは
法人成り(法人化)とは、個人事業主が株式会社や合同会社などを設立し、既存の事業を法人として引き継ぐことを指します。これは、個人事業主が法人という形に「成る」ことで、法的な地位や税務上の扱いを変えることを意味します。法人化により、個人の資産と法人の資産が分けられるため、リスク管理や事業の拡張に有利です。
法人成りの注意点
- 法人の許可取得までの営業
個人事業主としての古物商許可を持っている場合、法人許可を申請した後(審査期間中)、個人として営業を続けることが可能です。ただし、法人の古物商許可が下りた際には、個人の古物商許可証を返納する必要があることが多いです。ただし、法人と個人の両方で許可を維持することも可能です。その場合には営業所の管理者を分けるなどの工夫が求められます。営業所の管理者にはその営業所に通う義務があるからです。 - 売上の明確化
法人成り後は、個人事業主としての売上と法人としての売上を明確に分けることが重要です。法人としての売上を個人事業主として計上することは避け、法人の帳簿に正確に記録する必要があります。 - 営業所の管理
法人化に伴い、営業所の管理が重要です。法人の古物商許可を取得する場合、営業所の管理者が必要となります。営業所の管理者は、古物営業をする際には常駐する必要があるため、営業所を複数設ける場合には、それぞれの営業所に別の管理者を配置することが求められます。
法人成りにはメリットが多い一方で、手続きや管理の面での注意点もあります。適切に対応することで、スムーズに法人化を進めることができるでしょう。
法人で古物商を取得する際には目的事項の変更を要する場合がある

法人で古物商を取得するには、定款や登記簿謄本の目的事項を変更する必要がある場合があります。
下記では、登記簿謄本の目的事項の変更について解説します。
目的事項の変更とは
法人の目的事項の変更とは、法人の定款に記載された事業内容や目的を変更することを指します。目的事項は法人が行う事業の範囲を定めるものであり、法人は、通常この範囲内で活動します。事業内容が変わる場合や新たな事業を追加する場合には、目的事項の変更が必要となります。
目的事項の変更後は登記が必要
目的事項を変更した場合、変更内容を登記簿に反映させるために、目的変更登記を行う必要があります。期間は、効力発生日から2週間以内と会社法会社法第915条1項により定められています。この手続きを行うことで、法人の事業内容が正確に示すことができ、信頼性の確保や取引の円滑化が図れます。
法人で古物商を扱う場合の目的事項
法人が古物商を取り扱う場合、その目的事項には「古物営業法に基づく古物商」などが含まれる必要があります。古物商としての業務内容を明確に記載し、定款や登記簿に反映させることが求められます。
目的事項の変更には株主総会が必要
目的事項を変更するには、株主総会の開催と特別決議が必要です。株主総会での特別決議には、発行済株式の過半数を有する株主の出席と、議決権の3分の2以上の賛成が求められます。株主総会での決議後、変更登記に必要な書類(株主総会議事録、株主リストなど)を整え、法務局に申請することで、正式に目的事項の変更が完了します。
| 【参考】 >商業・法人登記の申請書様式 – 法務局 >株式会社変更登記申請書 – 法務局 |
古物商の取り方【法人編】よくある質問と回答
Q1.法人成りに際して個人の古物商許可証はどうなるのか?
法人成りに伴い、法人の古物商許可を取得した際には、通常、個人の古物商許可証を返納する必要があります。ただし、法人と個人の両方で許可を維持することも可能ですが、その場合には営業所の管理者を分けるなどの工夫が求められます。
Q2.法人成りの際に法人の古物商許可の申請中に個人の古物営業を続けることは可能か?
はい、法人の古物商許可申請中でも、個人事業主として事業を続けることは可能です。
Q3.法人成りに伴い、営業所の管理者はどのように選定すればよいか?
法人成り後、営業所の管理者は、営業所に常駐する必要があります。複数の営業所を持つ場合は、それぞれの営業所に別の管理者を配置することが必要です。
Q4.定款や登記簿謄本の内容に関する注意点は?
定款や登記簿謄本には、法人が古物商として営業を行う旨(目的事項)の記載が必要です。記載内容が不十分または古い場合、古物商許可の取得が難しくなる可能性があります。
Q5.法人成りに伴い、法人設立にかかる費用はどのくらいか?
法人設立には、登記費用や定款認証費用などがかかります。登記簿謄本の取得には600円の手数料がかかり、定款の認証費用は会社の種類によって異なります。
Q6.法人成りの際、法人の事業目的に古物商が含まれていない場合、どうすればよいか?
法人の事業目的に古物商が含まれていない場合、定款や登記簿謄本の内容を修正する必要があります。具体的には、法人の目的に「古物商」を含めるように修正手続きを行います。
Q7.営業所と自宅が遠い場合、どう対処すればよいか?
営業所と自宅が大きく離れている場合、営業所に常駐する義務が果たせない可能性があります。この場合、営業所への通勤が可能であることを証明する書類(公共料金の請求書や賃貸契約書など)を提出することが推奨されます。最も確実なのは、自宅の住民票を営業所の所在地に移すことです。
Q8.法人成り後、古物商の許可が下りるまで個人の古物商許可証を使用しても問題ないか?
法人成り後、法人の古物商許可が下りるまでの間、個人の古物商許可証を使用して事業を続けることは可能ですが、法人許可が下りた際には、個人の許可証を返納する必要があります。(ただし、管理者を別にする場合にはそれぞれ維持することも可能です。)
Q9.法人成り後、法人が古物商を運営する際の必要な許可や登録は?
法人成り後、法人が古物商を運営するためには、古物商許可証を新たに取得する必要があります。また、法人の営業所や管理者に関する規定も守る必要があります。
Q10.法人成りの際、古物商許可を取得するためにどのような専門家に相談すればよいか?
法人成りや古物商許可の取得については、行政書士に相談することできます。申請書類の準備や手続きに関するアドバイスを提供してくれます。
| 【おすすめの記事】 >古物商の資格を取得したい! 難易度はどれくらい? >古物商を副業で取得するための手続ガイド |
古物商許可は当事務所にお任せください!
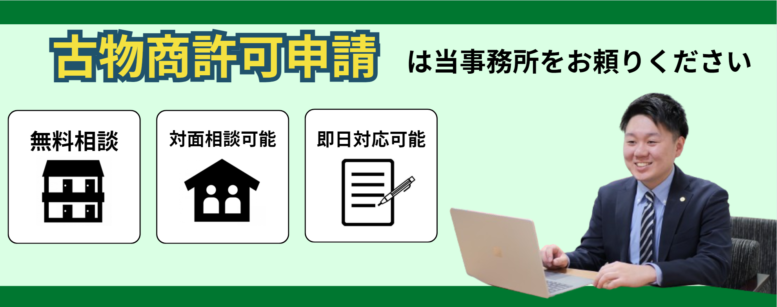
当事務所による代行サービスでは、古物商許可の取得に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請において確固たる実績を有しています。私たちのサービスは、お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、手続き全般をお手伝いいたします。また、当サービスでは不許可の場合に備えて返金保証を提供しております。
さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

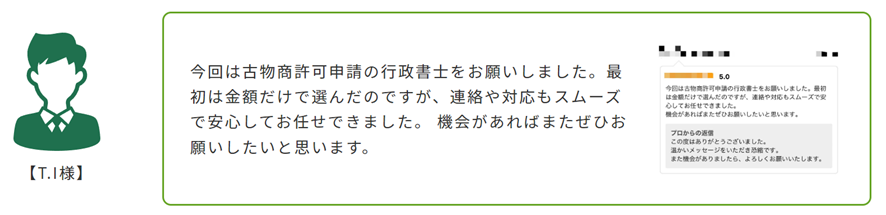

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様(法人の場合は代表者様もしくは従業員の方)のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商の取り方【法人編】必要書類等を徹底ガイド-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では法人の古物商許可の取り方について取得するための手続きの流れや注意点について詳しく解説します。
1.古物商の取り方【法人編】
⑴個人と法人の違い
個人: 個人事業主として自己名義で事業を行います。法人を設立せずに運営する形態です。
法人: 法務局に登記された法人(会社や団体)で、法人格を持つ団体を指します。法人は法的に独立した存在として事業を行います。
⑵ 法人の種類
法人には主に以下の4つの形態がありますが、最も一般的なのは株式会社です。
株式会社: 法人全体の約90%を占める、一般的な法人形態。
合同会社、合資会社、合名会社: その他の法人形態で、それぞれ異なる特性があります。
2.法人で古物商を取得する際の必要書類
法人で古物商を取得するためには、以下の書類が必要です。個人申請よりも多くの書類が要求されます。
- 別記様式第1号その1(ア): 法人の名称、所在、代表者の情報など。
- 別記様式第1号その1(イ): 役員の氏名、生年月日、住所など。
- 別記様式第1号その2: 主たる営業所の情報。
- 別記様式第1号その3: その他の営業所の情報(該当する場合)。
- 別記様式第1号その4: インターネットホームページのURL(使用する場合)。
- 法人の登記事項証明書(登記簿謄本): 会社の基本事項を証明する書類。
- 法人の定款: 法人の目的、組織、活動に関する基本規則。
- 住民票: 代表者の住所を明らかにするためのもの。
- 身分証明書: 従前の例による準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する書類。
- 略歴書: 最近5年間の略歴を記載したもの。
- 誓約書: 古物営業法第4条に該当しない旨を誓約する書面。
- URLの届出書: ウェブサイトでの取引を行う場合のURL届け出書。
個人と法人で異なる書類
個人の場合: 申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書。
法人の場合: 追加で登記簿謄本や定款が必要です。
3.法人で古物商を取得する際の注意点
定款または登記簿謄本の目的事項
目的事項: 法人の定款や登記簿謄本に古物商の営業を行う旨を記載することが必要です。これにより、法人が古物商としての営業範囲を自由に選べるようになります。
営業所から自宅が遠い場合: 営業所と代表者の自宅が大きく離れていると常駐義務を果たせない可能性があります。この場合、営業所への通勤が可能であることを証明する書類の提出や、住民票の移動が推奨されます。
4.個人から法人へ古物商を変更(法人成り)するには
⑴法人成りとは
法人成り: 個人事業主が法人(株式会社など)を設立し、既存の事業を法人として引き継ぐこと。
⑵ 法人成りの注意点
法人の許可取得までの営業: 法人成り後も、個人事業主としての営業を続けることが可能です。ただし、法人許可取得後は個人の許可証を返納する必要があります。
売上の明確化: 法人成り後は、個人と法人の売上を明確に分けることが重要です。
営業所の管理: 営業所の管理者は常駐が必要です。複数の営業所がある場合は、各営業所に管理者を配置する必要があります。
5.法人で古物商を取得する際には目的事項の変更を要する場合がある
⑴目的事項の変更とは
目的事項の変更: 法人の定款に記載された事業内容を変更することです。新たな事業を追加する場合には、目的事項の変更が必要です。
⑵目的事項の変更後の登記
変更登記: 目的事項を変更した場合、変更内容を登記簿に反映させるために目的変更登記が必要です。手続きは効力発生日から2週間以内に行う必要があります。
6.よくある質問と回答は前記トピックをご確認ください。
| 【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 |