古物商として営業を行うには、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県の公安委員会から許可を取得する必要があります。多くの行政手続きがオンライン化される中、「古物商」の許可申請についてはオンライン申請ができないのが現状です。古物商許可申請は、対面でのみ受け付けられ、直接警察署に出向く必要があります。申請には厳格な本人確認や書類審査が求められるため、申請をスムーズに進めるには事前準備が重要です。
この記事では、古物商許可申請のプロセスや注意点について詳しく解説します。スムーズに許可を取得するためのポイントも併せて紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
古物商について

古物商として営業を行うには、まず営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県の公安委員会から正式な許可を取得する必要があります。この許可を得ることにより、古物の売買や交換、委託販売などの事業を法的に行うことが可能となります。また、許可を取得した後も、定期的な報告義務や帳簿の適切な管理が求められ、法律に基づいた厳格な運営が必要です。
古物商はこんな時必要
- 個人や企業がリサイクル品を買取り、販売する際
- 中古品を扱う店舗やオンラインショップを運営する場合
- 骨董品や美術品、ジュエリーなどの高価な中古品を取り扱う業務を行う時
- 不用品回収業者として、顧客から買取った品物を再販売する際
- フリーマーケットや蚤の市で中古品の販売を定期的に行う場合
このように、古物商の許可は、中古品を取り扱うあらゆる場面で必要となり、事業の安定的な運営と法令遵守のために欠かせない要素となります。
| 【おすすめの記事】 >古物商の資格を取得したい! 難易度はどれくらい? >古物商を副業で取得するための手続ガイド |
古物商のオンライン申請はできない

古物商許可申請は、現在においても依然として対面式または郵送による申請方法が一般的です。多くの行政手続きがデジタル化され、オンラインで完結することが可能となっている中、古物商許可申請はオンライン化が進んでいないのが現状です。その背景には、いくつかの重要な理由があります。
まず、本人確認の厳格性が挙げられます。古物営業は、盗品が市場に流通するのを防ぐという観点から、非常に厳格な本人確認が求められます。これには、申請者が確実に申告者本人であることを確認する必要があり、オンラインでの本人確認では偽造やなりすましのリスクが高まる可能性があるため、対面での厳格な確認が求められています。
次に、書類の複雑性が挙げられます。古物商許可申請には、多岐にわたる書類が必要で、それらの書類には専門的な知識を持つ担当者による確認が不可欠です。例えば、申請書、誓約書、略歴書などいずれも正確かつ詳細な内容が求められます。これらをオンラインで適切に提出し、確認するシステムを構築することは、技術的にも、運用面でも非常に難しいとされています。
さらに、地域ごとの規制の違いも問題です。都道府県ごとに古物商許可に関する細かな規制や要件が異なるため、全国的に統一されたオンライン申請システムを導入することが困難と考えられます。たとえば、ある都道府県では提出書類の形式や内容が他の地域と異なる場合があり、こうした違いをすべて包括できるシステムを構築するには膨大なコストと時間がかかるでしょう。
これらの理由から、古物商許可申請は依然として対面による方法が主流であり、申請者は事前に十分な準備を行い、必要な書類を確実に揃えて申請を行うことが求められます。
古物商許可申請に必要な書類や申請手順

古物商の営業許可を取得するには、所定の書類を準備し、適切な手続きを踏むことが求められます。申請書は申請する都道府県の警察署で入手することが一般的ですが、事前に公式サイトからダウンロードできます。以下に、具体的な必要書類と申請手順について詳しく説明します。
必要な書類について
申請には主に以下の書類が必要です。これらの書類は、申請者の身元や適格性を確認するために提出を要求されます。
- 古物商許可申請書
申請者の基本情報や事業内容を記載する書類です。正確かつ詳細に記入する必要があります。 - 住民票の写し
申請者本人の住民票です。記載内容にマイナンバーが含まれていないものが求められます。発行日から3ヶ月以内のものを準備しましょう。 - 身分証明書の写し
本籍地の役所が発行する書類で、破産宣告を受けていないことなどを証明します。 - 誓約書
古物営業法に基づく欠格事由に該当しないことを誓う書類です。自ら署名して提出する必要があります。 - 略歴書
直近5年間の職歴や経歴を記載した書類です。正確な期間や職歴を記入する必要があります。
法人申請の場合には、上記の書類の他に会社の定款や登記簿謄本が必要となります。詳しい書類は警察署に事前に確認されることを推奨します。
古物商許可申請の手順
古物商許可の申請から許可取得までの一般的な流れは以下の通りです。オンライン申請ができないため、書類を整えたうえで、申請者本人が警察署に出向いて手続きを行う必要があります。
- 事前準備:必要書類の収集と記入
まず、上記で説明した各書類を集め、必要事項を記入します。不備があると申請が受理されないため、慎重に準備しましょう。 - 申請書類の提出:最寄りの警察署へ持参
準備した書類一式を、申請者自身が管轄の警察署に持参します。 - 申請手数料の支払い
申請時、書類に問題がなければ指定された手数料を支払います。 - 審査:書類審査と必要に応じた実地調査
提出された書類をもとに、警察による審査が行われます。場合によっては、営業所の実地調査が行われることもあります。 - 結果通知:許可または不許可の通知
審査が完了すると、許可が下りるかどうかの通知が来ます。通常、申請から結果が出るまでには約40日かかることが一般的です。 - 許可証の受け取り
許可が下りた場合、警察署から許可証を受け取ります。これで正式に古物商として営業を開始することができます。
各段階での留意事項
書類提出前に、不備や誤りがないかをしっかりと確認することが大切です。特に、記入漏れや誤字脱字があると申請が受理されない場合があるため、提出前に書類を何度も見直し、正確に記載されているかを再確認しましょう。また、申請書類を提出した後、審査が進む中で、追加の資料や補足情報の提出を求められることがあります。これに迅速に対応することで、手続きをスムーズに進めることができます。そのため、審査期間中は常に連絡を取れる状態を保ち、追加の要求に即応できる準備をしておくことが重要です。
| 【関連記事】 >古物商許可を個人事業主として取得する方法 >古物商の取り方【法人編】必要書類等を徹底ガイド |
古物商許可の欠格要件
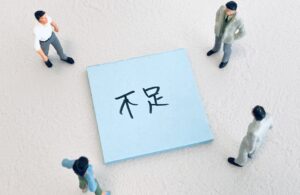
古物商許可を取得するには、申請者やその関係者が法律で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。個人の場合は申請者本人と古物商の管理者、法人の場合は役員や管理者全員が対象となります。これらの欠格事由に該当すると、申請しても許可が下りません。
古物営業法第4条に規定された欠格事由
| 1.破産手続開始の決定を受けて復権していない者 破産してまだ復権していない場合は許可が得られません。 2.一定の刑罰歴がある者 禁錮刑や懲役刑を受けた場合や、無許可営業や窃盗、背任、盗品の譲受けなどで罰金刑を受けた場合、執行が終了してから5年経過しない限り許可は得られません。また、執行猶予がある場合は、その期間が終了しないと申請ができません。 3.暴力団員やその元構成員 現役の暴力団員はもちろん、過去に暴力団員であった者も、脱退後5年間は許可を取得できません。さらに、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強い反社会的行動が認められる場合も該当します。 4.住居が定まらない者 住所が不明確であったり、住民票が確認できない場合も欠格要件に該当します。 5.古物営業法違反での許可取消し歴がある者 過去に古物営業法に違反して許可を取り消された場合、その取消しから5年が経過しないと再申請はできません。 6.精神障害により適正な営業が困難な者 精神疾患により業務の適正な遂行が難しいと判断される場合も許可が下りません。 7.未成年者 原則として未成年者は許可を取得できませんが、例外として、婚姻している未成年者や、法定代理人から営業許可を得ている場合は申請可能です。証明書類が必要となります。 |
具体的な対応について
特に刑罰歴がある場合や、欠格要件に該当するかどうか判断が難しい場合、申請予定の警察署で事前に確認することをお勧めします。また、未成年者が役員に就任している法人の場合も、例外的なケースとして事前相談が必要です。
以上の内容を把握した上で、申請を円滑に進めるため、必要な確認や準備を行いましょう。
古物商許可は当事務所にお任せください!
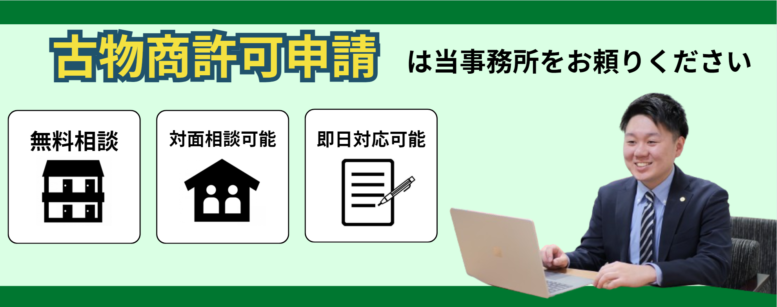
当事務所の代行サービスでは、古物商許可の取得に関する専門知識と豊富な経験を基に、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請をサポートしており、多くの実績を誇っています。古物商の許可申請はオンラインではできず、申請者が直接警察署に出向く必要があるため、手続きに不安を感じる方も多いかと思います。そこで当サービスでは、お客様がスムーズに許可を取得できるよう、書類作成から提出まで一括してお手伝いし、手間を最小限に抑えることが可能です。
また、不許可の場合には返金保証も提供しており、安心してご利用いただけます。口コミでの評価も高く、150件以上の口コミと総合評価4.9/5を獲得しており、多くの方から信頼されている実績のあるサービスです。オンライン申請ができない分、当事務所にお任せいただければ、確実で効率的な古物商許可取得を実現します。どうぞお気軽にご相談ください。

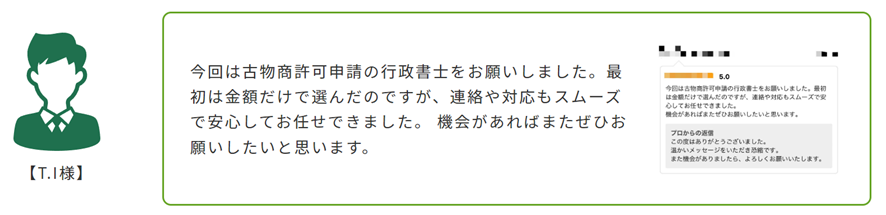

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商はオンライン申請できる?-よくある質問
Q.古物商許可はオンラインで申請できますか?
A.いいえ、古物商許可はオンラインで申請することはできません。申請は対面で行う必要があり、管轄の警察署に直接出向く必要があります。
Q.古物商の許可を取得するにはどのような手続きが必要ですか?
A.必要な書類を揃え、申請者本人が警察署で申請を行います。申請書、住民票、身分証明書、誓約書、略歴書などの提出が必要です。
Q.古物商許可申請の手数料はいくらですか?
A.古物商許可申請の手数料は19,000円です。
Q.古物商許可が必要な場合はどのような状況ですか?
A.リサイクル品や中古品の買取・販売、中古品を扱う店舗運営、骨董品やジュエリーの販売など、広範な業務において必要です。
Q.古物商許可の申請から取得までにどのくらい時間がかかりますか?
A.申請から許可が下りるまでには通常約40日かかりますが、地域や案件により異なることがあります。
Q.法人でも古物商許可を取得できますか?
A.はい、法人でも取得可能です。法人の場合、代表者や役員全員の書類提出が求められます。
Q.古物商許可が下りないケースはありますか?
A.はい、欠格事由に該当する場合は許可が下りません。具体的には、暴力団員、一定の刑罰歴、破産状態などが含まれます。
Q.申請時に提出する書類はどこで入手できますか?
A.申請書類は管轄の警察署で入手できます。また、事前に公式サイトからダウンロードすることも可能です。
Q.許可を取得した後に必要な手続きはありますか?
A.許可取得後も、定期的な帳簿の管理や看板の設置義務があります。法律に基づいた運営が必要です。
Q.申請者が未成年でも古物商許可を取得できますか?
A.原則として未成年者は取得できませんが、婚姻している場合や法定代理人の許可を得ている場合は取得可能です。
Q.古物商許可が必要ない場合もありますか?
A.一時的なフリーマーケットでの個人売買など、特定の状況では許可が不要です。ただし、定期的な中古品の販売には許可が必要です。
Q.古物商許可申請の審査中に面接はありますか?
A.ほとんどのケースでありません。しかし、営業所の実地調査が行われることがあります。
Q.古物商許可の更新は必要ですか?
A.現在の法律では、古物商許可に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし、変更事項があれば届出が必要です。
Q.古物商許可取得後に営業所を移転した場合はどうすれば良いですか?
A.営業所を移転した場合、移転先の管轄警察署に変更届を提出する必要があります。
古物商はオンライン申請できる?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商許可申請のプロセスや注意点について詳しく解説させていただきました。下記では、本記事の内容を簡潔にまとめて記載させていただきました。
1.古物商について
古物商として営業するには、営業所の所在地を管轄する警察署で都道府県の公安委員会から正式な許可を取得する必要があります。この許可がないと中古品の売買や委託販売を行うことはできません。古物商許可は、中古品を扱うリサイクル業者や骨董品店、不用品回収業者などにとって必要不可欠です。
2.古物商のオンライン申請はできない理由
古物商許可申請は、対面または郵送による手続きが必要で、オンライン申請はできません。これは、厳格な本人確認や書類審査の必要性、さらに地域ごとの規制の違いが背景にあります。オンライン化が進んでいる他の行政手続きと異なり、古物商許可では申請者が直接警察署に出向くことが求められます。
3.許可申請の手順と書類
古物商許可を取得するには、住民票や身分証明書、誓約書などの書類を揃え、警察署に提出します。申請手数料の支払い後、審査が行われ、通常約40日で結果が通知されます。申請者は書類に不備がないかを確認し、スムーズな申請ができるよう準備を整えることが重要です。
4.欠格要件について
古物商許可を申請する際、申請者や関係者が法律で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。例えば、一定の刑罰歴がある人や暴力団員は許可を取得できません。未成年者も原則として許可が得られないものの、特定の条件下では例外があります。
5.サービスのご案内
当事務所では、古物商許可の申請代行を専門とし、オンライン申請ができない煩雑な手続きをスムーズに進められるようサポートしています。口コミで高評価を得ており、安心してご利用いただけます。
| 【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |

