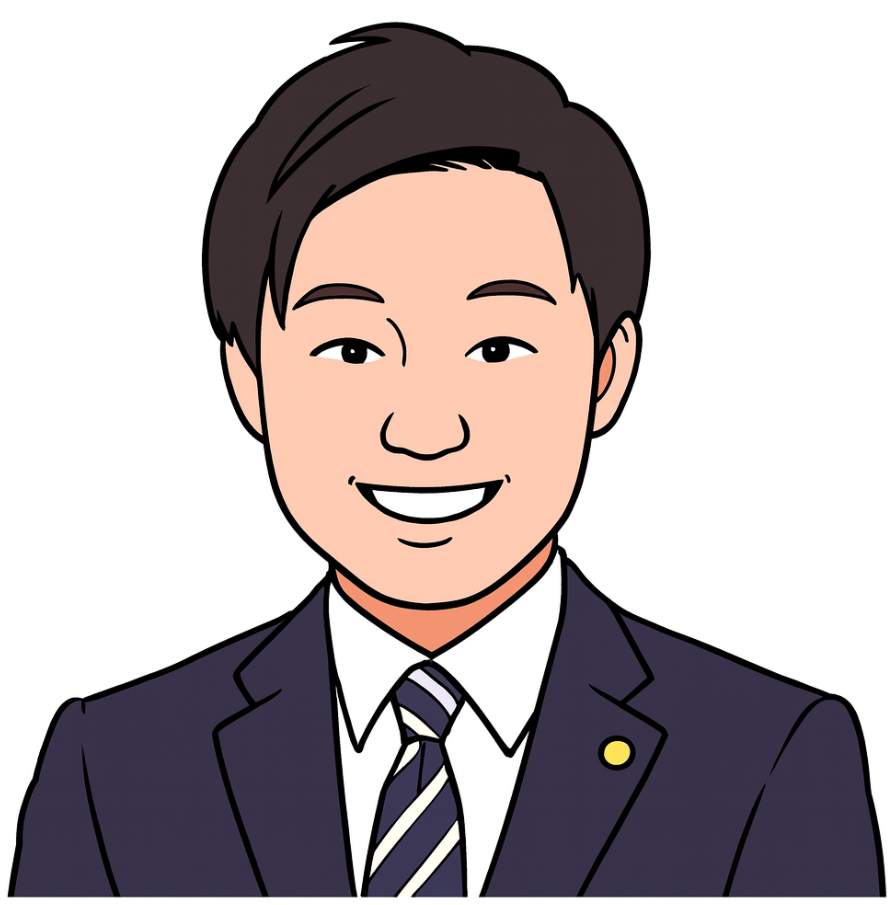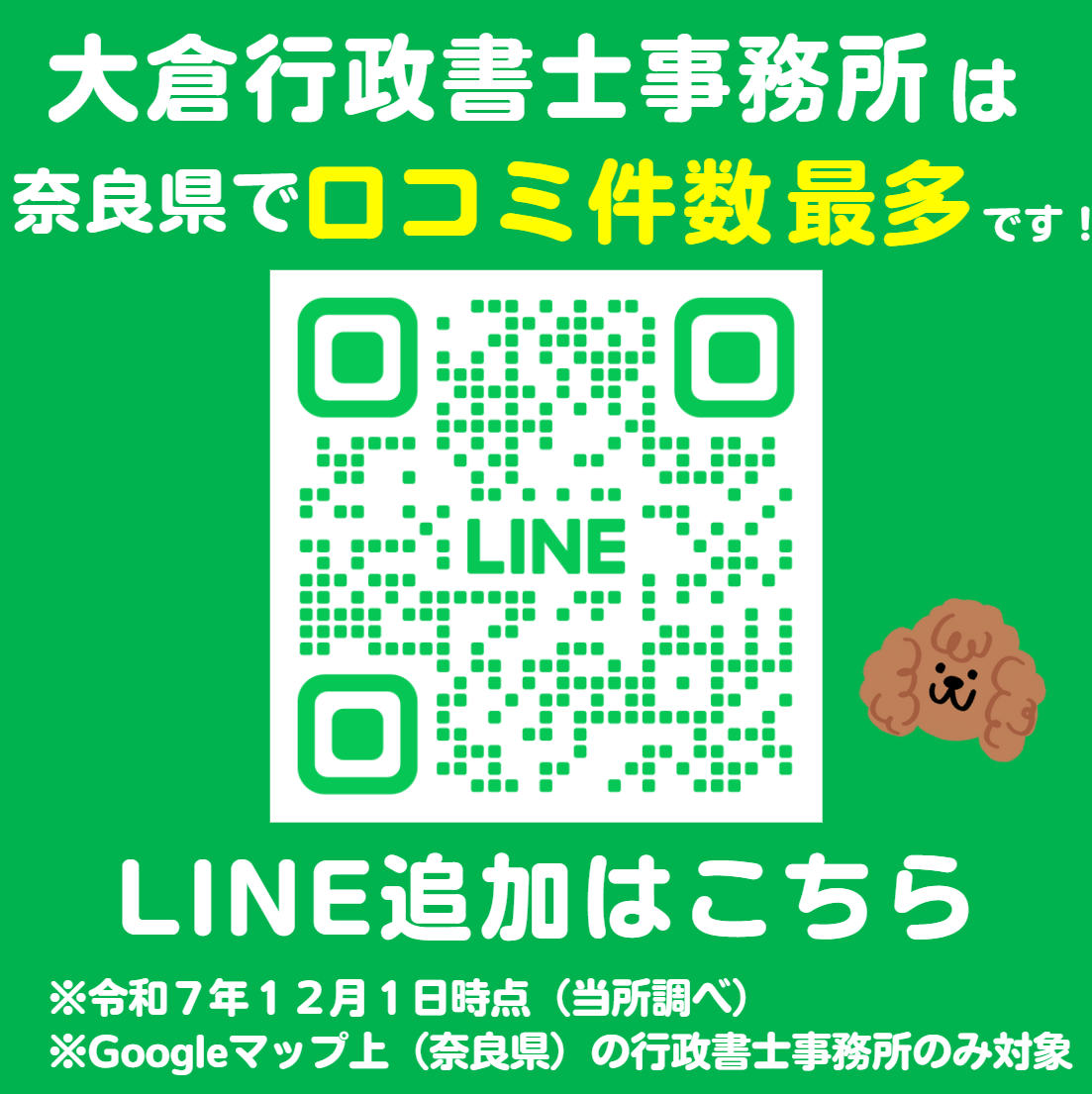古物商許可を取得するには、営業所の設置が重要な要件となります。この営業所が実際に古物営業を行う拠点となり、その場所が適切かどうか求められます。営業所として認められるためには、物理的に営業活動が行われる実体のある場所である必要があり、バーチャルオフィスや単なる郵便受けの住所では不十分です。
多くの方が考える選択肢の一つとして、「実家」を営業所として利用することがあります。実家は私的な空間であり、通常の営業所とは異なる点が多いですが、正しく手続きを行えば、営業所として使用することは可能です。実家を営業所として利用する場合には、特に注意が必要な点や、親や賃貸人の承諾が必要となる場合が多いです。また、申請者の住所と実家の距離が遠い場合には、適切な管理者の選任も重要な要素となります。
こちらの記事では、古物商許可で実家を営業所として利用する際の具体的な要件や手続きについて詳しく解説します。実家を営業所として申請する場合に考慮すべきポイントや、実際に営業所として認められるための条件、また申請時の留意点についても触れ、スムーズな許可取得のための情報を提供します。
古物商許可の概要

古物商許可とは、古物営業を行うために必要な許可であり、都道府県公安委員会に対して営業所を管轄する警察署を経由して申請します。
この許可を取得せずに古物営業を行うと、罰則が科されることがあります。
具体的な罰則としては、無許可営業を行った場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。古物営業には、古物の売買や交換、委託販売などが含まれ、骨董品や中古品、リサイクル品など幅広い品目が対象となります。古物商許可を取得することで、これらの古物を合法的に取り扱うことができ、事業者は信頼性を高めることができます。
古物商許可の申請要件
古物商許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
古物商許可を申請する際に、申請者が欠格事由に該当していないことが求められます。欠格事由には以下のような項目が含まれます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、特定の罪(無許可古物営業、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等の運搬、保管、有償譲り受け、または有償処分のあっせん)を犯して罰金刑を受け、執行終了または執行不要から5年未経過の者
- 集団的または常習的に暴力的不法行為などを行う恐れがあると認められる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令または指示を受けた者で、その日から3年未経過の者
- 住居の定まらない者
- 古物営業許可を取り消され、取消しの日から5年未経過の者(法人の役員も含む)
- 許可取消しに係る聴聞期間中に許可証を返納し、その日から5年未経過の者
- 心身の故障により業務を適正に実施できない者
- 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(相続人で法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く)
営業所を有すること

古物商許可を申請するためには、適法に営業できる営業所を有することが必要です。
営業所は、バーチャルオフィスや郵便受けのみの場所は認められず、実際に営業活動を行う実体がある場所であることが求められます。
さらに、住居専用の賃貸物件についても、原則として営業所としての利用はできず、利用する場合には所有者や管理人の使用承諾書等が求められます
必要な書類を揃えて申請すること
古物商許可の申請には、以下の書類を揃えて提出する必要があります。
- 申請書:所定の申請書に必要事項を記入します。
- 住民票:本籍地入りのものが必要です。
- 身分証明書:役所で取得する「後見、破産、禁治産」を証明する書類です。
- 誓約書(申請者、管理者):申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
- 営業所の賃貸契約書(賃貸の場合):営業所が賃貸物件の場合、その契約書の写し。
- 登記事項証明書(法人の場合):法人で申請する場合、法人登記に関する証明書。
- 定款(法人の場合):会社のルールを定める書類です。
これらの書類を持参した上で、都道府県公安委員会に対して営業所を管轄する警察署を経由して申請を行います。警察署の担当係が申請内容を確認し、問題がなければ古物商許可申請が受理されます。
| 【おすすめの記事】 >古物商の資格を取得したい! 難易度はどれくらい? >古物商許可を個人事業主として取得する方法 >古物商の取り方【法人編】必要書類等を徹底ガイド >古物商を副業で取得するための手続ガイド |
古物商許可の営業所に関する規定
営業所の要件(営業所として使用できること)
営業所は、古物営業を行う拠点となる場所です。そのため、倉庫や駐車場、古物営業を行わない場所、実体のないバーチャルオフィスなどは営業所として認められません。
営業所には管理者が必要!選任する際の注意

古物営業法では、営業所ごとに管理者を置くことが義務付けられています。
管理者を選任する上での注意点は次のとおりです。常時その営業所に従事し、古物の取引や帳簿の記載などを適切に管理する必要があります。
- 常駐性が求められる
管理者は責任者として、その営業所に常駐する必要があります。役職や経験に関係なく選任可能ですが、営業所に通勤可能な距離に住んでいることが条件となります。例えば、管理者候補の住所が通勤圏外の場合、「管理者として不適当」として申請が受理されないことがあります。管理者として認められるかどうかは警察署の判断によるため、事前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。 - 必要な知識経験がある
古物商許可を申請する際には、13種類の品目に分類される古物の中から取り扱う予定の品目を選んで申請します。特に、美術品、時計、宝飾品、自動車、自動二輪車・原付などを取り扱う場合は、それぞれに特有の知識や経験が求められます。例えば、美術品や時計、宝飾品を取り扱う場合には、その品物が本物であるかどうかを見極める真贋の目利きが必要です。これには専門的な知識や経験が求められ、詐欺的な取引や不正を防ぐために重要な役割を果たします。一方、自動車やバイクを取り扱う場合には、違法な改造や盗難品を見抜くため、車体番号の確認や改造の判別などに関する知識が必要です。こうした知識がないと、適切な取引ができなくなる可能性があります。 - 管理者は営業所ごとに1名必要
管理者は、営業所ごとに1名選任する必要があります(古物営業法第13条第1項)。複数の営業所を運営している場合、1人の管理者が全ての営業所を兼任することはできません。それぞれの営業所に対して、独立して管理者を選任することが求められます。これにより、各営業所での業務が適切に管理され、法令に沿った運営が確保されることになります。 - 欠格事由がない
管理者にも欠格事由がないことが求められます。また、古物営業法を遵守する旨の誓約書に署名する必要があります。
実家を営業所として利用できる場合とできない場合
原則として実家は営業所として利用できる

古物商許可の申請において、営業所に関する細かい規定はありません。そのため、実家を営業所として使用することは可能です。また、営業所として使用する実家は、賃貸物件でも自己所有の物件でも構いません。ただし、実家を営業所として使用する場合、所有者(多くの場合は親)の承諾が必要です。これは、営業所を使用する権限があることを示すためです。
実家を営業所として利用できない場合
実家を営業所として利用する際には、いくつかのトラブルが考えられます。これらの問題がある場合、警察署によっては実家を営業所として認められないことがあります。具体的には、次のような状態が考慮される場合があります。
- 親の許可がない場合
実家の所有者である親が、営業所としての使用を許可しない場合は、実家を営業所として使用することはできません。 - 賃貸人の承諾がない場合
実家が賃貸物件の場合、賃貸人(家主)の承諾が必要です。賃貸人の同意を得ていない場合、契約違反とみなされる可能性があります。そのため、賃貸人が営業所としての使用を認めるかどうかを確認し、必要な承諾を取得することが求められます。なお、賃貸人が営業所としての使用を認めない場合は、原則として実家を営業所として使用することはできません。 - 住所と実家の距離が遠く、管理者として適切でない場合
申請者兼管理者の現住所と実家の距離が遠い場合、管理者として適切に営業所を管理できないと判断される可能性があります。この場合、実家を営業所として使用することは難しくなります。
| 【関連記事】 >古物商の許可はアパートでも取得できるのか?行政書士が解説 |
親や賃貸所有者からの承諾を得るには
親や賃貸物件の所有者から承諾を得る際には、営業所としての使用に伴い人が訪問することに対する配慮が重要です。親や管理者にとっては、実家に度々人が訪れることが不快に感じられることが多く、賃貸物件の所有者も同様に、他の居住者に迷惑をかける可能性を考慮して断られることがあります。
このため、営業所の利用を申請する前に、親や賃貸所有者に対して、基本的にオンラインで営業を行う意向を伝えることが有効です。オンライン営業であれば、実際に商品を見に来る人がほとんどおらず、物理的な訪問が少ないため、彼らの懸念を軽減することができ、物件の使用の承諾を貰える可能性も高くなるでしょう。
住所と実家の距離が遠い場合の対応
別の管理者を選任する
申請者の現住所と実家の距離が遠い場合、実家を営業所として利用するためには、申請者自身が管理者として選任されるのではなく、別の適切な人物を管理者として選任する必要があります。この管理者は、実家からの距離が適切で、通勤可能な範囲内に住んでいることが求められます。つまり、管理者として選任される人物は、営業所の実際の運営において、物理的にアクセスしやすい場所に居住している必要があります。
両親を管理者にするのはNG

また、実家を営業所として使用する場合、両親などの家族が管理者として選任されることも考えられますが、一般的に、家族が営業所の運営に必要な知識や経験を持っていないことが多いため、適切な管理者としては難しいことがあります。
そのため、従業員や共同事業者など、古物営業法や関連法規についての十分な知識と経験を持つ人物を管理者として選任することが推奨されます。
このように管理者には、古物営業法に加えて、関連する法規や営業所の運営に必要な知識が求められます。形式的な名義だけの管理者では、申請が受理される可能性が低くなります。実際に営業所を適切に管理し、法令を遵守する能力がある人物を選ぶことが重要です。
古物商許可は当事務所にお任せください
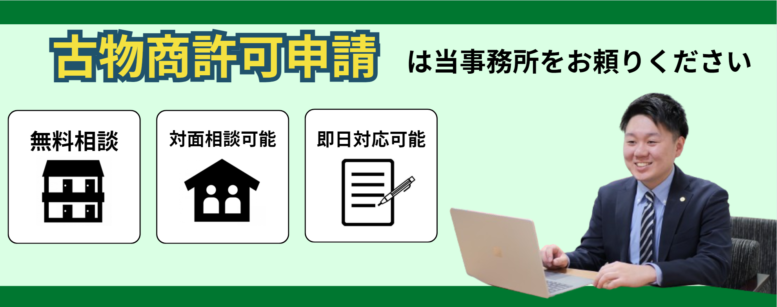
実家を営業所として古物商許可を申請する場合、通常のケースとは異なる点が多く、専門的な対応が必要です。そのため、行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、申請に関する専門知識を有し、スムーズな手続きをサポートするだけでなく、各都道府県や警察署に存在する可能性のあるローカルルールにも精通しており、適切なアドバイスを提供します。
当事務所の代行サービスは、古物商許可の取得において豊富な実績を誇り、大阪、兵庫、奈良、京都などで多くの申請を成功させてきました。お客様が問題なく許可を取得できるよう、申請手続き全般を丁寧にサポートいたします。また、万が一許可が下りなかった場合の返金保証もご用意しており、安心してお任せいただけます。
さらに、当事務所のサービスは口コミで高く評価されており、150件以上の口コミと総合評価4.9/5という実績を持っています。これにより、多くのお客様から信頼を得ており、安心して古物商許可の取得をお任せいただけるサービスであることがわかります。どうぞ、安心して当事務所にお任せください。

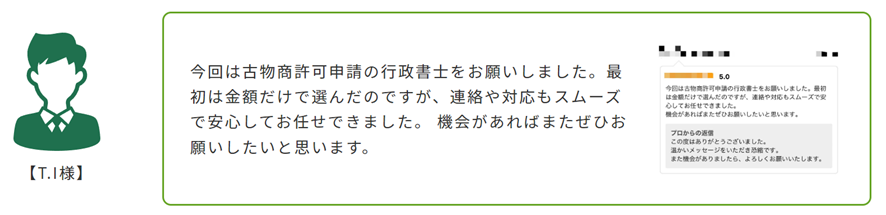

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商許可における実家の営業所利用について-よくある質問
Q1:古物商許可の申請に必要な営業所の条件は?
古物商許可を申請するには、実際に営業活動を行う物理的な営業所が必要であり、バーチャルオフィスや郵便受けのみの場所は認められません。
Q2:実家を営業所として使用する際に注意すべき点は?
実家を営業所として使用する場合、所有者や賃貸物件の場合は賃貸人の承諾が必要です。また、申請者兼管理者の住所と実家の距離が遠いと管理の適切性が問われることがあります。
Q3:営業所の管理者として求められる条件は?
営業所の管理者は常駐し、古物営業法や取り扱う品目に関する知識と経験が必要です。また、欠格事由がないことも求められます。
Q4:住所と実家の距離が遠い場合、どのように対処すればよいですか?
申請者の住所と実家の距離が遠い場合、実家に近い距離に住む適切な管理者を選任することが必要です。両親が適切な管理者でない場合は、専門知識を持つ従業員や共同事業者を選ぶことが推奨されます。
Q5:管理者に求められる具体的な知識や経験は?
管理者は古物営業法や取り扱う品目についての専門的な知識が求められ、例えば美術品や自動車などの取扱いに関する専門知識や経験が必要です。
Q6:実家を営業所として利用する際、親の承諾が得られない場合はどうすればよいですか?
親の承諾が得られない場合は、実家を営業所として使用することができません。他の物件を探すか、親からの承諾を得る必要があります。
Q7:賃貸物件を営業所として利用する際の承諾取得の手順は?
賃貸物件を営業所として利用する場合、賃貸人からの承諾を得るために、書面での同意を取得し、契約書に営業所としての利用を明記する必要があります。
Q8:管理者が不在の場合、どのような影響がありますか?
管理者が不在の場合、営業所の適正な管理が行われず、古物営業法の違反と見なされる可能性があり、行政処分や刑事処分が下されることがあります。
Q9:古物商許可の申請でよくある問題点は?
よくある問題点には、営業所の条件不備、管理者の欠格事由、必要な書類の不足などがあります。事前にこれらを確認し、整えておくことが重要です。
Q10:古物商許可申請を専門家に依頼するメリットは?
専門家である行政書士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進み、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができ、ローカルルールへの対応も適切に行われます。
古物商許可における実家の営業所利用について-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商許可で実家を営業所として利用する際の具体的な要件や手続きについて詳しく解説させていただきました。下記に本記事を簡潔にまとめた内容を記載させていただいております。
1.古物商許可の申請要件
⑴欠格事由に該当しないこと
破産手続きや特定の罪を犯していないことが求められます。また、暴力団関係者でないことや、業務を適正に実施できる心身の状態であることも重要です。
⑵営業所を有すること
営業所は実際に営業活動を行う場所で、バーチャルオフィスや住居専用の賃貸物件は適用されません。
⑶必要な書類を揃えて申請すること
申請書、住民票、身分証明書、誓約書、営業所の賃貸契約書(賃貸の場合)、登記事項証明書(法人の場合)、定款(法人の場合)などを提出します。
2.古物商許可の営業所に関する規定
⑴営業所の要件
倉庫や駐車場などは営業所として認められません。
⑵管理者の選任
・常駐性:管理者は営業所に常駐し、通勤可能な距離に住んでいる必要があります。
・必要な知識経験:取り扱う品目に関する専門知識が求められます。管理者は、法令遵守や取引の適正性を確保するための知識と経験が必要です。
・1営業所1管理者:複数の営業所がある場合、各営業所ごとに独立した管理者を選任する必要があります。
・欠格事由がない:管理者にも欠格事由がなく、古物営業法を遵守する旨の誓約書に署名する必要があります。
3.実家を営業所とする場合の検討
⑴実家の営業所利用
実家を営業所として利用することは可能ですが、所有者の承諾が必要です。また、賃貸物件の場合は賃貸人の承諾も必要です。
⑵利用できない場合
・親の許可がない場合:親が営業所としての使用を許可しない場合、実家を営業所として利用することはできません。
・賃貸人の承諾がない場合:賃貸物件の場合、賃貸人の同意がないと営業所として利用できません。
・距離が遠く管理者として不適切な場合:申請者の住所と実家が遠く、適切な管理が難しい場合、実家の営業所利用は難しくなります。
4.住所と実家の距離が遠い場合の対応
⑴別の管理者を選任する
現住所と実家の距離が遠い場合、管理者は別の人物を選任し、その人物が営業所から通勤可能な距離に居住している必要があります。
⑵両親を管理者にするのはNG
家族が管理者として適切でない場合が多いため、古物営業法や関連法規について知識と経験のある人物を選任することが推奨されます。
5.実家を営業所とする申請の際の留意点
実家を営業所として利用する申請は一般的なケースとは異なる点が多いため、行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は専門知識を持ち、ローカルルールにも精通しており、スムーズな申請手続きをサポートしてくれます。
| 【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |