古物商の許可を取得することは、リサイクル業界や中古品取引に携わる方々にとって重要な一歩です。古物商の取り方を知ることは、ビジネスを合法的に展開し、信頼性を高めるための必須条件となっています。古物商許可は、特定の13品目を取り扱う際に必要となり、個人でも法人でも申請が可能です。
こちらの記事では、古物商許可の申請プロセスを詳しく解説します。基本要件から必要書類の準備、申請手続きまでを網羅的に説明します。また、営業所の準備やURL届出の重要性についても触れます。申請が複雑に感じられる場合は、行政書士に相談することも選択肢の一つです。古物商許可を取得するための全てのステップを理解し、スムーズな申請を目指しましょう。
古物商許可とは何か
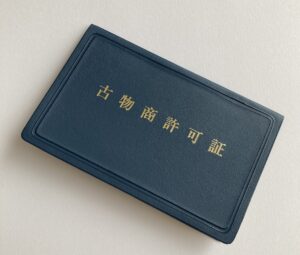
古物商許可は、法人や個人が中古品(古物)を売買または交換する際に必要となる許可のことです。この許可は、古物を営業する場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に申請します。主に、古物商許可が必要となるのは、中古品の売買、レンタル、交換などを行う場合です。意外かもしれませんが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当しますので知っておきましょう。
古物商許可が必要な理由
古物商許可が必要な理由は、古物営業法の第1条(目的)に明確に記されています。この法律の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。つまり、中古品の取引に許可制を導入することで、次のような効果が期待できます。
盗品の売買を防止する
中古品の取引には盗品が含まれるリスクがあります。盗品を購入すると、犯罪者に利益を与え、被害者に損害を与えることになります。さらに、犯罪が再発する可能性も高まります。古物商許可制度は、「誰が、いつ、どこで、何を売ったのか」を記録することで、盗品の販売を難しく且つ困難にし、犯罪の抑止効果を強化します。
犯罪被害の迅速な回復を支援する
許可制度を導入することで、盗品が市場に出回ることを防ぎ、被害者が早期に盗品を取り戻す手助けをすることができます。古物商は古物営業法により取り扱った商品や購入した当事者に関する記録を残しておく義務があります。この記録を基に、盗品の流通経路を迅速に特定できるため、被害者の損害回復が早まります。
窃盗などの犯罪を抑止する
古物商許可制度は、盗品が市場へ流通することを防ぐことができます。これにより、窃盗犯にとっての動機を減らすことができ、盗品の売却が困難であることが知れわたることで、窃盗自体を減少させることができ、犯罪の発生を抑止する効果が期待できます。
古物商許可の取得は、中古品取引業界で合法的に事業を展開するための重要なステップです。この許可制度を通じて、犯罪防止と被害回復の両面から社会の安全に貢献することができます。
対象となる品目

古物商許可の対象となる品目は、古物営業法施行規則第2条で13種類に区分されています。
以下に主な品目を示します。
| 美術品類:絵画、彫刻、骨董品、工芸品など 衣類:洋服、着物、帽子、布製品、布団など 時計・宝飾品:時計、眼鏡、宝石、装飾具、貴金属など 自動車:自動車本体、タイヤ、カーナビなど 自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類:カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡など 事務機器類:パソコン、コピー機など 機械工具類:工作機械、家庭電化製品など 道具類:家具、楽器、CD、DVD、おもちゃなど 皮革・ゴム製品類:バッグ、靴など 書籍:文庫、コミック、雑誌など 金券類:商品券、航空券、郵便切手など |
古物商許可を申請する際は、これらの品目から取り扱う予定の区分を選択します。複数の品目を選択することも可能ですが、最初の申請時には必要最低限の品目に絞ることで、スムーズに許可を取得できる可能性が高くなります。
古物商許可申請の基本要件

古物商許可を取得するためには、いくつかの基本要件を満たす必要があります。
これらの要件は、主に年齢制限と欠格事由に分類されます。
年齢制限
古物商許可の取得には年齢制限があります。原則として、18歳未満の未成年者は古物商の許可を取ることはできません。これは、法律上「営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者」として規定されているためです。
ただし、例外的なケースもあります。未成年者でも、古物商の相続人であるなど一定の条件を満たす人は許可を得ることができます。また、法人役員の中に未成年者がいる場合も、古物商許可を受けるのは「法人」であるため、許可を取得することが可能です。
欠格事由
古物商許可の取得を妨げる欠格事由には、以下のようなものがあります。
| 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者 禁錮以上の刑に処せられた者、または特定の罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行から5年を経過していない者 暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う可能性がある者 住居の定まらない者 過去に古物商許可を取り消され、5年を経過していない者 心身の故障により古物商の業務を適正に実施できない者 |
これらの欠格事由に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。特に法人で申請する場合、役員の中にこれらの欠格事由に該当する人がいないか注意が必要です。
古物商許可の申請プロセスは複雑で、要件を満たしているかどうかの判断が難しい場合があります。そのような場合は、行政書士に相談することをお勧めします。行政書士は申請手続きに精通しており、適切なアドバイスを提供できます。
| 【関連記事】 >古物商を副業で取得するための手続ガイド |
古物営業をするための営業所の準備

古物商許可を取得するためには、営業所を準備することが必須です。営業所は、古物の買取り、仕入れ、販売、交換、レンタル等を行う拠点となる場所です。自宅が営業所として申請することができる一方、単なる倉庫や駐車場、実体のないバーチャルオフィスは営業所として認められません。
営業所には、古物営業の責任者である「管理者」を常駐させ、古物台帳や古物商プレートの備え付け及び掲示をする必要があります。営業所として使用できるのかの判断に迷う場合は、管轄の警察署に相談することをお勧めします。
自宅を営業所にする場合の注意点
ネット上のオークションサイトやホームページを利用して取引を行うなどの場合、自宅を営業所として使用することが可能です。最近では、古物商もインターネットを主な取引の場とすることが増えており、自宅を営業所として活用することで、効率的にビジネスを運営することができます。しかし、自宅を営業所として申請する場合には以下の点に注意が必要です。
賃貸物件の場合
賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」となっていることがあります。この場合、賃貸人からの使用承諾書が必要となる可能性が高くなります。しかしこのような書類は、法定書類では無いので、必ずないからといって古物商許可が絶対に取得できないとは言い切れません。もしこのような状況であれば、行政書士にご相談ください。
マンション(集合住宅)の場合
管理規約に違反しないか確認する必要があります。マンションの管理規約は、共用部分の保護や住民の安全を確保などを目的とした重要な規約ですので、とても厳しいです。
賃貸物件を使用する場合
賃貸物件を営業所として使用する場合には、大家さんやオーナーの使用承諾書もしくは賃貸借契約書(事務所使用が認められている場合)が必要です。もし、賃貸借契約書の使用目的が「事務所使用」以外の場合には、事前に大家さんなどに相談し、「使用承諾書」を発行してもらいましょう。物件がテナントや貸店舗の場合は、使用目的が「事務所使用」となっているケースが多く、この場合には使用承諾書は不要です。
営業所の準備は古物商許可取得の重要なステップです。自宅や賃貸物件を使用する場合は、法的要件を満たし、必要な承諾を得ることが大切です。
| 【関連記事】 >メルカリで古物商を始める方法は?許可取得からURLの届出まで >古物商許可とヤフオクの使用URLについて >ebayで古物商のURLを届出する方法を【行政書士】が解説 |
古物商許可で必要な書類の準備

古物商許可の申請には、許可申請書と添付書類の提出が必要です。添付書類には、住民票の写し、身分証明書、略歴書、誓約書、URLの使用権限の疎明資料が含まれます。これらの書類は、申請者が古物商として適格であるかを確認するために提出を要求されます。
個人申請の場合
個人で古物商許可を申請する場合、主に以下の書類が必要となります。
- 古物商許可申請書
- 誓約書(個人用と管理者用)
- 略歴書(過去5年間の職業歴)
- 住民票(本籍地記載入りのもの)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 事務所の所有等を証明する資料(使用承諾書、賃貸借契約書を含む。)
- URLの使用権を証明する資料(該当する場合)
| 【関連記事】 >古物商許可を個人事業主として取得する方法 |
法人申請の場合
法人で古物商許可を申請する場合、個人申請とは異なる書類が必要となります。
- 定款(現行のもの)
- 法人の登記事項証明書
- 古物商許可申請書
- 誓約書(役員全員と管理者用)
- 略歴書(役員全員と管理者用)
- 住民票(役員全員と管理者用)
- 身分証明書(役員全員と管理者用)
- 事務所の所有等を証明する資料(使用承諾書、賃貸借契約書を含む。)
- URLの使用権を証明する資料(該当する場合)
個人申請と法人申請では必要書類が異なります。個人申請では本人と営業所管理人の身分証明書や住民票が必要ですが、法人申請では法人の登記事項証明書、役員全員と管理人の住民票と身分証明書が必要となります。申請の際は、これらの違いに注意して適切な書類を準備しましょう。また、インターネットで古物を売買する予定がある場合は、URLの届出が必須で、具体的にはURLの使用権限があることを証明する資料の提出が必要です。これは、プロバイダーからの資料やインターネットのドメイン検索サービス(Whois等)でプリントアウトしたものを提出します。
古物商許可申請書の作成方法
古物商許可申請書の書き方

古物商許可申請書は、申請プロセスの中心となる重要な書類です。
個人申請と法人申請で様式は同じですが、記入方法が異なりますので注意が必要です。
個人申請の場合
申請日:申請が正式に受理されるまで記入しません。
公安委員会名:申請する都道府県を記入します。
申請者氏名・住所:住民票に記載されている通りに正確に記入します。
フリガナ・氏名漢字:住民票通りに正確に記入します。
生年月日:日本人は和暦、外国籍の方は西暦で記入します。
電話番号:日中連絡がつく番号を記入します。
行商の有無:全国で商品を売るには「1.する」に〇を付けます。
主として取り扱う古物の区分:13種類の中から1つだけ選びます。
法人申請の場合は、会社名や代表者情報、役員情報なども記入する必要があります。
誓約書の記入のコツ
誓約書は、申請者と営業所の管理者が欠格事由に該当しないことを証明する重要な書類です。本人による署名が必要です。
略歴書の記入のコツ
様式は都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。略歴書には、最近5年間の経歴を記載します。5年以上前から変更がない場合は、その経歴の開始年月から記載します。空白期間がないように注意し、「無職、就職活動、転職活動及び専業主婦」などの期間も含めて記載します。経歴の最後に「現在に至る。」も忘れないように記入しましょう。
URLの届出について
インターネット(メルカリ、ebay、BASE等)で古物を売買する予定がある場合は、URLの使用権限を証明する資料が必要です。使用する会社によっては使用承諾書を発行してもらえる場合がありますが、発行ができない場合には、プロバイダからの資料やWhois等のドメイン検索サービスの結果を提出します。
| 【関連記事】 >メルカリで古物商を始める方法は?許可取得からURLの届出まで >ebayで古物商のURLを届出する方法 |
警察署への申請手続き

古物商許可の申請プロセスは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請の難易度は比較的易しいものの、警察署ごとのローカルルールがあるため、決して甘く見てはいけません。申請の準備段階から許可取得までには2~3ヶ月程度かかることを念頭に置いてください。申請の流れは以下の通りです。
ステップ1 警察署への事前相談
申請前に警察署での事前相談を行います。これにより、必要な書類や申請手続きに関する具体的な情報を確認し、申請がスムーズに進むよう準備することができます。
ステップ2 添付書類の収集
必要な添付書類を収集します。個人申請の場合には、住民票、身分証明書、使用承諾書などが求められます。これらの書類は、申請書類と一緒に提出する必要があります。
ステップ3 申請書等の記入
古物商許可申請書を記入します。申請書には、事業の概要や営業所の情報、代表者の情報などを正確に記入する必要があります。
ステップ4 警察署へ申請
完成した申請書と添付書類を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。申請の際には、警察署の窓口での確認や質問に対応する必要があります。
ステップ5 許可証の受け取り
許可申請が受理されると、審査が行われます。審査に通過すると、古物商許可証が発行されます。許可証を受け取った後、正式に古物商として営業を開始することができます。
警察署への申請手続きのポイント
申請手続きにおける細かいポイントを述べております。
警察署での事前相談
古物商の担当は警察署の生活安全課防犯係の古物商担当等です。古物商許可申請をする前には、必ず古物商の担当者と直接やり取りすることをお勧めします。これら担当に事前相談することで、以下のメリットがあります。
・担当者との良好な関係構築
・事前相談により、申請時にスムーズに進行する可能性が高まります。
必要書類の確認
警察署によって提出を求められる添付書類や申請書の部数が異なる場合があります。事前に確認することで、申請の手戻りを防ぐことができます。
事業内容の正確な伝達
事業内容や形態によって必要な書類が変わることがあるため、担当者に詳細を伝えることが重要です。
申請時の注意点
申請時における細かいポイントを述べております。
書類の準備
申請書一式を用意し、整理して提出しましょう。これにより、担当者の印象も良くなり、書類チェックもスムーズに進みます。
管理者の選任
営業所ごとに古物営業中に常駐できる管理者を置く必要があります。管理者は以下の条件を満たす必要がありますので、適切な者が管理者となっているかを確認しましょう。
・古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方
・営業所に通勤できる距離に居住
・複数の営業所で管理者を兼任していない
・古物商の欠格事由に該当しない
審査期間
申請から概ね40日以内に、許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備や添付書類の不足がある場合は遅れる可能性があります。
インターネット利用の場合
ホームページを利用して中古品の売買を行う場合、URL疎明資料が必要となります。どのような資料が適切かを事前に確認しましょう。
審査期間と許可後の手続き
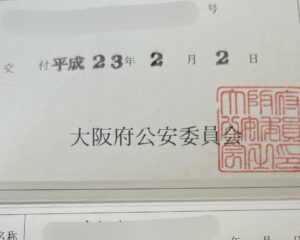
古物商許可の申請から許可証の交付までには一定の期間が必要です。
この期間中に警察による審査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。
標準的な審査期間
古物商許可申請の標準処理期間は40日と定められています。これは、申請が警察署に正式に受理されてから処分(許可)が下りるまでの標準的な目安となる期間です。具体的には、申請書が受理された翌日から起算して、土日を除く40日間が審査期間となります。
審査期間中には、以下のようなプロセスが行われることがあります。
営業所の確認
警察官が営業所を訪問し、実際の状況を確認することがあります。これは、申請書に記載された営業所の所在地が実際に存在し、営業に適した環境であるかを確かめるためのものです。訪問の際には、事務所の外観や地域によっては内部の写真を撮影されることもあります。
ポストや表札の設置確認
営業所としての体裁が整っているかを確認します。具体的には、営業所のポストがしっかりと設置されているか、表札や看板が掲示されているかなどが確認されます。これにより、許可後に営業が確実にできるかどうかを確認します。
許可証受け取り時の確認事項
審査が無事に完了し、許可証の交付準備が整うと、警察署の生活安全課防犯係の古物担当者から電話連絡があります。許可証の受け取りには、以下の点に注意してください。
・身分証明書の提示: 許可証を受け取る際には、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)を提示する必要があります。
・印鑑の持参: 許可証の受け取りには印鑑が必要です。申請時に使用した印鑑を持参することをお勧めします。
これらの確認事項を守ることで、許可証の交付がスムーズに行われ、営業を開始することができます
古物商 取り方の完全ガイド: 必要書類と申請手順-FAQ
質問1: 古物商の資格を取得するために必要な書類は?
回答: 古物商の資格取得には、申請書、身分証明書、住民票、事務所の使用権を証明する書類(賃貸契約書など)等が必要です。
質問2: 古物商の資格取得にはどれくらいの時間がかかる?
回答: 一般的に、申請の準備から資格取得までに2ヶ月から3ヶ月程度かかります。ただし、申請内容や地域によって異なる場合があるため、早めの手続きが推奨されます。
質問3: 古物商の資格取得にかかる費用は?
回答: 古物商の資格取得には、申請手数料や必要書類の取得費用がかかります。手数料は概ね2万円ほどです。
質問4: 古物商の資格を持っていれば、どんな古物を扱うことができる?
回答: 古物商の資格を持つことで、中古品や古物を売買することができます。ただし、特定の品目(例えば、銃器や高価な宝石など)には別途許可が必要な場合があります。
質問5: 古物商の資格を取得しても、取引先や顧客との契約には注意が必要ですか?
回答: はい、古物商の資格を取得しても、取引先や顧客との契約には注意が必要です。取引に関する契約書をしっかりと作成し、法的なトラブルを避けるための対策を講じることが重要です。
古物商許可の取得代行は
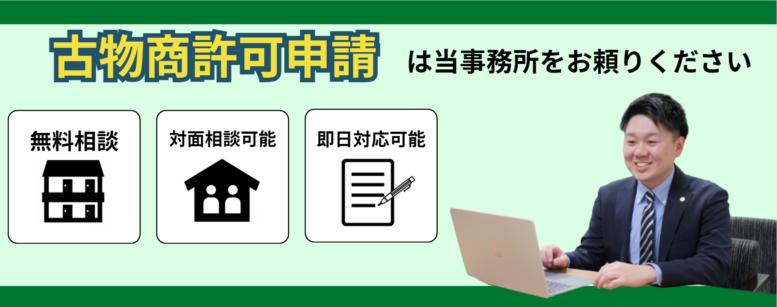
当事務所は、これまで多数の古物商許可申請に対応してきた実績があります。申請手続きは複雑で手間がかかるものですが、私たちはお客様の負担を最小限に抑え、スムーズに許可を取得できるようサポートいたします。特に、書類作成のみの対応が可能であり、全国どこからでもご利用いただけます。また、警察署での手続きは複雑で何度もやり直しを求められることがありますが、当事務所にご依頼いただければ、そのような手間を省き、確実に手続きを進めることができます。お客様の時間と労力を節約し、確実に古物商許可を取得するために、ぜひ当事務所にお任せください。
さらに、当事務所は口コミで高く評価されており、現在、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。
手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(申請書作成) 【全国対応】 |
25,000円(税込) | 申請書や必要な書類を取得し、警察との打ち合わせをします。お客様には書類を警察署に持っていただくだけです。 |
| 古物商許可(個人) | 40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) | 50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
| 書類取得(個人) | 2,000円~ | |
| 書類取得(法人) | 3,000円~ | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能: 書類の作成や取得を全て代行
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商 取り方の完全ガイド(忙しい方向け)―まとめ
下記は、本文の内容を目次よりも詳しく書いております。
1.古物商許可とは?
古物商許可は、法人や個人が中古品(古物)を売買・交換する際に必要な許可です。この許可は、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に申請します。中古品の取引を行う際、特に古物商許可が必要となります。古物商許可が必要な主な理由は以下の通りです。
- 盗品の防止: 古物商許可制度は、盗品が市場に流通することを防ぎます。取引の記録があることで、盗品の流通経路を特定しやすくなります。
- 被害回復の支援: 盗品が迅速に回収できるようになるため、被害者の損害回復が早まります。
- 犯罪の抑止: 盗品の売買が困難であることが周知されることで、犯罪の発生を抑止する効果が期待されます。
2.対象となる品目
古物商許可の対象となる品目は、古物営業法施行規則第2条で13種類に分けられています。主な品目は以下の通りです。
- 美術品類: 絵画、彫刻、骨董品など
- 衣類: 洋服、着物、布団など
- 時計・宝飾品: 時計、宝石、貴金属など
- 自動車: 自動車本体、タイヤ、カーナビなど
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類: カメラ、ビデオカメラなど
- 事務機器類: パソコン、コピー機など
- 機械工具類: 工作機械、家庭電化製品など
- 道具類: 家具、楽器、CD、DVDなど
- 皮革・ゴム製品類: バッグ、靴など
- 書籍: 文庫、コミック、雑誌など
- 金券類: 商品券、航空券、郵便切手など
3.許可申請の基本要件
古物商許可の取得には以下の基本要件を満たす必要があります。
- 年齢制限: 18歳未満の者は原則として許可を取得できません。ただし、法人の場合は役員に未成年者がいても許可は取得可能です。
- 欠格事由: 以下のような条件に該当する場合、古物商許可を取得できません。
- 破産手続き中の者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 暴力団員やその関係者
- 過去に古物商許可を取り消されて5年未満の者
4.営業所の準備
古物商許可を取得するためには、適切な営業所を準備する必要があります。営業所は実体のある場所でなければなりません。自宅を営業所として使用する場合には以下の点に注意します。
- 賃貸物件の場合: 使用承諾書が必要な場合があります。
- マンションの場合: 管理規約に違反しないか確認が必要です。
- 賃貸物件の利用: 大家さんやオーナーの許可が必要です。
5.必要書類の準備
古物商許可の申請には以下の書類が必要です。
- 個人申請の場合:
- 古物商許可申請書
- 誓約書(個人用と管理者用)
- 略歴書(過去5年間の職業歴)
- 住民票(本籍地記載入り)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 事務所の所有証明(使用承諾書、賃貸借契約書など)
- URL使用権証明資料(該当する場合)
- 法人申請の場合:
- 定款(現行のもの)
- 法人の登記事項証明書
- 古物商許可申請書
- 誓約書(役員全員と管理者用)
- 略歴書(役員全員と管理者用)
- 住民票(役員全員と管理者用)
- 身分証明書(役員全員と管理者用)
- 事務所の所有証明(使用承諾書、賃貸借契約書など)
- URL使用権証明資料(該当する場合)
6.警察署への申請手続き
古物商許可の申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請プロセスは以下のようになります。
- 事前相談: 警察署での事前相談を行い、必要書類や手続きについて確認します。
- 添付書類の収集: 必要な書類を揃えます。
- 申請書の記入: 申請書を正確に記入します。
- 申請の提出: 完成した申請書と添付書類を提出します。
- 許可証の受け取り: 審査後、許可証を受け取ります。
7.審査期間と許可後の手続き
申請から許可証の交付までの標準的な審査期間は40日です。審査期間中に警察官が営業所の確認に訪れることがあります。許可証を受け取った後は、許可証の内容を確認し、必要に応じて押印や署名を行います。
最後までご覧いただきありがとうございました。

