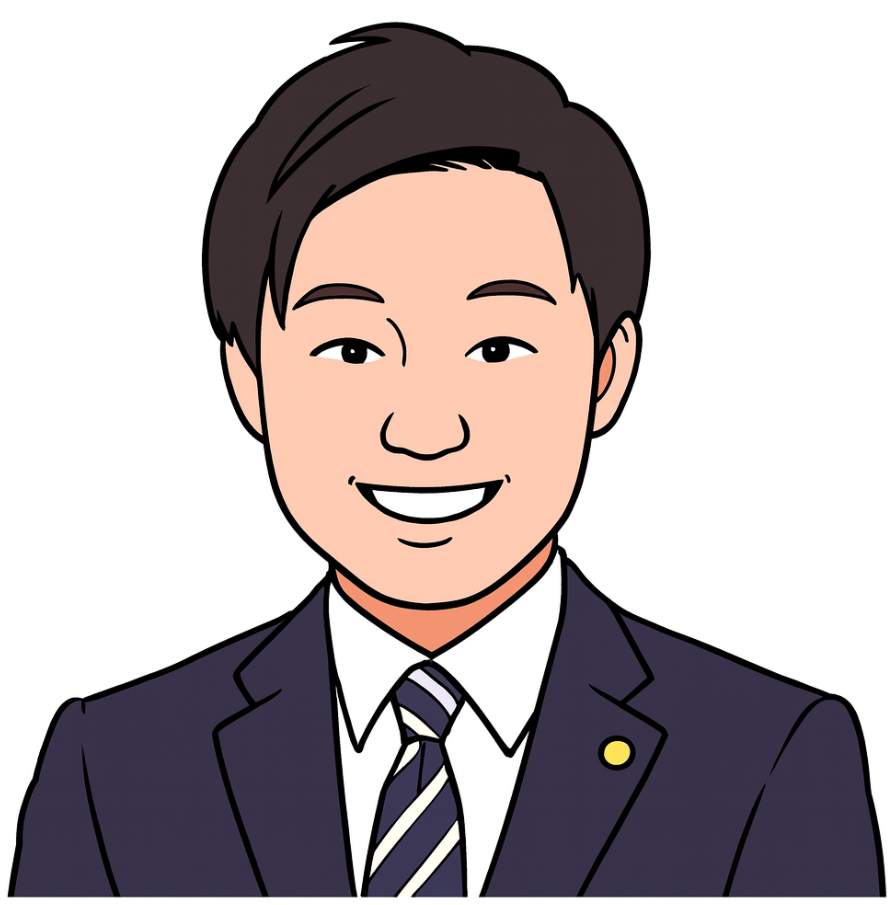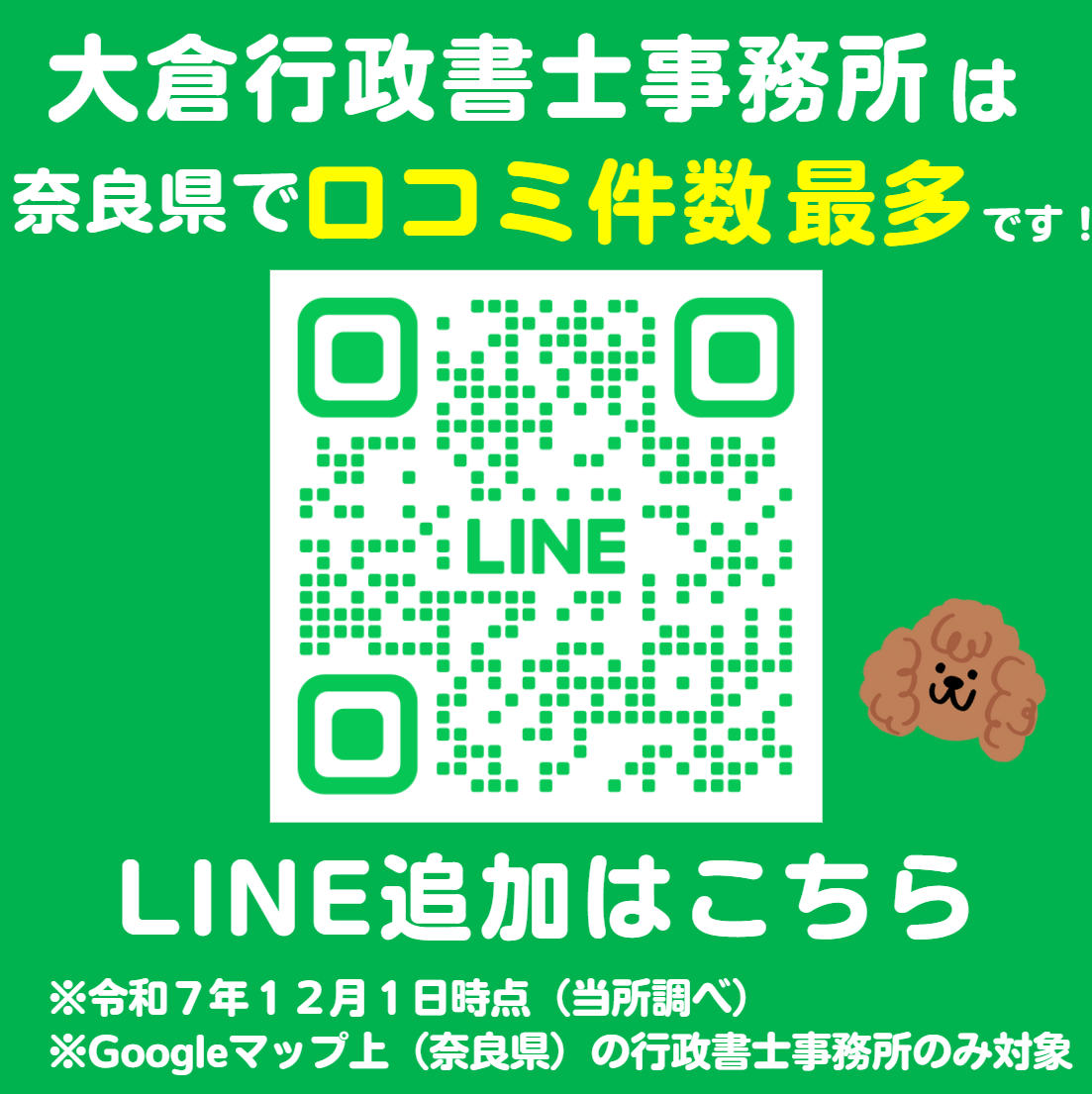フリーマーケットは地域の活性化やコミュニティの形成に大きく役立つイベントです。特に古物商として活動する事業者にとって、フリーマーケットは中古品の販売や交流の場として重要な役割を果たします。
こちらの記事では、古物商とフリーマーケットの概要、古物商許可の取得方法、フリーマーケットでの出店手続き、さらにフリーマーケットでの商品の仕入れ方法について詳しく解説します。
これからフリーマーケットへの出店を検討している方や、古物商としての活動を広げたい方にとって、有益な情報となることを願っています。
古物商とフリーマーケットの概要
古物商の定義と業務内容

古物商とは、中古品を取り扱う事業者のことを指します。古物営業法に基づいて、都道府県公安委員会から許可を受けた事業者が古物商として認められます。
古物商の主な業務内容には以下のようなものがあります。
- 中古品の買取
- 中古品の販売
- 中古品の交換
- 委託販売の仲介
古物商が取り扱う13区分
古物商が取り扱う「古物」には、以下の13品目が含まれます。古物商許可申請では、この中から主に扱う区分とその他の取り扱う区分を申請します。主に扱う区分はいずれか一つを選ばなくてはいけません。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
- 衣類(繊維製品、革製品)
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車および原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類(家具、楽器、CD、ゲームソフトなど)
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
| 【関連区分の記事】 >書籍商 >機械工具商 >美術品商 >衣類商 |
古物商許可申請について
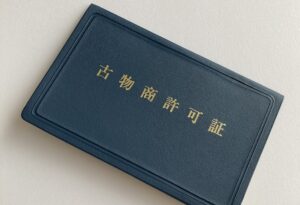
古物商許可申請は、古物の営業を行う場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に許可申請をします。古物商許可(個人)では主に次のような書類が必要です。具体的な書類は下記のおすすめ記事をご確認いただくか、警察にお問い合わせください。
- 申請書
- 住民票
- 身分証明書(役所で取得)
- 略歴書
- 誓約書(2枚)
フリーマーケットの定義と特徴
フリーマーケット(略してフリマ)は、個人や小規模事業者が不用品や手作り品を持ち寄り販売する市場で、以下のような特徴があります。
フリーマーケットの開催場所・方法
- 開催場所と形式
屋外や公共施設:フリーマーケットは一般的に公園や広場、駐車場などの比較的に広いペースが使用できる屋外や公共施設で開催されます。これにより、多くの出店者や購入者が集まりやすくなります。 - 地域ごとの開催
フリーマーケットは地域の活性化を目的として、町内会や地方公共団体が主催することがあります。このため、主催する地域の特色や文化が色濃く反映された市場が展開されます。例えば、大阪の鶴見緑地公園で開催されるフリーマーケットでは、広大な公園内での開催という特性を生かし、主に子供向けのおもちゃや遊具などの品物が多く並ぶのが特徴です。
フリーマーケットの取引

フリーマーケットでは、出店者と購入者が直接取引を行います。交渉が可能で、価格の値引きや商品の詳細についてその場で質問することができます。支払いは主に現金が一般的で、クレジットカードや電子マネーの利用は少ないですが、最近では時代に合わせて電子決済に対応するフリーマーケットも増えてきています。
その他のフリーマーケットの特徴
- 安価な価格設定
商品は比較的安価で販売されることが多いです。 - 様々な商品
不用品から手作り品、古本、ヴィンテージアイテム、衣類、家電など、多種多様な商品が並びます。これにより、一つの場所で様々な商品を比較して購入することができます。 - イベント性を持っている
フリーマーケットは単なる買い物の場にとどまらず、地域のイベントや祭りとしての側面も持ちます。
このように、フリーマーケットは単なる物品の売買の場にとどまらず、地域のコミュニティ形成や交流の場としても重要な役割を果たしています。
古物商許可が必要なフリーマーケットについて
古物商許可が必要かどうかは、フリーマーケットで販売する商品の種類や取引の形態によって異なります。以下に、古物商許可が不要な場合と必要な場合の具体例を示します。
【古物商許可が不要な場合】
- 自宅にある不用品を販売する場合
- 個人が不要品をオークションなどで売る場合(転売目的で購入した品物を除く)
- 無償で譲り受けた品物を販売する場合
- 相手から手数料を受け取って品物を回収し、販売する場合
【古物商許可が必要な場合】
- ネットショップで購入した中古品や古本、古着などをフリーマーケットで販売する場合
- 有料で買い取った品物をリサイクルしてフリーマーケットで販売する場合
- 仕入れた中古品やリサイクル品を転売目的で販売する場合
- 定期的にフリーマーケットで販売を行い、継続的な収益を得る場合
このように、販売の形態や商品の仕入れ方法によって古物商許可の要否が変わります。許可が必要な場合は、必ず事前に古物商許可を取得しておくことが重要です。
| 【おすすめの記事】 >古物商の資格を取得したい! 難易度はどれくらい? >古物商許可を個人事業主として取得する方法 >古物商の取り方【法人編】必要書類等を徹底ガイド >古物商を副業で取得するための手続ガイド |
古物商がフリーマーケットを開催するための手続き

古物商がフリーマーケットで商品を販売する場合、「行商」として申請をする必要があります。行商とは、一定の場所に店舗を構えず、移動しながら商品を販売する形態を指します。しかし、行商を申請する場合でも主たる営業所の申請は必須です。古物商が行商を行う場合の申請方法は以下の通りです。
【申請のポイント】
古物商許可申請書に「行商をする」と記載して申請する
行商の変更手続きについて
既に古物商許可を持っている場合で、申請の際に「行商をしない」と申請した場合には、行商を始める変更手続きが必要です。
具体的には、古物商の変更手続には書換申請と変更届出の2種類の手続きがありますが、行商の有無に関する変更には書換申請と変更届出(事後届出)の両方を行います。この申請により、古物商許可証の「行商」の欄が「しない」から「する」に書き換えられます。
行商の変更に必要な書類
- 変更届出・書換申請書(別記様式第6号):変更内容(行商をする)を選択する
- 古物商許可証(原本)
- 手数料「1,500円」
| 【参考】 >大阪府警察(変更届出(事後届出)) >大阪府警察(書換申請) |
古物商がフリーマーケットで商品を仕入れる方法
主な仕入先について具体的に説明
古物商がフリーマーケットで販売する商品の主な仕入先には以下のようなものがあります。
- 一般家庭からの買取
一般家庭から直接不要品を買い取る方法で、家の整理や引っ越しに伴う不用品が多いです。この方法では、多様な商品が手に入るため、フリーマーケットの品揃えが豊富になります。 - 出張買取
出張して家や事務所で不要品を査定し、買取するサービスです。デメリットとして断られるなどで時間がかかることが考えられますが、一件でも承諾があれば、比較的大量の商品を確保できます。 - 店頭買取
リサイクルショップや買取専門店に持ち込まれた商品を、その場で査定して購入する方法です。この方法では、即座に商品を手に入れることができますが、個人経営の店ではあまり利用されることは少ないです。 - 他の古物商からの仕入れ
他の古物商やリサイクル業者から商品を仕入れる方法で、取引先とのネットワークを利用して安価で仕入れることができます。 - 卸売業者
卸売業者から大量に商品を仕入れる方法です。新商品や人気商品を手に入れることができ、安価で仕入れることが可能です。ただし、卸売業者を見つけることが難しいです。 - 倒産品や在庫処分品の仕入れ
企業の倒産や在庫処分に伴う商品を仕入れる方法で、大量に安価で手に入る場合があります。主に卸売業者や清算会社を通じて仕入れます。 - メーカーや小売店の在庫処分
メーカーや小売店が在庫処分やセールを行う際に、安価で商品を仕入れる方法です。流行の商品や新商品が手に入ることもあります。 - インターネットオークションやフリマアプリ
インターネットオークションやフリマアプリを通じて商品を仕入れる方法で、自宅にいながら様々な商品を取り扱うことができます。 - 海外からの輸入品
海外で販売されている商品を輸入し、フリーマーケットで販売する方法です。海外の珍しい商品やトレンドを仕入れることができます。
仕入れの際の工夫や注意点
仕入れを行う際は以下の点に注意が必要です。
- 商品の真贋と盗品の排除
ブランド品や貴金属などの高額な商品は特に真贋が重要です。例えば、ブランド品では刻印やロゴの細部、質感などを細かく確認し、必要に応じて専門家による鑑定を受けることで偽造品を見極めます。疑わしい商品は仕入れないことが、信頼性の高いビジネスを維持するために必要です。 - 季節性や流行の考慮
季節ごとに需要が変わる商品を把握した上で、仕入れを検討することが重要です。たとえば、冬季には暖房器具や冬物衣料が需要が高まりますが、夏季には冷房関連商品やビーチグッズが人気です。また、季節性以外にも流行やトレンドも仕入れに影響を与えます。
フリーマーケットへ出店するまでの流れ方法

フリーマーケットで古物商をする場合には、古物商許可が必要となります。
古物商許可の取得からフリーマーケット出店までの流れは次のとおりです。
古物商許可の取得
フリーマーケットで中古品を販売する場合、まず古物商許可が必要です。取得のためには、以下の手順を踏みます。
- 申請書の準備:必要な書類や情報を収集し、申請書を作成します。
- 警察署での申請:管轄の警察署に申請書や添付書類を提出します。
- 審査・許可証の交付:欠格事由や営業所等の調査が行われ、問題がなければ古物商許可証が交付されます。許可証の交付を受けたら、フリーマーケットでの販売が可能になります。
出店に必要な連絡や手続き
フリーマーケットに出店するためには、以下の手続きを行います。
- フリーマーケット主催者への連絡
出店希望の連絡を主催者に行い、出店の可否や詳細な手続きについて確認します。連絡方法は、電話、メール、または公式ウェブサイトを通じて行います。 - 開催日時や場所の確認
フリーマーケットの開催日時と場所を確認し、出店のスケジュールを調整します。事前に現地の下見を行い、出店に適した場所を把握することも有効です。 - 出店料や必要書類の確認
出店に必要な書類(申請書等)や手続きを確認します。一般的には、古物商許可証のコピーや身分証明書などが必要です。出店料についても、主催者に確認し、支払い方法や金額を把握します。 - 出店スペースの予約
出店するスペースを予約し、指定された場所に出店の準備を整えます。スペースの広さや配置などについても、事前に確認しておきましょう。 - 出店料の支払い
主催者が指定する方法で出店料を支払います。支払い方法には、現金、銀行振込、またはオンライン決済などが含まれることがあります。支払いが確認されたら、正式に出店が確定します。
これらの手順を踏むことで、スムーズにフリーマーケットへの出店が実現できます。事前準備をしっかりと行い、トラブルを避けることが成功の鍵です。
出店に向けた準備
当日に必要となる物の準備は入念に確認しておきましょう。例えば、商品棚の準備には、商品を見やすく配置するためのテーブルやラック、値札や商品説明カード、包装材料(袋やラッピングなど)を用意しましょう。
さらに、現金取引に対応するためのレジや釣銭、電卓、領収書用の用紙や印刷ツールを準備します。また、屋外での出店に備えてテントや日よけを用意し、雨天決行であれば、雨天時のための防水対策グッズも準備しておくと安心です。
古物商許可の取得はお任せください
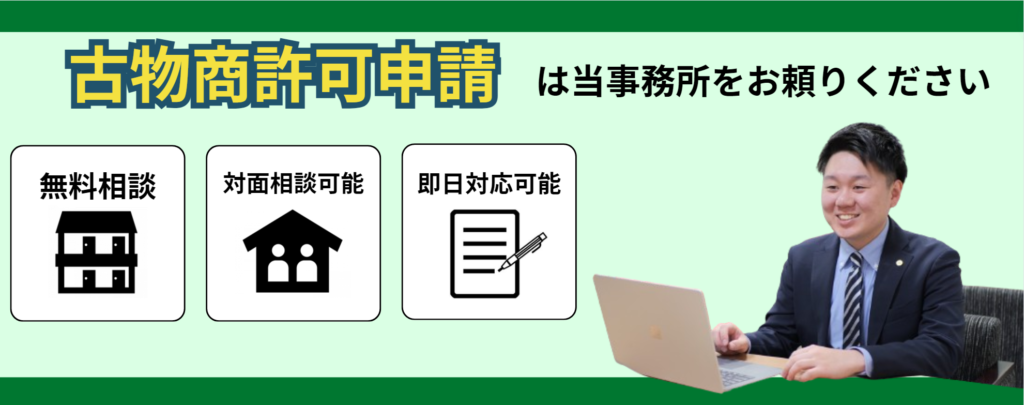
古物商がフリーマーケットを開催する際の必要性と手続きについて詳しく解説しました。古物商として適切に業務を行うためには、関連法規を遵守し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、フリーマーケットでの販売を成功させるためには、商品の仕入れから販売まで、細心の注意を払いながら準備を進めることが大切です。
当事務所による古物商許可代行サービスでは、古物商許可の取得に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都などでの申請において確固たる実績を有しています。私たちのサービスは、お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、手続き全般をお手伝いいたします。また、当サービスでは不許可の場合に備えて返金保証を提供しております。
さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

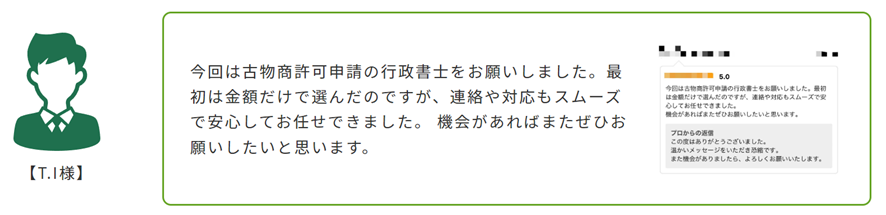

手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
| サービス | 料金 | 概要 |
| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
| 古物商許可申請書作成 (個人) |
33,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 古物商許可申請書作成 (法人) |
44,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
| 実費 | ||
| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
古物商とフリーマーケット:出店に必要な手続きについて-よくある質問
Q1:古物商許可とは何ですか?
A1:古物商許可とは、中古品の買取・販売を行う事業者に対して、都道府県公安委員会が発行する許可です。この許可を取得することで、合法的に中古品を取り扱うことができます。
Q2:古物商許可を取得するにはどうすればいいですか?
A2:古物商許可を取得するには、所定の申請書類を揃え、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に申請を行います。申請書類には、申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが必要です。
Q3:フリーマーケットで中古品を販売する場合、古物商許可は必要ですか?
A3:はい、フリーマーケットで中古品を販売する場合、古物商許可が必要です。個人の不用品を売る等の場合は許可が不要ですが、継続的に中古品を販売する場合は念のために古物商許可を取得しておくことを推奨します。
Q4:古物商許可が不要な場合とはどのような場合ですか?
A4:古物商許可が不要な場合は、自宅にある不用品を販売する場合や個人が不要品をオークションで売る場合などです。ただし、転売目的で購入した品物を販売する場合は許可が必要です。
Q5:フリーマーケットで出店するための手続きはどのように行いますか?
A5:フリーマーケットに出店するためには、主催者への連絡、開催日時や場所の確認、出店料の支払い、必要書類の提出、出店スペースの予約などの手続きが必要です。
Q6:行商とは何ですか?
A6:行商とは、一定の場所に店舗を構えず、移動しながら商品を販売する形態を指します。古物商が行商を行う場合、古物商許可申請時に「行商をする」と申請する必要があります。
Q7:フリーマーケットでの取引はどのように行われますか?
A7:フリーマーケットでは、出店者と購入者が直接取引を行います。交渉が可能で、価格の値引きや商品の詳細についてその場で質問することができます。支払いは主に現金が一般的ですが、最近では電子決済に対応するフリーマーケットも増えています。
Q8:フリーマーケットでの仕入れ方法は?
A8:フリーマーケットでの仕入れ方法には、一般家庭からの買取、出張買取、店頭買取、他の古物商からの仕入れ、卸売業者からの仕入れ、インターネットオークションやフリマアプリ、海外からの輸入品などがあります。
Q9:古物商許可証の変更手続きはどう行いますか?
A9:既に古物商許可を持っている場合で「行商をしない」と申請した後に行商を始める場合には、変更届出・書換申請書を提出し、許可証の「行商」の欄を「しない」から「する」に書き換える必要があります。
Q10:フリーマーケットでの販売を成功させるための準備は?
A10:フリーマーケットでの販売を成功させるためには、商品棚や値札、現金取引に対応するためのレジや釣銭、包装材料、テントや防水対策グッズなどの準備が重要です。事前に現地の下見を行い、出店に適した場所を把握することも有効です。
古物商とフリーマーケット:出店に必要な手続きについて-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商とフリーマーケットの概要、古物商許可の取得方法、フリーマーケットでの出店手続き、さらにフリーマーケットでの商品の仕入れ方法について詳しく解説させていただきました。下記に本記事を簡潔にまとめたものを記載しております。
1.古物商とフリーマーケットの概要
⑴古物商の定義と業務内容
古物商は中古品を取り扱う事業者で、古物営業法に基づき都道府県公安委員会から許可を受けます。主な業務内容は中古品の買取、販売、交換、委託販売の仲介です。
⑵古物商が取り扱う13区分
古物商が扱う古物は13品目に分類され、申請時には主に扱う区分を選びます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品
- 書籍
- 金券類
⑶古物商許可申請について
古物商許可申請は警察署経由で都道府県公安委員会に行います。必要書類は申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書です。
2.フリーマーケットの定義と特徴
⑴フリーマーケットの開催場所・方法
フリーマーケットは屋外や公共施設で開催され、地域の活性化を目的に町内会や地方公共団体が主催します。
⑵フリーマーケットの取引
出店者と購入者が直接取引を行い、交渉や現金での支払いが一般的です。最近では電子決済にも対応する市場が増えています。
⑶その他の特徴
フリーマーケットは安価な価格設定、多様な商品、イベント性を持ち、地域のコミュニティ形成に寄与します。
3.古物商許可が必要なフリーマーケットについて
古物商許可が必要かは、商品の種類や取引形態により異なります。自宅の不用品販売は不要ですが、仕入れた中古品の販売や継続的な収益を得る場合は必要です。
4.古物商がフリーマーケットを開催するための手続き
古物商がフリーマーケットで商品を販売する場合、行商として申請が必要です。既に許可を持っている場合でも変更手続きが必要です。
5.フリーマーケットへ出店するまでの流れ
- 古物商許可の取得
- 申請書の準備、警察署での申請、審査・許可証の交付。
- 出店に必要な連絡や手続き(主催者への連絡、開催日時・場所の確認、出店料や必要書類の確認、出店スペースの予約、出店料の支払い等)
- 出店に向けた準備(商品棚、値札、現金取引に対応するためのレジや釣銭、包装材料等)
これらの手順を踏むことで、フリーマーケットでの出店がスムーズに行えます。事前準備をしっかりと行い、トラブルを避けることが成功の鍵です。
| 【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |